
現代を生きる人たちへの自省録
先日、とある占い師は「あなたの人生は4分の1が終わった。」と私に告げた。それと同時に「次なる人生は、今までとは全く別のものになる。」とも予言された。
いわば、人生の第一章が、25年間という長い月日を経て幕を閉じたわけだ。
最近は30代後半と間違われるほどに老け込み、平均と比べると質量が大きな25年間だったという自負はある。
この節目とも言うべきタイミングに、私は今までの自分が何を感じたか忘れぬよう、ここに全ての行動と思考の経緯を記しておこうと思う。
かつて哲人皇帝とも呼ばれたマルクス=アウレリウス=アントニヌスが人に見せるわけでもなく思いの丈を書き綴ったように、未来の自分が過去にこんな自分もいたと振り返れるように、ここに内省を残す。
自省録のような普遍性と善き生き方はそこにはないが、今を生きる同士に今を生きる私のリアルな声が届き、少しでも困難に立ち向かおうとする者たちの"しるべ"になればと思って、秘めたる思いと知見を世に出すことにした。
※注:今回の記事は人に伝わるよう書いていないため、読む方がそれぞれの解釈をしていただければと思います。
第0章 意味
自由と意味づけ
サルトルの言葉「人間は自由の刑に処されている」は世界の広さをその目で見た者にのみ真なる意味が分かる言葉で、この世が一本道だと思っている限りは足枷を外して大空に羽ばたくことはできない。

職業や人間関係は過去の選択が次の選択にも影響を及ぼす点で真に自由とは言えず、後述する「風」をいかに味方につけるかで多くが決まる。
しかし、事実の解釈をどう行うかは個人の自由であり、人生の意味づけ次第でどんな風がその身に吹くかさえも変わり、運命は躍動する。

一例として私の今までの人生の一部を三次元上にプロットしたものが上記である。
一見5つは全く異なるものに見えるが、同一平面上に乗っているということはすなわち同じ意味を共有した経験であるということ。
同一平面上の経験であれば新しいチャレンジをするにしても過去の経験からその目的を与えることができる。
同一平面、つまり自らの人生の意味を見出す方法は以下の通りである。
①まずは今までの経験の元となっている意思決定軸をx軸・y軸・z軸と定義する。
②点Pが平面ABC上にある条件はOP=sOA+tOB+uOCと表現されるが、当然それを満たすs,t,uが都合よく存在することは
ないからこそ、人々は自らの行動に一貫性を見出せない。だからこそ数学的には邪道だが点A,B,Cを平面に近づけていく、
つまりは自らの経験を同じ平面上に載せていく「自己都合解釈」が必要となる。
③人生にある程度の同一平面を見出すことができれば、AP=sAB+tACとあるように、未知の経験Pに対してもそれが自分の
今までの人生の軸に沿うものか、もしくはPを自分の軸に近づける過程が発生する。意味づけは無論自分のモチベーションを維持して人生の有象無象全てに幸せを感じるという意味で最も有用であるが、実はチャンスを引き寄せるという点でも意味づけを行う価値はある。
最も分かりやすい事例で言えば、採用面接において就活軸が一本通っているだけで評価されることはおかしな話であり、そういう意味では人生の軸(意味づけ)というのは紛れもない錯覚資産である。
一昔前は各々の職分も固定化されてとにかく我武者羅に生きるという考え方が主流であったが、今は役割、生きる意味すら自らで規定しなければならない時代へと変わってしまった。
そんな時代もあってか、自らの軸を持つことが世のメインストリームとなり、社会的にも人間関係的にもチャンスを得やすくなった。
現代こそサルトルの言葉は我々に重くのしかかり、「実存は本質に先立つ」の「本質」とはそもそも何を指すのか見つめ直す必要がある。
先入観のジレンマ
意味づけを行う際には、意味の方向は一方向に定まらず空間的広がりがあることに注意しなければならない。
左図で表されるように何か一つのコミュニティ内では正義は一方向で、それに基づく人の価値も階層構造が形成される。しかし、実際の世界は右図のようにある世界の盛者は別の世界では凡人であることが展開図から読み取れる。

私は世界トップの難易度を誇る企業に所属していたが、その中の人間が全ての能力において他者より優れていたかというとそうとは言えず、デザインの話はクリエイター、実働の面は現場の人間の方が優れていたと感じることは多かった。
たまたま今の社会がロジカルなものを正とする風潮下でコンサルティングファームが評価されているに過ぎず、全ての思考業務がAIに奪われた時代には真心を武器とするサービス業が社会の頂点に立つ可能性も考えられる。
正解が無数にある複雑な社会にあっても、人々がコンサルや商社といった一辺倒なキャリアを求める理由はただ一つ、「迷わないことが楽だから」だ。

ひとたび他の世界(上図での隣り合う三角面)を知ってしまえば、自分がどの方向に進めば成功なのか幸せなのかを見出すことが格段に難しくなり、人生の迷子になりやすい。
このように世界を知っていればいるほど浅はかに何かを決めたり何かに幸せを見出すことが難しくなり、まさに「自由の刑に処される」状態となるのだ。

だが世界を知れば知るほど悪いことばかりかというとそんなことはもちろんなく、七色を知るものは白すらも見通し、七色を混ぜて黒を知っているのだ。
白は一般的に多様性と呼ばれるが、そのコアは普遍性。帰納的に万物の理を見出すことで、あっちこっち向いていた正義の矢印を一つに束ねることができる。
黒は現実性。この世の有機的なものは一つの秩序からできているわけではなく、それを解して創造するには正解を柔軟に使い分ける必要がある。
そして、一つの正義を背負った面や色といった概念が表象化したものこそが「コミュニティ」なのである。
第1章 コミュニティ
「コミュニティ」とは
これから論じる「コミュニティ」は地域社会や組織といった小さい概念を示すものではなく、共同体主義(コミュニタリアリズム)が扱ってきた概念に近しい。
リベラル・コミュニタリアン論争では、合理的存在の個人がそれぞれ善を追求すると唱えるリベラリズムと、共同体メンバーが共通して持つ共通善により個人も決定されると唱えるコミュニタリアリズムが長年論争を続けてきた。

ただこの論争は主にアメリカで行われてきたこともあり、アメリカ人と全く考え方の異なる日本人にこの対立を適用してよいかは疑わしい。
個人的には池上氏が提唱するアミタリアン的解釈が現代日本人のリアルに最も近いと思われ、SNSの台頭が友人間での正義の確立に拍車をかけており、これはコミュニティの限りではない。
つまり我々の人格形成に大きな影響を与えているのは仰々しい組織レベルのバックボーンではなく、その中で誰と接点を持ち、どれだけの深い会話を繰り広げたかに由来すると私は考える。
「コミュニティ」とは顕在化した人々の集合体ではなく、同じ正義を有した人々が結果的に同じ穴の狢となり組織を形成したに過ぎず、全ての組織がコミュニティであるという訳ではないのだ。

上記はあくまで一例だが、シルエットを見るだけで各界の人間がリアルな世界ではどんな仕事をしているか想像がつくように、「コミュニティ」「職分」「人生の意味」の3つには大きな関係性がある。
見慣れないものは右端の旅人かと思うが、まさに旅人の創造と境界の拡大こそが私の人生の「意味」とも言うべき、人生の終着点なのだ。
透明な世界
境界は世界と世界の狭間にあり、色を持たず構成員を持たない場である。
その場の役割は、どこか別の世界に行く時に経由するために存在する。

例えば知識界にいたビジネスマンが急にモノづくりをしたいと創造界のクリエイターになるには転職活動が必要だし、感情界にいたアーティストが想像界で抗弁を垂れる政治家となるためには人々の支持を集める選挙活動が必要となる。
広義で捉えれば求職者も選挙立候補者も境界を彷徨う旅人であり、つまり人は誰しもが刹那の旅人を経験するのである。
境界が広がるということはすなわち異界に挑戦できるチャンスが増えるということ、チャンスが増えればすなわち透明(もしくは黒)の人材が世に増えるということで、私は7年間両側からアプローチを続けた。
不可解な行動の種明かし

私の今まで行ってきた活動を全て知っている人からすると、その行動に連続性はなく何故それらを注視してきたか一貫性を見出さないかと思う。
それらは全て先述した世界の構造破戒のためだったが、上図のように目指すべき世界を因数分解すると理解いただきやすいだろう。
世界結合
挑戦する人がコミュニティを越境するには、まず世界が平らである必要がある。コミュニティ間の壁の高さが挑戦を阻害する。
具体的な取り組み》YouTubeを通じた多様な生き方の発信解放
愚者の言葉が挑戦者の一歩を妨げる。人生の主人公は自分自身。
他社の評価から解放され、周囲がむしろ応援するような環境を。
具体的な取り組み》海外インターンシップ「武者修行」を通じた自走式エンジンの搭載不充足
まだこの世界では足りないという渇望が次の世界への扉を開く。
現状に甘んじる者は外に世界があることすら気づかない。
具体的な取り組み》社会人向けインターンシップやen-courage等のエージェントを通じた、井の中の蛙脱却作戦混乱
脳天に雷が落ちたかのような衝撃的な体験が、不充足と正しいワクワクを生む。無知の知の眼鏡越しに外の世界を見るきっかけを作る。
具体的な取り組み》戦略コンサルティングファームへの転職オタク
何かを本当に好きであるならば一つの世界に引きこもることは本当はない。アクティブ・オタクになること、それが次の時代のチャレンジャーを生むことである。
具体的な取り組み》クリエイティブ活動と事業立ち上げ活動厨二病
できそうもないこと、青臭いことを口に出して言ってみよう。
できるかできないかに関わらず、妄想しなければ必ず実現できない。
具体的な取り組み》「ディズニーを創る」「世界一難しい企業に入る」「クリエイター/エンジニアになる」といった妄想の実現魔法
どうせなら切迫感でなくワクワクして越境しよう。同じメッセージであってもワクワクする魔法をかければ、夢や希望になる。
具体的な取り組み》ディズニーでの施策やボカロPとしての発信ダンス
ダンスするように今を本気で生きよう。例えそれがどんなものだったとしても本気でやれば次の世界も見えてくる。
具体的な取り組み》アメリカや離島への脱走・副業6社の両立
ただ、人の視野を広げて挑戦しろと言っても説得力も何もないので、私はまず自分が目指す世界の住人となれるような生き方をしてきた結果、類を見ない自分だけにしか築けない人生を形作ることができたと感じている。
この話を聞いて自分には無理だと思う人もいるかもしれないが何も難しい話をしているわけではなく、自らの中でパラダイム・シフトが起これば誰もが自由に好きな世界に飛び立つことができる。
そもそも自分にしかできない再現性のない話であれば社会に生きる全ての人を変えることなど到底できず、わざわざこの場で発信するべき話でもない。
最も大事なものは先述した「意味付け」であることに間違いはないが、手段レベルの話では「風」と「時間」を操ることがキーになってくる。
第2章と第3章ではそれぞれが何であるかを見ていこうと思う。
第2章 風
風の探求
「風」は私のオリジナルワードゆえ、そもそも何を指しているのか説明していなかったと思うが、定義があるものというよりは「何となく上手くいく/いっている方向」という見えない代物である。
多くの日本人がこの感覚は持ち合わせており、「追い風」「向かい風」といった言葉をビジネスシーンで用いる時の「風」とは、その時代の潮流だったり事業が上手くいく方向であり、向かい風が不利であるのは風が吹く方向を正と定めているからだ。

火/陽があるところに上昇気流が生まれ、低気圧となったそこに高気圧の箇所から風が吹き込む。
ビジネスで盛り上がりを見せているIT市場はレッドオーシャンとなり、そこに風が吹くように他業界から参入が起こる。
この風を読み取り、時には自らの周りに風を吹かせ、時には風が生み出す大波に乗るような「風のコントロール」、それこそが目的は維持した上で人生にうねりを起こし越境の源泉ともなる力なのだ。
チャンスが巡ってくるかは運で掴み取れるかは実力次第とよく言われるが、私から言わせれば風を読み取れるか次第だと思う。
実例を示して、風の自らに従わせることの重要性を見ていこうと思う。
風が吹く場所ではなく吹かせる場所に
以前に以下のような相談を受けたことがある。
「異性からモテたいのだが、どうすればいいのか。」
私は「モテたいと思うほどモテないので、モテることを意識しなければモテる」と伝えた。

モテるとはすなわち他者から自分に特別な感情のベクトルが向くということだが、上図を見て分かるように左の他愛はいかなるチャンスも逃さないが、右図の自愛は同じく自愛の人間・風を吹かせるほどの発信力がない人間を振り向かせることはできない。
モテたいなどの自己中心的な欲を持つことはいわば自愛であり、かからない場所に罠を仕掛け続けるのではなく自分が槍を持って出かける方が早いだろう。
外向きの風は何も好きと伝え続けるという話ではなく、極論恋愛的な感情がなくとも外向きの発信や行動、建設的な人間関係構築を続ける人は、どんな人からも魅力的に映るものだ。
(むしろ外向きの思考の人は、恋愛で自分を縛ることを避ける傾向が強い)結果的に「モテようとしない方がモテる」ということになり、私自身も恋愛に興醒めな時に限って何故か人から好かれたりしたものだ。
この性質を逆手に取り自分の居心地の良い環境を作り上げることもまた可能である。
私はマウントの取り合いや猿山争いをする無意味な競争主義が非常に嫌いだが、そんな関係性を避けるために女性社会に身を投じた。
同性同士はエディプス・コンプレックスのように、ついつい自愛に走り他者比較をしてしまいがちである。
私の周りに女性の友人ばかりいることから女たらしと言われたりもしたが、上記の理由から女性もしくは女性的な感性を持った男性の友人しかできなかったというのが本音である。
自分が生きやすいためにも、より多くの人と関係を築くためにも、風が吹いて一見盛っているように見える場所よりも、今まさに風を吹かせているダイナミックな場に身を置くことを推奨する。
第3章 時間
時間を巡る争い
ミヒャエル・エンデの『モモ』では時間は盗まれるものであり、現に我々が忙しくて心を失くすような時には時間を誰か・何かに奪われたと感じることが多い。
だがいくら毎晩深夜まで働こうと、参加した飲み会が無駄な時間だと思おうと、契約主義の現社会においては必ずそれら行為の前に「リスクを受け入れてでもこの行為をしよう」という自らの意思決定のタイミングがある。
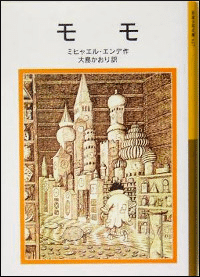
現代社会の全ての根幹は「時間投資の連続」というのが私の仮説である。
仕事も恋愛も趣味もそれに時間を割く価値があるかどうか個人がその都度意思決定を行っており、お金も関係性も時間で換算されるほど我々の人生は時間という最上位概念に支配されている。
「どの企業に入るのが最も得られるものが多いか?」という問いは常にキャリア選択で論点となるが、時間と価値は等価交換ゆえ、究極どの会社に入ったとしても得られるものの総量は100%で何に価値が配分されるかが企業によって差があるだけに過ぎない。

やりたいことができる会社に入って薄給で夢を追いかけるのも良し、高給企業でやりがいを感じなくても高い給料を得るも良し、自らにとってチャレンジングな企業で将来お金や時間を生み出すスキルを得るも良し。
ただ、給料が高いのは皆がやりたくない仕事だからであり、スキルを得るにはそれなりの時間を投じる必要があり夢を追う時間が減るといったように、各々の価値はトレードオフであり全てを一度に得ることができないように世の中できている。
コストパフォーマンスという考え方は短い時間軸であればどれだけスキルや年収が増えたという一般概念で表現しうるが、長い目線で見ると効率性を追い求めるのは一手段であり目的とはなり得ない。
持て囃されたスキルは社会の大きな流れの中では一瞬で使い物にならなくなったり、高年収と引き換えの長時間労働は体に無理をさせて将来働く可能性さえも奪ったりする。
即ち、時間の総量が同じで効率的な時間の投資方法もない以上、人生という名の事業ポートフォリオをどのように構築していくか、第0章で論じた意味をもとに何をとり、何を手放していくか線引きをすることが自らの生き方そのものであるかもしれない。
時間という一般概念からの解放
手放すとはいっても自分が大事に思っているものを手放すことは勇気がいるものだ。
それよりは先に、自分を無意識に縛っている先入観から解放されることの方が、万人が簡単に取り組むことのできる方法である。

上記の私の今までの略歴を見て分かるように、周囲から私の一番の強みは「同時に色々なことを進めること」だと言われてきた。
マルチタスクはできないと感じる人もいるかもしれないが、実は私も1ヶ月の間に同時にやっていたものは多くて2〜3つ程度だ。
大事なことはあくまで時間に関する思い込みから解放されることで、以下のように先入観を手放していくことが自らの時間の使い方を見直す第一歩となるだろう。
「1年間のうちに〇〇をする」といったように一般的に使われる尺度で期限をなんとなく決めない
「何かをしている期間は他のことはしない」と一つのことだけに盲目的になると全体像が見えずかえって手詰まりの時間が増える
時間がある時は今やっていることに近しいことではなく真逆の分野の見聞を深めたり将来を先取りする方が後々時間の余裕ができる

上図をもとにそれぞれの要点を説明していこう。
「1年間のうちに〇〇をする」といったように一般的に使われる尺度で期限をなんとなく決めない
「今年こそは〇〇するぞ」と新年の抱負をするのが私も大好きだが、大前研一氏の「最も無意味なのは、『決意を新たにする』ことだ」という言葉は非常に衝撃的だった。
もし具体的な目標を立てたとしても、その目標達成期限を1年以内としたことには何の意味があるのだろうか?
パーキンソンの法則といって仕事は使える時間ギリギリまで膨張するという特性があり、折角仕事を効率化して早く終わらせてもその仕事のために残された時間があると成果の細部が気になってしまった覚えはないだろうか?
つまり、1年以内に達成を目指した目標は、実質半年で成果が出ていてもなんとなく「より良く」できないかと考えてしまうのだ。「何かをしている期間は他のことはしない」と一つのことだけに盲目的になると全体像が見えずかえって手詰まりの時間が増える
一個の目標を必死に追いかけると、時にどうすればいいか悩んで立ち止まってしまう場面はないだろうか。
自分が今必死に悩んでいることは、誰かが過去に悩み抜いて既に答えが出ていることだったり、自分が今いる以外の世界では常識となっていることも多い。
また、一つのことに夢中になると作業など各論の話に拘りやすく、そもそも何故その仕事をしているのかという「論点」を見失いやすい。
(と私は上司から何度もフィードバックを受けたものだ)
具体的には私の場合は以下のようなことがあった。
・サービスAは提供価値の質こそ良いものの集客に悩んでいたが、同時に手掛けていたサービスBは強固な顧客基盤を抱えてサービスの幅広さに課題を抱えていた。サービスAをサービスBの提携コンテンツの一つとすることで両サービスの課題は同時に解決された。
・クライアントの担当者は凄腕営業や完璧なプレゼン資料があっても首を縦に振らない方だったが、テーマパークやボカロといったエンタメを用いた関係構築でラポールを形成したことが契約に繋がった。
上記のような事例は社会経験が薄い私の話よりも、ぜひ高山 洋平さんの著書を読んでいただき、身の回りに溢れている事象からいかに学べるかを体感してみて欲しい。時間がある時は今やっていることに近しいことではなく真逆の分野の見聞を深めたり将来を先取りする方が後々時間の余裕ができる
想像もつかない組み合わせの化学反応が思わぬ成果を生むという点では2と近しい考え方だが、イノベーションが真逆の組み合わせであるほどその効果が大きいように、自分が今やっていることと真逆のことを別軸で学んでおき周囲と差別化したい時にそのスパイスを自らの努力の積み上げに振りかけると恐ろしく芳しい香を周囲に放つ。
例えば仕事でもプライベートでも相手と信頼関係を築くのは一筋縄ではいかないが、相手がエモーショナルであればロジカル、相手がロジカルであればエモーショナルな自分の価値を訴求すると信頼を得やすい。
逆のように感じるが、人間は同様の能力を持つ者には同族嫌悪が働き、その能力の見極めもシビアになってくる。
私は1社目のエンタメ会社で自分が苦手なことに挑み、2社目はその真逆のコンサル会社に入社したが、1社目では「この会社では珍しくロジカルな人」と言われ、2社目では「この会社でエモーショナルな人は珍しい」と言われ、両社で面白い仕事を任せていただけた。
1・2・3の複合系で時間にまつわる話をもう少ししておくと、踏むべきステップが明確な事象に関しては「先取り」というチート方法が存在する。
最も説明しやすいのは就活の事例だ。

就活は一般的に大学3年生からインターン参加と当時言われてきたが、1の法則に則った私は大学2年生から就活を始めた。
大学3年生から就活を始めることは非常に非効率であり、どんぐりの背比べ環境下で制限時間を企業に握られたまま与えられたルールで戦わなければならない勝負を勧んで引き受ける義理なんてない。
大学低学年で就活を始めればそれだけで注目を浴びてお得だし、考える時間は山ほどあり同時並行で色々な経験を積みながら就活というものを客観的に観察できる。
そもそも就活は開始時刻が決まった勝負でないにも関わらず、一斉勝負にした方が合理的だという理由だけで今の形をとっているので、中途採用では時間や勝負という考え方に縛られることはないし、最近は時間に縛られない優秀な学生と採用するために優良企業は新卒採用の前提条件を変えてきている。
新卒採用はあくまで一例だが、ここで最も言いたかったことは自らの運命を決定づける時計を相手の手に握らせてはならないということだ。
今の会社がもう少し長く勤めれば昇進&昇給を約束すると言っていて転職することができない。
恋人は1年以内に結婚しなければ別れようと言っているので折角巡ってきた海外での新しいチャレンジをすることができない。
ただ1人の親友が自分を見限るのが怖いので、月に1回の飲み会は気乗りしなくても参加しなくてはならない。
占い師をしているとこのような相談がたくさん寄せられるが、自らが納得しないまま時間という重要資源を他者に渡す行為は、自らの自由を捨てて相手に降伏する行為に等しい。
自らが人生の意味に近づけば近づくほど時間という資源は枯渇しやすい傾向にあるため、人間は前進して得られるものが増えれば増えるほど、また手放すという意思決定をしなければならない場面が増えてくるのだ。
手放すことと愛すること
私が一番最初に「手放す」という言葉を見聞きしたのは、藤井風さんの「帰ろう」という曲の歌詞だった。
「去り際の時に何が持っていけるの 一つ一つ荷物手放そう」

社会人3年目を迎えた自分は度重なる環境変化の中で、毎日このフレーズと風船が空へと飛んでいく情景に触れて、涙を流し続けていた。
常に何かを得続けて前に進み続けなければならない。
何を得ても何者になろうとも満たされ続けない。
そんな終点なき荒野を砂嵐で傷つきながら歩いていた自分にとって、「手放す」というのは最初は受け入れ難い選択肢だった。
後に私は心と体を壊して働けない身となり、自分が病気であると分かった時はお金も信頼も人間関係も全て失ったように感じた。
だが、私が実際に見たものは、どんな自分になっても周りにいてくれる最愛の人・家族・親友、お金がなくても慎ましく楽しいパートナーとの生活、あなたにしか任せられないと自分の帰りを心待ちにしてくれた会社の人たち。
確かに周囲にいる人の数こそ減ったが、それは自分を道具としか見ていなかった縁を切るべき人間がいなくなっただけで、本当に大事な人と大事なものだけをひとつずつ積み上げていく日々は私にとってこの上なく幸せな日々だった。
その時に初めて、「幸せ」とは「何かを選び取る」ことではなく、「選び取ったもの以外を手放すまで、何かを愛すること」だと気づいた。

前段で話した通り、時間は誰かから奪われるものではなく、自らの意思で自由に投資して、自分が理想とする人生を実現するための資源である。
投資先には限りがある。
自分の無力さを自覚して、やりたいこと全てを追えると思わないことだ。
そう考えると、あなたが手放してもよいと感じたものは何だろうか。
それを手放すと誰かが悲しんだり自分が不安になったりするだろう、でもそれを手放さないと本当に大事なものさえ愛することはできない。
私も思い切って自分の外と内の間に境界線を引いてみて、外にあるものを少しずつでも手放していきたいと思う。
(手放すことをより深く知りたい方は以下の書籍を強くお勧めする)
終章
まずは、10,000字を超える長文をここまで読んでいただき、ありがとうございました。
偉そうに御託を並べてしまった自覚はありますが、今このメッセージを書かなければならないという強い衝動に駆られ、重い腰を起こしました。
この記事は元々私の大事な人の悩みを少しでも和らげたいと思い書き始めたもので、多くの人に公開するつもりはありませんでした。
ただ、この数年間で多くの人からジャンルを問わずたくさんの相談を受ける中で、自分が与えていただいた経験の数々は本当に貴重で意味あるものだったと再認識して、そこでの気づきをオープンソースとすれば自分がリアルで干渉できなかった人たちの人生も少しでも明るくすることができるのではないかと考えました。
個人的に、この4章に凝縮したエッセンスは応用すればあらゆる事象に通ずるものかと思います。
具体的なHow toを書いてないのは意図的なもので、やり方に拘るのではなく考え方に拘る人がもっとこの世の中に増えればいいなという思いです。
椎名林檎さんの「NIPPON」という曲の「ほんのつい先(さっき)考えて居たことがもう古くて」というフレーズが大好きで、目まぐるしく変わる環境下で私がこのnoteに書いたことも今の社会の見方を切り取ったものに過ぎず、1年後の自分はこの文章を見て稚拙だと笑うかもしれません。
ただ、誰かが稚拙だと思う言葉も、別の誰かにとっては背中を押す宝物になるかもしれません。
周囲からの評価やルールに縛られず、その時感じたことをそのまま紡いだ言葉。ぜひ次はあなたの言葉を聞かせてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
