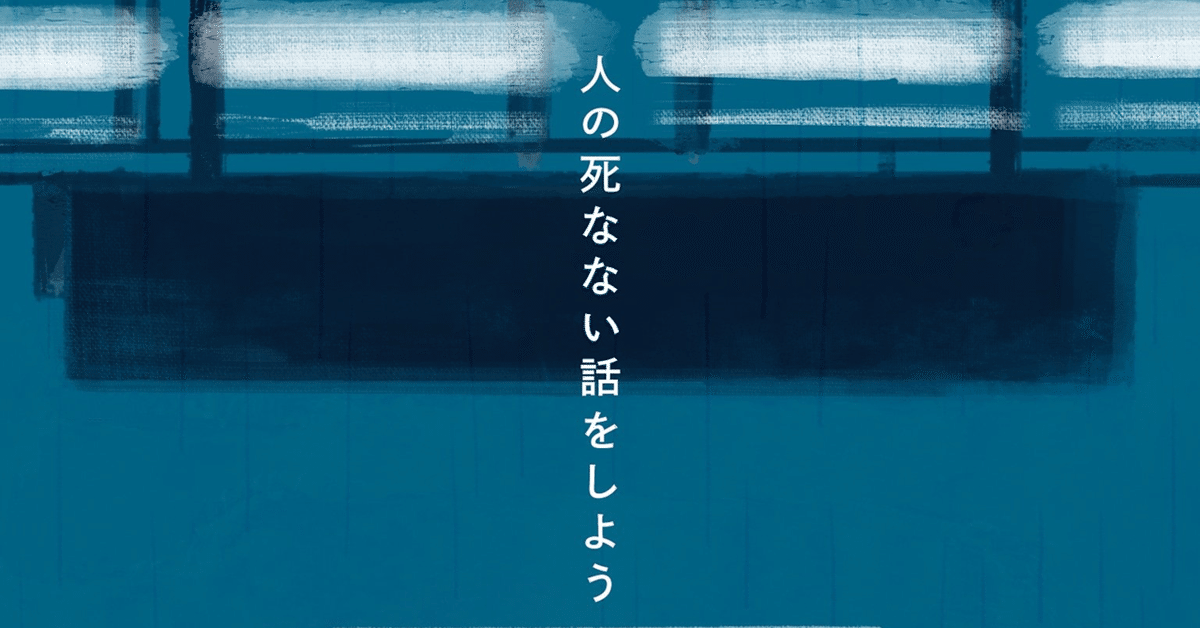
書評 『人の死なない話をしよう』
本書をインターネットで注文し、届いた品を見たとき、この本は開封することも読むという工程に含まれている本だ、と直感した。
(なのでそれは2か月ものあいだ封を切られないまま紙の山の中で眠り続けることになってしまったのだが。)
本書の著者は笠原楓奏さん。
インターネットで活動する歌人だ。
笠原さんの強みはその発想力といえる。
特にその強みは連作で大いに発揮され、既存の連作観にとらわれずに新しい枠組みを開発している。
そして私が言及したいのは、笠原さんはただ発想力の人というだけではないということだ。
その枠組みの美味しいところを最大限に生かして、作品を一つの形にするのがとてつもなく上手なのである。
本書のあとがきで著者自らがアイデアだけで戦っていると書いていたが、そんなことはないと断言することができる。
読者はまず彼の作品のギミックに感心し、その後作品の完成度に感心することになるのだ。
そしてこの「感心」は、歌人という一面を持つ私の視点だと、「嫉妬」に置き換えることもできる。
本書の中にもそんな独創的な連作がいくつも収録されているが、そのギミックについて、ここで触れることは避けようと思う。
一つ言うならば、私が著者の中で一番好きな連作である「砂山のパラドクス」が収録されていて嬉しかったということは記しておきたい。
この作品に「砂山のパラドクス」というタイトルを付けることがまず一つすばらしい。
あと一点だけ、本書は前半はタイトルがつけられていない短歌が並び、後半には連作が載るという構成になっている。
この構成、具体的には前半の短歌群にタイトルを付けないという判断も、後半の連作のアイデアをより印象付けるものとして成功していると感じた。
それを聞いて前半にはギミックが含まれていないのかと思う方もいるかもしれないが、そんなことはないので安心してほしい。
さて、本書のタイトルは『人の死なない話をしよう』であるが、とても攻めたタイトルだろう。
一般的な歌集では、タイトルには歌集に収録された1首の一部から、その歌集の雰囲気を表すフレーズが用いられることが多い。
その点では本書も同じではあるのだが、『人の死なない話をしよう』というタイトルがこの本の特徴を直接的に言語化しているというように捉えることもできてしまうのだ。
確かにあとがきに「人が死なない」ことは本書のテーマであると著者自らが書いている。
テーマを設けたことが著者にとって創作上の縛りになったかは分からないが、読者がこの歌集を読む上での多少の縛りとなっているのではないだろうか。
それは、ある感情を引き起こす物事として、死は一つの極大値であるといえるからという点が大きい。
死が引き起こす「ある感情」とは、例えば悲しみである。
赤の他人の死を喜んで待ち望む人は少ない。ゼロであるとは言い切れないだけでもうゼロに等しい。
そんなストレスのかかる感情を最大級に引き起こす「人の死」が表れないことは、本書に向ける注意力をごく僅かに散漫にさせる。
そしてその代わりにではないが、どのような感情帯の歌を読み手が期待することになるのかという問題もある。
人が死なないからハッピーという方向に振りきるなんてほど単純ではない。
またもっと単純に、読者が「本当に人が死なないのか?」という疑念を頭の隅にでも置いて読んでいく可能性がある。
人以外の死が出れば、間違ってはいないがもやもやするようなひっかかりが残るという副作用もある。
このように、歌集の中身の良し悪しに関わらず読者は無意識の境界線上で本書への集中力を落として読むことになると感じていた。
ここから本書の歌をいくらか引用する。
面接の椅子がめちゃくちゃふかふかでそういう罠だと思って座る
バファリンの優しさの方だけ集めなんの役にも立たない薬
半額の寿司が売れてる半額になれば俺でも売れるだろうか
実は掲載されている歌は割とシニカルなものが多い。
一首目、見た目は普通なんだけれど座ってみるとびっくりするくらいふかふかな椅子ってあるよなあと思いながら、そのような椅子をイメージしてこの歌を読んだ。
面接の”罠が仕込まれていそう感”は、あまり意識されないところに確かにある気がした。
「めちゃくちゃ」が罠っぽさを引き立てている。
実際の面接でそんなに良い椅子が使われるのはあまりイメージできなかったが、その現実から0.5歩離れたような場面設定が心地よく、そんな中でも主体のシニカルさが表れている油断のなさが好きだったためこの歌を引いた。
二首目、”バファリンの半分は優しさで出来ている”を受けた一首。
「優しさの方だけ集め」ることは実際にはできないが、その様子はなんとなくイメージでき、半分と書かれていないがちょうど半分を取り出す様子を頭で補完することができる。
共通認識のあるモチーフを信頼し、おかしな光景もしっかりと読者の頭に写す描写力も素晴らしい。
そして下句で「なんの役にも立たない薬」と皮肉たっぷりに言う。
「優しさ」を「なんの役にも立たない」と一刀両断している訳だが、結びの「薬」が凶悪だ。
元は薬であったのだから、「優しさの方だけ集め」たそれも「薬」なのだと、押し付けられるような主張がある。
三首目、そのシニカルな思考は自分自身にも向けられる。
「俺」が「売れる」かもしれないという考えに至ったということが面白く、突拍子もないように思える思考の発端が「半額の寿司」にあるのだと分かればそこに不思議な現実味が生まれる。
主体が半額になるような時間の寿司コーナーにいるのに、「売れてる」と半額の寿司と中立な位置を取ろうとしている視点も興味深い。
そして読者は寿司が売れたのは半額になったからなのだと、この上句に思わされる。
その上で「俺」を引き合いに出されると、揺らいでしまう。
著者の歌の特徴として、音読して心地よいものが多い。
せり、あのさ、土曜、例えば、ほとけのざ、やっぱ、すぐ来て、私に会いに
五百年くらい経ったら教科書に「の戦い」で載りそうな夜
All right のこえだめであるスタンドでまだ大丈夫そうに振る舞う
一首目、春の七草に韻を近づけたことで、諳んじるように軽やかに読むことができる楽しい一首だ。
「ほとけのざ」を変えずにそのまま言う感じもおどけた感じでかわいらしく、「ほとけのざ」の五文字とも丸みがあるため、視覚的にも柔らかい印象がする。
その軽やかさによって、主体の思いがこちらにもするっと伝わるのだ。
二首目、この歌は文字数だけを見れば、四句の「「の戦い」で」が6文字で字足らずの歌ということになる。
だが、私はこの歌を読んだ際には、”の_たたかいと”というように、「の」の後に一拍分の休符を入れて七拍で読んだ。
読んでみれば定型のように感じるのだ。
三首目、初句の「All right」は日本人としては"オールライト”とも読んでしまいたくなるが、三句に「スタンド」とあるので、これはガソリンスタンドの店員が言う”オーライ”のことだと分かる。
それが分かったとき、「All right」を”オーライ”と読むという気持ちよさが生まれる。
ちなみにこの歌も、「こえだめ」が”声”の掛詞になっていて、視覚的にも面白い歌である。
口にして心地よい、というのはなじみがあるということだ。
私たちがよく使う話し言葉のような感覚で、著者は短歌を正に詠っているのだろう。
読んで楽しい歌、ということは著者にとってもそうであるはずだ。
きっと短歌を詠むという行為は著者にとって重要な部分を占めているのだろうと感じることができる。
実際、短歌を詠むことに関する歌が作中にいくつか収録されている。
例えば次のような歌だ。
だとしても生きていくのだ僕たちは下手な倒置でごまかしながら
深読みをする人々を媒介し歌は知らない街で咲くのだ
許すとか許さないとか理不尽な人に許されたくて定型
このように詠むことについての歌がいくつも挙げられるということは、著者にとって身近なモチーフであるということに他ならない。
歌を詠むことが著者になじみがあるということから、この歌集のいたるところで垣間見えるシニカルなユーモアは、著者自身の特徴なのではないかと考えることができる。
その上で本書のタイトルである『人の死なない話をしよう』について、これについても、この歌集の中での戦略という意味ではなくもっと根本的な著者の信条なのではないか。
この歌集を読むことで、自然にそう感じる。
短歌というものが自分に近ければこそ、死の話をすることに慎重になるということもあろう。
そして手の内を明かして損をするようなことも、短歌が自分に本当に近いのならば自然にできるのではないか。
そのような選択をして、真摯に詠まれた歌が本書には載っている。
だから私たちはこの歌集を素直に楽しむことができるのだ。
たぶんそろそろ怒られる頃だろうこれが歌かは君に任せた
私は紛れもなく歌であると、声高々に主張したい。
![]()
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
