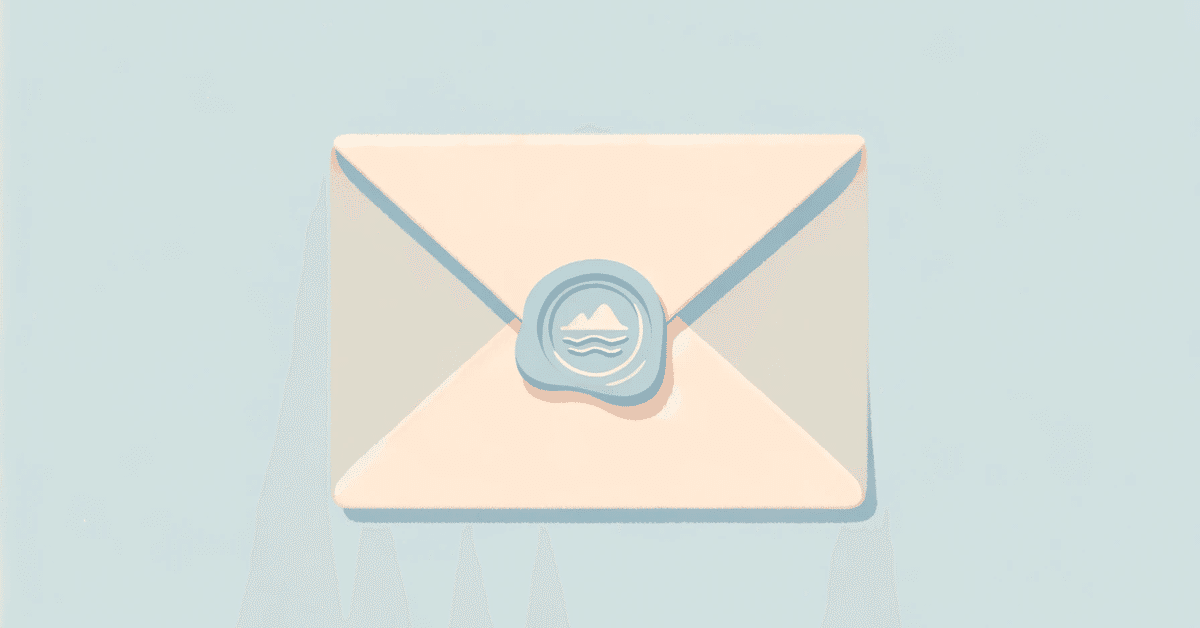
【短編小説】画人失名氏の手紙
【失名氏】(しつめいし)
名前のわからない人を示すときなどに用いる語。なにがし。無名氏。
謹啓
この時節ますます厳寒耐え難く、淋しく木枯らしの吹く毎日ですが、先生はいかがお過ごしでしょうか。
昨年治療頂いた折には、ひとかたならぬお世話になりましたことを大変感謝しております。それはもうお礼の言葉も見つかりませんほどで……。
私はあれから随分と心持ちが軽くなり、ふた月ほどはつつがなく日常を送ることができました。これまで対人関係を常に遠ざけ、何事にも没頭することができず、正体不明の不安と恐怖に苛まれながら一生を過ごしてきたというのに、本当に奇跡のようなことです。
何より喜ばしかったのは、絵描きの仕事に一心に打ち込むことができたということです。
あれ程まで不安なく、時を忘れ画室に籠もっておれたのは生まれて初めてのことでした。
出来上がった幾枚かの絵を知り合いの画商に見せると、思いもせぬ高値で買い取ってくれました。世紀の大傑作だなどと絶賛しておりましたが……いえ、事実がどうかなどは知れません。田舎の祖父母が聞いたら卒倒してしまうような値打ちを付けられたその絵は、今もその画商の元で行く先なく眠っていることでしょうから。
しかし、いずれにしても私が一定の間「幸福らしきもの」を手にしたのは、確かなことです。
ご聡明な西ノ宮先生は、端から気が付いていらっしゃったことと存じますが、それが仮そめの幸福に過ぎなかったこともまた確かなことです。
先生は親身に私の問題を解決しようと尽力してくださったというのに、私はあの時、本当のことを一切打ち明けることができなかった。それはある些細なくだらない、しかし私の人生を変えた出来事についてでございます。
臆病な私は愚かにも肝心要の部分を先生にお話しせずして、先生のご高庇を求めたのです。どうか愚かな私をお赦しください。
もしも先生のお気持ちやお時間が許すようであれば、どうか、どうか、最後までご卒読下さいませ。
それだけが、先生に本当のことを知って頂くことだけが、愚生の最期の望みでございますゆえ……。
*
私は生まれも育ちも東京ですが、父の実家は群馬の吾妻郡にあります。
父方の祖父母は吾妻郡に在る榛名山のふもとで、農業をなりわいに暮らしていました。
私には三歳の頃から母がおりませんから、三歳から十歳くらいまでの七年間、父の出張の度にひと月ふた月、長い時は半年ほど祖父母のもとに預けられていました。
両親は私がまだ物心もつかぬ頃に離婚しました。
母を失った私に対して父は特別に愛情を注ぐわけでもなく、両親が離婚するまで孫の私との関係が希薄だった祖父母にしても、突然湧いて出たような孫の存在を喜ばしくは思っていませんでした。
父の悪気のない淡白さや冷酷さは、まことに因果な血筋か、継承された文化だったのでしょう。私は一切の幼少期を、誰からもほったらかされて育ったと言っても過言ではございませんでした。
しかし群馬に預けられている時、祖父母が農作業をしている間はいつも一人で遊んでおりましたが、退屈したことはありませんでした。
都会で育った私にとって、延々と続く青々とした田畑や、広々とした造りの木造家屋、周りを取り巻く深緑の山々は、この上ない格好の遊び場でした。水の引かれた田んぼでおたまじゃくしを捕まえたり、さまざまな虫を捕まえては虫かごに入れたり、畔から落ちぬように駆け回ったり、納屋にある竹馬の使い方もわからずに投げたり引き回したり、影ふみや石けりをして遊んだり、都会ですることのできぬ一人遊びは、七年の間すこしも尽きる気配がございませんでした。
私が小学校に上がった年の、夏も盛りの頃でした。今でもアブラゼミの五月蠅い鳴き声が耳に焼き付いています。
私はその日、いつものように稲田を耕している祖父母のそばを離れ、裏山へ出かけました。
様々な尽きない遊びの中でも、私は農家の裏山に通うことが非常に気に入っていたのです。足しげく通い、蝶を捕りカブトムシを捕り、木の根を枕に昼寝をしたりするのが常でした。
祖父から聞いた話によると、その山は昔はなだらかな丘に過ぎなかったのだそうです。昔まだ曾祖父母が生きていた頃、村人たちが協力しあって土や砂を盛り杉を植え、長い時間をかけて小山に育て上げたのだと。
謂れも、真偽の程さえも闇の中ですが、言われてみればその山は、どこか人工的な手の入った独特な均整が保たれているようでした。
たとえば杉林の並びや、岩石の転がり方、山全体が描く曲線一つをとっても、それぞれがある意図を持って配置されたかのように、どこか不思議な美しさを持っているのです。
この話を聞いた私は、幼心にダイダラボッチのことを思いました。ご存知でしょうか、山や湖を作ったとされている、天に頭が届くほど大きな体を持った妖怪のことです。
群馬に伝わる民話に、富士山、榛名山、浅間山の三山を作ったのはダイダラボッチであり、彼らは競って三山を作ったけれども、あと一息のところで富士山のダイダラボッチが勝ったのだ、という民話がございます。
その話を知っていたためでしょうか、子供が砂遊びをするように、ダイダラボッチがしゃがみこんで丘を山へと作り替えるさまを、当時の度々空想するようになりました。私は裏山を作ったのが本当はダイダラボッチだと信じていました。その名にあやかって、裏山を密かに「ボッチ山」と呼ぶこともありました。「ひとりぼっち」の「ボッチ」でもあったかもしれません。
ボッチ山で、あの日私はバッタを捕って遊んでいたのです。濃厚な草いきれがむっと立ちのぼるほど、湿気が多く日差しの強い日でした。私は汗まみれになって、バッタを追い回しては転がるようにあちこちを駆け回りました。虫取り網とバッタの入った虫かごを、何度も落としては拾ったことをよく覚えております。
どこへ行っても空調が存在しない事実すら、当時の私にとってはまったく嬉しい事実でした。
汗まみれになって泥まみれになっても、素っ裸になって庭のホースで汚れを流してしまえば済むのです。
目の回るような暑さの中で、その時の私は目の前にあるバッタをただ捕ることだけに夢中でした。まさしく夢の中のように、ほかの出来事に一切ピントが合わず、地には足がつかずに浮遊しているような、それはそれは不思議な心地だったのです。どこへ行っても同じ杉林が並んでいるような、ボッチ山の奇妙な光景も手伝ってのことかもしれません。その日はいつもよりも一層強く興奮して、殆ど憑かれたように四肢を闇雲に振り回していたような気がいたします。
そうしているうちにあっという間に時間が経って、日の暮れ始めたころのことです。
ふと我に返ってみると、なにか名状すべからぬ違和感が胸元に澱んでいることに気が付いたのです。
無我夢中のうちに大事なものをどこかに落としてきてしまったような……、何か恐ろしく膨大な質量の、遣る瀬ない喪失感のようでもございました。
その頃にはすでに、虫かごの中には大小さまざまのバッタが数十匹ひしめいておりました。採った自分自身でさえも、その姿を見て不気味に思ったほどです。
仕方がないので半分逃がしてやりながらも、私はその違和感の正体を必死に模索いたしました。
私が縋るような気持ちで思い浮かべたのは、意外にも母の姿でございました。
とうに記憶から無くなってしまっていたはずの、私が赤子の頃の母の姿です。しかしその姿は、姿と呼べるほど確かな輪郭を持っておらず、舗装されていない道の水たまりに映った影のように、危うく儚いものでございました。
次に、不意に消え失せた母の影の代わりに私は、父の姿を思い浮かべました。
いつもは私に対してにべもしゃしゃりもない父が、私に相向かって世の中のことわりを説いてくれた時のことを回想したのでございます。
すると荒波立っていた心が、いくらかの間は凪ぐようでございました。
しかし、父が私の名を呼ぶところを思い浮かべようとした途端、違和感の正体を知った私は心底恐ろしくなって震えあがりました。
私は自分の名を忘れていたのです。それも綺麗さっぱり跡形もなく……。
*
たとえ健忘症になったとしても、自分の名だけは忘れぬのだと聞きます。
認知症になった患者も、自分の名を忘れるのはかなり症状が進んだあとのこと。それほどまでに自分の名は、産まれた時から親や兄弟に繰り返し刷り込まれてきた根の深い記憶であり、人の自己形成の根幹を成すような重要な記憶なのでしょう。
先生は脳科学にも通暁していらっしゃるそうですから、釈迦に説法かもしれません。
しかしどれほどそうした事実が科学的に証明されていようと、あの時私は確かに自分の名を完全に失ったのでございます。
無名の一個人となった私は、しばらく頭を抱えその場に屈み、冷や汗を流し、暗闇の中で手探りをする想いで自らの名を捜索し続けました。思いつく限りの名を端から並べたり、祖父母や東京の友人が私の名を呼ぶところを順番に思い浮かべようとしたりしました。
しかしそれが徒労だと真に理解した時、幼い私の心を襲ったのは、最上の恐怖でした。両目からとめどなく涙がこぼれ落ち、全身が痙攣するようにわななくのを止められず、自らを抱き締める恰好で、恐怖に気が狂いそうになるのを堪えました。
その恐怖は、命の危機を感じた時に抱く「死への恐怖」によく似たものでした
「大げさな」と誰しも冷笑するかもしれません。それほどまでに、実に想像を絶する不可解なものなのでしょう。学知や教養のある識者でも、どれほど人の心中を正確に忖度できる賢者であってさえも、この恐怖を真の意味で理解することは、とうてい不可能なことでございましょう。
幼い心にも、広大な裏山のどこかにあまりにも大きな落し物をしてきた事実に、恐怖のみならず凄絶な罪の意識や羞恥心さえ感じておりました。自分の名を忘れたなどとは、決して人に話せることではないと。
もしも知られれば頭の弱い子だと蔑まれ、苛まれ、疎んじられ、周囲の全ての人々から迫害を受けるのではないかとさえ考えました。ですから私はひとしきり悩んで祖父母の家へ帰った後も、そうした一連の出来事を誰にも打ち明けることができず、恐怖に打ち震え続けたのでございます。
来る日も来る日も、朝餉や夕餉の用意された居間で、私は祖父母のどちらかが早く自分の名前を呼ばないものかと内心遑々としておりました。
しかし常日ごろから私と目も合わせないような祖父母が、わざわざ改めて私の名を呼ぶことなど非常に稀なことで、結局私は自分の名前がわからぬままに、信じがたいことですが、二週間もの時を過ごすことになったのでございました。
私はその間も形ばかりは虫取り網と虫かごを持ってボッチ山に通ったものですが、遊戯に熱中できる日などありませんでした。私とは何者か、私という存在に意味はあるか、そもそも私という存在は本当に在るものなのか……。
そんなことを、拙い語彙の中で必死に考え続けました。大抵の場合は途中で疲れて眠くなり、杉の根を枕にして日が暮れるまで眠っていました。
自らの名を失った二週間の期間は本当に辛く恐ろしいものでしたが、不思議とボッチ山で昼寝をしている時だけ、その時だけは、無名であることがむしろ心地良いような気がいたしました。
杉林のざわめきが、胎内に居た頃に聞いていた母の心音を思い出させたためでしょうか。それとも、杉の根の曲線が、赤子を抱く母のかいなのように、優しかったためでしょうか。
いずれにせよボッチ山での昼寝は、まだ自らの名も知らず、自己という概念さえ知らなかった赤子の頃に戻ったような、つかの間の平穏を蘇らせてくれました。
しかし夕時になって一度目が覚めると、再び底の見えない絶望の淵に沈んで、弱冠七歳の私は、毎夜人知れず涙を拭ったものでございます。
二週間経った早朝、家に父が迎えに来た時、床についていた私の体をゆすってその名を呼んだ時、どれほど生き返った心地がしたか知れません。
バラバラに解けた紙切れのようになっていた自己認識が、一つの糸に手繰られてキチンと綴じ直され、その時やっと「私」が「私」になったようでした。
そうだ、これこそが私の名だと、私は飛び起きるなり安堵のあまりしばらく号哭したほどでございました。
父はその姿を、父恋しさのあまり取り乱しているのだと受け取ったようでしたが、それもあながち間違いではございませんでした。
父が私の名を呼んだという事実だけではなく、父という確固たる存在そのものが、危うく揺れていた私の輪郭を取り戻してくれたのです。私は、神々しい我が父を仰ぎ見ました。喉の渇きに苦しむさなかキリストに一杯の水を与えられたような想いで……。
*
それからも私は幾度も祖父母の元へ預けられましたが、同じことは二度と起こりませんでした。
私はどちらかと言えば人より物覚えの良い子供だったと思います。ですから一層、あのようなことが起きた理由は不可解なままでした。
例の出来事以来しばらくの間は、東京へ帰ってからも、自分の名を書いたものを一つでも身につけていないと、安心して遊ぶこともできませんでした。
しかし何事もなく歳月が過ぎゆくにつれて、あの時の恐怖の記憶もすっかり消え去り、私の記憶の中であたかもはじめから無かったことのようになりました。人の心の仕組みというのは不思議なものです。
フランスの心理学者、ピエール・ジャネの説を借りるなら、人の心はいくつもの部屋を持っていて、その中を行ったり来たりします。忘れてしまいたいような忌々しい恐怖や痛みの記憶は、なるべく遠く離れた部屋へ隔離し、完全に幽閉してしまうのだそうでございますね。
しかし例え隔離せども幽閉せども、記憶はその時のままそこに存在しております。一体どのような切っ掛けで再び顔を出すかなどは、自分でさえ知れたことではないのでございます……。
そうして例の出来事をすっかり忘れおおせたような気がしていた、中学生の頃のことでございました。
私は当時、初恋に悩まされておりました。初恋相手は、同学年の男子の間でも高嶺の花とされていた、長いおさげ髪の似合う楚々とした少女です。
立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花……とは、まさしくああいった少女の形容でしょう。彼女の組と私の組とは教室が廊下の端と端ほど離れておりましたし、むろん口を利いたことは一度もございません。知っているのは少女の美しい顔かたちとその名と、時折廊下ですれ違う時に聞く、鈴のなるように高らかで儚い笑い声や話し声だけ。
今にしてみれば、なんと幼く浅はかな初恋でしょう。しかしお恥ずかしながらも当時の私は、彼女との交際を、果ては結婚までをも真剣に算段に入れて、彼女に懸想していたのです。
当時私が美術部の活動のあと家へ帰って真っ先にしていたことは、彼女の名をノートに書くことでした。
彼女の名を構成する四つの漢字を、繰り返し、繰り返し丁寧に書き連ねますと、不思議とその名が自分ただ一人の手中に収まったような気がしまして、只々、奇妙な征服感で胸が恍惚となるのでした。
彼女の顔かたちはもちろんですが、私は彼女の下の名が特別に好きでした。
その名は彼女の相貌によく似合ったとある花の和名でした。実を言うとそれは母の名と一字一句違いないものだったのですが、その事実が思いにどれほど影響を及ぼしていたのかは、未だに不明瞭なことでございます……。
実らない懸想を続けていた私でしたが、中学も卒業間近になって、ようやく彼女に愛の告白をすることを決断いたしました。
友人づてに彼女を裏庭に呼び出して、初めて彼女と面と向かって言葉を交わしたのでございます。はじめは、「やあ」だの「どうも」だの、意味の無い文句をうわごとのように呟くしかできませんでしたが、彼女がそれでも全てを包み込むように穏やかに微笑んでおりますのを見て、勇気づけられた私は意を決しました。
肝心の愛の文句は忘れてしまいましたが、彼女がその言葉を聞いて、戸惑いながらも白い頬をうっすらと赤く染めていたことだけはよく覚えております。
私を見る彼女の大きな瞳がかすかに潤む様子に、私はすっかり見惚れてしまいました。
彼女が発します「ありがとう」というたった一つのたどたどしい言葉に、天にも昇るような心地がいたしまして、私は益々彼女の虜となり、言葉を失って立ち尽くしてしまいました。その日は気怠くなるような曇天の日でございましたが、不思議と辺りは降り注ぐ光に満ち溢れているかのように感じました。
私がそうしてまごついている間、彼女もまた目を伏せ、私と同じくらいに恥じらっておりましたので、互いに何も言えぬまま沈黙が続きました。
しかし、それが所在の無い沈黙でないのは不思議な心地でございました。
そうしてしばらくの間が空いた折に、ふと彼女が思い出したように私に尋ねたのです。
「あなた、お名前は」と。
私は我にかえって返答しようとして、たじろぐことになりました。
薔薇色の世界は途端に色褪せ、本当に目の前が真っ暗闇になるのを感じたものです。
お察しでございましょう、私は再び自らの名をすっかり忘れてしまっていたのです。
*
幼いうちならまだ釈明のしようもあったかもしれません。しかし、当時十四歳でした。
その直後、私は少女を置き去りにして教室へ飛んで帰り、錯乱しながら自らの教科書に書かれたその名を発見し、安堵しました。以前のように二週間も自分の名を忘れたままというような大惨事には至りませんでしたが、十四歳の当時形成されつつあった自意識や自尊心に、あれほどまでに大きな傷を付ける出来事は外にございませんでした。かつてのような野性的な恐怖心よりも、羞恥心の方が勝ったのでございます。幼い頃と違って、いつでも名前を確かめる術があると心のどこかで判っていたためでしょう。
それからというものの、私は初恋の彼女とは目を合わせることもできぬまま、中学校を卒業することになりました。
そうした出来事は、爾後散々注意を払っていたにも関わらず、私の人生の中で数度に渡って起こりました。
ある時は美大受験のさなかに、ある時は絵を描くために遠方の山奥へ旅に出たさなかに。私はその度に深く狼狽し、自らを軽蔑し、当分の間は様々なことに手がつかなくなりました。初めのうちは時が過ぎれば忘れていた恐怖が、回数を重ねるうちに常日ごろから薄らと影のように付きまとうものになってゆきました。名前の忘却が、必ず何かしらの物事に深く熱中している時に訪れるものだと気づいて以来は、私が本当の意味で何かに没頭できる機会は殆ど無くなりました。
むろん私は、脳医学や心理学などの見地から原因が突き止められないものかと、さまざまの文献を読み漁ったものでございます。
医者に脳波や脳磁図も診てもらいました異常はなく、精神科医や心療内科医では「あなたが望むなら」といくつかの病名を提示されましたけれども、その病名を得たところで納得もできず、服薬やカウンセリングで治療が進むとは思えませんでした。
そうして自分の不可解な病と戦いながらも、二十歳を過ぎた頃に父の許を離れ、三十歳を過ぎた頃に、日曜画家として細々ながらも飯が食べられるようになりました。
西ノ宮先生のことを知り合いの画商から紹介してもらったのは、三十一歳の折のことでした。先述の、私の絵を買い取ってくれた画商です。いつも気難しく不幸そうな顔をしていた画商が、ある日を境に眉根を寄せずに快活と話すようになったのを見て、人の性根がこれほどまでに変わることがあるものなのかと、私は心底驚きました。
先生にはじめてお会いして、そのお人柄に触れた折、私ははじめて「もしかするとこの不可解な病も治るのではないか」と希望を抱きました。全てをただあるがままに包み込むような眼差しや、厳しくも決して他を否定することのない語調、そして泰山のように揺るぎない存在感。
今にして思えば、私は先生と出会って初めて、父性や母性とはいかなるものかということ知ったような気がします。
しかし私はすんでの所で先生に全てをお話し申し上げる勇気のない臆病者で、私が先生に仮初めの告白をして手に入れたものがやはり仮初めの平穏だったということは、昨年の治療からふた月経ち、父が老衰で亡くなった折に知りました。
私は深い痛哭に暮れ、やはりその時も自らの名を忘れていました。私の中には、恐怖でも羞恥心でもなく、茫然自失とした無気力さだけがございました。「父が居なくなってしまったら、誰が私の名を思い出させてくれるのだろう」と、幼子のように漠然と考えもしました。
父の葬式では長男の私が喪主を務めましたが、私は挨拶の度に自分の名前を確認しなくてはなりませんでした。その時だけはもう、何度自らの名を見ても、自らの名だと認識できなくなっていたのでございます。
父の納骨まで済んだあと、私は一枚の大きな油絵を描きました。かつて画商に称賛された絵よりもっとずっと大きなカンバスに、私はただ無名の一個人として、今この心の中にある景色をありのままに映したのでございました。
完成したその絵を見ると、不思議な気持ちになりました。
暖色を多く使って描かれた山の絵は、ボッチ山に似ているようでした。そして見ようによっては、優しかった母のかいなや、父の大きな背中にも似ているような気もしたのでございます……。
*
そうして私は、三十二になったこの折に、再び吾妻郡の祖父母の農家に舞い戻ったのです。
幼い頃と比べて農家の梁や木柱はひどく傷み、所有する稲田は他所に買われていました。
一家の主の祖父は亡くなっていましたが、今年米寿を迎えた祖母は変わらず健康で、家事の合間に切り絵などをして、日々を楽しみながら暮らしていました。
認知症の兆候が見られる祖母は、すでに孫である私の名前を覚えていませんでした。
ただ、昔よく家で預かっていた子供だということはわかるようで、私が住み込みで家の世話をしたいと伝えると、こころよく許してくれました。
それからというものの、日々祖母の身の回りの世話や、家事炊事、庭の手入れなどをする生活を続けてもう一年が経とうとしております。祖母は稀に私を呼ぶときも、ただ「坊や、おいで」とだけ呼びます。彼女が私の名を呼ぶことはこれから先もきっと無いでしょう。
私は相変わらず無名の一個人として、時折暇を見つけては画帳や画布を持って田園の風景画を描いたり、あの不思議な魅力を持つボッチ山へ行って、杉の根を枕に昼寝をしたりして過ごしております。
身の回りのものを全て処分してここへやって来た今となっては、私がそうしようと思わぬ限り、自らの名を確かめる術は一つもございません。
しかし先生、私を愚かだった思ってくださって構いませんが、どうか哀れだとはお思いにならないで下さい。自分の名を失った今、私はようやく真の幸福を手に入れたのです。
今こうして筆を走らせながら想いを、愚直に申し上げますのならば私は……、私はただ、自らの名も知らず母のかいなに抱かれていた赤子の頃に戻りたかった。
そうでございます。私の名は、かけがえのない母と父だけに所有される、唯一無二のものであって欲しかったのでございます。
*
私の話はこれまでです。管々しい身の上話を最後までお読み頂き、心の底から感謝申し上げます。
この手紙を書き終えたら、私はより人目に付かぬ山奥へ隠遁しようと考えております。
私の名を知る者が本当にただの一人も居ない山奥へ……。それゆえ、この手紙に差出人の住所氏名の表記がございませんことのご無礼を、なにとぞお許しください。
気候不順の折柄、先生のご自愛を切にお祈り申し上げております。
それでは……。
謹白
画人失名氏
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
