【幸せとは?(前編)】#問い2
このテーマは、昨年度6年生の担任をしているときに道徳の授業に考えたものです。皆さんは今、幸せですか。そうだとしたら何がそのような現状をもたらしていると考えますか。仮にもしそうでないとしたら、これから幸せになるためにどうするべきだと考えますか。
goo国語辞典で調べると「幸せ」の意味を調べると、【①運がよいこと。また、そのさま。幸福。】と【②その人にとって望ましいこと。不満がないこと。また、そのさま。】と出てきました。これらを参考に、
幸せ=人生の満足度 として定義します。
僕は、今年から自分の好きな教育について学ぶため大学院に進学しました。担任は大変ですが、子どもの成長を真近で感じ、見守ることができるやり甲斐のある仕事です。現職のときは、学級にいるときが本当に楽しくて教室を離れたくないくらいです(笑)もちろん、理不尽なクレームも何度も経験しました。自分に非があって改善のしようがあるものならまだしも、「いや、さすがにそれは自分を嫌いなだけでしょ・・・」ということがありました。また、保護者の力だけでは解決することができないのか学校外でのトラブルの仲裁に入ること、きちんと我が子に事実を確認せずに臆測だけで文句だけを言ってくること、関西弁が嫌いだと言われたこと(笑)、今思えば「担任にだって人権があるよ」って思います。でも、僕はそんな日々でも幸せでした。厳密に言うと、そういうときは辛いし、悔しいし、腹が立ちます。でも、教室で授業をしているとき、子どもたちと話すとき、遊ぶときどれも幸せなんです。
じゃあ、「今は?」って思いませんか。今は正直に言うと幸せではないです。それは、自分の心の満足度が低いからです。「やっぱり働きたい」と毎日思うし、「もしかして研究の道は向いていないのかな?」とも思います。でも、それは、自分のやりたいことや行っていることがまだ身を結んでいないからだと思います。つまり、その成果が可視化できていないし、実感できていないのです。
話を変えますが、昨日、久しぶりにスペンサー・ジョンソンの「頂きはどこにある?」を読みました。この物語は、谷間に住む不幸な若者が憧れの山の頂きに行き、偶然にもある老人かと出会います。その老人からある話をされ、若者の人生における考えが変化していくというものです。読んだことがある方も多いのではないかと思います。
外部の出来事はかならずしも思いどおりにはならない。しかし、心の中の山と谷は考え方と行動しだいで思いどおりになる
「なるほどな〜」と思ったのと同時に、このマインドは分かっているけど実践できないものでもありますよね(笑)30分程度で読めます!
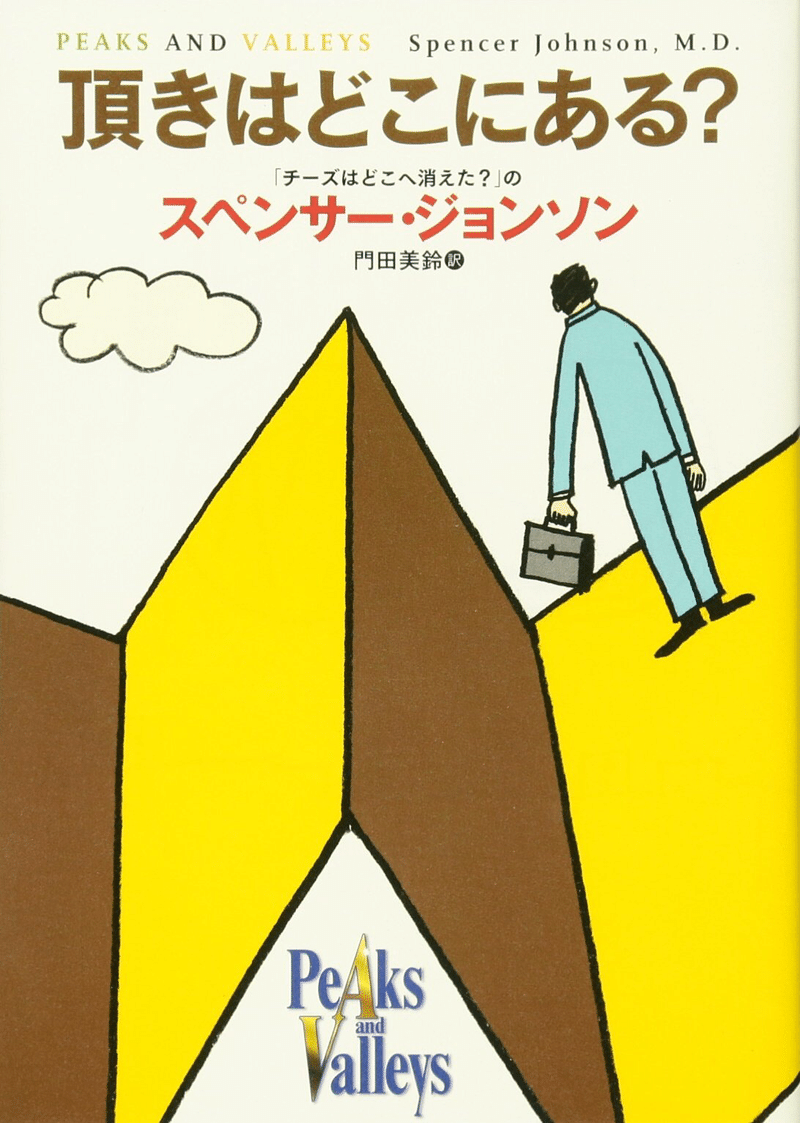
結論から言うと、
幸せとは、自分らしくあること
だと考えています。
絵を描くのが苦手なのに、それを毎日10時間しなさいと言われたら嫌になりませんか。他にも歌が下手で歌を歌うことに抵抗があるのに、歌手を目指して練習に励みなさいと言われたら絶望的な気持ちになりませんか。それは、自分の好きなことではないし、何より実現できる可能性がすくない、もしくは生産性のない行為だと分かっているからだと思います。これらは、その人らしさには繋がらないことだと言えるでしょう。だからこそ、幸せに生きるためには自分がじぶんらしくいられる好きなことやものを見つけることが大切だと思います。人は死ぬときほとんどの場合1人です。自分のことを大事にして、自分が幸せな気持ちで過ごすために向き合う時間を作ってみてはいかがでしょうか。(家族、恋人、友人、お金、全ての答えに正解・不正解はないはずです。自分の人生ですから。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
