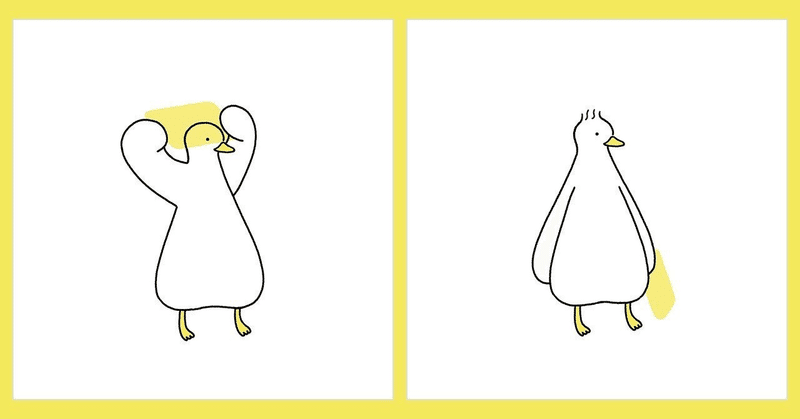
認知行動療法的な生き方「思っちゃダメなことなんてない」
学生の頃、私はまあまあ真剣にメンタルをやられていた。結果から言えば社会人になったら9割良くなったので、おそらくは自分の力でどうにもできない・後がない・金がないあたりが主なストレスだったんだと思う。
学生こそが青春、人生の夏休み、社会人になったら自由がなくなるだとか言う人がよくいるが、私はそうでもなかった。学生の頃は学びが多く楽しいことももちろんあったが、ずっと閉塞感や焦燥感を感じていたような気がする。社会人になってからの方が断然生きるのが楽だ。大変だけど、自分の人生を選びとって生きている実感がある。
でもそれがわかったのは、環境が変わった後のことだ。渦中はその世界が全てだった。
どうにもならなくなったとき、大学専属のスクールカウンセラー的な人に頼ったことがある。心療内科には行かなかった。お金がなかったから。
そこで認知行動療法というメソッドを知り、本当に簡単ないくつかのワークを行った。もうカウンセラーの先生の名前も顔も忘れてしまったけど、このときに得た学びはその後の私の人生でひとつの指針となり、危ないところで助けになってくれた。だから認知行動療法は、共感覚と並んで私が生涯にわたって学び続けたいテーマのひとつだ。
今日はその認知行動療法について、私なりに理解したこと、役に立っている考え方などをメモしておきたいと思う。
よくない悪魔は、大抵の場合突然やってきて、正しく判断する力を簡単に奪っていく。元気なときにしっかり整理して、いざというときに手にとれる距離に置いておくのが良いと私は思う。
認知行動療法とは
生きていく中で、自分の外からの刺激に対する認知→感情→身体反応→行動の一連の流れは常に起こっている。この流れのうち、最初の「認知」と、最後に起こす「行動」にフォーカスする方法の総称を認知行動療法という。と私は解釈している。
療法、とついているので、一連の流れが自分にとって良くないパターンに陥ったときに、このフレームワークに沿って考えることで問題を解決したり、気持ちを楽にしたりしようということだ。
例えば、簡単な例で言うとこういうこと。
コップを落として割ったというできごとに対して
①またやらかした!私ってやつはいつもそうなんだ!人間のクズ!(認知)
②悔しい、情けない(感情)
③喉が詰まり動悸がする(身体反応)
④ストレスからの爆食い(行動 = できごと)
⑤また食べたわ。太る。ダメ人間だ。(認知) 以下続く
この場合、自分でコントロールできるのは認知と行動。それ以外は、コントロールはしないが観察する。
うつなどの治療の際、一般的には認知の悪い癖を正していくことがメインになるようだが、これはなかなか難しく、成果が得られるまで長い時間がかかるものだと思う。簡単に認知のゆがみが治るなら困っちゃいないのだ。
当時の私は認知の癖を治す努力をしつつ行動を変える練習を優先して行い、さらにコントロールできない部分に関してはひたすら客観的に観察するというワークを通して、認知行動療法の入り口を体感していった。
観察する
②「感情」と③「身体反応」はコントロールできない。できないながらも、できるだけ客観的に言葉にしてみる。
悲しい?というより悔しいかも。あと片付けがめんどくさいから嫌な気持ちになっている。
あー、今喉が詰まっているな。冷や汗が出ているな。3分くらいで収まった。
ワークとして取り組むときはこれらも記録をつけた。普段は記録は取らないが、頭の中で言葉にするだけでもけっこう効果があった。悪いスパイラルに入る前に立ち止まるような感覚だった。
ポイントは、感情にフタをしないこと。そしてそう感じてしまった自分のこともそのまま観察する。嫌な気持ちになっちゃいけない!などと思いがちなところを、ただ観察するためにそのまんま受け止める。これが結構難しい。
感情そのままを書き表すとすごい性格悪い奴になってしまうこともよくある。でも、あなたの頭の中を覗ける人はいない。行動はダメなことがあっても、思っちゃいけないことなんてないのだ。
褒められたら嬉しい!そうでしょそうでしょ!
邪険にされたらがっぺむかつく!
それでいい。頭のメモにそのまま書いておく。がっぺ、むかつく、と。
ジャッジはしない。こう思う自分は悪くもないし善くもなく、ただの自分だ。
良い行動の準備運動
④「行動」を変えるにはどうしたらいいか。これは、フラットな状態のときに、自分がやりたいこととか楽しいことをたくさん考える練習をした。
認知行動療法が必要ない人にはわからないかもしれないが、「お金がないから」「今は忙しいから」「私なんかが」などいろんな理由をつけて、楽しいことを先延ばしにする癖が私にはあった。
とにかくどんなことでもいい、何のしがらみもなかったら何をしたいか、バスの待ち時間で3つ頭に浮かべるなど決めて練習した。とにかく瞬発力が大事だ。
お腹いっぱい好きなだけイクラが食べたい。
クーラーを効かせた部屋で昼まで寝て夜までゼルダやりたい。
好きな家具を買っておしゃれな部屋に住みたい。
好きなこと・やりたいことを普段から思い描いておくと、いざというときにスパイラルにはまる前に気持ちをポジティブにもっていけるようになる。らしい。結果として同じ行動になったとしても、よし!イラつくぜ!チョコパイ2個食べちゃうもんね!と言って食べるのは心が健康なので良い。⑤に進みにくくなるから。
準備運動なしではうまく走れないように、好きなことをやるにもアップがいるのは衝撃だった。我慢することに慣れすぎていて、なんならそれが美徳だとすら思っていたから。
ポイントは「何のしがらみもなかったら」を頭につけること。これは準備運動なので、実際にやる必要がない。カロリーもお金も気にしないで、顔くらいあるでっかいハンバーグを食べたくなろう。
認知の歪みを正していく
①の認知の癖を治すのは、根気よく・論理的に反証を述べていく方法をとった。これは難しかったが、まずは自分の気持ちをそのまま記録につけることで何個か典型的なパターンがあることを指摘してもらえた。私が陥りやすいのは次の4つだった。
・過度な一般化(いっつもこうだ!)
・0か100かの極端な思考(今日失敗したからダメ人間だ)
・予期不安(また同じことが起こったらどうしよう)
・決めつけ(この苦しみは終わらない。ずっとこのまま)
いっつもこうだ!に対しては、「いやだいたいはうまくできてるからいっつもじゃないですよね」
今日失敗したから私はダメ、に対しては、「今日、失敗以外の部分は誉められるところもあったんだから、ダメ人間度は10%くらいでいいんじゃないですかね」
また同じことが起こったら、に対しては、「起こるとは限らないことに今から備えても具体的にやることないからとりあえずいいのでは?」
ずっとこのままかもしれない。に対しては、「今日のことだけでそんな判断ができる根拠ありましたっけ?そんなことなかったですよね?」
私の歪んだ認知に対して、ひろゆきもびっくりの反証を述べていく先生。そう、これはパターンなのだ。わたしはテンプレート。反証もまたテンプレートだ。歪んだ認知がやってきたら、パターンを見極めてすかさず反証を唱える。呪文のように。
「気の持ちよう」をもっと理詰めでやったらこうなるのではないか。ポジティブシンキングとか引き寄せの法則とかはなんだかふわふわしていて性に合わなかったが、認知行動療法は入力のパターンを変えて出力された結果を記録する実験だと思えたのが良かったのかもしれない。側から見たら同じでもいい。私が楽になれるならなんだっていいのだ。
認知の癖は今でもまだ完全に治ってはいない。それでも、あの頃感じていた絶望感に比べたら断然楽勝だ。100点じゃなくてもいい。大学なら75点で単位は取れる。だったら4人にひとりは合わない人がいてもオッケーだし、4日に1日最悪な日があっても合格だ。
それでも本当は全部全部うまくいってくれよって思ってる。
そしてそう思う自分を観察している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
