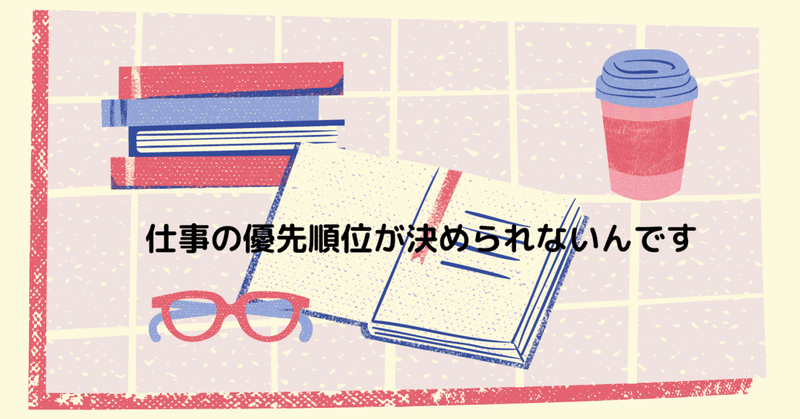
優先順位をつけるには「経験」と「賢さ」が必要
「○○先生、仕事の優先順位を間違えているんじゃないの?」 初任の頃、学級通信を書いていた私に先輩教師が言われた言葉である。
今回は「仕事の優先順位」について考えてみたい。
働き方改革においても、「仕事の優先順位」という言葉がよく使われる。「仕事の優先順位を考えることで、業務の効率化を図ることができる。」「緊急で重要な仕事になる前に、早めに仕事に着手することが必要だ。」「優先順位をつけて業務の削減をしなければならない。」などいろいろな声が聞こえてくる。
「優先順位」を決めるのは何だろうか。
組織の中で互いに連携して仕事することを踏まえると、優先順位は「仕事の種類」によって決まると考える。
仕事の種類を大まかに2つに分けると、①学年・学校全体に関わる仕事、②個人完結型の仕事である。
優先順位の高い仕事は、①学年・学校全体に関わる仕事である。このような仕事を後回しにしてしまうと、自分がボトルネックになり、他の人の仕事が滞ってしまう。この滞りは連鎖することになり、誰かの時間を奪ってしまうだけでなく、学年・学校に大きな迷惑をかけてしまうことがある。「自分のことばかりしかしない。」と思われるだけではなく、仕事ができない人の評価を下されやすい。
①個人完結型の仕事とは、基本的に他の人の力を借りずとも、できてしまう仕事である。例えば、学級通信の作成、教材研究、学級設営等などである。極端に言うのならば、やらなくても他人(同僚)には直接的に迷惑がかからない仕事である。
冒頭の先輩教師の指摘は、教務主任から依頼されたアンケートを締切日までに提出せず、学級通信の作成、つまり個人完結の仕事をしていたことへの指摘であった。今となってはよく理解できる。
確かに、組織で仕事をすることを踏まえると、基本的な優先順位は①➁である。しかしながら、①が多すぎて②に手が回らない、時間が取れないことも大きな問題がある。なぜなら、➁には、子どもの成長や学力向上に関わる「学級経営や授業」が含まれているからである。
組織ではなく、子どもへの還元という視点でみると「学級経営や授業」の優先順位は高いはずである。多くの先生方は、形骸化したアンケート調査に回答するより、授業の準備に時間をかけることの方が大切だと思われるだろう。
つまり、仕事の優先順位は、どのような視点でみるかによって変わってくるのである。しかしもそれが刻々と変化するのである。このことが優先順位を決めることを難しくしていると考える。
限られた時間の中で、状況をみながら「優先順位」を決めることは、ある程度の「経験」、そして、仕事の軽重を見分ける「賢さ」(クレバーの方)が必要になると考える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
