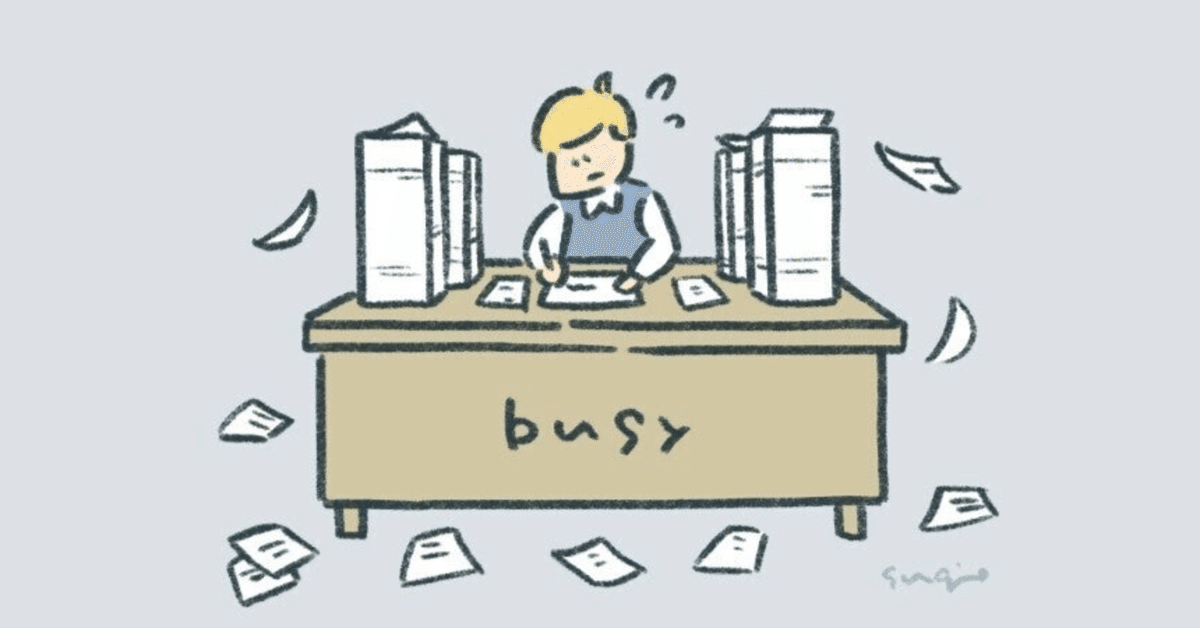
天邪鬼の眼☕️通信~学年別時数表+単元配列表|教務&学年主任サポート~
新しい年度を迎えるにあたって、年間の授業時数を算出する業務があります。1年間の年間の行事予定など次年度に予定されている入学式、健康診断、遠足、林間学校、運動会、卒業式などで要する時間を除いた年間の総授業時を日々の教育活動の時間として落とし込んでいくものです。
毎日毎日どれだけの授業時間を確保するのか、各教科に充てる時間を割り振り、文部科学省が示す、標準授業時数を確保するように計画を立てるいわば、学校教育活動の時間を確保する根底にある計画です。
ちょうど、超多忙な年度末、年度初めに係る仕事になると思いますので、少しでも業務の軽減につながることになれば嬉しく思います。
職場で年度末になると耳にしていた言葉
— Itten | 働き方改革研究 (@KazItten) January 19, 2023
1月 行ってしまう
2月 逃げてしまう
3月 去ってしまう
新しい年を迎えていたと思ったら、1月も下旬
この短い日々の中に、年度末を迎え山盛りの仕事
余程、先を見越して計画的に取り組まないと😵💫
こうした超多忙な年度末にこうした業務も押し寄せてきます。
大抵は、教務さんが、こうした仕事を担っていると思います。各学年にもまたがる部分もあり、そのあたりは格が年の主任の先生がその計算をしているのが一般的かと思います。そうした面倒な計算を自動化して、少しでも”楽”をできるようにしたシステムをご紹介しておきます。
触るまでに面倒を感じて、既存のもので済まそうとする力学は、学校にありがちなことです。それ位、新しいことを取り入れたり、覚えたりすることに割く時間すらないのが、リアルな学校の姿だからです。
とはいえ、働き方改革の第一歩目は、機械にやってもらえることは機械にまかせる。つまり、自分が手を動かさずにできることはできる限り、手放し、アウトソースすることです。
こちらのシステムを利用していただくことも含め、働き方改革のヒントになることを願っています。
<特徴>
教務担当が作成する「年間時数予定表」(いわゆる下駄箱)のワークシートで,モジュールに対応したもの。今回は、単元配列表作成機能を追加。次のシートで構成されている。
①年度選択で年間カレンダーを自動生成 ※2027年度まで対応(夏季休業期間が2020年度継続想定)
②設定した基本週時数表を基に曜日別時数表を自動生成
③モジュールを記号入力で自動計算(1/2h→a、1/3→b等,3つまで設定可)
④各週の教科別時数を自動配分(要手修正、モジュール時数は最後に追加)
⑤1枠に異なるモジュールの混在可(2つまで),毎日モジュールにも対応(週5回まで)
⑥行事名と時数はリストより選択入力(要事前設定)
⑦印刷では時数表をA3横1ページに集約。2ページ目は学期別の詳細集計あり。
⑧「単元配列表」作成機能を追加。単元名と時数をリストより選択入力できる。
⑨同時に配布した「年間行事予定表」から入力した時数や休業日等の設定を自動コピーできる。
⑩別の「学年別時数表」から入力済み各データを自動コピーできる。
こう書き連ねると、使いこなすことに抵抗も感じてしまうかもしれませんね。なかなか教務や学年主任の先生方に向けてこうしたことを紹介するような機会、研修もありません。
そんな機会を設けて、ハードルをさげ利用してもらったり、楽をしようという考え方を展開したり、働き方改革の一助になればと思っています。
ご依頼があれば、システムの配布と合わせた使い方研修のようなものができれば、ハードルはさがるのでしょうが、その時間の確保もままならないところですね。ご興味がありましたら、DMでも構いませんのでご連絡ください。
学校現場では、なかなか細かいシステムまでは共有がなされておらず、その学校その学校で使われてきたものが踏襲されることが多いと思います。こうした方が便利だと思っても新しく何かを組み上げる時間を手元の仕事に使って業務を進めたい気持ちが優先するはずだからです。例えば、教務や教頭のように学校全体の運営に関わる手間のかかる資料を作成することでもかなりアナログ的に仕事をしてそれなりの時間をかけている例をたくさん目にしてきました。しかし、その仕事に就く期間も短ければ、2,3年で切り替わることもあります。そうすると、楽になることを目指して、手間をかけて仕組みを構築するのはなかなか手掛けられません。そんな風にして面倒なやり方でも学校学校で使われていたものが利用されてくことも少なくありません。ましてや、PCを活用するとなるとそこにも大きなハードルが生じてきます。そんなことで、システムの共有化が進んでいないのではないかと思います。
しかし、有効なシステムは、簡便なものでも自治体内の学校で共有すれば、どこに行っていも同じように使えて新しく何かを覚える苦労も減ります。また、続けて使用していれば、経験者も増え、システムの活用自体も浸透していき、益になることが多いと考えています。ただ、既存の流れでは、そうしたことがなしえていません。システムの共有には、初期の段階で研修等も必要になるかもしれませんし、全体を俯瞰してコンサル的にアドバイス、助言するようなことで形作れたらよいのではないかと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
