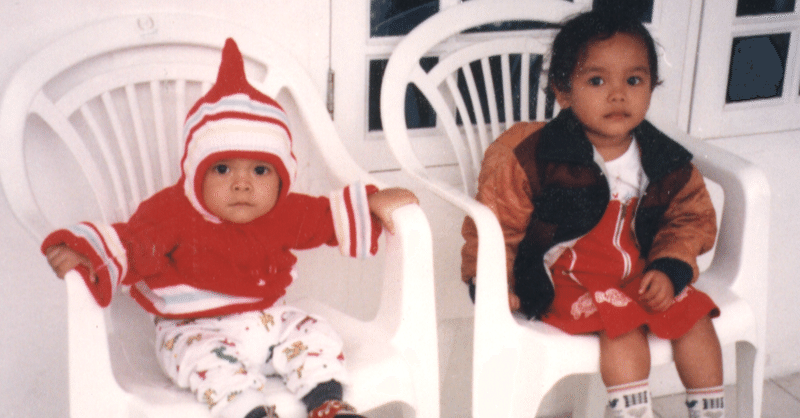
自分を知る時
マタイ26:69-75
いざという時に自分がどう行動するのか。
いろいろな危機管理の想定はありますが、個人の危機管理は、なかなか難しいものです。いざという時に、自分がどうするかわからない、というところが正直なところ。
もしかしたら、その時の姿が、自分で知らなかった本当の自分かも。
そうした記録が、福音書にあります。一番弟子を自認していたと思えるペテロの失敗談が赤裸々に記されているのです。イエス・キリストの一番弟子でもそうなのか、と、安心させてくれるための物語かと思えるくらいの内容です。
でも、福音書を最後まで読み、続きの記録を読むと初めて、この大失敗経験があって、本当の自分を知り、本当の力を発揮するための準備ができたのだ、とわかります。
ペテロは外で中庭にすわっていた。するとひとりの女中が彼のところにきて、「あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だった」と言った。 するとペテロは、みんなの前でそれを打ち消して言った、「あなたが何を言っているのか、わからない」。
そう言って入口の方に出て行くと、ほかの女中が彼を見て、そこにいる人々にむかって、「この人はナザレ人イエスと一緒だった」と言った。 そこで彼は再びそれを打ち消して、「そんな人は知らない」と誓って言った。
しばらくして、そこに立っていた人々が近寄ってきて、ペテロに言った、「確かにあなたも彼らの仲間だ。言葉づかいであなたのことがわかる」。彼は「その人のことは何も知らない」と言って、激しく誓いはじめた。するとすぐ鶏が鳴いた。
ペテロは「鶏が鳴く前に、三度わたしを知らないと言うであろう」と言われたイエスの言葉を思い出し、外に出て激しく泣いた。
マタイによる福音書26章69-75節
1.女中の一言におびえるペテロ
「たとい、みんなの者があなたにつまずいても、わたしは決してつまずきません」、と豪語を放ったペテロは、ただ一人、イエス・キリストの裁判が行われる邸宅の庭に入り込みます。
多勢に無勢。
さすがのペテロでも、心細かったかも。
それ以上に、やはり官憲に捕まったらどうなるかわからない不安が、心を覆っていたかもしれません。
そんな時に、突然、突き刺さるような声が聞こえてきます。
「あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だった」
女性の声でした。普段だったら、女性の非難めいた声だったとしても、さほど気にしなかったペテロかもしれません。女性には、公的な訴えをする権利はありませんでしたし。それに、イエス・キリストと共に歩んだ3年以上の期間、女性がけっこう身の回りで活躍するのを、ペテロは見慣れていたはずです。
でも、この一言に、なぜか飛び上がるほどに驚いて、思わぬ返事をしてしまいます。みんなの前でそれを打ち消して、「あなたが何を言っているのか、わからない」と言ってしまうのです。
次が、自分を知っている風なものの言い方をした女性の声。
「この人はナザレ人イエスと一緒だった」
女性一人が相手でも、心に大風が吹き荒れたようにざわついたのが、今度の一言は、周りの人々、みんなに聞こえるように話されたのです。当然、多くの男性もそこにいます。
そこで彼は再びそれを打ち消して、「そんな人は知らない」と誓って言ってしまいます。「誓って」は、まさに「神に誓って」。ユダヤ人にとっての「誓い」は、神の呪いを受けてもよい、とのメッセージでした。
二度あることは三度ある、か、三度目の正直、か。最後は、「激しく誓」って、「その人の事は何も知らない」と、より強く、よりはっきりと、嘘を言ったら神に呪われてもいい、自分は無関係だ、と大声で叫んでしまったのでした。
2. 泣き崩れるペテロ
今度は、人の声ではなく、鶏の声を聴くのです。
ようやく、自分がついさっき聞いたばかりの言葉を思い出します。
イエスは言われた、
「よくあなたに言っておく。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らないというだろう」。
ペテロは言った、
「たといあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは、決して申しません」。
マタイによる福音書26章34,35節
そして、人々のいる庭を飛び出して、激しく泣くのでした。
知らないなどとは決して言わない、と啖呵を切ったのに、見事にそれを破ってしまった自分が情けなかったのでしょうか。
女性の声一つにおびえてしまった事への無念さでしょうか。一番弟子を標榜していたのに、いかに自分が小心者だったのか、それを気付かされての悲しみだったでしょうか。
ペテロは自分のことを悔やんだだけではなかったのだろう、と思います。鶏の声を聴いて思い出したのは、自分の強がりの言葉ではなく、イエス・キリストの言葉でした。ペテロは、イエス・キリストを愛していたのを自覚したのでしょう。それなのに、自分から、裏切ってしまった。それが悲しかったのだろうと思うのです。
3.本当の自分を知る
イエス・キリストを愛していたのに、裏切った。自分の弱さを知るとともに、自分の内に本当に存在していたイエス・キリストへの愛を、知ることになったのか、と思えるのです。
自分の弱さ。
ペテロが、この時までイエス・キリストについてこれた「力」は、自分の頑張りだったのかもしれません。
その延長で、「あなたがたは皆わたしにつまずく」と言われれば、「たとい、みんなの者があなたにつまずいても、わたしは決してつまずきません」と答え、「今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らないというだろう」と言われると、「たといあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは、決して申しません」と答えていたわけです。
自分の弱さを知る時に、ずっと歩み続けるために本当に必要となる力に気がつくようです。
ペテロにとっては、イエス・キリストを愛していることが、力となっていきます。
弟子たちにとって、キリストへの愛とは何だったでしょうか。キリストと一つであること、共に歩むことへの希求です。
スタートは、そうではなかったかもしれません。「キリスト」は、イスラエルを救い、国を再興させてくれる偉大な王だ、と、信じて、仕えることから始まったのでした。けれども、3年以上にわたってキリストの身近にいて、その愛を感じないではいられなかったのです。
もしかして、ペテロは、イエス・キリストへの愛を、ずっと自覚していなかったかもしれません。自分の熱血さ、熱心さで、ついてきているんだ、というつもりだったのでしょう。でも、咄嗟の出来事で口からついた言葉、そして、思い出した言葉。
キリストを裏切ってしまった事への後悔は、キリストへの愛を自覚させることへとなったのです。
マタイの福音書では、ペテロの個人的な記事は、これが最後となります。不面目な終わり方ですが、それをよしとしているような感じ。隠さなければならない失敗ではありませんでした。むしろ、公開すべき失敗。それによって自分を知り、最後まで走り続けるためのターニングポイントがある、という模範でした。
イスカリオテのユダとは決定的に違っていたのです。
神のみこころに沿うた悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。
コリント人への第二の手紙7章10節
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
