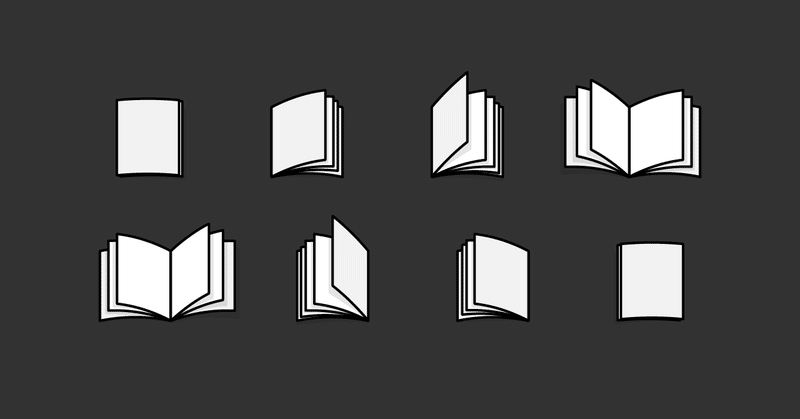
ウクライナ情勢を理解したくて3月に読んだ本4冊
2月末、ロシアによるウクライナ侵攻に目を疑い、大きな衝撃を受けた。自分が生きている時代に侵略戦争が発生したことに呆然とし、何を考え、どう行動すれば良いのか分からなくて途方に暮れた。そんな中で、知ることから始めようと本を手に取った。読むことで少しずつ、考える足場が出来たように思う。もちろん完成していない。これからも読み続ける。
ひとまず3月に読んだ4冊を記録する。
①「NATOの教訓」
ウクライナ出身の論客グレンコ・アンドリーさんの著作。PHP新書。NATOに焦点を当て、その流れで日本の国防の在り方を論じた本だが、ロシアやウクライナについても触れられている。比較的短時間で読める。
侵攻直後で、まだ書店でのフェアも突貫工事だった時期に紹介されていた。結果的に、素早く、かつポイントとなる要素を頭に取り込むことに役立ってくれた。
ウクライナ情勢に直接関連しない項目も多い。しかし、例えばロシアが近年、憲法を改正し、明らかに領土拡張を想定した記述になっていたとの指摘は、今回の事態がある種「計画的」だったことを示すものであり、ロシアの本質的な「凶暴性」を感じた。
NATOという軍事同盟がロシアに対して抑止力になり、NATOに加盟するバルト諸国はこのおかげで小国ながらロシアの侵略を免れている。集団安全保障体制の威力を感じるとともに、今後ともNATO加盟が難しくなったウクライナの安全保障をどうすればよいのかという疑問も浮かんだ。
②「ハイブリッド戦争」
テレビニュースの解説でもよく拝見する廣瀬陽子さんの著作。講談社現代新書。ロシアの軍事戦略に焦点を当てた本で、タイトルのハイブリッド戦争がキーワードだ。
字の見た目的にはSNSなどインターネットとリアルの戦闘を混在させた戦争が思い浮かぶが、本書を通読するとその本質は「平時と戦時のハイブリッド」だと言えると思う。つまり、戦争だけが戦争ではなく、戦争でない時間空間もまた戦争的に捉え直すという考え方だ。
具体的には、ロシアは米大統領選でヒラリー陣営が不利になるようなフェイクニュース工作に加担したとされる。これは、トランプ氏が台頭することで、米国の国内情勢を不安定化させることが出来ると踏んだからだ。つまり、ロシアにとっては平時の米国を揺さぶることが「戦争」なのだった。
そう考えると、今回のウクライナへの侵攻も、NATOへの揺さぶりをかけることや、ウクライナ国内を不安定化させるとこそのものが狙いかもしれないと考えられる。「火種」を仕込むこと自体が目的というわけだ。バイデン政権が何もできない印象を引き出し、米国の影響力を相対的に低下させる意図もあるかもしれない。このように、軍事攻撃の意図も「ハイブリッド」的に見る視点が本書によって獲得できる。
③「物語 ウクライナの歴史」
元駐ウクライナ日本大使黒川祐次さんの著作。中公新書。一時期どの書店でも品切れで、かなり探し回って入手した。今は増刷され、手に入りやすいと思う。
そして、探し回る価値ある一冊だった。ウクライナの歴史、文化、地政学的立ち位置などが網羅されている貴重な本だ。特に、文化的な豊かさが愛を持って語られている点が稀有である。
本書を読むと、ウクライナがウクライナとして国家的に確立していた時期は比較的短く、だからこそ「国を守る」ことに対して強い意識があるのではないかと思わされる。国としての歴史が浅いのではなく、キーウ公国など大国の歴史は深いが、その分侵略・占領を受けた時期も相応にあるということである。
たくさんの芸術家や文豪を生んだウクライナ。ゴーゴリやチャイコフスキーはウクライナにルーツがあり、スプートニク計画の技術者も輩出したそうだ。これからも国際的に重要な存在になることは疑いない。
そんなウクライナにいち早く平和と平穏が訪れてほしいと願わずにはいられない。
短いが、個別の感想も書いた。
④「戦争の文化」
「敗北を抱きしめて」で有名なジョン・W・ダワーさんの著作。岩波書店。上下巻で分厚いが、文章が上品で、読みやすい。
本書はウクライナ特集では必ずしも取り上げられない一冊だと思うが、戦争を真正面から捉えた点で関連性は深いと言えると思う。
たとえば、本書では真珠湾攻撃や911テロが米国の「恥」であり、敵への「憎悪」を招く行為として語られ、その言説を梃子にして日本やアフガニスタンへの攻撃に踏み切ったことが指摘される。これは、プーチン氏がウクライナ東部の情勢や「NATOの東方拡大」に関してロシアの脅威を掻き立て、ウクライナをナチスドイツに見立てて一方的に攻撃した過程と重なって見える。
原爆の使用には、巨大なテクノロジーを使ってみたいと言う抗うことの難しい科学の魔力があると指摘されているが、これも、超音速の最新兵器を使用したロシアの姿に重なる。つまり、「戦争の文化」はやはり我々の周りにつきまとうということ。それだけ強固なのだ。
だからこそ、戦争の文化について考える意義がある。本書は本質的にウクライナ情勢を理解するための一助であると言えると思う。
本書も感想をまとめた。
〜〜〜
繰り返す通り、まだまだウクライナ情勢を理解できているわけではない。あくまで「理解したくて」読んだ本であり、その営みは今後と続けていきたい。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
