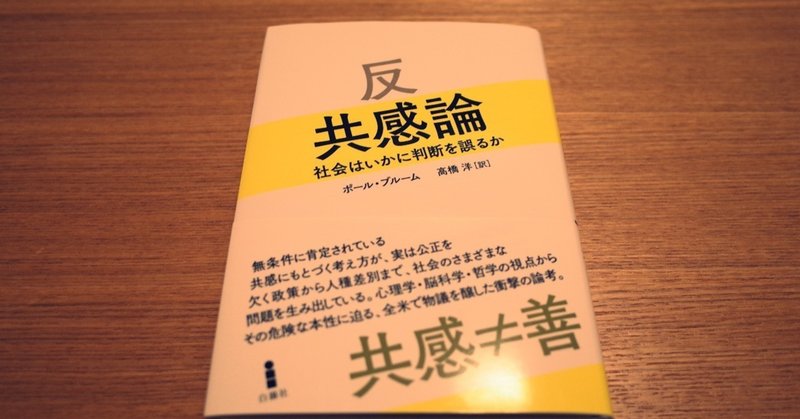
読んだ本たち②ー言葉を分けてみる
最近読んだ本たち。タイトルはトンデモ本、逆張り本みたいだけど、どちらも頭を刺激するいい本でした。無意識に使っている言葉を吟味して「腑分けする(分けてみる)」ことの大切さを説いているのが共通しました。
・「反共感論 社会はいかに判断を誤るか」(ポール・ブルームさん、高橋洋さん訳、白揚社)
共感はスポットライトだ。人の感情を揺さぶって、様々なアクションを呼び込む。少し前に海を渡った難民の子の遺体が無残にも海岸に打ち上げられた写真が報道された時、世界中で議論になった。裏を返せば、スポットライトは「ある場所」にしか注がれない。その子の写真が話題になる以前/以後に難民問題を議論する人は決して多くはないと思うし、その子のことを考えている時、ほかの理由で窮地に陥っている子のことを考えるのはなかなか難しい。
情報過多の時代において、スポットライトは奪い合い状態になっている気もする。いろんな場所から「共感してほしい」というメッセージが発せられる。でもスポットライトは全てを照らせない。そして強力であるからこそ、光を当て続けるのは疲れてしまう側面もある。
対して思いやりは、もっと柔らかい。強力ではない分、共感より広く注げる。共感しなくても思いやりを発揮することもできる。例えば医者は、患者に共感しすぎれば患者の体を切り裂くメスを握れはしないだろう。本書によると、チンパンジーが苦痛を感じる仲間を慰める時、その表情は特に普通で、理性的に相手に必要だからやっているという感じらしい。本書は共感を否定するわけじゃない。でも確かに、思いやりと分けて考えると、もう少しうまく社会を回せそうな気がする。
・「友だち幻想 人と人の〈つながり〉を考える」(菅野仁さん、ちくまプリマ〜新書)
一番グッときたのは「やりすごす」という話。学校では「みんな仲良く」と教わる。なんだか最近「つながり」が強調されている気がする。でも、「つながり」とは果たして「仲良くする」ことなんだろうか。
実は「みんな仲良く」より「仲良くなれない人ともなんとなくうまくやる」ことの方が大切なんじゃないか、というのが本書の指摘。そのためには恨みや反感、嫉妬といった負の感情をやりすごして、自分よりできる誰かを「あの人はあの人で私は私」と思えたほうが楽だと教えてくれる。つまりこのフレーズ。
要は、「親しさか、敵対か」の二者択一ではなく、態度保留という真ん中の道を選ぶということです。(p92)
この「やりすごす」というのは汎用性の高い概念な気がする。辛い状況、納得のできない現状もやりすごしてみたっていいかもしれない。いますぐに「いい」「悪い」で分断してしまうこともないのかもしれない。「生きる」という言葉には「納得して生きる」「不満を抱きながら生きる」のほかに「やり過ごしながら生きる」もあるのかも、と思った。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
