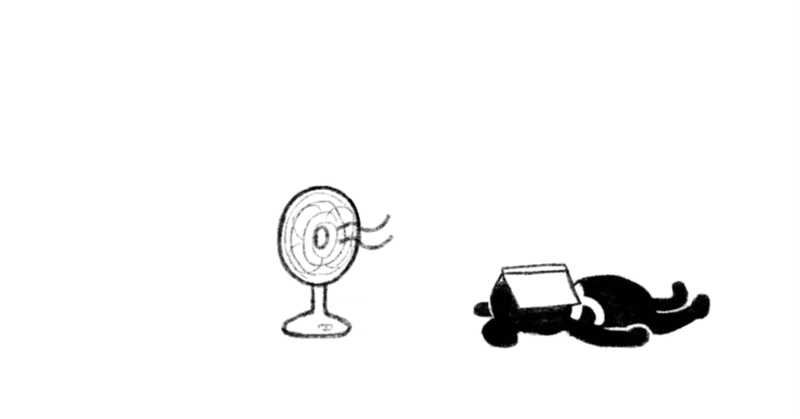
2022年上半期に読んで胸に残った本10選
2022年上半期も、たくさんの素敵な本に出会いました。その中から特に胸に残ったおすすめの10冊をピックアップしご紹介します。小説4点、ノンフィクション6点。長引くコロナ下の日常を捉え直す作品や、スケールの大きな超大作、視点を劇的に変える科学モノなど、いずれも世界の窓を少し開いてくれ、新しい風を心に吹き込んでくれる本たちです。
①「地図と拳」
「ゲームの王国」で日本SF大賞を受賞した小川哲さんの最新作。本編600ページ超のいわゆる「鈍器本」ですが、読み始めると止まりません。
舞台は満州。日露戦争前夜の1899年から、第二次大戦終戦後の1955年までの半世紀を描き、SF作品としても、歴史小説(歴史改変小説)としても、青春小説としても、ミステリーとしても大作であり傑作。編集担当者の方が「世界文学が誕生した」とツイッターに投稿されていましたが異論はありません。紛れもない金字塔。2022年は「地図と拳」が生まれた年として記憶されるのではないでしょうか。
群像劇なのに、一人一人のキャラクターが主人公クラスの輪郭を持ち、はっきりしたキャラクターの分だけ背後に伸びる影も大きい。日本の「戦争加害」という重いテーマに正面から立ち向かった骨太な物語でもあります。これから再び巡ってくる終戦の夏に読むにはぴったりかと思います。集英社、2022年6月30日初版。
感想記事はこちら。
②「なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない」
臨床心理士の東畑開人さんが、紙面上でカウンセリングを再現したユニークなノンフィクション。しかし本書は自己啓発本とは違い、悩みの解決策を示すものではありません。むしろ「じょうずに悩む」ための「補助線の引き方」を教えてくれる。
補助線を引いたところで問題は解決しないけれど、五角形が三角形と四角形に分解できるとわかれば、途端に取り組みやすくはなる。「馬とジョッキー」「働くこととと愛すること」など、その補助線が独特で、どこか温かい。
上半期に読んだ本を思い返した時、この本の背表紙を見返すと少し心がホッとしました。お守りのように本棚に鎮座してくれている、そんな本。新潮社、2022年3月15日初版。
感想記事はこちら。
③「この道の先に、いつもの赤毛」
米作家アン・タイラーさんが独身中年男性を主人公に描くヒューマンストーリー。甘さを含みながらビターで、ほどよいホットコーヒーのような物語。
コロナ前の、人と人が何気なく出会い、どんどん家の中にも入り込んでいく世界がここにはあって、どこか切なく、懐かしくなる。一方で主人公は、周囲の人とうまく距離感を保てない気質もあって、それはコロナ下で人と人がどう関わり合っていけるかというテーマを先取りしているようにも読める。
本書を読み終えると孤独は悪いものではないと思える。一方で、もう少し人と関わってみようかとも思える。ちょうど良い塩梅。早川書房、2022年3月20日初版。
感想記事はこちら。
④「給料はあなたの価値なのか」
タイトルはもちろん反語で、「給料はあなたの価値で決まるわけじゃないんですよ」と言い切ってくれる痛快なノンフィクション。とはいえ檄文やエッセイではない。米国の政治経済学者ジェイク・ローゼンフェルドさんが著した、れっきとした学術書。
では何で給料が決まるのかと言えば、著者は社会制度、経済的な仕組み、会社のカルチャーなどさまざまな環境要因だと指摘する。これは、エッセンシャルワーカーに冷たすぎるいまの格差的な給与状況は変えられることを意味するし、一方で高い給与を受け取っているだけの人間が「生産的」で「高価値」じゃないんだよと釘を刺す意味にも受け取れる。
マイケル・サンデル氏「実力も運のうち」などと共に、近年のメリトクラシー(能力主義)のあり方を考える格好の一冊でした。みすず書房、2022年2月10日初版。
感想記事はこちら。
⑤「世界史の考え方」
今春から高校で始まった新科目「歴史総合」はどうやって学んでいけばいいのか、専門家の小川幸司さんと成田龍一さんが対話形式でまとめた一冊。世界史と日本史を横断的に考えること、時代を「輪切り」に俯瞰すること、そのために「問い」を設定すること。一見すれば抽象的な歴史的考察・歴史的叙述の営みを、実践的に示してくれるから腹落ちする。
なにより本書は、新しい学習指導要領で重視される「対話」を実演してくれている。小川さんと成田さんは互いの説明に耳を傾け、補足し、時には視点を変えたり論を展開する。「論破」や「対決」ではなく、重要なのはこうった言葉・考えのやりとりなんだと学ぶことができました。岩波新書、2022年3月18日初版。
参考文献が多数示されていて、読了後の読書の展開にも困らない。私は遅塚忠躬さん「フランス革命 歴史における劇薬」(岩波ジュニア新書)を手に取りましたが、これまた面白い本でした。
感想記事はこちら。
⑥「脳は世界をどう見ているのか」
とにかく面白い。ぶっ飛んでいるけれど、読めば納得。何が分かるのかうまく説明できないけれど、読了後も知的興奮が収まらない。細胞の集合体でしかない(その点で他の臓器と変わらない)脳に、なぜ知性が宿るのか?その疑問に起業家で神経科学者のジェフ・ホーキンスさんが真正面から挑む本。
本書が、というか著者がすごいのは、脳の機能に関して部分的な説明ではなく、全体像を示す「グランド・セオリー」を編み出そうとすること。言うなれば地球の動きを解明するだけではなく、「地動説」をまとめようということ。最もハードルが高い作業に著者は逃げずに立ち向かう。
そうしてできたのが本書で示される「1000の脳理論」で、脳科学初心者の読者には正否の判断までは難しいものの、「これが現実だったら納得だし面白い!」という思いが止まらない。この本面白いですよと、さまざまな人に勧めたくなる。そして著者の活動を今後も応援したくなる。早川書房、2022年4月20日初版。
感想記事はこちら。
⑦「映画を早送りで観る人たち」
現在のカルチャー、消費行動を鋭く抉る改作。パッと視界が開け、同時に自分自身の日頃の行動を顧みたくなる。ライター稲田豊文さんの慧眼が光る。
ネットフリックスなどで当たり前となった「倍速試聴」は、なぜ若者に好まれるのか?その問いを当事者インタビューをまじえて掘り下げる。「コストパフォーマンス」ならぬ「タイムパフォーマンス」(タイパ)や、友人との関係構築のためにコンテンツを消費せざるを得ない現実。「なるほどなー」「たしかになー」という感想が止まらない。
消費行動は文化や社会、そして人間に深く根ざしている。そのことを明快なグラフィクスのように示してくれる。そして、失われつつある「作品を味わう」ことの尊さや難しさを立ち止まって考える機会になりました。光文社新書、2022年4月30日初版。
感想記事はこちら。
⑧「ルーティーンズ」
最初の緊急事態宣言が出た2020年春の東京を舞台に、父母娘(保育園児)の家族の日常を切り取った物語。主人公も作家で、これが著者長嶋有さんのエッセイなのか小説なのか分からなくなるような淡いタッチが特徴でした。
しんどくて、先が見えなくて。それでもやってくる日常を、こんな風に愛おしく感じ取れたらいいなと思える。希望の火が灯るとか、そんな大袈裟ではないけれど、「今日も生活をしていこう」と背筋が伸びる。
帯の紹介文で藤井隆さんが「不要不急の言葉で、僕の生活も止まった。この本を読んで、あの時期のごたついてた気持ちをひとつ整理してもらえた」と書かれているけど、まさに。沈んでいた日々が悪くはなかったと思えました。講談社、2021年11月8日初版。
感想記事はこちら。
⑨「中央線がなかったら」
タイトル通り、東京の多摩地域の代名詞である中央線を「ひっぺ剥がしてみたら」その土地にはどんな歴史、文化が眠っているのか。身近なのに実験的で、自分の地元の地域を散策してみたくなる一冊。
「ブラタモリ」を紙面上でやってくれるような本です。建築史に詳しい陣内秀信さんと、社会文化を研究する三浦展さんのタッグで、実際に街を歩き、文化を紐解きながら、中央線のない街の姿を浮き彫りにしてくれる。
実は中央線の歴史は浅く、もともと当時は重要ではなかった広い土地に貫通させたものだそうで、古代からの文化で言えば中央線から離れた場所の方が寺院など重要拠点が多い。これは他の地域でも同様のことがありそう。
コロナ下で遠くには旅行できない昨今、足元の街を「発見しなおす」という営みは大きな楽しみになりそうだと感じました。ちくま文庫、2022年1月10日初版。
感想記事はこちら。
⑩「小説の惑星」
上半期はたくさんの素敵な短編集に出会いまして、その中でも一冊あげるとすれば伊坂幸太郎さん編の「小説の惑星 ノーザンブルーベリー篇」。姉妹編の「オーシャンラズベリー篇」も同じように面白い。
伊坂さんが「短編小説のドリームチームを組んだらこうなる」という作品群を選び出してくれた本書。井伏鱒二のように教科書に載っていそうな作家から、一條次郎さんという最新作家まで網羅されている。面白い作家さんはやはり面白い小説を読んでいる。「you are what you eat」という格言を思い出すような、伊坂幸太郎さんの「構成成分」を目の当たりにできる作品集でした。
他には「昭和の名短篇」(荒川洋治さん編、中公文庫)や、「中央線小説傑作選」(南陀楼綾繁さん編、中公文庫)もナイスでした。
感想記事はこちら。
下半期もたくさん素敵な本に出会えますように。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
