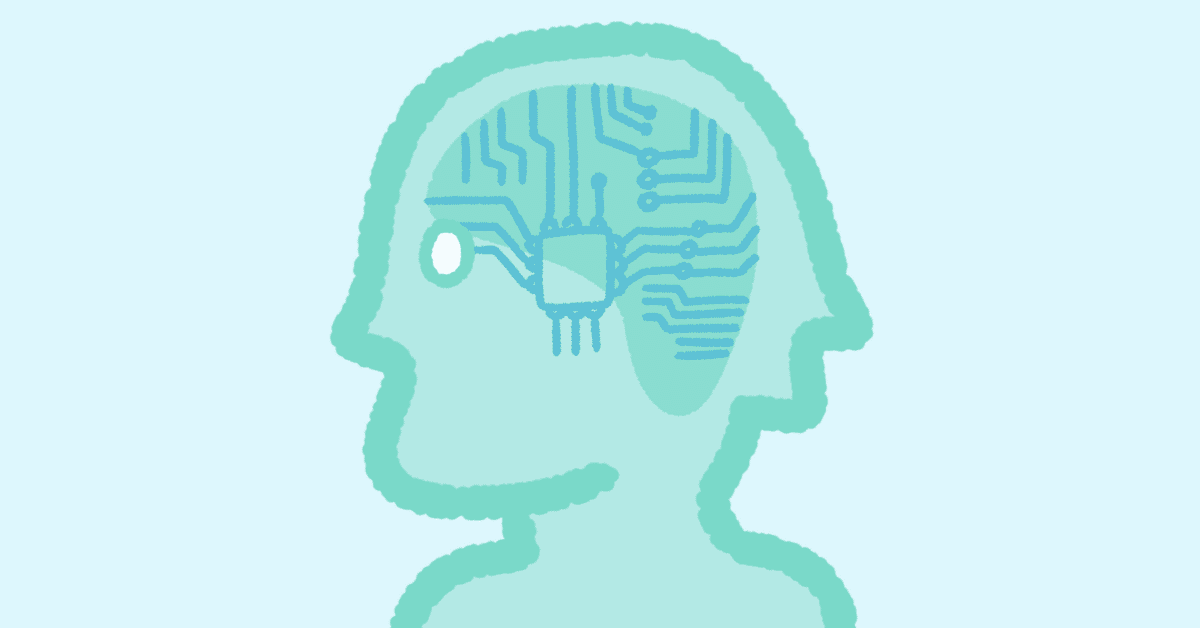
システム化という強みーミニ読書感想『ザ・パターン・シーカー』(サイモン・バロン=コーエンさん)
ASD者(自閉症者)の支援に長らく取り組んできた心理学者サイモン・バロン=コーエンさんの『ザ・パターン・シーカー』(篠田里佐さん訳、2022年11月29日初版、化学同人社)が学びになりました。ASDに特有のパターンを好む思考を「システム化メカニズム」と定義し、人類のさまざまな発明に寄与したと説く。ASD者やその家族へのエールと、社会変革を求めるメッセージが込められていました。
システム化メカニズムとは、物事を「if-and-then」のフォーマットで分析する考え方。日本語にすると、仮説や前提(if)、変数となる行動(and)、結果分析(then)となるでしょうか。たとえば著者は、人の手ではとても持てない巨石を、牛にひかせる方法で運ぶことを発明した古代人の発想をこう表現する。
石が非常に重く(if)、それを自分の雄牛にくくりつけると(and)、巨大な石が動く(then)
たしかに、ASDの特性のある人はif-and-thenの思考に基づき、何らかのパターン行動を繰り返しているように感じます。同じ行動を飽きずに繰り返しているのは、if-and-thenが機能するのか検証しているか、実はandを微妙に変化させて、thenの揺らぎを確かめているかのような。もちろん、それが定型発達者からすると違いがわからず「同じことをひたすらやっている」と感じるわけですが。
牛による石運搬のように、著者はシステム化メカニズムが人類の発明の源だと言います。言い換えれば、ASDの特性が発明の駆動力だと。
しかし本書で語られているのは、いわゆる「ギフテッド礼讃」ではありません。著者は、システム化メカニズムを語る上で「アル」と「ジョナ」という2人の人物を鍵としています。
アルは、誰もが知る発明家、トーマス・アルバ・エジソン。そしてジョナは、著者が知るASDの若者です。ジョナも優れたパターンシーカーで、たとえば海の微妙な波の変動を見極めて魚が集まる漁場を見抜くプロですが、人と目を合わせるのが苦手な特性もあり、企業に採用されずにいます。
同じような非凡な能力があるのに、なぜジョナは評価されないのか?システム化メカニズムがあるから良いんだと、それで割り切れる現実ではないことを著者はよく分かっています。
また、もちろん、全てのASD者がシステム化メカニズムに特化しているわけではないし、他の障害を併発しているケースもある。その苦労に悩む当事者や家族にも思いを馳せます。
しかしながら、「ASD者は発明の寄与者なのだ」という高らかな宣言は、「普通に合わせるべきだ」という社会圧力への強力な対抗軸になる。その点で、当事者やその家族に勇気を与える内容でした。
この記事が参加している募集
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
