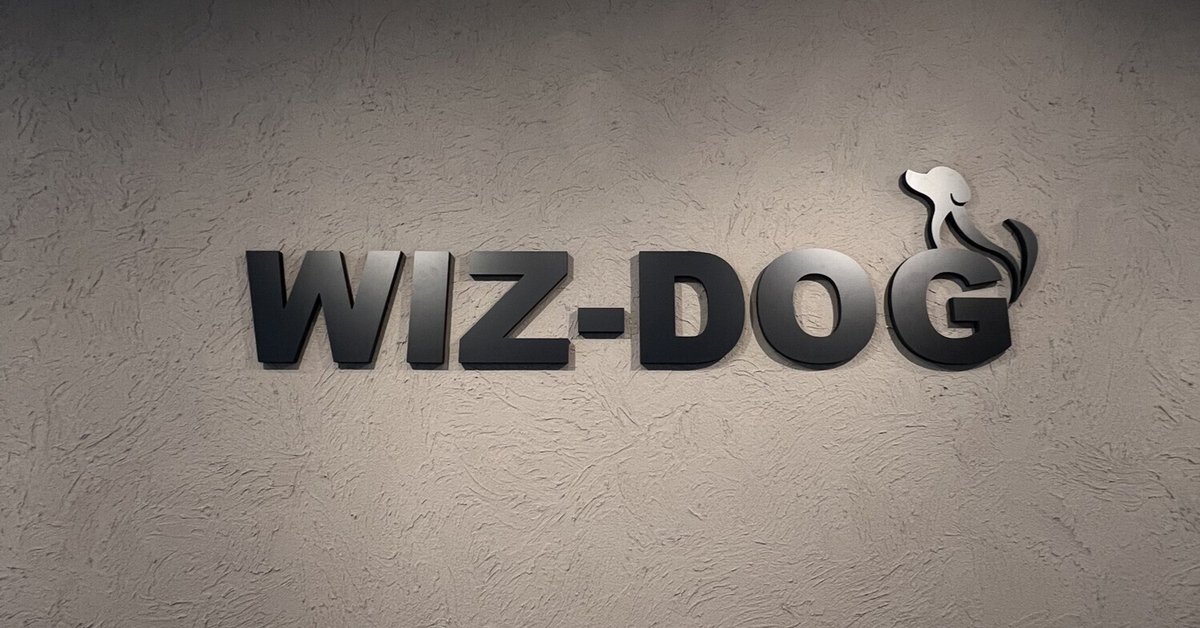
13.犬の歩様
四足動物の歩き方あるいは走り方というと、馬術やドッグショーの関係者などがその知見を多く持っていますが、それらは、一般家庭犬の「健康」維持や回復、診断などの現場でも大いに活用できると思います。
今回は、まずその入り口について考えてみたいと思います。ただ、四足歩行の場合、どの歩様を「歩く」と表現していいのか「走る」と表現していいのかよくわかりませんので、ワードとしては「歩き方」を使います。
ヒトの歩く運動と走る運動
「歩く」という運動と「走る」という運動の違いをご存知ですか?
ヒトの場合、遅い速いと言ったスピードで決めているのではなく、両肢を交互に動かして移動する時、常にどちらかの肢が地面に着いている動作を「歩く」運動、どちらの肢も宙に浮く瞬間が伴う動作を「走る」運動と定義しています。歩く運動では両肢が地面に着いている時間はありますが、走る運動ではその瞬間はありません。
「歩く」運動は、主に体重移動を利用しますが、「走る」運動は、主に後方あるいは上方に蹴りだす強い力を利用します。また、その両運動には、着肢の遠位(肢の体幹から遠い方)から近位(体幹に近い方)に向かって負重されるか、瞬間的に着肢全体に負重されるか、の違いもあります。つまり、歩く運動と走る運動では使われる筋肉などや骨への衝撃の与えられ方、力の伝わり方などが異なるんですね。さらに心肺機能への負荷にも違いがありますので、健康維持あるいは回復を目的とした場合、どちらの運動を選択すべきかは、個別に判断しなければならない非常に重要なポイントになります。
イヌの歩き方いろいろ
では、イヌの歩き方はどうでしょう。イヌはヒトと違って四足歩行ですので、ヒトの「歩く」と「走る」の違い、その定義がそのまま当てはまるわけではありません。
ヒトがイヌを横につけてゆっくり歩く時、どの瞬間も地面に2本以上の肢が着いています。これを「ウォーク:なみあし」と言います。四肢その他カラダへの負担は少なく疲れにくい基本となる歩き方です。
黄信号を渡る時などでヒトが速足になると、イヌも速度を上げて軽快に跳ね気味に小走りのようになりますよね。この歩き方を「トロット:はやあし」と言います。「トロット」でもスピードが上がると4本肢すべてが宙に浮く瞬間が現れるケースもありますが、通常速度での「トロット」では4本肢のうち2本の斜対肢(しゃたいし:斜め向かいの肢同士)は地に着いてもう一対の斜対肢が宙に浮きます。斜対肢が対になって動く歩き方は「斜対歩:しゃたいほ」と呼ばれる歩き方で、「ウォーク」やこの「トロット」も含まれる基本的な肢の運び方です。
整形外科的不具合を診断する時、獣医から「少し速めに歩かせてください」と指示されることがあります。跛行、特に痛みを伴う跛行は、「ウォーク」ではよくわからなくても「トロット」にするとはっきりわかる、ということがあるのです。
ちなみに、「アンブル」や「ペース」といった左右同じ側の肢同士(側対肢:そくたいし)を対にして歩く様を「側対歩:そくたいほ」と言います。左の前肢と後肢を、右の前肢と後肢を、それぞれ同時に前に運ぶ歩き方です。キリンやラクダはこの歩き方が一般的で、イヌについては、それが一般的となっている一部の犬種もありますが、多くの犬種では、疲れた時や老犬などでたまに見られるとされています。でも、よく見ると幼犬や成犬でもしばしば観察されますよね。肢の長い四足歩行は斜対歩だと同じサイドの前肢と後肢が当たる(ニッキング)から側対歩になるのだ、と説明されることがありますが、真偽のほどはよくわかりません。
さて、「トロット」のスピードが上がっていくと、通常、瞬間的に3本肢が宙に浮く「キャンター:かけあし」という走り方、そして瞬間的に4本肢が宙に浮く「ギャロップ:しゅうほ」となっていきます。「ギャロップ」でも、肩関節と股関節が同時に伸展した時に4本肢が宙に浮く(ちまたで「飛行犬」と言われる状態になる)走り方を、特に「ダブルサスペンションギャロップ」と言い、最もスピードが出る走り方とされています。
歩様と健康
イヌも、ヒト同様、健康維持あるいは回復を目的とした運動をやらせる時、歩く運動と走る運動のどちらが良いのかを選択しなければなりません。ただ、「歩く」という動作は、基本的に体重移動で緩やかな負重の繰り返しですが、階段を下りる運動などでは、たとえ常に着肢している「歩く」という運動であっても、走る運動と同様の衝撃を骨に与えることになります。つまり、言葉の定義よりも、どんな運動をさせることがその犬にとってふさわしいのかは飼い主がちゃんと判断すべきだと思うのです。
「歩かせるか走らせるか?」 こんなたった一つの単純な問いかけに答えるだけでも、いろんなことが書けるんですね。「ウォーク」と「ギャロップ」では、運動強度も異なりますし、脊椎の動かし方も異なりますので、具体的にどんな歩きや走りがどういった場面でどう健康に寄与するのか、と言った問いかけについては、また別の機会にご説明します。
面白いと思います。
WIZ-DOGドッグトレーナー 大谷 奈津子

