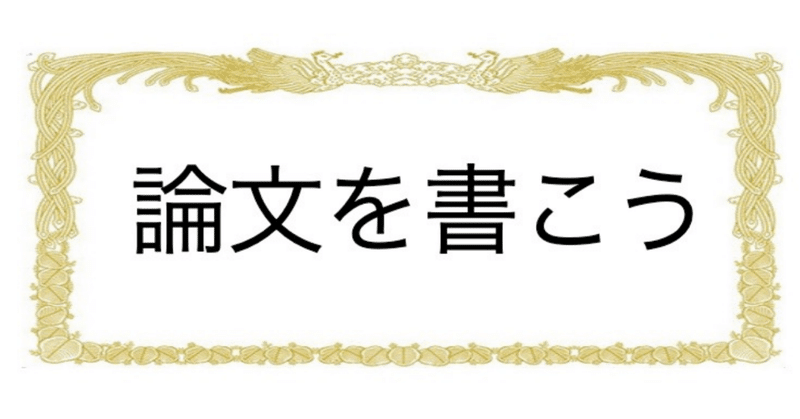
大学院へ進学を考えている学生へ 〜学会論文投稿スケジュールについて〜
工学部の大学院2年間というのは,本当に忙しくもあり,開発者・研究者として飛躍的に成長できる貴重な時間です.失敗を恐れることなく,学生らしい若さ溢れる姿勢で取り組んでほしいと思っています.
私は社会人ドクターとして,これまで国内外含めて20以上の論文を投稿してきました.(2度,論文賞を受賞ました.)新年度が始まるにあたって,大学院への進学を考えている大学4年生あるいは大学院生に向けてエールを送りたいと思いました.学士/修士/博士に求められる資質は以下のようなものだと思います.
Bachelor(学士):与えられた課題を論理的に解決できる
Master(修士):課題に対して適切なアプローチを考案できる
Doctor(博士):社会課題を発掘し,その本質を見極めることができる
進学を考えているなら,学会への論文投稿は必ずするぞという気持ちで望んで欲しい.学会によって,受付日や発表日はまちまちなので,自分の研究テーマおよび進捗に応じて担当教授とよく相談しながら,どの学会に提出するのが相応しいのかを決めて下さい.できるだけ計画通りに研究が進められるように,ここでは,一般的な論文発表までの全体のスケジュールを示します.参考にして自身のスケジュール立案に役立ててもらえたら幸いです.応援してます.頑張って下さい.

<Abstract提出>
投稿先によってまちまちですが,だいたい250〜500単語程度で論文の概要をまとめたものを提出します.ここでは,①なぜこの研究が必要なのか(どんな課題を克服できることができるのか),②課題解決のためのアプローチ,③どのような結論が得られたのか(最も述べたいこと)を完結に述べる必要があります.何度も紙に書いては,修正するといったことを繰り返して,もっと的確な表現はないかを探って下さい.これをすることにより,飛躍的に後の本文執筆の時間が加速するはずです.(これは慣れであり訓練だと思って取り組んで下さい.もし執筆時間が次第に加速しないのであれば,訓練不足だと思って下さい.)
企業との共同研究の場合は,特許性があるかどうかもしっかり検討するようにして下さい.自分だけあるいは大学の研究室だけでは,類似特許を調べるのに時間がかかりそうなら,共同研究先の企業の中に知的財産を扱う部署があるでしょうから,その部署とも情報共有を図るとよいでしょう.
<Full Paper提出>
Abstractを提出してから,1ヶ月ほどでアクセプトかどうかの連絡が事務局よりメールなどで帰ってきますので,迷惑メールボックスに入っているかもしれないので適宜確認すること.受理されていたら,Full Paperに向けて全力投球です.だいたい3ヶ月ですので,着実に執筆作業を進めるようにして下さい.これも投稿先によりますが,A4サイズで6〜12ページでページオーバーすると1ページごとに追加費用が発生する場合もあります.投稿規定をよく読むようにして下さい.ほとんどの学会サイトにワードなりのテンプレートファイルがあるはずですので,それをダウンロードして執筆することになります.
構成としては,
1章 緒言(背景,これまでの研究,着目している課題)
2章 課題に対するアプローチ
3章 理論説明
4章 実験やシミュレーション条件・内容
5章 結果
6章 まとめ(考察と今後の方針)
というように学術論文の型がありますので,小説のようなどんでん返しや誇張,たとえなどの飾り付けは一切不要と考えて下さい.

<査読>
Full paperを提出してからアクセプトされるまでの2ヶ月間に,査読者からコメント・質問等のやりとり3〜5回ほどあります.非常にいじわるな質問から,ナイスアドバイスといったものまで様々ですが,基本的に無償で忙しい中,親切にコメント下さっています.まずは感謝です.査読者に回答する際には,必ずお礼の言葉を添えること!.誤解を招く言い回しや分かりにくい部分などを指摘下さっていますので,丁寧に回答および論文修正しましょう.これは,自分の論文が良くなる方向への避けては通れない工程だということを認識しましょう.
もし,英語論文なら,①三単現(三人称,単数,現在)のs,②時制の一致(現在,過去,未来),③助動詞(may,can,should)これらは特にチェックする.①〜③の間違いがあまりにもひどいと,内容以前の問題で拒絶されます.
<プレゼンテーションに向けて>
アップデートを重ねた論文が受理されたら,それでやれやれという訳には行きません.まだまだやらなければいけないことがあります.
①プレゼン資料作成
・目安は1スライド/1分 ⇒ 20分のプレゼンならスライド20ページ
②バックアップ資料作成
・紙面の都合上,論文内には掲載していない図表とそれらの説明
・追加実験をしたのであればそれらの結果
・理論の詳細説明
・関連論文の概要
③発表原稿の作成
述べるべきことをきちんと言語化することにより,説明がうまくなります.すらすら言語化できないなら,本番で分かりやすいプレゼンができると考える方がどうかしています.
④Q&Aの準備
自己ロールプレイングを必ずして下さい.想定質問を自分で考えてみる.聴講者のつもりで,最低でも5つの質問を書き出してみて下さい.どうしても質問が思い浮かばないなら(そんなはずはないはず!),友達や他の研究者に尋ねてみる.そして,その質問に対する回答もきちんと言語化する.この作業が論文のクオリティを飛躍的に引き揚げます.さらに,次の研究課題を考える足掛かりとなります.
⑤発表練習
わざと自分の目の前に50人程度の聴講者がいることを思い浮かべながら,入場から退場まで時間を測って,本番さながら,声の大きさも含めて練習する.これを10回以上やっておけば,本番で緊張して真っ白になるということはまずありません.Fight!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
