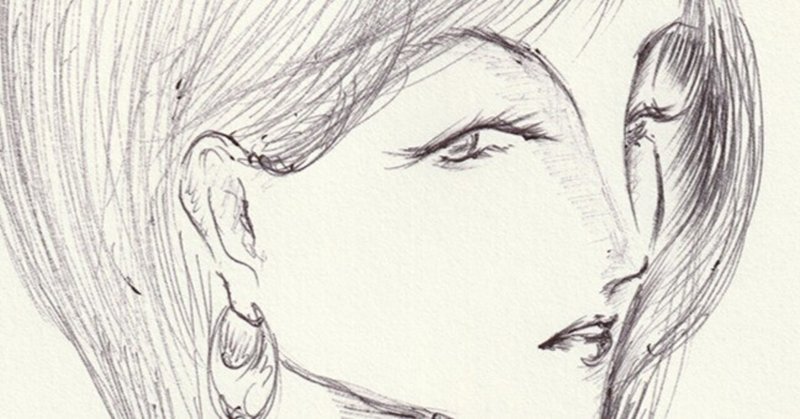
その名はカフカ Preludium 長めの追記
今年1月にピリカ文庫へ寄稿しました短編『その名はカフカ』、その後調子に乗って長編として「Preludium(前奏曲、プレリュードの意)」という副題をつけ約四カ月にわたって書き進めてきました。
先日5月11日の投稿をもってPreludiumを終了とし、次回からは副題を新たに進めていきますので、ここで一度、いろいろ今までのお話についての追記・解説のようなものを書いてみたいと思います。
最初の短編とPreludium全14話はこちらのマガジンに収まっています。
登場した都市の位置
Preludiumで登場人物たちが滞在した都市と、話題になっただけだけど物語の流れに位置関係が重要な都市を書き込んだ地図を作ってみました。

これで弾薬貯蔵エリアからウクライナまでトラックが帰る途中でバンスカー・ビストリツァが通過地点になるであろうことが分かるかと思います。グラーツからワルシャワに帰るティーナを途中まで車に乗せていく予定だったアダムが弾薬庫に近い位置にいた、というのもこれで納得いただけるかと。
弾薬貯蔵エリアのある村も、名前はあります。
日本で話題になったのかどうかも分かりませんが、2014年の10月と12月に、実際に爆発事故がありました。10月の事故では二名の従業員が亡くなり、すべての処理には2020年10月まで、約六年を要したそうです。そして2021年4月、何とそれらの事故は事故ではなく、ロシア参謀本部の手によるものだという疑惑が発覚しましたが、ロシア側の調査協力は得られず、未だ(少なくとも表向きは)未解決のままです。
実は第11話の爆発はもともと、レンカが10月に実際に起きた爆発に巻き込まれる、というアイデアが発端でした。しかし現実世界において解決していない事件をフィクションに利用する、というのは抵抗があり、もし「事件の真相をでっちあげている」という受け取り方をされたら、という心配もあって早々にそのアイデアは捨てました。それに10月まで引き延ばしたくなかった、というのもあります。
そして、この2014年に本当にあった爆発事故の検索に引っかかってしまわないよう、その土地の名前の表記も避けることにしました。
物語の舞台の時代
Preludiumでは第1話が2013年11月で始まり、最終話の第14話が2014年の5月でした。そんなに遠くない過去を描いているわけですが、これは意図的に選んだ、というより偶然呼び込んだ気持ちのほうが強いです。
最初の短編で、主人公が12年前にプラハに滞在していた、と設定しましたが、短編の執筆開始当初は20年前としたのを「いや、それ時間たちすぎ」と変更した記憶があります。
長編を書き始めるにあたって、その「12年前」というのは2001年にしたい、と思い、そうすると短編での主人公がプラハを再訪問したのは2013年になる、ということで深い計画もなく決定しました。結果、ウクライナのマイダン革命と時期が被ることになり、実は『その名はカフカ』全体を通しては別の土地の政治的背景がもっと重要なのですが、Preludiumではウクライナ騒乱を中心として展開する流れとなりました。
なぜ書いているのか
ピリカ文庫に寄稿した短編に「続きが読みたい」と複数の方に言っていただき、もともとKavkaことニシコクマルガラスから発想した物語は長めのものを想定していたことから、まさか自分が手を出すとは思ってもみなかった長編連載に踏み切りました。
ただ、今の私の「なぜ書いているのか」に対する答えは、「自分のために書いている」。
自分のこの長編に文学的価値があるなんて、これっぽっちも思っていないし、読んでくださっている方々によくひねったトリックやら謎解きやらで驚いていただくエンターテイメント性も狙っていないし、そもそも私にはそんな実力はありません。裏社会を暴きたいわけでもないし(お話の中ではけっこう自分で作っちゃってます)、ましてや政治的メッセージや信念を伝えようなどという意図は全くなく、私では役不足です。
前項で「偶然にも時代設定が2013年始まりになった」という書き方をしました。本当に偶然だったんです。
しかし何とも不思議な偶然で、2012年後半からの三年間ほどは、私が「これまでの人生でどん底と呼べるものがあるとしたらこの時期だろう」と思っている期間なのです(そして物語が始まっている2013年年末くらいは一番落っこちたところの底辺でした)。もしかすると私はこの苦しかった時期に自分とは全然別の人生を送っていた人たちを描いて、いわばその時期の清算をしたいのかもしれない、と論理的には説明しがたい運命的なものを感じています。
(「どん底」についてどこかで書いたな、と思ったらこちらでした↓)
ですから、この『その名はカフカ』も、永遠に書き続けられる話ではなく、長くて2015年までじゃないか、と思っています。パンデミック中にレンカがどのように活動するのかなんて、想像できない。その気になったら2001年をZEROとでも題して書くかもしれませんが。
レンカについて
主人公のレンカは当初、何の愛もなく作ったキャラクターでした。「嫌な奴を主人公にしちゃったな。痛めつけ甲斐があるぜ」なんて思っていたんです。私と同じ1980年生まれですが(2014年時点で34歳)、自分の分身を作ったつもりはさらさらなく、同い年にしたのは単に「計算しやすいから」。他の登場人物たちの歳も、主人公を軸に計算できれば簡単、と。
ところが第5話でレンカが過去の失った記憶に触れようとしているイメージ画を描いたところ、私の中で彼女の存在が全然違ったものになってしまったのです。おかしな話だと思われるかもしれないのですが、一枚の絵を描いただけで、レンカは私の中で「嫌な奴」から「愛情を注ぐべき対象」にガラリと変化してしまいました。
バレエ公演に行く、というエピソードは、この時思いつきました。当時私が感動した舞台を、レンカにも見せてあげたい、と。
そしてその後もレンカの人生に自分を注ぎ込んでいきました。ところどころのエピソードには私自身の過去が反映されています。あ、もちろん私は犯罪組織なんてご縁はありませんよ(笑)。ちょっとずつ、形を変えてレンカの中に私が入っているけれど、レンカはあくまで私とは別人です。
年齢の話が出たので、主要キャラクターたちの生まれ年をまとめておきます。
レンカ(1980)
エミル(1987)
アダム(1965)
ペーテル(1994)
カーロイ(1964)
サンドラ(1969)
ティーナ(1966)
サシャ(1967)
短編の主人公(1973)
ーーーーー
ペーテルの弟(2000)妹(2002)
アダムの娘(1992)
ご自身の生まれ年と同じキャラなんかが見つかった方には、より親近感をもっていただけるかな、と。
ちなみにカーロイは「こういう人間に生まれて人生を謳歌してみたいわ」という私の理想と妄想を詰め込んだキャラクターです。ということで、これから先も彼の人格からぼろが出ることはまずないでしょう。笑
挿絵について
第4話ですでに「キャラクターの肖像を描くだけ」に飽きてしまった私。その後は思いつくままにいろいろなスタイルの絵を挿絵として載せてきました。この話が本になることはまずないとは思いますが、もしも変な気を起こして「本にしよう!」なんて言い出したら、統一感を出すため挿絵は全部描き直しすることになるでしょうね。
Preludiumのために描いた絵の中で一番のお気に入りは最終話のニシコクマルガラスです。
『その名はカフカ Preludium』に関する補足はこのくらいでしょうか。
第1話は3000字ほど、第2話は2500字ほどだったので、このくらいで書いていくのかと思いきや、その後どんどん長くなっていき、もう少しで6000字行きそうだった回もありました。こんな長ったらしい筆者の自己満足でしかない連載にお付き合いいただいている皆様、本当にありがとうございます。
これからも、どうぞよろしくお願い致します。

本編の挿絵としては登場させられなかったペーテル女装図でございます…
次章の第一話はこちら↓
【2024年1月追記】
長編『その名はカフカ』は紙の本でも読めます。
豆氏のスイーツ探求の旅費に当てます。
