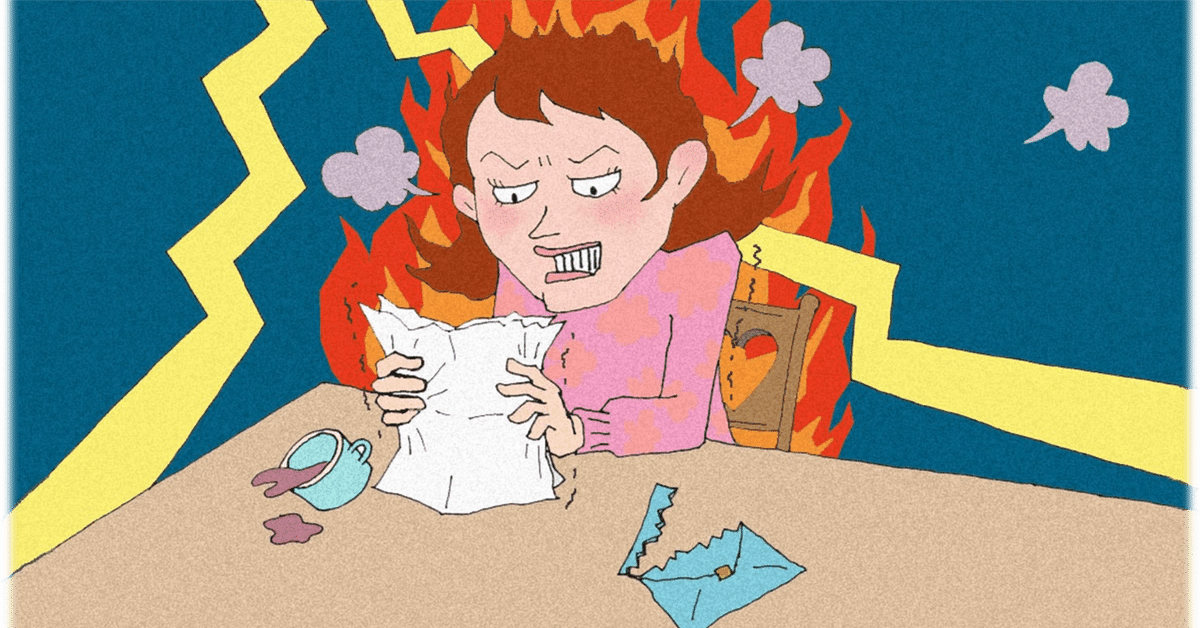
「博士論文が書けない」とはどのような状態か?Part3(学術論文のパッケージングを考える編)
前回の振り返り
前回の「博士論文が書けない」とはどのような状態か?Part2(博論計画が立てられない編)では、博士課程に進むことができた(すなわち博論計画が認められた)のに博論に着手できないパターンについて言及しました。この段階で足踏みしている人はそれほど多くないかもしれませんが、僕の経験上、毎年ごくわずかながらも、修士論文で取り組んだテーマと全く違うことを博士課程で取り組もうとしてしまう人が一定数いらっしゃること、そしてできればそれは避けたほうが良いことを指摘しました。
論文の査読が通らない?
本記事のメインスコープ:国内の学術誌に査読付き論文を通すこと
「博論が書けない」という状態を分解した上での第2段階は、Part1(リンク)でも言及した通り、「博論を構成する原著論文が書けない」という段階です。この段階を更に分解して大別すると、①原著論文そのものが書けないという状態と、②原著論文の査読が通らない、という2つの段階に分けることができるはずです。
もっと詳しく分解すると、適切な問題が設定できないとか、シャープなリサーチクエスチョンに絞り込めないとか、適切なデータセットが入手できない(定量研究)とか、適切なケースが選択できない(定性研究)とか、論文が書けない理由は無限に湧いてきます。この課題を突き詰めていくと、「良い論文を書くためには?」という壮大なテーマに行き着いてしまいかねません。そうなると、僕自身の能力の範疇はもちろんのことながら、もはや研究分野の壁すらも超越した議論になってしまうので、議論の対象と範囲を限定する必要があるでしょう。
そこで、本記事のシリーズが「博士論文」であることを踏まえ、次の2つの前提を置くことにしました。それは、①投稿者の想定が国内の経営学系の博士課程に所属する大学院生であること、②投稿先は国内の経営学系有力学術誌であること、の2点です。
このような前提を置く理由を一応説明しておきたいと思います。①は、本記事のテーマであるため、あえて言及するまでもないかもしれません。②については、海外誌もスコープに入れるとなると、分野も細分化される上に、レベルも玉石混交である為、議論が複雑化してしまうことを懸念しています。この点について賛否が分かれることは承知していますが、少なくとも国内の経営学系の博士課程では、国内の有名学術誌に査読付き論文が複数採択されていれば、博論の執筆が認められるケースが多いはずです。加えて、2023年現在では、国内の主要学術誌に3本くらい査読付き論文が掲載されていれば、ファーストキャリアのポジションの書類選考に通るの条件の一部を満たすこともできます(十分条件ではない)。
加えて、この記事の著者である僕自身が、国内の主要学術誌として、『組織科学』、『日本経営学会誌』、『VENTURE REVIEW』、『赤門マネジメントレビュー』などへの掲載経験(及びレフェリー経験)があるため、肌感覚を踏まえたアドバイスができると考えたためです。
学術論文のパッケージングとは
優れたアイディアの論文 vs パッケージングに優れた論文
この記事のタイトルに興味を持って記事をご覧くださっている研究者の中で、国内外の主要誌に論文をバンバン通しているという方はそれほど多くないでしょう。もしかすると、これから初めての論文投稿を控えている方もいるかもしれません。その段階の研究者には、自分が書いた論文の原稿がどの程度の評価を得られるのかさっぱり手応えがわからないという悩みを持っている方も少なくないことでしょう。では「査読に通る」論文とはどのような論文なのでしょうか。
(もちろん僕くらいのキャリアで「質の高い論文とは…」といった議論を展開するつもりはありません。あくまでも「査読に通る」論文に議論を限定しつつ、さらに巨人の肩に乗りながら検討を続けたいと思います。)
ここでは、一橋大学の小野浩先生がテキサスA&M大学に在籍されていた時代にご執筆されたエッセイから、学術論文の「パッケージング」という概念をお借りしたいと思います。「パッケージング」とは、マーケティング用語に着想を受け、研究アイディアとその成果を取りまとめ、論文というかたちに「商品化」する一連の流れを指します(小野, 2014)。小野先生は、パッケージングの重要性について次のように述べられています。
どんなに優れた商品であっても,デリバリーに失敗したらその商品は死んでしまう。マーケティングではこの類の失敗例は無数にある。投稿論文の世界でも,どんなに良いアイディアであろうと,それをうまく表現して読者に伝えることができなければ論文は死んでしまう。パッケージングのしかたによって勝敗が分かれてしまう。悔しいことだ。それだけ論文のパッケージングは重要なのである。
小野(2014)では、この問題意識に基づき、論文の評価を下図のような、①パッケージングの良し悪し(縦軸)と、②研究アイディアの良し悪し(横軸)の2軸のマトリックスで表現されています。

ここで注目すべきは左上と右下の象限でしょう。左下はあえて言及するまでもありませんね。学術論文として世に出て評価される論文というのは、恐らく右上の象限のような、「パッケージングにも研究アイディアにも優れた論文」であることでしょう。他方、左上と右下の象限のように、どちらか一方が優れている論文に対する評価はどうでしょうか。小野(2014)によれば、編集委員の間では、「研究アイディアとしては平凡であるけども、パッケージングに優れた論文」の評価のほうが、「研究アイディアには優れているけれども、パッケージングに課題がある論文」よりも高くなる傾向にあるそうです。
いかがでしょうか。ここまでの記事をご覧になった方々の反応は、(晴天の霹靂とまではいかなくても)「そうだったんだ!」という方と、なんとなく感じていたことが言語化されてそれを追認するような感覚になる方と、「そんなの当然だよ」という反応をされる方の3種類に分かれるのではないかと思います。もちろん、お読みいただいている方の反応は以後の内容に影響しないのですが、論文の「パッケージング」に興味が湧きませんか?論文のパッケージングを構成する要素については、小野先生のエッセイをご覧頂くのが一番です(DOIが付与されていないので当該論文を発行している学会のリンクを貼っておきます)。
もっとも、この記事が小野先生のエッセイの解説に終始していては面白くないので、以降では、小野(2014)に基づきながらも、自らの経験などを踏まえた論文のパッケージングについての検討を続けます。
なぜイントロダクションが命か?
学術論文のパッケージングを構成する要素で最も大切なのがイントロダクションです。学術論文におけるイントロダクションの重要性については、僕がここで改めて説明する必要はないかもしれません。大学院生の読者であっても、指導教員からイントロの重要性は教わっていることでしょう。
ここでは、少し視点を変えて、レフェリーはイントロダクションをどう読むかについて言及してみたいと思います。読者視点で見た場合、その論文を読むかどうかの意思決定は、要約(アブストラクト)→イントロダクションと続くことかと思います。そして、イントロダクションが面白ければ結論を読み、重要そうな論文であれば、腰を据えて本文を読み直すといった具合でしょうか。
レフェリーの場合、この順番が少々異なります(個人差はあります)。僕の場合、査読依頼が来たら、まずイントロダクションで論文の目的と問題意識を確認し、参考文献リストを見て、論文の立ち位置を把握するようにしています。自分の研究分野である場合、よほどのことがない限り断らないのですが、暇で仕方がないという状態はまずありえないので、イントロと参考文献リストを確認したあとは、査読の締切を確認の上、まずはそれまで手掛けていた仕事(研究とは限らない)に戻ります。これは、あくまでも僕のケースですが、同じような対応を取るレフェリーは少なくないと思います。
一方で、僕が国内の有力誌のSEを務める先生から聞いたことがあるのは、イントロダクションの十数〜数十行でリジェクトするかどうかの意思決定の9割を済ませるという恐ろしい情報です。もちろん、実際に最初の数十行しか読まずにリジェクトかどうかを決めているということではなく、最初の数十行を読めば、精読に値する論文か否かの判断はつくということでしょう。
ちなみに僕自身は、少なくない数の査読の経験があるものの、レフェリーとして査読に回ってくる論文は、SEによるスクリーニングを終えた論文ばかりなので、「最初の数十行でリジェクト確定」というほど酷い論文にはあたったことがありません。
上記の内容を総合すると、査読依頼が来た場合、レフェリーはまず、イントロダクション(と参考文献リスト)を読む。実際に詳細な内容を読み込まれるのは、ある程度時間が経過してからの場合があるが、その時にはイントロの情報のみである程度の意思決定がされている、ということが示唆されます。もちろんレフェリーによってやり方は千差万別だとは思いますが。あくまでも考えられるケースとしての話です。
以上の点を踏まえると、「イントロダクションが命」というメッセージに現実味が帯びてくるとは思いませんか?
より具体的には、以下の点を死守してほしいと思います。
イントロダクションの節だけで論文のストーリーが把握できるように。特に目的と問題意識にはできるだけ早めに言及するように。
誤字脱字は絶対に避ける。
投稿規定(フォーマットや引用の仕方)も完璧に遵守。
要するに、レフェリーにリジェクトの判定をさせる材料を与えないようにするということですね。2番目と3番目は注意深く作業をすることで比較的簡単にクリアーできそうですが、1番目はそれほど簡単でもなさそうです。
論文のストーリー
リサーチ・クエスチョンが定まるのはいつか?
ここまで、イントロダクションの重要性について、主としてレフェリーの視点から言及してきました。さて、先に挙げた小野(2014)の中で、著者は指導教員から「フィクションを読みなさい」というアドバイスを受けたことがあるそうです。小野(2014)では、フィクションを読むことで、イントロダクションでのフックの利かせ方や全体のストーリーの読ませ方が向上することが示唆されています。確かに、小説や漫画の著者は、自分でストーリーを構築し、登場人物にストーリーを進行させながら、読者目線での謎解きが興味深いように一貫した構造を構築することに長けています。
この「謎解き」を学術論文に置き換えると、論文のイントロダクションで提示されている問題設定、先行研究の検討を踏まえて具体的に導き出されるリサーチクエスチョン(RQ)、仮説、そして分析結果の考察、結論に至るストーリーであると言えるでしょう。
この点に関して、佐藤(2021)では、次のように言及されています。
(前略)研究テーマの決定やリサーチ・クエスチョンの設定という作業を調査の出発点だと考えないようにする、ということです。この誤解の背景には、論文や報告書では多くの場合、テーマや調査課題についての記載が最初の方(導入部、序章など)に置かれているという事情があります。しかしこれは、あくまでも全体の文章を読みやすいものにする便宜的な工夫に過ぎません。その意味では、一種のフィクションだとさえ言えます。
以降では、多くの大学院生が苦労する、RQを含めたストーリー構築について言及したいと思います。ここから先も巨人の肩に乗ることにしましょう。余談ですが、RQについては、東京大学の大木清弘先生が書かれたエッセイ「筋が悪いリサーチクエスチョンとは何か?」が非常におすすめなのでリンクを貼っておきますね。
上述の引用の通り、RQを調査の出発点だと考えないようにするとして、RQが明確になるのは一体いつなのでしょうか。引き続き佐藤(2021)を引用します。
現実には、<調査研究のごく初期の段階で分かりやすい文章の形でリサーチ・クエスチョンが示されて一連の作業がスタートし、また調査の全プロセスの中で終始一貫してその謎を問いていく>というような経緯をたどることはむしろ稀です。(中略)リサーチ・クエスチョンは、調査の出発点というよりはむしろ「ゴール」の近くに置かれていると言ってもいいでしょう。
著者視点と読者視点を使い分ける
僕自身、博士課程に進んで以降、論文を書く生活が10年を超えました。平均すると査読付き論文を毎年1本ずつ位は世に送り出すことが出来ています。数年前には書籍も出版しました。それらの経験の中で、研究の殆ど最後の方になって「自分が明らかにしたかった問題はこういうことだったんだ」ということが分かったことは1度や2度ではありません。論文投稿の締切り当日に自分の本当のRQが明らかになった論文もあります。
つまり、研究を進めていく中で、問題意識もRQも途中で変わるのは普通のことです。言い換えれば、著者は謎解きをリアルタイムで進行していくわけです。ある程度解が見えてから原稿を執筆する。ここに罠が待ち受けています。なぜならば、著者は数ヶ月、数年に渡って1つの問いに対して取り組み、同じデータや現象を追いかけているため、調査を続けているうちに、自分の中でのみ明らかになっていることと、世の中の他の人も知っていることとの境界が曖昧になってしまいがちです。「この研究はもはや誰もが知っている常識なので価値がないのではないか」というふうに。
実際、査読をしていても、著者の視点と読者の視点が混在してしまっているような論文に時々出くわします。著者の視点と読者視点をうまく使い分けながら謎解きを進行することができれば、パッケージングの良し悪しも大分変わってくるのではないでしょうか。
論文改訂時のパッケージング
論文の改訂時にも「パッケージング」は存在します。このお作法が分かっているのと分かっていないのとでは、最終的な採択(アクセプト)の可能性が倍半分くらい違ってくるのではないでしょうか。何のどの部分が「パッケージング」なのかに言及する前に、まずは順番に話を進めていきましょう。
査読結果が届いたらレターを熟読すべし
大前提として認識しておいたほうがいいのが、「論文のデフォルトはリジェクト」だということです。例えば、『組織科学』の場合、SEダブルリジェクトになるのが全体の30%前後、SEが引き受けてレフェリーに査読が回り、そこで一発リジェクトになるのが30%前後、一発アクセプトや一発マイナーリビジョンもほぼ無いので、改訂指示(メジャーリビジョン)が来るのは初回投稿の40%前後です。最終的な採択率が25%から30%なので、改訂指示をうまく乗り切れば半分以上の論文は採択されるという計算になります。経営学系国内誌の場合、数値の多少の上下はあるにせよ同じような統計になると思います。
何にせよ、論文を投稿したら基本的にはそれがリジェクトであっても、査読結果のレターを受け取ることになります。この査読結果が届いた際のことを高橋(2004)では次のように語られています。
とにかく、まずはエディターの手紙、レフェリーのレポートを読まなくては。そして……。私の場合、ここで 100%激怒することになります。多分みんなそうでしょう(かの有名なサイモンの自叙伝にも激怒すると書いてありました)。まさしく、はらわたが煮えくり返るほどの激怒です。
僕の場合、高橋伸夫先生のように100%激怒とまではいきませんが、まあ確かに似たような感情になったことは無くもないと言ったところでしょうか。
ただし、論文本体には絶対に手をつけるな
さて、激怒したかは別として、論文の審査結果がリジェクトではなく、メジャー・リビジョン(マイナー・リビジョンでもやることは同じ)だった場合、まずやることは、穴のあくまで査読結果のレターを熟読することです。ここで絶対にやってはいけないことは、レターを受け取った当日に論文本体の改訂に手を付けることです。これは絶対にやらないようにしましょう。
①レフェリーコメントの分解とグループ化
僕がいつもやることは、2名のレフェリーとSEのコメントを良く読み、コメントを分解してグループ化します。そうすることで、漠然と読むよりも、コメント一つ一つが頭に入ってきますし、後述する対応リストの作成もスムーズに進みます。
この作業は、査読結果のレターを受け取った当日に終わらせてしまいましょう。
②グループ化したコメントに基づく対応方針のメモ作成
メジャー・リビジョンになった論文を再投稿する際は、改訂した原稿だけでなく改訂リストの添付を求められることが殆どです。改訂リストは改訂後に作成するものですが、論文本体の改訂に着手する前に、①でグループ化したコメント毎に対応方針を自分用にメモしておくと論文本体の改訂も、改訂リストの作成もスムーズにいくでしょう。
この作業は、査読結果のレターを受け取った翌日の午前中に終わらせてしまうと精神面での安定が得られやすいです。
③対応方針メモに基づく論文本体の改訂
論文本体の改訂時の注意点は、レフェリーの方を向いて改訂するのではなく、読者を向いて改訂することに気をつけてください。時折忘れがちになってしまうのですが、2名のレフェリーの向こうには読者がいます。レフェリーは読者に代わってこの原稿が世に送り出されてよいかどうかを審査しているわけですから、レフェリーからの指摘はレフェリーに返す意識ではなく、読者がどう受け取るかを意識しながら原稿に反映させることを心がけましょう。
④改訂リストの作成は論文本体の修正と同じかそれ以上に慎重に
非常に個人的な意見ですが、僕は論文改訂時のパッケージングは、改訂リストに宿ると思っています。レフェリーのコメントには、全てに対して1つ1つ丁寧に真摯に回答することを心がけましょう。レフェリーも人間です。
僕がレフェリーをやっていて一番ムカッときた経験は、初稿で指摘した致命的な欠陥に対して改訂稿で全く修正されておらず、改訂リスト中に「貴重なご指摘ありがとうございます。今後の参考にさせて頂きます。」とだけ書いてあったことです。これは学会発表でその場をうまく切り抜ける時に使う常套句であって、改訂リスト中で使っていいフレーズではありません。もしどうしても指摘通りに改善できない(あるいはレフェリーの指摘自体が的外れ)のであれば、その旨をきちんと説明する必要があります。場合によっては改訂リスト中だけでなく、論文本体の脚注などにもエクスキューズを入れる必要があるかもしれません。
ちなみに、高橋伸夫先生は、改訂リストが論文採択の成否を分けることを以下のような表現で示唆されています。
はっきり言ってしまえば、レフェリーは、最初のレフェリー・コメントを書くまでが仕事のほとんどで、他人の論文の内容など、ほとんど覚えていないのです。数ヶ月も時間が空いていれば、なおのこと忘れています。だから、「変更点リスト」の完成度が高ければ高いほど、レフェリーもエディターも、そのリストに書いてあることが、原稿上も実現されていることを確認するだけになってしまうわけです。しかし、 その部分が弱いと、レフェリーもエディターもまた論文を最初から読み直すことになり、そうすると、前回読んだときには気がつかなかった欠点や短所が次から次へとボロボロと見えてきて、再度、ボロクソに書かれたレフェリー・レポートを受け取ることになってしまいます(高橋, 2004)。
おわりに
今回の記事は結構長くなってしまいましたが、国内の博士課程の大学院生には有益な情報を出し惜しみ無く書いたつもりです。感想やコメントをお待ちしております。もっとも、この記事自体は、僕が博士課程の大学院生の頃から専任教員のポストに就職して間もない頃に集めたソースと、そこから概ね4-5年の間の実体験に基づく経験との融合に基づく記事となっています。
もしかすると、記事で言及した数々の点について、若干のアップデートが生じている可能性もあるので、その点はお含み置きください。また、次回は、博士論文の構造についてを書こうと思います。気長にまっていてください。
参考文献
小野浩(2014)「学術論文の「パッケージング」:投稿作法を考える」『日本労働研究雑誌』56(4), pp58-63.
佐藤郁哉(2021)『ビジネス・リサーチ (はじめての経営学) 』東洋経済新報社.
高橋伸夫 (2004) 「英文論文のススメ-若手研究者に贈る言葉-」 『赤門マネジメント・レビュー』 3(1), pp9–41.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
