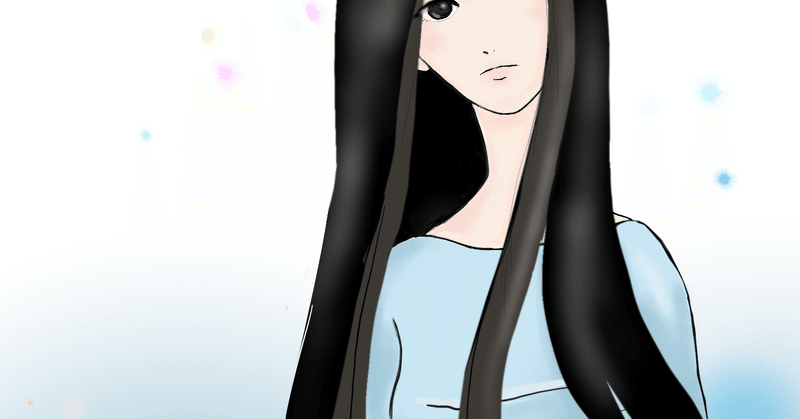
火の山九 第一章 幽霊の世界「キャンパスで僕が嘔吐し続けたこと」
少年の首を抱きしめる少女、
枯れ草の中で自分の身体を燃やしてしまいたいと願う少女、
火の山で冷たい炎に包まれて消えていった少女、
そして、水月はそれが自分の化身だという。
だが、僕には水月は透明な、汚れのない、無垢な女学生としてのイメージしか抱けない。
僕が水月を抱きしめようとすると、水月はいつの間にかするりと腕から抜けだし、僕を途方にくれさせてしまう。二人は火の山という共通の夢を抱いている。それなのに、僕には水月の正体をどうしても掴むことができないでいる。
水月の謎。それが僕をどうしようもなく不安にさせる。
あの噂は、本当なのだろうか?
僕の目の前ではあれほど透明な水月が、夜になると姿を変え、僕の知らない表情を見せるのだろうか?
僕はK大学前の喫茶店で、珈琲を一人飲んでいる。
時折、嘔吐感が津波のように押し寄せる。珈琲は一口飲んだままで、いつの間にか生ぬるくなってしまった。
比較的広い店内を見渡してみる。やはり水月の姿はどこにも見えない。以前二人で夢の話をしたあの座席には女学生が二人向かい合って座っている。
僕は岡田の言葉を、頭の中で何度も反芻していた。
夜、繁華街で、水月が男の腕に絡みつくようにして歩いていたという。岡田が偶然目撃したそうだ。水月は普段とはすっかり衣装を変え、真っ赤に唇を塗り、その妖艶な姿は誰の目にも留まるほどだと、岡田が言った。
「あいつ、男がいるぞ」
と、岡田が得意げに言った。
僕は瞬時に全身に鳥肌が立つのを感じた。今までそうした事態を一度も想定していなかった。水月の透明さを信じ込み、彼女に男がいることなど想像することさえしたことがなかったのだ。
「おい、幽霊の正体を暴かなければ」と、岡田が言った。
「ああ」と、僕は生半可な返事をして、無理に微笑んで見せたが、胸の鼓動を押し隠すのに懸命だった。
今すぐにでも水月に会いたかった。
会って、事の真相を確かめたかった。岡田の話はすべて誤解だと、水月の口から直接聞きたかった。
「そんなこと、水月は一言も僕に言わなかった。とても信じられないよ」と、僕が力のない声で言った。
「ああ、俺だって自分の目を疑ったよ。でも、どんなに化粧をしていたとしても、水月は水月で、間違いないさ。だって、あれほどの美人、どこを捜してもそんなにはいるはずがないものな」と、岡田が言った。
念のため、もう一度店内を見回し、水月の姿がないことを確かめて、席を立った。
岡田と別れて、もう一度大学のキャンパスに戻ることにした。
ざわざわと胸騒ぎがした。ゼミも無断欠席だった。水月は今まで一度もゼミだけは休んだことがなかったのだ。
水月に何かあったのだろうか。もし、そうなら、なぜ僕に連絡を取ってこないのだろう。岡田が言うように、本当に男ができたのだろうか。
僕は水月の姿を追い求めて、大学のキャンパス中を彷徨った。しかし、水月はどこを捜してもいなかった。
以前、水月と二人で腰掛けたベンチに一人で座ってみた。足下には銀杏の葉が重なるように落ちていた。ふと、水月の言葉が蘇ってきた。
「私は心も体も汚れているの」
水月はそう言って、差し出す僕の手を振り切って、ふわっと立ち上がった。
そうだった、確かにあの瞬間、僕は別離の予感に苛まれ、いつまでも水月の後ろ姿を見守っていたんだ。
「心」はともかく「体」が汚れているって、いったいどういうことなのだろうか。やはり水月は僕の知らないところで、男とつきあっているのか。しかも、その男は僕のような地位も金も何もない学生ではなく、社会的地位の高い大人の男性なのか。その男とは肉体関係を持っているから、「体が汚れている」と言ったのか。
そう思うと、次から次へと嘔吐感がこみ上げてきた。呼吸をするのも苦しかった。心臓がきりきりと痛んだ。岡田の言葉が脳裏で繰り返し蘇ってきた。
水月に男がいるなんて、とても信じられなかった。水月の持つ透明感、その無垢な肢体に男の匂いは一切感じなかった。そうだ、僕が水月の手に触れただけでも、彼女の体は小刻みに震えていたはずだ。
それなのにーー。
次の週も、水月はゼミに顔を出さなかった。
何人もの同級生に尋ねたが、誰一人水月の状況を知るものはなかった。学内で水月を見たものはいなかったのだ。おそらくずっと大学には来ていないのだろう。
嘔吐感は断続的にやってきた。
ほとんど食事は喉を通らなかった。講義に出ても、僕の眼は無意識のうちに水月を捜して彷徨っていた。
夜、夢の中でも、水月を追いかけていた。まさに二十四時間、水月を追い求めていた。これほど水月を必要としているのかと、水月を見失って初めて気がついた。でも、今となってはすでに手遅れなのだろうか。
水月の家まで、尋ねていこうと思った。だが、僕は水月について、何一つ知らないのだ。
水月は本当に幽霊だった。
僕の脳裏にはどろっとした疑惑が次々と自分の意志とは無関係に浮かんできた。僕が水月の情報を知らないのではなく、水月が自分の情報を僕に隠していたのだ。いや、僕に教えたくない情報があったのだ。
そして、清純な女性を見事に演じて、僕の心を翻弄した。水月は幽霊なんかではなく、成熟した肉体を持った一人の女性なのだ。
だが、僕を弄ぶ必要などどこにもないではないかと、思い返した。二人に共通の「火の山」の光景も作り話とは思えない。僕の思考はいつもそこで停止した。
マスターの喫茶店は、臨時休業だった。
いったいいつまで閉めているのだろう。扉は固く閉じられ、たった一枚、「臨時休業」と書いた紙が扉に張っているだけだった。その扉には配達された新聞紙が突っ込まれていて、その下には入りきらない新聞紙が散乱していた。
マスターはどこに行ったのだろう。
一週間前にマスターと会ったが、臨時休業のことなど、何一つ話さなかった。いったいマスターに何が起こったのか。僕は不吉な予感に苛まれた。たしかに世界は変わりつつある。マスターは想念が変われば、世界もまた変わると言った。その変わりつつある世界の中で、僕は水月を見失っている。
僕は一人途方に暮れていた。いや、そんな悠長な状況ではない。僕は始終嘔吐し続けていたのだ。
ようやく、僕は大学の学生食堂で岡田を捜し当てた。
世界が変わっても、岡田だけは変わらずにいてくれたのだ。岡田は相変わらず大きな黒縁眼鏡をかけ、髪が少し伸びて、耳をすっかり覆い隠していた。
「水月を見なかったか?」
岡田は怪訝そうに僕を見て「知らないよ。前に、男と歩いているのを見たって、お前に言ったろ? あれが最後だよ」と言った。
「水月が行方不明なんだ」
「行方不明? 風邪でも引いたんだろ。そのうちゼミに顔を出すよ」
「でも、何だか変なんだ。いやな予感がする」
「いやな予感?」
岡田が聞く
「ああ、水月を見かけた時のこと、もっと詳しく話してくれないか?」
僕はどんな小さなヒントでも、岡田から聞き出したかった。何もしないで、ただ水月をじっと待っているのは、苦しくて耐えられそうもない。
今、この瞬間でも、何かをしないではいられそうもない。そうだ、水月を捜し出すのだ。
岡田は何かを思い出すように、しばらく遠くを見た後、「相手は相当なお金持ちだぜ」と言った。
「歓楽街の中心で、二人は腕を組みながら、高級レストランから出てきたんだ。俺たち貧乏学生では、絶対には入れないところだよ」
岡田の言葉の一つ一つが、僕の胸を突き刺した。水月がつきあっている男が金持ちならば、僕が決して与えてやれない夢を、男は惜しげなく与えてやっているのだ。
胃の淵から、嘔吐感が込み上げてくる。その場で蹲って、思う存分吐きたい気分に駆られた。
「何時頃?」と、僕が聞いた。
「お前、変だぞ。何だか警察から尋問を受けているみたいだ。おそらく八時過ぎだと思う。あっ、そうか。その時間帯だと、同伴かもしれないぞ」
「同伴?」
僕が聞き返した。
「お前、遊びのこと、何にも知らないな。客との同伴だよ。ホステスが客と一緒に食事をして、その後一緒に店に入るのさ」
僕はしばらく事態が呑み込めなかった。
もちろん、夜、飲みに行くのは決まって居酒屋だ。それも月に一度の贅沢、キャバクラなどまったく無縁の世界だと、今まで関心を抱いたことすらない。
それが突然、僕の目の前で実体のある世界として現れた。
「水月がホステスになったのか?」と、僕が恐る恐る聞く。
岡田は笑いながら、「おい、早とちりするなよ。まだ相手の男が愛人か客かなんて、分かったわけじゃない」
僕の心に岡田の言葉は届かなかった。水月が愛人になろうと、ホステスになろうと、僕が今まで抱いていた水月のイメージが音を立てて崩れたことだけは確かだ。僕は勝手に作り出した水月の虚像を、いつの間にか実体と思い違いをしていたのだ。
そして、水月は僕の知らない世界に去ってしまった。僕に何一つ告げずに、しかも、突然に。
「そうだ、水月がホステスになったのなら、彼女をつかまえる方法がある」
「えっ?」
僕は思わず岡田の顔を見上げた。
「毎晩同じ時間帯に店に出勤するはずだから、あの辺りで見張っていたら、いずれで会うことができるぞ」と、岡田が言う。
「そうか」
僕は黙って頷いた。今すぐにでも水月をつかまえて、真相を確かめたい。このまま放置された状態が続くと、僕の心臓はこれ以上耐え切れそうにない。水月に会えるなら、僕は毎晩何時間でも見張り続けるだろう。
「あっ、いけない。もう次の講義が始まる」
岡田がそう言って、慌てて立ち上がろうとする。そして、
「探偵業もたまにはスリルがあって、面白いぞ」と、別れ際に言った。
「お前はお気楽でいい」
僕はそう言って、手を振った。
それからどれだけキャンパスを彷徨っただろう。僕の眼は絶えず水月の姿を探し求めたが、やはり彼女の姿を見かけることはなかった。
僕は懸命に水月の情報をかき集め、頭の中でそれを整理しようとした。幼い頃、母親に火の山で焼かれたこと、ずっとひとりぼっちで淋しかったこと、そして、火の山の夢を僕と共有していたこと。
でも、水月の住所も知らない。携帯番号も知らない。家族関係も知らない。生い立ちも知らない。僕は水月に関して、現実の情報を何一つ持ち合わせていなかった。
僕の胸の中にいつの間にか住み着いた少女の幻影と水月が重なって、僕は現実と幻想との境界をすっかり見失っていた。そして、今、僕は何の手がかりもないまま、現実の水月を捜し求めている。
嘔吐感は止まらなかった。
やがてすっかり疲れ果て、僕はキャンパスの最も奥深いところにある、六号館の裏の芝生で体を横たえた。そこはこんもりと木々が繁り、ちょっとした隠れ場所になっている空間だった。
いつか水月と二人で仲良く並んで、寝そべったことがある。あの時、水月は「私にはあなたしかいないの」と囁いた。
芝生の上に寝転がると、青い空が透き通るようだった。早朝に小雨でも降ったのか、芝生はほんのり湿っていた。
木の枝の先には小さな露が溜まっている。今にも落ちそうで、かろうじて枝にしがみついている。
学生サークルであろうか、遠くで男女の歌声が聞こえてくる。急に体がふわっと軽くなり、世界が突然、僕の前から消えた。
随分眠った気がする。
微かな気配に目を覚ました。
「捜したのよ」
目を開けると、目の前に水月の姿があった。
水月は大学のキャンパスにふさわしくない、明るいピンクのワンピースを着ていた。いつもより少し濃い目のルージュを塗っていたが、それがきらきらと光って艶やかだった。目の錯覚かと何度も瞬きしたが、水月の姿が掻き消えることはなかった。
「僕だって、ずっと捜してた」
脳裏に水月に投げかけたい言葉が次々と溢れ出してきた。いったいなぜ、何のために、どんな理由があって、どんな思いで、連絡を絶っていたのか、と。
水月はそっと僕の髪を細い手で撫で、
「ごめんね。お母さんが病気だったの」と言った。
その瞬間、僕は自分の体が軽くなるのをはっきりと感じていた。様々な疑問がすべて氷解したわけではない。それどころか、新たな疑惑が次々と浮かんでは消えた。だが、それとは別に、胃の底に沈んだ嫌な固まりが溶け出し、体が宙に浮くような感じがした。
突然、笑いが込み上げてきた。笑いは止めどなく込み上げ、僕は声を押し殺しながら、笑い続けた。
「やっぱり変な人」と、水月が優しい調子で言った。
僕には水月が現実に僕の目の前に存在し、しかも、僕に屈託のない笑顔を見せるだけで、今までの苦しみから一度に解放された気がしたのだ。
これほど水月を必要としていたのか。
「よかった」
僕は起き上がり、真正面から水月の顔を改めて見つめ直した。
「いやよ、じろじろ見たら」と、水月が言った。
水月のキャンパスに不似合いな派手な衣装を見て、僕は何だか不安になってきた。
「今日はそんな格好して、どうしたの? この後、お店にでも出勤するの?」
僕の口から思わずそんな言葉が飛び出した。水月は一瞬きょとんとした表情になって、
「お店?」と、首を傾げた。
そして、「何を寝ぼけているの?」と、僕の額を軽く指で弾く仕草を見せた。水月が特に不快な表情を見せなかったことに安堵し、「キャバクラのホステスになったのかと、心配していたんだ」と言った。
「えっ、ホステス?」と、水月が驚いた声を出す。
そして、僕の顔をまじまじと見つめた後、水月はクスッと笑って、「あなた、狐に化かされたのよ」と言った。
僕は思わず空を見上げ、大きく息を吸った。澄みきった青空が僕の眼の中に飛び込んできた。何のためにあれほど苦しんだのか。絶えず僕を襲った嘔吐感が、すっかりと消え去っていた。
「岡田が言ったんだ。夜、歓楽街で、君が男と腕を絡めて歩いているのを見たって」
水月はその言葉を聞いた後、少し顔をしかめて、「バカね、私、そんな所、行ったこともないわ」と言った。
「よかった。本当によかった。人違いだったんだ」
「もちろんよ」と、水月が微笑んだ。
ただ次の瞬間、水月の表情に暗い影が残ったことを、僕は見逃さなかった。僕の胸の奥に一瞬、不安の影がよぎった。
久しぶりに会った水月は、かつての水月とどこか違っていた。容姿も声も、そして表情も、仕草も何一つ変わったところがないのに、それでもやはり何かが確実に変わっていた。
彼女を構成する細胞の一つ一つが、それぞれほんの少しずつ変化したように思えて、それが僕を絶えず不安にさせた。もともと透明感があった水月の肢体が、さらに透明さを増したようだった。その分水月の存在が希薄になり、僕はその頼りなさに戸惑っていた。
水月は黙ったまま、僕の横に腰を下ろした。甘い石けんの匂いが鼻につき、僕は一つ溜息をついた。
今僕が手を伸ばせば、水月の両肩を抱き寄せることができる。だが、水月との間には見えない壁が横たわっていた。その透明な壁は思いの外頑丈で、とても突き崩すことができないように思えた。
僕は黙って水月の横顔を見つめていた。水月が以前よりも美しくなったような気がして、その美しさが逆に僕の胸を締め付けた。何だか水月が身近な存在ではなくなったような感じがした。
水月も正面の木々を見つめたまま、自分から口を開こうとはしなかった。
僕は水月が口を開くのを恐れた。何か取り返しが付かないような、そんな言葉が口から零れるのを恐れた。
突然、水月が僕の方を振り向いた。その視線が僕の眼を貫いた時、僕は言葉を失っていた。
「もうじき冬ね」と、水月がぽつりと言う。
「ああ」と、僕が答える。
たったそれだけの会話なのに、僕は水月の口調から不吉なものを予感し、極度な緊張を解くことができなかった。水月の声には暖かみが欠けていたのだ。
「もうすっかりお尻が冷たくなっちゃった」と、水月が言う。
「どこか場所を移動する?」と、僕が慌てて聞く。
「ううん、ここでいいの。しばらくここでこうしていたい」
そう言って、水月は両腕を少し後方の地面に突き、自分の体を支えるようにした。両足が、僕の前に綺麗に揃えて投げ出された。
「お母さんが病気だって?」と、僕が恐る恐る聞く。
「うん。でも、もう大丈夫よ。連絡できなくて、本当にごめんなさい」
「随分心配したんだ。ずっとずっと水月からの電話、待っていた」
僕はそれだけ言うと、しばらく口をつぐんだ。言いたいことは山ほどある。でも、今それを言い出したら、止まらなくなってしまいそうで、怖かった。
「本当にごめんなさい。でも、かけられなかった」
「かけられなかった?」
僕は訝しげに、水月を見た。水月はゆっくり頷いて、
「お母さんの看病をしながら、繰り返し考えたの」と言った。
「何のこと?」
僕は不吉な予感に怯えながら、おずおずと聞き返した。
「もちろん、あなたとのことよ。だから、あなたには会えなかったし、電話もしなかったの。一人きりでゆっくりと考えたかったから」
水月は何かを思い詰めたような表情で、じっと正面を向いていた。いったい何を思い悩む必要があるのだろう。二人は愛し合っているし、そこには何の障害もなかったはずだ。僕は何かを言わなければならなかったが、その時どんな言葉も思い浮かばなかった。
ふと水月の体に指で触れたいという衝動に駆られた、体のどこかに接触していなければ、水月がどこか遠くに行ってしまいそうで、不安だった。
水月の周囲にできた透明な膜を、どこか一点突破しないと安心できなかった。
水月は相変わらずじっと前方を睨んで、僕に厳しい横顔を向けたままだった。水月の小さな額にいったいどんな情念が渦巻いているのか、僕にはまったく見当が付かなかった。
水月は乾いた唇を噛みしめて、
「私たち、もう会わない方がいいと思うの」と小さな声で言った。
その瞬間、僕はさっと全身に鳥肌が立つのを感じた。死刑の判決を受けた罪人のように、僕は水月の言葉をどこか遠くで聞いた気がした。
喉がからからに渇いている。僕は掠れた声で、かろうじて「どうして?」とだけ聞いた。
「どうして? 僕のことが嫌いになったの?」
水月は宙を睨んだまま、ゆっくりと首を横に振った。
「じゃあ、どうして?」
僕は語気を強めて、たたみ掛けるように言った。手のひらはぐっしょりと汗ばんでいた。思わず水月の肩を揺さぶろうとした時、
「そんなに責めないで」と、水月が哀しげな声で言った。
「だって、分からないよ」と、僕が声を振り絞るように言う。
水月は何とも答えない。ただ澄んだ瞳から一滴、大粒の涙がこぼれ落ちた。
二人は黙ったまま、校舎の陰の銀杏の木を見つめていた。風が吹くたびに、木の葉が一枚ずつ、落ちていく。
僕は息を潜めて、水月の次の言葉をじっと待った。水月の肩が微かに震えているのが分かった。
僕はすっかり混乱していた。どうしていいのか、何も分からなかった。水月の決意を翻意させる言葉を懸命に考えたが、適切な言葉が何一つ思い浮かばない。
第一、水月が突然別れの言葉を告げる理由などどこにもないではないか。お互いに魂がつながっていると、あれほど愛を語り合ったはずなのに、理由もつけずに一方的に別れを宣言するなんて、とても信じることができなかった。
いったいあの時の水月はどこに行ってしまったのだろう。目の前の水月は透明で、息を呑むほど美しく見えた。それだけに水月の心が自分から離れてしまったと思うことは、心臓が締め付けられるようでつらかった。
突然、凶暴な感情が心の底から沸き上がってきた。心のどこかでそれだけは言っていけないという思いが掠めたが、自分でもそれを止めることができなかった。
「やっぱり他に男ができたんだ」
僕はその言葉を呑み込むことができなかった。そして、口にした後味の悪さが、僕を不快にさせた。
その瞬間、水月がいきなり立ち上がった。一瞬、上気した顔で僕の方を振り返ったが、その後何も言わずに歩き出した。僕は顔から血の気が引き、慌ててその背中を追いかけようとした。
そのとたん、水月がくるりと振り向き、「ひどい、私をそんな女だと思っていたの?」と僕を睨みつけた。
僕は呆然と立ちすくんだ。水月はきりりと僕を睨みつけたまま、唇を微かに震わせた。
「ごめん」
僕が小さく言う。
水月の厳しい表情に見て、僕は何か取り返しの付かない言葉を発してしまったことに気がついた。
僕は何かを言わなければいけないと思ったが、どんな言葉も脳裏には浮かばなかった。それどころか体が硬直して、足を一歩踏み出すことさえままならない。水月の感情の激しさに呆然とするばかりだった。
突然、水月の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。暫く何かを訴えるように僕を見つめた後、水月は僕に背を向け、小走りに去って行った。僕にはただ黙って、水月の後ろ姿を見つめ続けるしかなかった。
やがて水月の姿が小さくなり、僕は今まで座っていた芝生の上にぐったりと腰を下ろした。全身の力が抜けて、もう立ち上がる気力さえなくなっていた。
いったい水月の世界にどのような変化が生じたのだろう。そして、その世界にはもう僕が入り込む余地などどこにもないのだろうか。
水月が座っていた辺りをそっと手で撫でてみる。ほんの少し温もりが残っているような気がして、芝生に頬をこすりつける。芝生は少し湿っていて、草の匂いが呼吸と共に肺の中に入り込む。
僕は仰向けに寝転がってみた。視界が涙でぼんやりと滲んでいた。
何もかもが終わってしまったのだろうか。
こんなにもあっけなく、すべてが崩れ落ちてしまうものなのか。
この一週間、死に物狂いで水月を捜したことを思った。あの時絶えず感じていた嘔吐感は、もう体のどこにも残ってはいなかった。
立ち上がることのできないほどの虚脱感に襲われていた。僕には水月の怒りの激しさが理解できなかった。
見上げた空が、透き通るほど青かった。
☆第一章完結です。第二章からは、更に物語は大きな展開をし始めます。乞うご期待を。またもしよければ、感想をコメント欄にお書き下さい。
ありがとうございます。とても励みになります。
