
お絵描き初心者におすすめしたい。簡単に続けられる練習法4選
こんにちは。ご無沙汰しております。
課題に追われて中々更新できずにいました…申し訳ない…(:3[___]
前回は「お絵描き初心者は覚えておきたい大事なポイント」と題して、「基礎編」をお届けしました。
今回は第二弾として「練習編」、いわゆるお絵描きに興味はあるけど、何から始めればいいのかわからない!って方に向けた記事です。
紹介に入る前に、前提として頭に入れておいてほしいことがあります。
今回お伝えする練習法の目的は「短期間ですぐ上達!」ではなく、「年単位で継続し続けること」です。最終的な目標はお絵描きの習慣化で、「暇だしとりあえずゲームでもするか~」と同じように「暇だしとりあえずお絵描きするか~」となれることを目指しますが、ずぼらな私は習慣化に丸三年かかりました。。。
この経験もあって、継続することの重要性をお伝えしておきたい…となったわけです。イラスト上達を謳った教本は山ほどありますし。
なのでこの記事では難しい練習法を紹介せず、毎日やりやすい簡単な方法のみ取り上げています。とっつきやすいものだけを用意したので、人によっては「そんなもんとっくに知ってるわ!」ってなるかもしれませんが、一つでも参考にして貰えれば幸いです🙇
ちなみにおすすめの画材はA4用紙(500枚入りのコピー用紙)とH・4B鉛筆(三菱のUNI)です。どれも質より量が重要なので、安価な素材で気兼ねなくガンガン描きましょう。
では本題に入ります。今回紹介するのは「パターン運動」「ラインオブアクション」「単純化」「ドローイング」の4つです。
①一定のパターンを反復練習する「パターン運動」
皆さんはこういう落書きを見たことはあるでしょうか。

何の変哲もないただの落書きですが、実はこれって線を引く上で結構大事な基本動作だったりします。
腕はどの方向にも自由に動かせますが、きれいな線を引くための方向はある程度限られてきます。
右利きの人なら、腕を内転させながら斜め左下に線を引く動作をすることで、勢いのある線を引くことができます。指先だけ使った場合でも似たような感じになる。
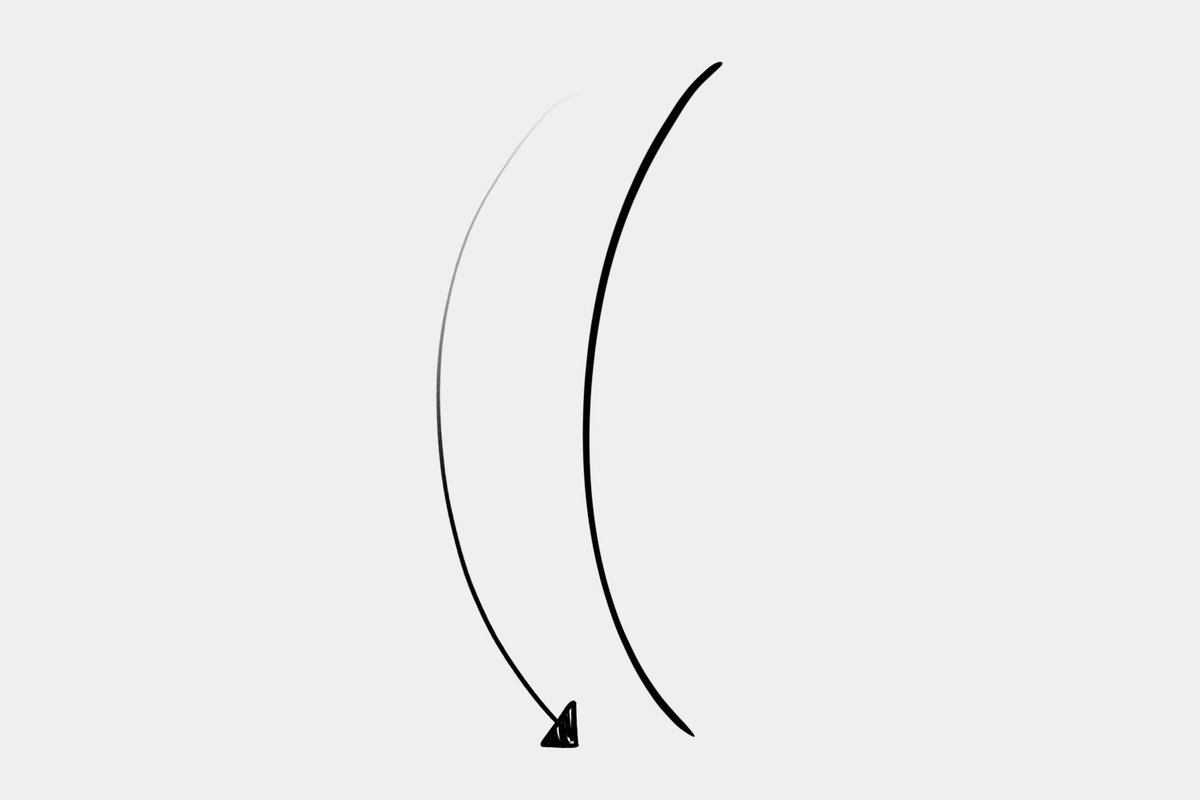
一見簡単ですが、腕の細かい筋肉の使い方にコツがあるので、最初は上手くいかないかもしれません(腕の内転に三角筋を、肘の固定に上腕三頭筋を使う)。
なので練習を重ねる必要があるのですが、それに最適なのが先述の落書きというわけです。
やり方は見ての通りで、反時計回りにぐるぐる線を引くだけ。
自分はこれに様々なパターンを加えて遊んでます。腕全体と指先を交互に使い分ける、特定のタイミングで力を入れてみる、時計回りにも回してみる等々…

普段から色んな方向に線を引いておけるようになると、思い通りの線がサッと引けるのでおすすめです。スピードが重要なドローイングでは特に重宝します。
基本動作を身につけるには反復練習が必須です。野球でいうところの素振りと同じ。
Hの鉛筆でがりがり描きましょう。ちなみに腕を動かすことが大事なので、同じ紙に重ねるように複数回描いても用紙の節約になるのでOK。紙はしわくちゃになりますが

②人体を一本線で表現する「ラインオブアクション」
動きを一本線で表現する練習法。媒体によっては呼び方が違うことも。


棒人間と似たような感じですが、ラインオブアクションではなるべく一本線でモチーフの動きを表現する必要があります。
単純な線を引くだけなので、まだドローイングに抵抗がある人にも始めやすい簡単な練習法です。
簡単なら結局は約に立たなくなるんじゃ?と思うかもしれませんが、間違いなくずっと役に立ちます。
複雑で難解なポーズを表現したいと思ったときにも、ラインオブアクションが動きの骨格部分+ポーズのガイドを果たしてくれます。たとえどんなにすばらしいイラストでもスタートはこういう簡単なことからだったりするので、是非やりましょう。
③モチーフをシンプルに捉える「単純化」
世の中に存在するモチーフはどれも複雑な形状をしていて、素材の材質や形状・陰や光の当たり方によって膨大な情報量を持っています。それらを全て描き切るのは至難の技なので、シンプルな形状に置き換えてわかりやすくしよう!となったのが「単純化」です。

皆さんの中には無意識に細部から描き込み始めてしまい、いざ全体を見てみたらバランスがガタガタになっていた経験はありませんか?自分は山ほどあります。
そういった事故を防止するために有効なのが単純化です。予め全体のシルエットをシンプルに捉えておくことで、バランス崩壊を防止できるというわけです。
これもお絵描きのどのシーンでも役に立ちます。スケッチやデッサン、ドローイングに本番でも有効な手法なので、できれば普段から意識的にやるようにしましょう。
また、モチーフをシルエットで捉える能力はできるかできないかでイラストの見やすさに大きく関わってきます。単純化はそのスキルを身につけるきっかけになるので、やって損はありません。
実際にスケッチするのも有効ですし、出先で「あれは丸っぽい」「あれは横に長い四角」とか考えるだけでもかなり変わってきます。意識的に習慣化しましょう。
④日々の日課「ドローイング」
スケッチや素描とも言いますが、今回のドローイングはPOSEMANIACSの「30秒ドローイング」を指します。有名な練習法なので、知っている人も多いのではないでしょうか。

これに関してはあれこれ説明するよりも、立中順平先生のドローイング本を読んだ方が早いです。人体を描く際のテンプレートもありますし、詳しいやり方やポイントは大体載ってます。
自分はお絵描きに関する教本を色々買ってきましたが、初心者に1冊だけ提案するとしたらこの本を薦めます。それくらい良本です。
自分も毎日ドローイングをやってます…が、あんまり人には見せません。というか、とてもじゃないですが人には見せられない(

これ、15秒ドローイングで1列に4体×3列の合計12体のポーズを描いてます。裏面も同様で、1日に24体描いてます。
A4用紙に収まりきらないので、ポーズの重なりを無視してガリガリ描くようになりました。その結果がこれだよ!
※自分は思い通りの線が引けるかどうかでその日の調子を判断する、いわゆる調子の把握にドローイングを用いているので、振り返りが大切な初心者にはオススメしません(
ここで一つ覚えておいてほしいのは、練習結果を無理に人に見せる必要は無いことです。SNSで毎日報告しなくていいんです。
自分も最初のころはSNSに投稿してましたが、他の上手い人と比較してしまったり、練習が義務化してしまってお絵描きが辛くなったのでやめました。今では人の目を気にせず、正真正銘の落書きを伸び伸びとやってます。その結果がこのザマですが(
当然ですが、毎日投稿するな!って意味ではありません。「投稿してない人もいるよ!辛いなら投稿しなくてもいいんだよ」「いい年して子どもの落書きみたいなことしてるやつもいるよ」ってことで一つ…いや二つか。
話を戻しまして…
始めのうちは余裕のある制限時間(60秒や90秒)にして、描き終わったら「どうすればもっと上手くなるかを考えて言語化し、メモ帳に記録して次回から改善していく」みたいな感じで、振り返りながらやるクセをつけると、継続と同時に上達もできます。4Bの鉛筆でガリガリやりましょう。
●まとめ
以上、ざっくりとご紹介でした。
自分の始めの頃は①を毎日こなしつつ、②・③・④をその日の気分でやってました。
現在も①で腕の準備運動を行い、④を日課として毎日続けています。
人によっては「こんなのやったところで意味あるの?」と思うかもしれません。正直自分も疑心暗鬼でした。でも、少なくとも自分は効果がありました。
記事の冒頭でもお話したように、この練習法の目的は「上達」ではなく「継続」することにあります。ぶっちゃけ何描くかなんてどうでもよくて、年単位で何かしら描き続けることに意味があります。質より量、量あっての質です。
なので調子が乗ってきたらデッサンや模写、何なら実際にイラストを描いたりと、色んなことにどんどん挑戦していきましょう。大抵のことはいざ始めてしまえば意外と何とかなります。それなりの下準備は必要ですが。。。
以上、継続しやすい簡単な練習法のご紹介でした。
もしよければスキやフォローをお願いします!また、メンバーシップでのご支援もぜひお待ちしております🙇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
