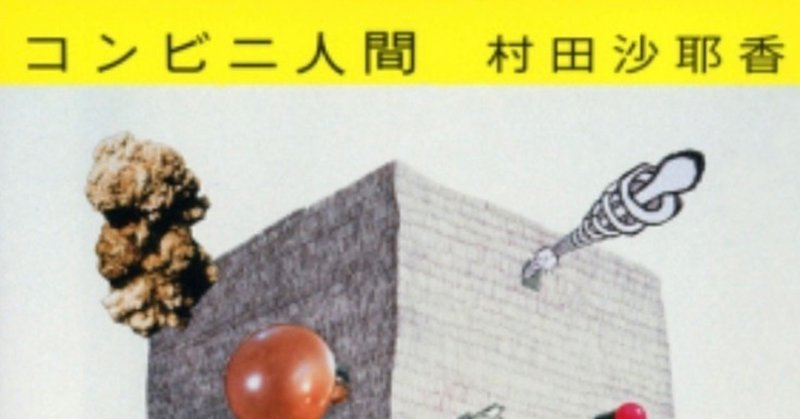
多様性って何?村田沙耶香さんの寄稿・全文⑬
どうもアコニチンです。
このnoteでは、代表作に「コンビニ人間」のある作家、村田沙耶香さんの多様性についての考え方について抜粋してあります。前半は⑫と同じ内容になっております。中略の部分も需要があれば書きますので、コメントもしくはTwitter→@debateaconitine にお願いします!
・・・・・・
子供の頃、大人が「個性」という言葉を安易に使うのが大嫌いだった。
確か中学生くらいのころ、急に学校の先生が一斉に「個性」という言葉を使い始めたという記憶がある。今まで私たちを扱いやすいように、平均化しようとしていた人たちが、急になぜ? という気持ちと、その言葉を使っているときの、気持ちよさそうな様子がとても薄気味悪かった。全校集会では「個性を大事にしよう」と若い男の先生が大きな声で演説した。「ちょうどいい大人が喜ぶくらいの」個性的な絵や作文が褒められたり、評価されたりするようになった。「さあ、怖がらないで、みんなもっと個性を出しなさい!」と言わんばかりだった。そして、本当に異質なもの、異常性を感じさせるものは、今まで通り静かに排除されていた。
当時の私は、「個性」とは、「大人たちにとって気持ちがいい、想像がつく範囲の、ちょうどいい、素敵な特徴を見せてください!」という意味の言葉なのだな、と思った。私は(多くの思春期の子供がそうであるように)容易くその言葉を使い、一方で本当の異物はあっさりと排除する大人に対して、「大人の会議で決まった変な思い付きは迷惑だなあ。また大人たちが厄介なこと言いだしたなあ」と思っていた。平凡さを求められたほうが、それを演じればいいのだから、私にとってはずっとましだったのだ。「(大人が喜ぶ、きちんと上手に『人間』ができる人のプラスアルファとしての、ちょうどいい)個性」という言葉のなんだか恐ろしい、薄気味の悪い印象は、大人になった今も残っている。
大人になってしばらくして、「多様性」という言葉があちこから、少しずつ、聞こえてくるようになった。
最初にその言葉を聞いたとき、感じたのは、心地よさと理想的な光景だった。例えば、オフィスで、様々な人種の人や、ハンデがある人、病気を抱えている人などが、お互いのことを理解しあって一緒に働いている光景。または、仲間同士の集まりで、それぞれいろいろな意味でのマジョリティー、マイノリティーの人たちが、互いの考え方を理解しあって、そこにいるすべての人の価値観がすべてナチュラルに受け入れられている空間。発想が貧困な私が思い浮かべるのは、それくらいだった。
それが叶えばいいという気持ちはずっとある。けれど、私は、「多様性」という言葉をまだ口にしたことがほとんどない。たぶん、その言葉の本当の意味を自分はわかっていないと感じているからだと思う。その言葉を使って、気持ちよくなるのが怖いのだと思う。私はとても愚かなので、そういう、なんとなく良さそうで気持ちがいいものに、すぐに呑み込まれてしまう。だから、「自分にとって気持ちがいい多様性」が怖い。「自分にとって気持ちが悪い多様性」が何なのか、ちゃんと自分の中で克明に言語化されて辿り着くまで、その言葉を使って快楽に浸るのが怖い。そして、自分にとって都合が悪く、絶望的に気持ちが悪い「多様性」のこともきちんと考えられるようになるまで、その言葉を使う権利は自分にはない、とどこかで思っている。
こんなふうに慎重になるのは、私自身が、「気持ちのいい多様性」というものに関連して、一つ、罪を背負っているからだ。
(中略)
誤解なく伝えられるように願っているが、あるときから、メディアの中で、私に「クレージーさやか」というあだ名がつくようになった。それは、最初は友人のラジオの中で、愛情あるお喋りの延長線上で出てきた言葉だった。だから、最初、私はうれしかった。
けれど、だんだんそれが、単なる私のキャッチフレーズとして独り歩きするようになった。ある日、テレビに出たとき、そのフレーズをキャッチコピーのように使うことを、私はいいことだと思って許諾してしまった。多様性があって、いろいろな人が受容されるのは、とても素敵なことなのではないかと思ったのだ。
そのとき、私という人間は、人間ではなくキャラクターになった。瓶に入れられ、わかりやすいラベルが貼られた。テレビに出ると、そのフレーズがテロップになり流れるようになった。私は馬鹿なので、社遺書はそのことが誰かを傷つけていることに気づかなかった。
「村田さんがお友達に『クレージー』と言われているのは、村田さんが愛されているのを感じて、私までうれしいのですが、テレビやインターネットでそう呼ばれているのを見ると、とてもつらく、苦しい気持ちになります」
文面や詳細は違うが、私の元に何通かこのような手紙が届いた。理由は様々で、「村田さんと自分は似ていると感じるからかもしれませんが、自分が言われているような気持ちになります」という方もいれば、「村田さんのことを知らない人に村田さんが笑われれているのを見るのが、残酷な構造を見ているようでつらいです」という方もいた。「村田さんはどうおもっていらっしゃいますか?」という、心のこもった、丁寧な質問に、私はまだ返事を書くことができていない。
笑われて、キャラクター化された、ラベリングされること。奇妙な人を奇妙なまま愛し、多様性を認めること。この二つは、ものすごく相反することのはずなのに、馬鹿な私には区別がつかないときがあった。
「村田さん、今は普通だけれど、テレビに出たらちゃんとクレージーにできますか?」
深夜の番組の打ち合わせでプロデューサーさんにそういわれたとき、あ、やっぱり、これは安全な場所から異物をキャラクター化して安心するという形の受容に見せかけたラベリングであり、排除なのだ、と気が付いた。そして、自分がそれを多様性と勘違いをして広めたことにも。
私は、そのことをずっと恥じている。この罪を、自分は一生背負っていくことになるのだと思う。私は子供の頃、「個性」薄気味悪さに傷ついていた。それなのに、「多様性」という言葉の気持ちよさに負けて、自分と同じ苦しみを抱える人を傷つけた。
私には「一生背負っていこう」と思う罪がいくつもあるが、これは、本当に重く、そしてどう償っていいのかわからない一つだ。
どうか、もっと私がついていけないくらい、私があまりの気持ち悪さに吐き気を催すくらい、世界の多様化が進んでいきますように。今、私はそう願っている。何度も嘔吐を繰り返し、考え続け、自分を裁き続けることができますように。「多様性」とは、私にとって、そんな祈りを含んだ言葉になっている。
・・・・・・
以上で引用を終わりにします。
「多様性」は気持ちのいい言葉で、なんとなく言っておけばいいんでしょ?というか、これさえ言えば「多様性」を理解している、自分が時代の流れに乗った人権主義者になったような(決して老害などではない)気になれます。大学で、ジェンダーに関する講義を受けたときも、キーワードとして「多様性」を使う=「性の多様性」に理解を示している、みたいな節があったのを覚えています。もちろん先生は「多様性」「多様性」と言っていたわけではないし、「性の多様性」の本質を探る授業だったんですけど、これさえ言えばOK!単位くれる!授業理解してる!とアピールする「ただの言葉」に成り下がっていた気がします、私の中で。
感想はさておき、多様性に関する持論を下にあげておきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
