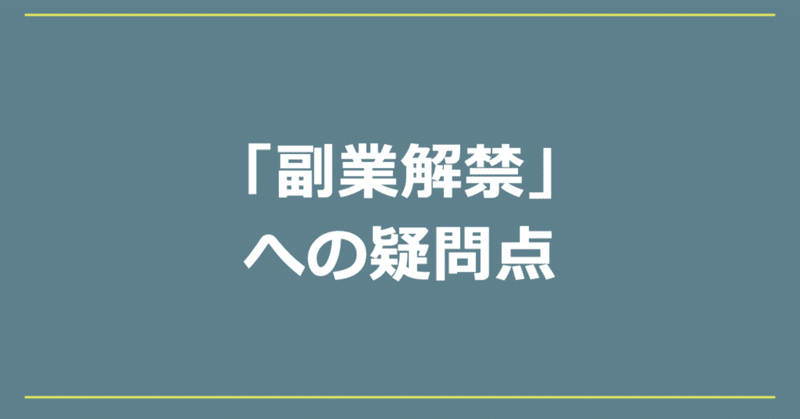
「副業解禁」への疑問点 (2022/6/27)
記事の長さはおよそ2,000文字。3〜4分程度で読めます。
副業解禁、企業に促す
厚労省 制限なら理由開示
成長分野に人材移動
記事のポイント
厚労省は企業に対し、従業員に副業を認める条件などの公表を求める方針。
副業や兼業について定めた厚労省の指針を7月に改定する。罰則等の強制力はなく、国から企業側への要請の位置づけ。
厚労省の指針はすべての企業を対象に原則、副業を認めるよう促している。
現在の指針では①労働者の安全 ②業務秘密の保持 ③業務上の競合回避 ④就労先の名誉や信用、の4点いずれかを妨げる場合、企業は副業を禁止または制限できると定めている。
厚労省は指針を改定し、副業についての姿勢や容認する条件等の開示を企業に要請する。副業の可否はすでに就業規則で示している企業も多いが、ホームページなどで公開し、外部の人や投資家などにもわかるようにする。
政府は副業の普及が成長分野への人材移動につながると見る。
ランサーズ社によると、雇用形態に関係なく2社以上の企業と契約する兼業の形で働いたりする国内労働者数は2021年の推計で812万人。前年比で15%増え、労働力人口の1割を占める。
企業側にとっても副業をする従業員が社内にないスキルやノウハウを身に付ければ、自社の成長や新規事業に役立てられる可能性がある。
最近ではキリンホールディングスや三菱地所、IHIなど大手でも副業を認める動きが相次ぐ。
**********************
成長分野への人材移動を目的に、副業や兼業を原則認める方針なのだそうです。
今回の改定について、みなさんはどう思われますか?
私は、兼業・副業を原則解禁すること自体には反対ではありませんが、今回の改定方針にはいくつかの疑問点がありますね。
「成長分野への人材移動」につながると思えない
大企業に属したまま兼業・副業で別の仕事ができるのであれば、わざわざ安定した大企業を辞めてまで成長分野の企業に移動しようと思う人は限られるのではないでしょうか。
大企業で働いている=就職先に大企業を選んでいるということは、勤務先には「安定性」を重視している方が多いのではないでしょうか。
一般的には成長分野の企業は、仕事内容はチャレンジングで魅力的だとしても、規模としてはまだまだ小規模で不安定な場合が多いと思います。
大企業に属したままで副業できるのであれば、安定した立場を捨ててまで転職する人は少ない気がします。
兼業・副業できるスキルを持った人がどの程度いるのか
兼業・副業するためには、他社がお金を払って使いたいと認めてくれるスキルを持っている必要があります。
日本企業では、専門的なスキルを深めるより、自社内で使えるスキルを広く・浅く学ばせる傾向が強いように思います。
そんな環境で育った方の中に、他社が価値を認めるほどのスキルを持った人がどれくらいいるのでしょうか?
少ないとすれば、厚労省の目論見ほどの人材の移動は起きないのではないでしょうか。
社内にないスキルやノウハウが身に付くか
兼業・副業を解禁する企業は、社員が他社で副業することで社内にないスキルやノウハウを身につけてもらい、自社の成長や新規事業に役立てられる可能性に期待しています。
副業が成り立つのは、特別なスキルを持ったA社の社員Bに、そのスキルが社内にないC社で働いてもらうからです。
副業を受け入れるC社にとっては、社員Bに働いてもらうことで社内に新たなスキルやノウハウが蓄積されるのは間違いないでしょう。
一方、BがC社で働くことで、A社の新規事業に役立つほどのスキル・ノウハウが身に付くものなのでしょうか。
そもそもそれほどのスキル・ノウハウを他社から持ち帰ってもいいものなんでしょうか?
雇用形態の違いは何か?
兼業・副業が原則可能となると、「正社員」と「業務委託」など雇用形態の違いが曖昧になってきますね。「正社員とは何か?」の再定義が必要になりそうですね。
制限理由の開示を促す必要はあるのか
兼業・副業を認めるかどうかは、各企業が判断することだと考えます。
副業を認めないことで、仮に企業の評判が下がったとしても、そういう決定をした企業が受け入れればよいことです。
そうならないよう、第三者が開示しろと指図することではありません。
副業を認めるように促すことはわかりますが、制限なら理由開示を求めるのは明らかにやりすぎに思えますね。
役所がなんらかの方針を決めれば、たとえ強制力がなくても、 ー 少なくても表面上は ー 大企業は遵守しようとします。
今回の改定では経団連等の経済団体とも連携するそうなので、その傾向が強くなるでしょう。
政府(厚労省)の目論見通りには、いかないように思えてなりません。
本投稿は日経新聞に記載された記事を読んで、
私が感じたこと、考えたことについて記載しています。
みなさんの考えるヒントになれば嬉しいです。
「マガジン」にも保存しています。
「学びをよろこびに、人生にリーダシップを」
ディアログ 小川
美味しいものを食べて、次回の投稿に向けて英気を養います(笑)。
