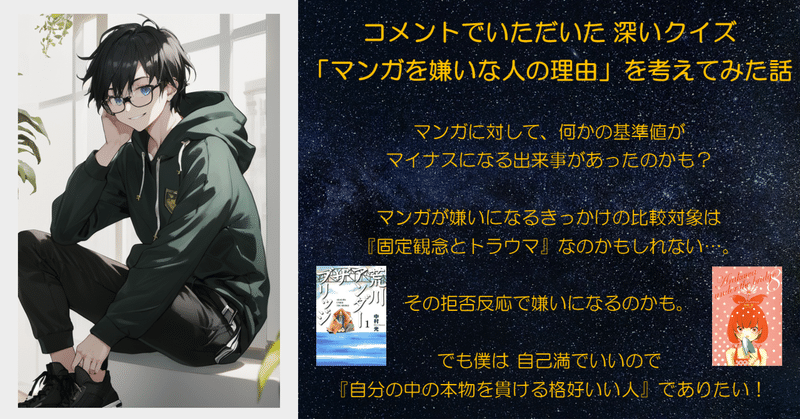
【自分語り日記】コメントでいただいた深いクイズを考えてみた話
今回はマンガが好き過ぎて、マンガの貯蔵量が60,000冊を越えながらも、毎月新しいマンガを買い漁る僕が、とある記事のコメントでいただいたクイズについて考えをまとめてみたお話を記したいと思います。
細かな経歴はプロフィール記事を見ていただけると幸いですが、この記事の概要をお伝えすると「先日、僕の記事にたくさんの長文コメントをくれた方がいて、最後に投げかけてくださったクイズの答えと考え方」をリンクさせた経験を書いています。
お題は『マンガを嫌いだと思う人は、なぜ、マンガが嫌いだと言うのか?』です。
深い…。マンガが好きな僕には考えつかない質問だと思い、クイズへの回答という意味も込めて、僕なりの考えを深掘りしたいと思います。
回答に行きつく5つの思考アプローチ
僕はまず『マンガを嫌い』という言葉の中で、マンガと嫌いを接続している言葉が『を』なので、もともと好きかそもそも興味がないとか、普通で何とも思わないとか、そういった基準値が何かをきっかけにマイナスになって「嫌いになった」というニュアンスなのかな?と考えました。
そうすると、『何かと比較して』マイナスになることがあったんだろうなと推測できるので、一般的にマンガが嫌いになる理由にはどんなことがあるかなと、少し整理してみました。
①表現方法が合わない
②テーマが合わない
③読書環境の違い
④時間や興味の制約
⑤カルチャーへのギャップ
パッと思いついたのは、この5つです。
簡単にどんなことかをまとめると、①「表現方法」はマンガには独自のアートスタイルや物語性があるので、イラストの絵やコマ割り、ストーリーなどが自分の好みに合わない場合に、マンガそのものが嫌いになる可能性があるのかな?…と思います。
②の「テーマ」は、マンガにはたくさんのジャンルが存在するので、その内容も多岐にわたるため、特定のテーマ性が好みに合わない場合ですかね。
先ほどのストーリーにも関わってくる部分ですが、ファンタジーやラブストーリー、バトル、ヤンキー系の喧嘩が苦手など、そのジャンルやテーマ性に対するなどが自分の好みに合わない場合に、マンガそのものが嫌いになる可能性があるのかな?…と思います。
③「読書環境の違い」は、マンガは視覚的なコンテンツなので、絵で語ってくる表現や文章を読むことが苦手な人にとっては、辛い部分があるかもしれません。
視覚的でも文章を読まなくていいアニメなどの動画や聴覚的で音で楽しんだり、小説やビジネス書なども読み上げてくれるものがあったりする世の中なので、本を読むこと対する環境が自分の好みに合わない場合に、マンガそのものが嫌いになる可能性があるのかな?…と思います。
④ 「時間や興味の制約」は、マンガって長編(巻数が多い)やシリーズになるものがおおいので、マンガに時間を充てることが難しいと感じる人もいるのではないでしょうか。
YouTubeやTwitter、Instagram、TikTokなどいろんな趣味に使いたい時間があると思いますし、長編作品だと作中でテーマがガラッと変わったりもするので、②のテーマと絡めて、マンガそのものが嫌いになる可能性があるのかな?…と思います。
最後の⑤「カルチャーのギャップ」は、マンガの中にたまに反映される日本独自の文化や社会的背景が理解しづらいという場合ですね。
②のテーマにも関わってきますが、まさに自分と異なる価値観が描かれているので、好みというよりも生理的に受け付けないという感覚で、マンガそのものが嫌いになる可能性があるのかな?…と思います。
これら①〜⑤の理由の組み合わせやこの他の要因によってマンガを嫌う理由は異なるかとは思いますが、特に②と⑤の『テーマ・カルチャー』あたりが『何かと比較される対象』となっているのではないかと思いました。
マンガが嫌いと思う理由(行きついた回答)
僕は結論として、マンガが嫌いになるきっかけの比較対象は『固定観念とトラウマ』ではないかという考えに行きつきました。
マンガでいい思いをしたことがなかったり、「マンガって〇〇だからかなぁ」みたいなものが刷り込まれたか、形成されているからだと思います。
これらの想いはマンガだけでなく、小説や映画なども当てはまるのではないかと思いますし、唐突ですが僕は「環境の違い」の観点で映画が苦手です。
映画というか60分を超える動画は見ていると眠くなり、見れない体質みたいな感じなので、ドラマなども結構きついタイプですが、嫌いになっていくのは過去のトラウマや培われた固定観念です。
金曜ロードショーなどでジブリ作品を毎週楽しみにしていても最後まで見れず、最後まで見ることのできない(結末を知れない)ものを見るのは無駄だと思う固定観念が作られて、そして映画などに興味を持たなくなっていく。
それはジブリだけなく、トイストーリーやミニオン、タイタニック、ハリーポッター、パイレーツオブカリビアンなどの海外作品の有名どころであっても…。(古い作品の知識しかなくてすみません…)
僕は周囲の人たちから「人生を損してる」と言われ続けていますが、人生で一度も映画館に行ったことがなく、DVDやBlu-ray、TV放映で映画を最後まで見た作品がありません。
それは、僕が『固定観念とトラウマ』によって、映画が嫌いという深層心理で拒否反応が出ているのだと思いますし、好奇心旺盛ですぐ行動するタイプではありますが、ここまできて映画を見るのはどうなんだろうという謎の虚勢から行動を起こせなくなっている始末です…。
話が脱線しましたが、この『固定観念とトラウマ』によって勝手に自分の好きなことや許容範囲と比較して、無理と判断されたものが受け付けなくなるんだと思います。
「マンガの持つ多様性」が、自分の価値観や個性に合わないと拒否反応を起こしているのかもしれませんね。
たくさんのコメントをいただいた中に、このような内容がありました。
今、大勢の人に流行ってるマンガの傾向ってなんだと思いますか?『いろんな時代』に『冒険』できて、『知らない世界』に『連れ出してくれる』マンガが流行ってます。簡単にいうと、現実逃避のマンガが流行ってます。ストレス社会なので。
この現象は逆に『固定観念とトラウマ』に共感を得たいからなのかもしれません。
僕は『荒川アンダーザブリッジ』という作品が大好きです。
主人公のリクが荒川の河川敷の住人たちの意味不明な考え方や価値観に染まりつつ、ふと村長の行動を褒めるP子の言葉にハッとさせられて、ギャグ漫画なのにシリアスすぎて笑えない作品です。
非常識って何?他の人と違うところ?だったらあの人は確かに非常識だわ。誰よりも非常識。非常識だけど、非常識な生き方にブレがない。なぜならそれが村長の中で一番本物の生き方だからよ。自分の中の本物を貫けるって、格好いいでしょ?
この言葉はまさに多様性や個性の受容が求められる時代になってきたこともあって、僕は「常識って何?」と問われることで、自分の中の本物を貫く生き方に改めて気づかされたからこそ、いろんなマンガを読み続けて発信する側に回ろうと思ったきっかけをくれた作品でもあります。
世の中的に、いろんな種類の『ストレス』がかかるようになって、無意識にそれを溜めていることもあると思います。
そして、ストレスがかかる事象にはたくさんの種類がありますが、「ストレスをかけてくる人」や「上乗してくる人」がいることもあり、「逃げよう・サボろう・やめよう」とすることで、軽くすることもできます。
コメントでは僕を労ってくれたのか、心配してくれたのか、そんな無理をするなと温かい言葉が並べられていました。
でも僕は『荒川アンダーザブリッジ』の村長(カッパ)に憧れ、自己満でいいので『自分の中の本物を貫ける格好いい人でありたい!』と思っています(笑)。
まとめ
Q:『マンガを嫌いだと思う人は、なぜ、マンガが嫌いだと言うのか?』
A:『固定観念とトラウマに対して、無意識に比較して拒否反応が起きているから。』
答えが合っているのかどうかはわかりませんし、その拒否反応に突っ込んでいく必要もないと思います。
でも僕のnoteのサブテーマでもある『一歩を踏み出す勇気』には、「マンガの持つ多様性」を考慮して、マンガというコンテンツ・媒体やその中で自分の好みと異なる作品やジャンルを試してみることで新しい発見があるかもしれません。
そこで巡り合う価値観や発見できたことで、少しでも一歩を踏み出すきっかけになれたらと思っています。
僕は仕事柄、メーカーの人事で採用や研修を行なっているため、後悔しないように全力で取り組んでみることをオススメしている立場です。
だからこそ一歩を踏み出すために勇気をもらえる言葉を大切にしていきたいです。
僕はストーリーのある内容の本を読むことが好きで、それは「いろんな人の気持ちになれるから」という部分があります。それは小説やドラマや映画、アニメなどもそうなのかもしれませんが僕はマンガでした。
そして名言・自分に刺さる言葉を集めることを始め、いまでは60,000冊を超えるほどマンガに熱中し、そしてこの経験を踏まえて、マンガやその作品の中にある名言で誰かが救われる可能性があるならnoteに残して伝えたいと思ってブログを始めました。
今回はとある方からのコメントについて考えてみるという、少し興味を持ちづらい内容だったかもしれませんが、自分の気持ちを整理するための日記であることも含めて、この記事を残したいと思います。
それでは今回はここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
