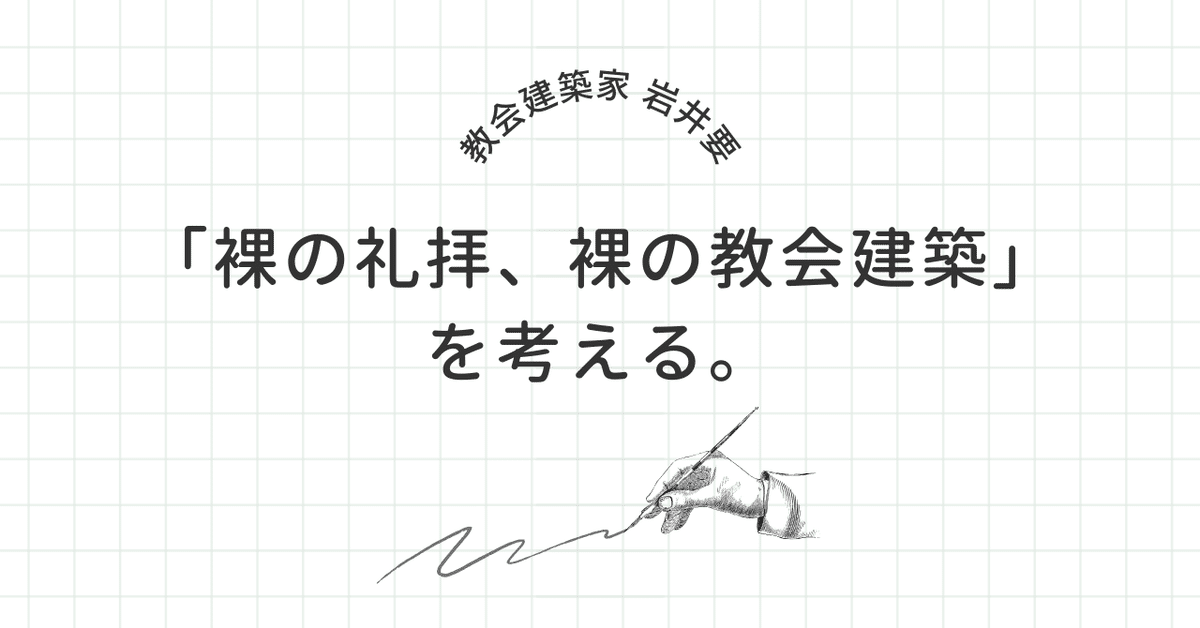
教会建築家岩井要の著書を通して、「裸の礼拝、裸の教会建築」を考える。
執筆日:2023年12月07日(木)
更新日:2023年12月07日(木))
オフィシャルサイト(ポートフォリオサイト)
裸の礼拝、裸の教会建築
教会建築を数多く設計された岩井要氏が1965年から約30年間で手掛けた作品を収めた著書『天と地をつなぐ空間-教会堂 : 岩井要・真建築設計事務所作品集1965-1995』(日本基督教団出版局, 1995.11)は、日本の教会建築の歴史を丁寧に紐解きながら、ご自身の教会建築に対する考え方を述べつつ、最後に今後の教会建築の在り方を示しています。日本の教会建築は、少子高齢化、信徒数の減少、建築費の高騰、老朽化や耐震問題が顕著に表れ、建替えの必要が迫られている教会を数多くあります。この様な状況の中、日本の教会建築、特にプロテスタント教会の建物では、たくさんの諸室を今までと同じように求めることの必要性に疑問を感じていました。過度な装飾のように、たくさんある部屋は、限り少ない予算の中で、多くの割合を占めてしまい、一番大切な礼拝堂の席数を小さくせざる負えない状況をつくりだし、本末転倒のような気がしていました。もちろん、尊敬する建築家奈良信氏が「総合的施設が伴ってこそ始めて教会」だと述べていることに反論はないのですが、平均の信徒数が20人程度の小さな教会がほとんどのプロテスタント教会では、もっと削ぎ落としていく必要があると思っています。奈良信氏に直接、教会建築で大切なことは何かを伺った際には、「礼拝堂とつながる集会室」の重要性を語られていたいの覚えています。確かに、礼拝が終わると、集会室に集まり、昼食祈祷会などの交わりのときをもつ教会が多くあります。
神学者であり日本基督教団隠退教師の加藤常昭氏が「教会堂とは、そもそもいいったい何なのであるか、どのように建てたらよいのかという問いは不可避である。私たちの福音宣教のわざに教会堂は不可欠のものであるのか。信じて生きる者にとって、礼拝堂はいかなる意味を持つのか。教会や教会堂の大小を問わず、これらの問いに対する答えをどうしても手に入れなければならない」と述べているように、前述した諸問題や、コロナ禍を経験した私たちは、これからの教会、教会建築をどのようにしていかなければならないのか、多様な人々と共に熟慮していく必要があります。
教会建築と共に歩む
わが国最初のプロテスタント教会堂は、宣教師J.H.バラとS.R.ブラウンによって横浜に建築された。1871年(明治4年)のことである。
この建築は石造の小会堂で、後に「神聖なる犬小舎」と綽名されている。今年1995年より124年前のことである。
ここに収めた作品は、1965年前後から約30年間に、私の主宰する真建築設計事務所が手掛けた教会堂とYMCAその他の集会施設である。今年は敗戦50年という節目でもある。この時に自らの仕事を記録し、また顧みることによって、改めて戦後の会堂建築を考えるよすがとしたいと思う。幸い初期の頃からずっと一緒に仕事をしてきた建築写真家・佐藤雄一氏の協力を得て、ようやく作品集の実現をみることとなった。
ところで、この30年を含む戦後50年の教会建築の変遷を位置づけるためにも、日本の会堂建築の歴史を復習しておく必要がある。明治以来たどってきた会堂の歴史はどのようであったろうか。大正、昭和の戦前と戦後はどう変ったのであろうか。またそれらの歴史をふまえつつ、今日の教会は何を考えているのであろうか。次の時代に向かってどのような課題を担っているのであろうか。そう考えていくと、ここで触れるには少々問題が大きすぎる。またそれを論じるには充分な準備もない。しかし不充分ながら日頃考えたことをこの機会に覚え書きとして記すこととした。
会堂建築の歴史I
——明治初期の会堂から1945年まで——
わが国のプロテスタント教会は、教勢の進展に伴い、明治の中頃から、東京、横浜、京阪神の地域を中心に、全国各地に少なからぬ会堂を建築していった。その建築の推移は、当然のことながら、日本の建築界の近代化と軌を一にするものであった。明治期には、来日宣教師自身が、ついでその指導・影響を受けた宮大工や棟梁たちが、建築の主な担い手であった。明治の後期から大正期になると、教会堂の建築にも政府雇用の外国人建築家や、彼らに育てられた日本人建築家が登場し、やがてキリスト教界内部で育った建築家も現れる。建築工法や技術の面では、レンガ造、石造など西欧式工法に従って建築したり、木造の場合も洋式トラス(会堂の大きい空間を覆う骨組)が採用されたりする。やがて鉄筋コンクリート造が普及するにつれて、大都市の教会はこれに倣うものが多くなった。しかし大多数の中小教会堂では木造建築が主流であった。
さて戦前60年余りの間、日本の教会堂の建築表現に最も大きな影響を与えたのは、どのような様式であったろうか。それは一言でいえば米国のピューリタニズムの流れを汲む様式であった。しかしその流れは必ずしも明快なものではなく、日本に派遣された宣教師が所属する教派によって、異なっていたと考えられる。しかも丁度その時代は欧米のプロテスタント教会堂が大きく変化し、混乱した時期でもあった。19世紀から20世紀初めにかけての建築様式の傾向は、一般にロマン主義と呼ばれた。この傾向は当時の会堂建築にも影響を及ぼしたが、これに対して英国教会内部ではゴシック・リバイバル運動が起った時期でもあった。
こうした背景の中で日本の初期会堂建築のスタイルがつくり出されていったことは、今日に至るまで大きな意味を持っている。
戦前の教会建築の歴史は、共著『教会建築』(日本基督教団出版局、1985年)の中で奈良信氏により興味深くまとめられている。氏の著述に学びつついくつかの点に触れておきたい。その中で特に注目したいのは、小崎弘道牧師の構想により辰野金吾の設計になる霊南坂教会(1917年)とW.M.ヴォーリズの建てた一群の教会堂である。霊南坂教会は当時日本建築界の大家による設計(後の研究でヴォーリズの相当な協力があったとされている)として著名であるが、奈良氏はむしろ小崎牧師の構想に着目して、次のように述べている。「小崎には本来『大教会』という発想が常にあった。それは必ずしも『大礼拝堂』ということばかりではなく、教会というものは、礼拝堂の他に、日曜学校の礼拝堂や教室、青年会・婦人会の部屋・図書室・事務室・客室・食堂・厨房・浴室・遊戯室、といった総合的施設が伴ってこそ始めて教会なのだ、といった考えが彼にはあったように思える」(前掲『教会建築』)と。今日多くの教会がこの構想に倣っていることを思えば、小崎の構想を実現した霊南坂教会の歴史的意義は大きい。
一方ヴォーリズは、母国米国でおこなわれたクラシカル・リヴァイバル、コロニアル・リヴァイバル様式を中心とし、ゴシックやロマネスク様式のもつ魅力を加味して、彼独自のスタイルで教会堂を設計した。福島教会、明治学院礼拝堂、大阪教会をはじめ数多くの作品を残している。ヴォーリズの残したスタイルも今日の会堂建築に強い影響を与えたと言えよう。この時期辰野やヴォーリズ以外の建築家はどうであったろうか。吉武長一(第二次銀座教会)、古橋柳太郎(安中教会)、西村伊作(倉敷教会)、中村鎮(天満教会)、村野藤吾(南大阪教会)、山本拙郎(富士見町教会)、A.レイモンド(東京女子大学礼拝堂)——括弧内は作品——などが挙げられる。ここでは村野藤吾、レイモンドと中村鎮の三人についてのみ触れておく。村野がその後建築界の大家として1984年に没するまで長年活躍し、数々の名作を残したことは有名である。晩年には日本ルーテル神学大学のチャペルを設計している。南大阪教会は彼の独立直後の作品であり、1982年に同じ村野の手により改築されたが、初期の塔屋は今も残されている。優れた建築家の設計によるその教会堂を私が知ったのは、全くの偶然で、まだ高校生の頃であった。それは私にとって近代建築というものと出会った機会のひとつでもあった。
一方、レイモンドの東京女子大学礼拝堂は1938年に完成した。レイモンドは戦前旧帝国ホテルの建設のためF.L.ライトの助手として来日し、その後戦前戦後を通じて日本で活躍し、優れた作品を残すと同時に多くの日本人建築家を育てた。軽井沢の聖パウロ教会(1934年)は有名である。東京女子大学の礼拝堂は、師のオーギュスト・ペレの影響が強いとされるが、それに加えて彼自身の境地が拓かれており、今もなお瑞々しい感動を呼ぶ。当時の日本はいわゆる「満州事変」(1931年)をきっかけに日中戦争へと突入していった時期でる。建築界では従来の様式主義の建築からから近代建築への脱却を目指す運動が先駆者たちによって起されていた。その頃、建築界にとって歴史的事件となった帝室博物館(現在の国立博物館)の競技設計(1931年)がおこなわれた。この応募要項には後に「帝冠様式」と呼ばれた和風の屋根をデサインすることが条件とされたが、建築家前川国男は落選を覚悟の上で近代建築様式による提案をおこなって抵抗した。
このような時期にレイモンドによる東京女子大学の礼拝堂が誕生したことは注目に値する。
近代建築の礼拝堂を一貫して推進した建築家に中村鎮がいる。彼は、日本の教会堂の様式は近代合理主義によるべきであると早くから主張し、それを実践した。須磨教会、弓町本郷教会、島之内教会、天満教会等、少なからぬ作品を残している。低コストで鉄筋コンクリート造の会堂を作るために自ら開発したコンクリート・ブロックを用いた。
私は阪神大震災の直後、たまたま天満教会を訪ねる機会を得て、改めてその仕事の入念さを偲ぶことができた。
会堂建築の歴史II
——1945年以降——
第二次大戦が終って私たちはかけがえのない多くの人や物を失った。教会堂の再建や修復もそうした中で始められた。
最初は、米軍の使用していたカマボコ型のプレファブ建築を転用したり、急ごしらえのバラックの会堂が目立った。少しゆとりができた頃、木造の新しい会堂が建ちはじめた。
専門家に設計を依頼する教会も多くなった。
ヴォーリズやその後継者たちの他に、田中真雄や奈良信といった建築家が数多くの会堂を手掛けている。
やがて日本の建築界では、公共建築を中心に近代建築が盛んに建設されていった。ようやく仕事の場を与えられた建築家が、競って近代合理主義の建築に新しい時代の夢を託したのである。
近代合理主義の建築とはどのようにして生れたのか、ここで簡単に触れておくことにする。産業革命による近代化は建築の分野でも大きな変化を促した。とりわけ、鉄、ガラス、コンクリートなどの建築材料の生産が工業化され、それに伴って建築構造技術も飛躍的発展をみた。そのことは従来の石造やレンガ造と全く異なる考え方で建築物をつくることを可能にした。
一例を挙げれば従来の建築にとって壁は視覚を遮蔽したり、風雨の侵入を防ぐといった機能と同時に、建築構造としても重要な役割を担っていた。しかし近代建築ではこの機能を分離して、鉄骨や鉄筋コンクリートの柱や梁に構造を負担させ、壁は機能に応じて軽い間仕切で仕切ったり、ガラスの窓にすることができる。科学技術の発達がそれを可能にしたのである。ここに従来と全く異なった建築が誕生した。それが近代合理主義の建築であり、機能主義の建築とも言われた。またこの新しいスタイルは科学的な客観性と普遍性をもつ世界共通のものとして国際様式とも呼ばれるようになった。厚い石の壁と小さな窓に閉されていた西欧の人々にとっては、まさに近代の黎明をつげる象徴的出来事であった。
すでに述べたように、日本では戦時中から建築事情の悪化や軍による表現の規制から建築運動も休止状態にあった。戦後の復興期に建築界が一挙に近代建築に傾斜していった事情は充分に理解できる。
科学的に必要不可欠な要素だけで建築物をつくるという近代建築の理念は、乏しい戦後の日本にとってまさに当を得たものであった。しかしこのことがやがて経済合理主義の立場でしか建築物をつくらない風潮を生み出した。また普遍性を掲げながら実は西欧的な価値観によって民族性や伝統の問題が検証されることなく切捨てられていった。これらのことが後に日本の建築界にも大きな問題を投げかけ、ひいては健全な建築観が社会に育つことの妨げの一因ともなった。
こうした事情はあったにせよ、会堂建築も近代建築による新しい表現を模索しはじめていた。木造ではあるが、機能的な平面、勾配のゆるい屋根、水平な軒天井、矩形の大きな窓、直線的な塔など、明快な表現が取り入れられた。山口文象設計の久ヶ原教会(木造、後に改築された)が雑誌に紹介され、印象に残っている。
1953年に忘れることのできない教会堂が出現した。村野藤吾設計の世界平和記念聖堂(カトリック教会・広島)である。この聖堂は長堂形式で天井も高く、カテドラルという空間を、私にはじめて体験させてくれた。理屈を形にしたような近代建築でなく、建築の古典に対する深い造詣と創造力の豊かさに強く感動した。
私が郵政省建築部の勤務を経て独立したのは、1962年の春であった。60年安保闘争の後で、東京オリンピック(1964年)、初の超高層霞ヶ関ビル(1968年)、日本万国博覧会(1970年)へと日本の高度経済成長が始まる直前であった。
戦後の会堂建築の歩みの中で、記録に値するいくつかの動きがあった。まず、1964年に日本基督教団の会堂建築委員会が『教会建築図集』を刊行したことである。当時の委員長・津田正則牧師と書記の稲垣守臣牧師を中心に、田中真雄、奈良信、高田悠、増谷宏と岩井が協力して戦後建築された会堂の設計図を収集し、若干の解説を付したものであった。きわめて地味な孔版印刷であったが、予想外の人気を集めた。会堂建築についての資料が全くなかった故であろう。
次に、これと前後して「教会建築研究会」が始められた。まず教会堂の使われ方を実際に調査してみようという試みであった。これは、当時私の勤務先の郵政省建築部に居合せたキリスト者建築家の発意によった。それは高田、増谷と私の三名で、発足後は、田中、奈良の各氏にも協力を仰いだ。この調査は後に『礼拝と音楽』誌上に数回にわたり発表された。
一方建築学会では、『建築設計資料集成』の戦後の大改訂が企画され、宗教建築部門にはじめて教会の項が加えられることになった。編集には玉真秀雄(清水建設、教会建築の歴史的研究で知られる)が主査となり、カトリック、日本ハリストス正教会、聖公会の建築家たちが加わった。
今井兼次、三井道一·道男父子、元田稔等が協力し私も手伝った。今思えば大先輩の方々と一緒に作業のできた貴重な機会であった。この仕事は教会外はもちろん教会内部でも相互に知りにくい資料を具体的に収録した点で評価すべきであろう。
そして最も大きな出来事は、共著『教会建築』の出版であった。この企画は、高橋保行(日本ハリストス正教会)、土屋吉正(カトリック教会)、長久清(関西学院大学)、加藤常昭(日本基督教団)の教職たちに、建築家として、奈良信、岩井が参加して執筆、加藤常昭牧師がとりまとめの責任を負われ、日本基督教団出版局より出版された。
これら戦後の諸活動の特徴は次の三点にまとめることができる。
第一に、教職も建築家も会堂建築について初めて共同の研究や作業をおこなったことである。共同することによってお互いに問題の所在を確認し、認識を深めることができた。
第二に、建築計画の視点から従来の教会堂を調査し、今日の教会活動にふさわしい計画的な手法を探ろうとした点である。教会は一度建築されると、長い間見直されることなく習慣が持続することが多い。こうした日常を見直すことは、礼拝をはじめ教会の諸活動を自覚的にとらえなおすことでもあった。
第三に、最も大切な事が起った。それは教会自身が、どのような会堂を建築すべきかを問い直しはじめたことであった。共著『教会建築』の作業は、この問いに立ち向かった最初の作業であった。同著の“まえがき”に、加藤常昭牧師は次のように述べている。「教会堂とは、そもそもいいったい何なのであるか、どのように建てたらよいのかという問いは不可避である。私たちの福音宣教のわざに教会堂は不可欠のものであるのか。信じて生きる者にとって、礼拝堂はいかなる意味を持つのか。教会や教会堂の大小を問わず、これらの問いに対する答えをどうしても手に入れなければならない」と。
日本の教会は、会堂建築の根本的課題に向かってこの時ようやく動き始めたといってよい。
戦後の会堂建築についての著作では、長久清著『礼拝と礼拝堂』(日本基督教団出版局、1970年)も時宜を得たものであった。著者は神学者として欧米の礼拝改革の歴史を研究され、実際に世界各地の礼拝堂を訪ねてこれを紹介された。その中で現代の礼拝革新運動(リタージカル・ムーブメント)や各地の新しい礼拝堂の傾向を具体的に紹介された。これは教会内部にも、私たち建築家にとっても、大きな刺激となった。
会堂建築の中で考えたこと
I 初めての会堂設計
——逗子教会、船橋教会——
私が独立後初めて設計を依頼されたのは逗子教会(1964年)(現在は改築されてしまった)であった。教会建築については経験もなく、勉強しようにも整った文献もなかった。わずかな手掛かりといえば、学生時代に出入りしたいくつかの教会であった。
私は牧師の家庭に育ったため、教会生活についてはわずかな経験はあった。しかし当時私の父は開拓伝道ばかりしており、教会堂らしい建築とはほとんど無縁であった。
逗子教会の設計は、礼拝堂の手前1、2階に小部屋を配した単純な平面であった。礼拝堂では聖壇部分を特別な空間表現とせずに、会衆席と一体に扱った。建築表現としては、開口部を上下の連窓としたことが特徴で、構造は軽量鉄骨造であったが柱型は内外共に厚いラワン材で囲った。屋根はゆるい勾配とし、開口部には細かい面格子を配した。木部は黒褐色の塗装、外壁は白いリシンの吹付けとした。内装は床以外の壁と天井にラワン合板を生地のまま使った。全体として当時の木造近代建築の表現に素直に従ったものである。工夫といえば合板の曲げやすいのを利用して一寸変った曲面天井にしたことであった。外観は和風、真壁造を意識したもので、全体として当時私の育った郵政省建築部のデザインに影響を受けたものであった。
その頃私の考えた礼拝堂は次のようなものであった。平面計画、空間表現は近代建築の方法によること、使用する素材はなるべくそのまま表現に生かすこと、当時出まわりだした新建材は使わない、予算が乏しくても建築として最低限の質を確保する等、きわめて素朴な事柄であった。建築として最低限の質を確保することをわざわざ取り上げたのには理由がある。当時私の眼にした市中の小会堂のデザインにはかなりひどいものが少なからずあった。これでは日本のプロテスタント教会は会堂建築を見る限り、文化全体に対してきわめて無頓着であるという印象をまぬがれない。建築を志す者として恥ずかしくもあった。建築と単なる建物とは違うのだ、予算がなくても最低限建築として通用する会堂を創ろうではないかという意味のことを、機会あるごとに発言した時期もあった。
逗子教会の設計は何故和風、真壁造のデザインだったのであろうか。それは当時郵政省の建築を率いていた建築家小坂秀雄氏の影響による。氏の作品は近代建築を継承しつつ、日本の伝統建築を新しい感覚で表現し高い評価を得ていた。私の大学在学中の指導教官でもあった。すでに1950年代中頃から建築界では日本建築の伝統について論調が高まっていた。ちょうど政界の「55年体制」の始まりと重なる時期で、戦後の大きな節目でもあった。
その頃私はまだ官庁勤めであったが、やがて独立すると目前の仕事に追われ、伝統建築の問題にどう関わるべきか手探りの状態であった。その時期に出会ったのが日本の民家であった。
小住宅を設計しながらどこか根なし草のような落ち着かない気分でいた時に、日本の住宅史の中で現代まで一貫して骨太く生き残っている民家に眼を開かれた。それが船橋教会のデザインを生むきっかけになった。関東の養蚕農家には子どもの頃を過した体験もあった。そのお陰で私がなんとか身近に取り組むことのできた仕事であった。しかし伝統や土着化という問題と教会建築を結びつけるためには、幾重にも重い課題があることを知ってそれ以上進むことはできなかった。それよりも当時の私にとっては現実の会堂建築の質を底上げすることが気になっていた。それには「建築」とは何かを問うことが先であった。実はこの状況は今でもそれほど変っているわけではない。建築は文化の所産であると言いながら、この国ではそれ以上に、財産として、あるいは経済価値を生む手段としてつくられてきた。それは、資金の余裕がなければ間に合わせの建物でよいという考えになり、反対に贅沢になれば権威の象徴として建築を利用するという考えになる。その傾向はいまだに消えていない。
Ⅱ 都市の会堂設計
——儀式と祝祭の空間——
こんな中でも会堂設計の大切さを理解する教会が次第にふえて、私たちもやりがいのある仕事に恵まれるようになった。ことに、新潟、松本、旭川、豊橋など地方の教会から声をかけられたことは大いに励みになった。
やがて目白教会、銀座教会と都内の表通りに面した会堂を設計することになって、地方都市や郊外の会堂とは違った課題を負うことになった。それは喧騒な市街地の中でいかにして礼拝堂らしい空間を確保するかということであった。
もともと礼拝がおこなわれる空間は儀式と祝祭の場であり、非日常的空間である。これに対して高密度な都市空間はきわめて日常的なものに満ちている。日本の神社や寺院は、多くの場合適当な広さの境内地に恵まれている。鳥居や山門と共に境内地の自然は日常から非日常へと空間体験を移行させてくれる。一方われわれの教会堂は境内にそのようなゆとりがない。そこで礼拝堂にとって会堂の壁は大切な意味をもってくる。西欧の聖堂は広場に面しているが、市街地に対しては厚い石の壁で囲われている。
これに倣って目白教会や銀座教会では窓をなくしてコンクリートの壁で囲い込む方法をとった。壁によって日常空間から非日常空間への転換をはかった。自然採光を限定し内部を暗くした。雑踏の街路から一歩礼拝堂に入った時に静かな祈りの場が備えられている——そのような空間づくりを志したように思う。
さて会堂建築で身障者の方々に配慮するようになったのはいつ頃からであったろうか。福祉施設や病院に較べるとかなり遅れたように思う。
1981年は「国際障害者年」であった。国連はこのとき身障者の「完全な社会参加と平等」をテーマに掲げ、日本でもようやく街づくりに身障者のことが配慮されるようになった。
会堂建築でも、出入口の段差をなくすこと、身障者用トイレ、スロープや昇降機の設置等、具体的なことが取りあげられた。しかし今もって充分な対応ができているわけではない。
ひとくちに身障者といってもさまざまな場合がある。私たちはそうした障害を学習することすら不充分である。まして障害をもつ方々の経験や気持を理解することはなかなかできない。
たとえこれらのことをある程度心得たにしても、施設としての対応は限られている。
何より必要なのは、会堂建築の機会に会員が皆でこの問題を学び、共に考えることであろう。できれば実際に障害をもつ方やお年寄りを交えて話し合いたい。これらの方々の経験や気持に触れることから始めたい。そしてできることから実現し、不足をいかに補うかを具体的に話し合うことが必要である。ことに多くの教会堂にはふだん誰もいない場合が多い。こうした事情も考えないと、施設ばかり整えても役に立たないのではなかろうか。軽々に論じることではないが、障害者やお年寄りに対する施設の問題は、単に建築上のことに止まらない。多方面にわたる問題の解決を教会に求めている。
都市型の教会で次に起った変化は、会堂建築の諸設備がより複雑で高度になっていったことである。世の中が豊かになるにつれて、照明、放送、冷暖房などの設備に対する要求がより高度になった。人々は日常生活が向上するにつれて会堂にも同じ快適さを求めた。さらにパイプオルガンが普及しはじめると、礼拝堂の音響効果にも関心が強くなった。このような傾向を受けて建築全体の設計や施工も変化した。
床、壁、天上、開口部などは、断熱材、結露防止、遮断性などの性能を高める必要に迫られる。たまたま、建築を工場製品のように品質や性能面で評価しようという考え方が建築界に導入された時期であった。これは会堂建築にとっても必要なことではあるが、コストや維持費の増大を考えると必ずしも喜ぶべき傾向ではなかった。しかし一方では都市環境は急速に悪化しつつあった。特に礼拝堂の静けさを確保するためには、騒音、採光、空気の汚染などに対して有効な装備を必要とした。私は銀座教会をはじめとしてある規模の教会堂でこれらの事柄を研究し実践した。
こうして日本の教会堂のハード面での質は急速に向上したが会堂建築の寿命については新しい局面を迎えることになった。
Ⅲ 生きている教会堂
——人々と共に、時代と共に——
会堂の機能は、一般にそれほど変化するものではない。これまでは付帯設備も至って簡単であり、多くの会堂は長い歳月の間充分に用いられてきた。ところが最近の建築は意外に短命である。むしろある程度の年数をもちこたえればよいという考え方に変ってきた。それは社会の急速な変化に対応して、建築の機能も変化を要求されるからである。骨組みなど主要な部分以外は一定期間で償却し、新しく改装できるようにつくる——これが最近の建築である。もともと設備関係の機器類や配管は15年前後で交換が必要である。内装材や部屋の間仕切りも交換しやすくしておけば、新しい設備にも対応しやすくなる。
だが教会堂はそれほどの変化を必要としない。むしろできるだけ長持ちする建築がよい。度々の募金による資金の調達は大変であり、維持費も少ない方がよい。
設備の複雑化と建築生産の考え方の変化はどちらも会堂建築にはなじみにくい。このような時代の傾向にどう対処していったらよいかは、今後の大きな課題である。
実は会堂建築の耐久性に先だって言及しなければならない問題がある。それは建築の保存と再開発である。私にとって、銀座教会以降、富士見町教会、東京YMCA会館、三崎町教会などの改築にあたって、それは切実な問題となった。銀座教会(第三次会堂、富永襄吉設計、1928年)は基礎の松杭が腐蝕して建物全体が傾斜していた。富士見町教会(山本拙郎設計、1930年)は調査の結果構造体がかなり痛んでいることが判明した。東京YMCA会館(曽根・中条事務所設計他、1929年)は数度の増改築等を繰返した結果、機能・設備等全般にわたって諸事業の経営に支障を来していた。それらを解決するには改築しか道がなかった。しかしいずれも、長年の間、街の顔のひとつとして人々に親しまれてきた建築である。銀座教会は鐘楼と外壁を覆う蔦に独特の風情があったし、富士見町教会は緑青色の尖塔がそびえ立ち、讃美歌のチャイムが響いていた(改築時には構造上の危険により尖塔部分はすでに解体されていた)。東京YMCA本館は、パラペットに洋瓦を葺いた独特のファサードと内部の重厚なデザインによって、神田っ子をはじめ多くの人たちに愛されてきた。これらの建築が失われると決まったとき、関係者の想いは私の想像をはるかに超えるものがあったと思う。私自身はこの時これらの建築が人々と共に生きていることを肌身で知らされた。そして私の考えていた保存と開発の問題は単なる観念にすぎなかったこと、またこの厳しい現実の前に全く無力であったことを知らされた。YMCAの場合には本館部分の修復保存や壁面保存なども真剣に取りあげられたが、いずれの場合も敷地の狭さ、さまざまな建築規制、予算の制約、機能上の要求などの厳しい条件があり、全面改築を迫られることになった。
これらの建築は関東大震災後1930年前後に相次いで建築されたものである。ちなみに東京都内に残っている同時代のプロテスタントの会堂建築としては、弓町本郷教会(1926年)、本郷中央会堂(1929年)、信濃町教会(1930年)、下谷教会(1930年)などがある。
周囲の街の開発が進められようとも、少なくとも教会は生き残っていけるように私は思っていた。しかし都心の教会はそう単純ではなかった。自らの保存への意志や努力だけでなく激しい速度で変化する都市の環境とも戦わなければならなかった。1968年東京霞ヶ関に超高層ビルが出現した。1970年には田中角栄が「日本列島改造論」を打ち出している。ビルの高層化と巨大化は東京をますます高密度にし、車社会の進展と共に環境悪化は急速に進んでいった。
たとえ建築の耐久性に不安がなくても、環境悪化に対抗するためには、改築に近い装備の変更、それに伴う費用を負担しなければならない。銀座教会を例にとれば、都心から移転するかどうかというところまで問題は深刻であったと聞いている。どうしたら維持コストの高い都心に止まり得るか。これが再開発への発想に発展していった理由のひとつであろう。
1970年代に入った頃から、私たちも近代建築が切捨ててきた部分と共に人間の個性や感性が埋没しつつあることに渇きを感じていた。富士見町教会や阿佐ヶ谷教会では礼拝堂空間の構造的表現を実現したが、こうした手法のほか、空間づくりに曲面を加えたり、ディテールに装飾的要素を加えること、従前の会堂のイメージを部分的に再現すること等もデザインに加えられた。会堂を設計する度に少なくともひとつのテーマを求めてその教会の個性を出そうと心がけた。
Ⅳ 時代状況の中での建築
1980年代後半から日本経済は平成景気——いわゆるバブルの時代を迎える。同時に世界の構図は新しい時代に向かって大きな変換を遂げつつあった。この時期建築界を襲ったのがポストモダニズムの建築である。すでに近代主義のゆきづまりはさまざまな分野ですでに起っていた。
多様性を失い、画一的・没個性的になった近代主義=モダニズムに対する反省から、これまで意識的に切捨ててきた部分を再評価しようとする反モダニズムの流れが起った。これがポストモダニズムと呼ばれる思想とデザインで、建築界はいち早く反応を示した。
ちょうど起ったバブル景気に支えられて、わずか数年の間に、東京の至るところに奇抜なデザインの建築が出現した。オリンピックの時と同様、ひとつの節目ごとに都市の混乱が増幅するという感じであった。しかしバブルの退潮と共にポストモダニズムのデザインはたちまち冷え込んでいった。それはまるで流行病のようであった。この現象は、外来文化の受容における日本の弱点をいみじくもあらわしている。明治以降の日本は近代化を急ぐあまり、それ以前の歴史的なものを大胆に切捨ててきた。その体質は今日まで続いている。建築家大谷幸夫氏はシンポジウム『戦後建築界の来た道行く道』(企画編集・東京建築設計厚生年金基金25周年記念出版編集委員会、1995年)の中で次のように述べている。「今まで歴史的につくってきたものを受け止めて、それを乗り越えていくという操作を綿密にやった上で、ポストモダンの手法なり考えを受け入れていたら、日本に見られるようなあれほどはしたない事態は起こらなかったと思います。そうした土壌が育っていないところで、いきなりポストモダンに入り、やみくもにいろいろなデザイン要素を引き入れ、文化系を異にする遺伝形質を無造作に導入した、これはまるで倫理観なき臓器移植です。そういうことをするから、拒絶反応が出るわけです」。まさに同感である。こうした風潮が改まらぬ限り建築も建築家の信用も不毛のままであろう。
建築家の倫理の問題で見過せないのが戦争中の責任の問題である。一部の建築家は筆を折って抵抗したが、一部ではたとえば忠霊塔の競技設計に参加したり、大政翼賛会志向の建築に加担した建築家がいた。戦後、音楽、演劇、文学、美術の各分野で戦争犯罪問題を取りあげているが、建築界では全く取りあげられてこなかった。
そのことをあらためて知ったのは『燎』という同人誌の企画による座談会によってである。(『燎』第25号「小野薫のこと——東京「帝国」大学の問題の一環として」——侵略戦争加担の責任、11頁、49頁、神代雄一郎、宮内嘉久、武者英二)。
建築界で戦争責任問題に消極的であったのは、建築が芸術一般と異って依頼主があって初めて実現する創作行為であることと深く関っている。依頼主の多くは官庁や企業であり、建築家はそうした体制側の強い制約を受けている。創り出した建築が社会的な存在である以上、建築家は当然さまざまな責任を負うものである。しかしもの創りとしての倫理的責任についてはともすれば稀薄である。思想や表現の自由が実現した今日、戦時中の建築家の言動を歴史的事実として重く受止めておかねばならない。
私自身のわずかな経験でも建築家がもの創りの倫理を貫くことは容易でないことを思う。私たちの時代には日本が高度成長期に入り、日照権問題や景観破壊、歴史的建築の保存と再開発など社会的問題が次々と起った。また時代の急激な変化に応じて建築思想と表現も大きく揺れ動いた。
こうした状況にあって問題をどれだけきちんと受止め対処してきたのであろうか。自らかえりみて忸怩たる思いである。
近代建築は日本の近代化を推進すると同時に、経済的合理主義に突き進み自ら出口を失った。「だが、しかし『近代』は終ったわけではない。(宮内嘉久著『建築ジャーナリズム無頼』晶文社1994年)。
自ら対決し批判的に乗り越えるべき相手を明らかにしないまま、次々といそがしく世界の動向を先取りしてきたのが戦後の日本であった。政治や経済の世界と同様に建築界にも大きな課題が残された。
バブルの時期に会堂建築が受けた影響は、建築コストの上昇だけではなかったように思う。周囲につられて知らぬ間に贅沢になったことは否めない。会堂建築の構想全体が身の丈を越えたことはなかったろうか。
教会も設計する私たちも、このあたりでもう一度考えてみる必要があるように思う。
まとめのことば
——礼拝堂にふさわしい空間づくり——
どのような建築空間が礼拝堂にふさわしいのか。この問いに応えることは非常にむずかしい。プロテスタントの礼拝堂には特別の約束事はないからである。教会堂には説教台、聖餐卓、会衆席、オルガンが配置され、これに洗礼槽や洗礼盤が加わることもある。しかしこれらは機能上必要ではあるが、必須ではない。唯一の表象とされる十字架も掲げない教会堂がある。正面に聖壇(通称)と呼ばれるステージ状の部分があるが、これも設けない会堂がある。つまり礼拝堂に必須の道具立ては何もないと言ってよい。
礼拝堂は集会場や公会堂に似ているがこれらとも違う。講演を聞かせる場所ではない。音楽ホールや劇場のように、そこで演じられる出し物を見たり聞いたりする場所でもない。
礼拝堂で礼拝がおこなわれるときには、聴衆や観客はいない。すべての人たちが礼拝に参加するからである。そこに参加する牧師も信徒も共に神の言葉を聞き、神に祈り、讃美の歌を歌う。だから無人のホールや礼拝堂に立入ってみると、ずいぶん違うように見える。しかしそれは現代の建築がそれぞれの用途によって機能的に異った装備をもっているからだ。古い西欧の建築をみると宮殿が美術館になっていたりするが、それなりに現代に生かされている。礼拝堂で音楽会が開かれることは当り前になっているのだから、その逆のことがあっても不思議ではない筈だ。
もともと建築の根元的な姿はそういったものだ。いろいろな装置や装飾をとり去ったときに裸のままの建築というものが見えてくる。
キリスト教の起源は、幕屋で礼拝していた砂漠の民の宗教である。礼拝の場所はユダヤ教のシナゴーグ、信者の家、ローマ皇帝に迫害された時代には地下墓地(カタコンベ)の礼拝所とさまざまに変っている。キリスト教独自の礼拝堂が完成したのは、中世のロマネスクやゴシック様式の時代である。しかもそれらが完成した時に教会自身の堕落が始まっている。なんと皮肉な話ではないか。ルネッサンス以降も教会はギリシヤやローマの異教の神殿を模したり部分的に再利用したりして礼拝堂をつくっている。一方ではこんな聖堂もある。堀田善衛氏の『情熱の行方』(岩波新書、1982年)の中には、スペインの小さな町にある小聖堂が紹介されている。「要するに直径五メートル半ほどの、そして高さはハメートルほどの円筒形の石小屋なのである。・・・・・・・・・単純にして素朴なものだ。神の家として、多くのものは要らないのだ。近所から鍵をかりて来て内側へ入ってみても、なかには、何もない。・・・・・・神もまたいまはお留守のようである」。
この小聖堂はサン・ペレ・エル・グロスという名で、記録によると紀元1026年に建設されたと氏は記している。そして「これらの単純素朴な石小屋教会は、私の見た限りでは、そこに一つの共通するものがあると思われる。それは、それが現に教会として使用されていてもいなくても、いささかもじめじめと生や死を思わせたり、抹香臭かったりはせず、すべてがからっとしていて私にいわば宇宙感覚のようなものを与えてくれることである。千年近い時間と、狭小なりとはいえ天と地をつなぐ象徴的空間がそういう感をかもし出すものであろうか」と。いささか引用が長くなったが、建築のエッセンスのようなこの小聖堂のことを知ると、当時に較べて人間はどれだけ進歩したのだろうかと思う。われわれは千年後にこれほどのものを残せるのであろうか。
こうしてみると礼拝堂の建築について、それほど多くを語る必要はないようだ。必要なのは、教会も、建築を設計する者も、あまりにも積ってしまった厚い衣を脱いで、もう一度裸の礼拝、裸の建築を見据えることかもしれない。
神に捧げる礼拝堂は最高に美しいものでありたい。ロマネスクやゴシック様式の大聖堂はその想いを実現した傑作にちがいない。
あの空間の呼び起す感動を私たちはいつまでも残したいと思う。しかし同時に、西欧の中世が教会を中心とした巨大な権力と、それを支えるための抑圧された民衆の時代であったことも忘れてはならない。
これスペインの小聖堂はこの点もう少し違っていたのではないか。それは日本でいえば鎮守の杜に作られた社のようなものではなかったか。もしそうであれば小聖堂には信心深い村人たちの自発的な手造りの跡が残されてような気がする。
私たちの教会堂も、発意から完成までには多くの人々の想いが込められている。しかし現代の建築はさまざまな理由からその寿命は次第に短くなっている。とても中世の聖堂のようにはいかないであろう。それならば何が残ってゆくのであろうか。それは多分建築という物の方でなく、物にこめられた精神の方ではないか。会堂建築に関わった人たちが建築主も設計者も施工者も、皆が限られた時間の中で熱い議論を闘わせ、心を通わせあったことではないか。
今回写真に加えて個々の会堂建築に短い文章を添えた。その中に記した人々は単なる回想以上の大きな意味をもっている。
会堂を受継いだ人たちは、彼らを記憶することによって、この建築を愛し、できる限り長く用いてほしい。それが生命に限りある建築との共生ということではないか。
主な建築作品
日本基督教団 船橋教会 (1965年)
日本基督教団 新島教会 (1967年)
日本基督教団 松本教会 (1969年)
日本基督教団 旭川六条教会 (1974年)
日本基督教団 豊橋中部教会 (1976年)
日本基督教団 牛久教会 (1976年)
日本基督教団 越谷教会 (1977年)
日本基督教団 武蔵野緑教会 (1980年)
日本基督教団 目白教会 (1980年)
日本基督教団 山梨教会 (1981年)
日本基督教団 城西教会 (1982年)
日本基督教団 銀座教会 (1982年)
日本基督教団 富士見町教会 (1985年)
日本基督教団 三軒茶屋教会 (1985年)
日本基督教団 阿佐ヶ谷教会 (1986年)
日本基督教団 高崎教会 (1986年)
日本バプテスト連盟 常盤台バプテスト教会 (1988年)
日本基督教団 砧教会 (1989年)
日本基督教団 福井神明教会 (1990年)
日本基督教団 三崎町教会 (1992年)
日本基督教団 小田原教会 (1994年)
日本基督教団 京都丸太町教会 (1995年)
新島学園礼拝堂 (1988年)
東洋英和女学院礼拝堂(1991年)
和泉クラークホール (1992年)
東京YMCA山中湖センター (1983年)
東京YMCA 妙高高原ロッジ (1985年)
東京YMCA国際奉仕センター(1991年)
にじのいえ (1973年)
学生キリスト教友愛会 (1988年)
参考文献
真建築設計事務所, 佐藤建築写真事務所 著『天と地をつなぐ空間-教会堂 : 岩井要・真建築設計事務所作品集1965-1995』(日本基督教団出版局, 1995.11)
「励ましのお言葉」から「お仕事のご相談」まで、ポジティブかつ幅広い声をお待ちしております。
共著『日本の最も美しい教会』の新装版『日本の美しい教会』が、2023年11月末に刊行されました。
都内の教会を自著『東京の名教会さんぽ』でご紹介しています。
【東京・銀座編】教会めぐり:カトリック築地教会、聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂、日本基督教団銀座教会を紹介
