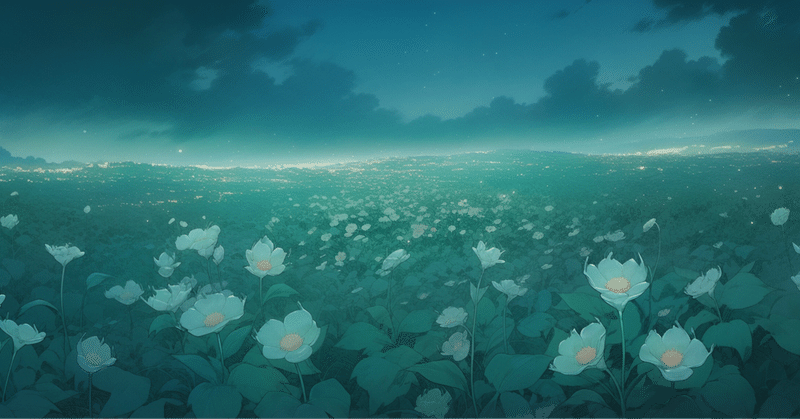
#10 【戦中|小学生時代】”綴り方”って授業、知ってる?

舞台
(福岡県)久留米
人物
主人公 :花山 三吉
家族構成:父、母、七人兄弟(五男二女)
三吉は四男坊
題名
草笛の記
物語
戦中 戦後 青春のおぼえがき

第一章 幼少時代
※上記のリンクから飛べます
第二章 小学生時代
(一)支那事変勃発す
軍都 久留米の動き
忘れ得ぬ先生たち
(二)国民学校の発足
軍国主義教育の台頭
遊びは戦争ごっこや水泳
(三)太平洋戦争へ突入
木銃・木刀・薙刀を量産
骨折入院で文学書乱読
第二章 小学生時代
(一)支那事変勃発す
忘れ得ぬ先生たち
三吉が得意とした学科は「国語」と「綴り方」であった。
とくに「綴り方」(作文)の時間は、楽しかった。一時間のあいだに二枚も三枚も書いた。このきっかけは一年生のとき、校内誌「白路」に、「綴り方」で書いた文章が掲載され、みんなから褒められたことにあった。その内容は、父や兄弟と揃って「銭湯」に行った、というものだった。
三吉は、家の風呂釜の交換の際、生まれて初めて「銭湯」に行ったのである。大きな風呂に大勢で入って、嬉しかった感想を詳しく、少し修飾して書いた。誰が描いたのか頭がツルツルに禿げた親父と四、五人の子供が手にタオルをさげた風呂帰りの挿絵が、漫画ふうに載っていた。その絵を見て父は愉快そうに笑った。父の頭はまっ黒だったからである。
一年生から四年生までの担任は岡崎先生だった。先生は、いつも詰襟の服をきちんと着た恰幅(かっぷく)のよいひとで、校内誌の編集者でもあったので「綴り方」は特に熱心に指導した。
先生の趣味は写真撮影だった。放課後に三吉は写真撮りによく狩り出された。三脚を運んだり、銀紙を貼った板で陽の光りを反射したりした。写真を撮るとき、先生は授業中よりも厳しい顔をした。
その影響で三吉も写真が好きになった。四年生のとき「東郷堂」という店で、箱形の黒い小さな写真機を買って貰った。フィルムは撮るたびに一枚づつ入れて、中の紙を引き上げてからシャッターをきり、シャッター速度は手かげんだけの簡単なものであったが、不思議に良く撮れた。
五年生のときの担任は牟田という「地理」が得意の先生だった。全国の名所旧跡の「絵はがき」を集めて、生徒が自由に見て学習できるように、教室に、たくさん仕切った棚を作って、その仕切った桝の中に絵はがきを入れた。三吉が撮った久留米市の写真も「わが郷土」の桝にしまった。この棚を作る時は鋸、鉋などの道具や板、釘など、必要な物のほとんどを、三吉が家から持っていった。三吉は何となく得意な気持ちで、せっせと板を切り鉋をかけた。こういうことは、「門前の小僧」で良く出来た。
この牟田先生は日本地図を徹底的に教えた。まず日本国の形を正確に描けるまで描かせた。つぎに日本国中の主要な山脈と川を、それから主要都市名を、丸暗記させて正しい位置に記入させた。
「大人になったら必ず役に立つけん頑張って覚えろ」というのが口癖だった。三吉は先生の熱意を感じて「地理」も好きになった。全国の絵はがきを見て、見知らぬ町への大きな想いを抱いた。特に雪国の冬景色は珍しさを超えるものであった。
続く
坂田世志高
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
