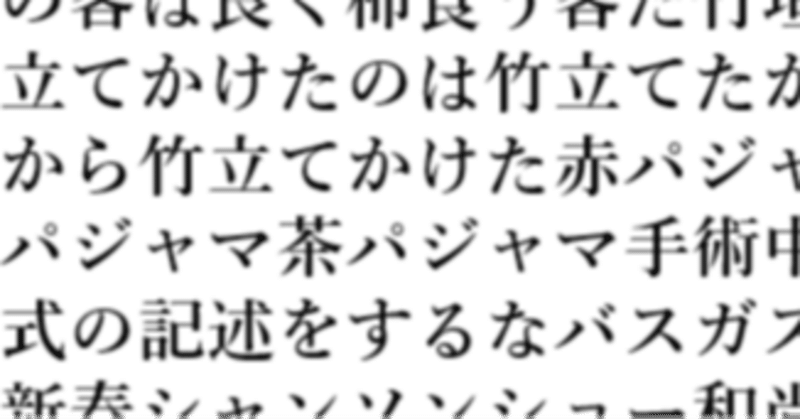
言語化とは世界の編集である
数年前から言語化の会という名前で若い起業家たちと集まっているけれども、改めて言語化とは何かと考えると「世界の編集」ではないかと思います。言葉にするということは世界からそれを切り出すということで、文章は世界の分け方、つまり編集方法を提示しているのではないかと思います。
例えば人間以外の生物にとって世界は「捕食する、遺伝子をつなぐ、捕食される、それ以外」という見え方になっているのではないかと思います。詳しくは「生物から見た世界」に書かれています。生存に関わるところの情報は重く、関係ないところの情報は軽くなっているはずです。イメージで言えば白黒なんだけれど、大事なところだけ鮮明に詳細に浮かび上がるような世界の見え方ではないかと想像します。
逆に自分から見える世界の情報量を完全に均等にしてしまえば、世界は何一つ分かれていない状態になるでしょう。分かれていない状態に自分自身すら含まれるので、いわば観察者不在の状態になるのではないかと思います。ジルテイラーが奇跡の脳の中で、脳卒中で左脳が機能麻痺した状態を詳細に書いていますが、そこで世界が分かれていなかったと書いています。つまり世界は分かれているのではなく観察者が分けるということです。仏教では無分別といい、言語が生まれる前の世界が分かれていない状態を意味します。
初めて聞く言語は最初ただの音の羅列に聞こえて、全く意味がわかりません。ところがこの音が「あなた」という意味でなどと教えてもらうと急にその音だけ浮き出て聞こえてきます。音の羅列の中、つまり情報ですが、そこの切り取り方を教えてもらうことで、音を分けて意味が理解できるようになります。言語化はこれに似ていて、本来は分かれていない世界の分け方を提示しているのではないかと思います。
右左という言葉も人類の発明品です。右左という言語がない民族では、目の前に左から、コップ、帽子、靴を置いて「後ろを振り返って後ろに同じように並べてください」というと、後ろを振り返ってその人にとって左から、靴、帽子、コップと並べます。その民族は自分の位置を川の上流側にいるか下流側にいるかなどと理解をしています。左右という言葉がなければ世界の捉え方も違います。
さらに視覚は補正をすることがよく知られています。無意識にです。つまりどんなに頑張っても私たちは直接ものを見ることができず”脳が見せるものしか見る”ことができません。網膜が得た情報を編集し私に見せるこのプロセスに、言語が影響しているとしたら、まさに世界の見え方に言語化は影響を与えていることになります。
言語化は世界の捉え方を提供するわけですが、この極みが単一の言語に集約することです。例えば「神」や「民主主義」や「モチベーション」や「メタバース」などです。どうとでも編集できる世界を一つの言葉で切り取り整理します。これは本当に人々の世界の捉え方を変えてしまい故に世界の構造自体を変えてしまうほど強力なのですが、あまりに抽象度が高いが故に認識に大きな開きが生まれます。認識に開きがあるということは人によって単語が意味するところが違うということです。
私たちは何気なく言葉を受けとり学んでいます。しかし、幼少期に親から言われた「あれがブーブーよ」という一言でまさに動く大きな物体が車として認識されます。そしてその車が「大きい車と小さい車」になり「ダンプカーやタクシー」になり「軽自動車や商業車」になり「トヨタや日産」になっていきます。そして世界を分ける作業は物質的なものから概念的なものへと移っていきます。言語化能力とは世界の編集能力のことであり、それはつまり世界をどう見るかを選択するということでもあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
