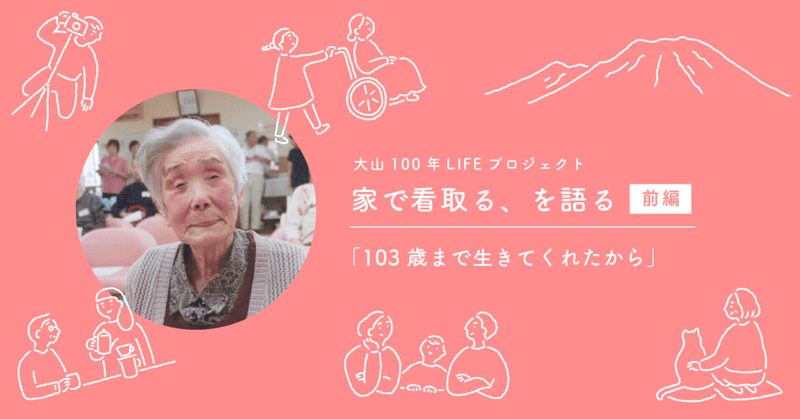
家で看取る、を語る〈前編〉「103歳まで生きてくれたから」
髙虫千枝子さん。享年104歳。満103歳10ヶ月。千枝子さんは、最期の時を迎えるまでの2ヶ月間を、大山診療所の元所長(2019-2021年)である朴大昊(ぱくてほ)医師をはじめ地域のスタッフに支えられながら、鳥取県大山町の自宅で過ごした。千枝子さんを看取った息子の勲(当時74歳)さんと勲さんの妻・澄子さん(当時70歳)に、千枝子さんの生きてこられた時間や在宅介護の日々、最期の時をどのように過ごされたかなどを語っていただいた。
農業で鍛えた身体で「100歳まで生きる」
旧名和町の農家の家に生まれ、結婚する前は保育の仕事をしていた千枝子さんは、19歳の時に大山町の農家である髙虫家へ嫁いだ。農業に明け暮れる日々の中、かつては茅葺き屋根だったこの家で、戦前に4人、戦後に2人の子どもを産み育てた。勲さんは、下から2番目。終戦後に生まれたため、勲章から由来して名付けられたそうだ。
澄子:「おじいさんがなんせ軍人さんでしたからね。だから、あちこち行ってなかなか帰ってこない。おばあさん、えらかったわな。子どもは6人おるし。昔の人はねえ、ほんに鍛えちょられます」
勲:「田んぼに養蚕、乳牛も飼ってタバコも作ってた。朝間から晩まで働いているような母親でした。若い時に力仕事したから、元気が出たじゃないかな。それで長生きするだが」
敷居をまたぐ時につまずいて顔から転んでも、打った鼻の頭が赤くなっただけ。農業で鍛えられた千枝子さんは、それほど身体が丈夫だったという。血圧やコレステロールの薬を飲んでいた時期もあったが、95歳の時には胃薬のみになっていた。
「100歳まで生きる。東京オリンピックまでは生きる」。そうご自身で目標を立て、好き嫌いなく食べ、糖尿病予防に毎朝梅干しを一個食べるなど食生活にも気をつけていた。その甲斐あってか、90歳の頃から介護度はずっと【要支援2】のままだった。デイサービスに週2回通っていた千枝子さんだったが、新型コロナウイルスのためデイサービスを2ヶ月休んだことで身体が弱っていったという。
弱っていく千枝子さんと、家に訪れる普段着の医師
勲「歩かなかったですけん、一遍に弱った。ご飯食べんですけんな。それですぐ朴先生に電話して、点滴してもらうと元気になるんですけどね。でもまたご飯あげても食べん。あれには参りました。何回も繰り返して。先生が、『こりゃあ1週間に1回は見に来ないけんな』って言って」
澄子「『おばあさん、明日朴先生が来るだよ』って言ったら『そげかあ』って急になんだか元気になって。人間ってやっぱり、好きな人が来るっていうと歳は関係ないんだわな。まあ、おばあさん100歳まで生きただけんね、少しはうちらも面倒みんとね」
千枝子さんは、炊事場も風呂もトイレも一番近くにある、玄関に入ってすぐの部屋で過ごしていた。徐々に食事を摂ってももどしてしまうようになり、緊急で点滴をしに来てもらうことが多くなっていった。
勲「気の毒だっただけどね。それでも、電話すると昼休憩には来てくれるですよ。点滴してもらって、最後の針を抜くのは教えてもらって私がしてね。まあ抜くほどですけんな」
澄子「点滴がまたな、血管が細くってだんだん入らなくなるが。じっとしとっても動いちゃうし、時々腕がぷくーっと膨れるだが。で、『点滴が動いてません』て電話したりしてな。そしたら朴先生が来てくれて『おばあさん痛かったなあ』って。
診察の時もね、こうして触るのよ、身体を。顔見て。人間って、そのぬくもりがあって安心しますが?あの姿がよかったなと思ってます」
勲「いい先生でしたじぇ。ほんとに。朴先生は白衣なんて全然着ならんかったもん。自然の服装。先生には見えんだが」
白衣を着ない、人間らしいぬくもりのある医師が、困ったら家に駆けつけてくれる。こうして朴医師やスタッフに支えられながら、勲さんや澄子さんが千枝子さんを家で介護する生活が始まっていった。
(後編へつづく)

インタビュアー:中山 早織
元書店員の助産師・コミュニティナース。2014年に東京より鳥取へ移住。現在は大山町で地域活動や聞き書きを行う。大山100年LIFEプロジェクトメンバー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
