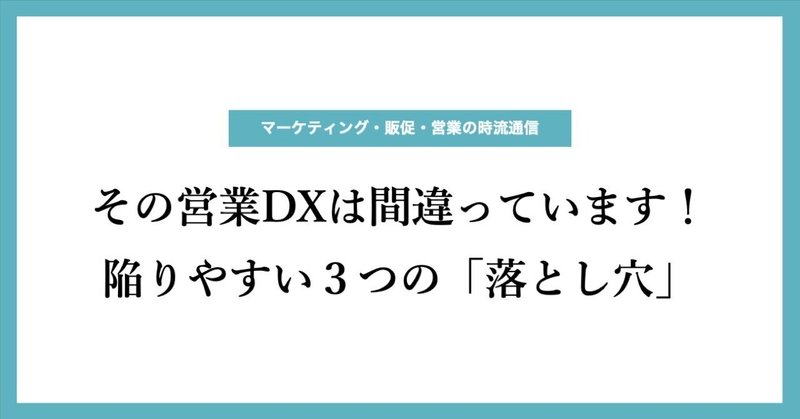
その営業DXは間違っています!陥りやすい3つの「落とし穴」
おはようございます。
カイロスマーケティングで代表を務めております、佐宗(さそう|@dsasoon)と申します。
「DX白書2023」によると、約3〜4割の中小企業がすでに営業DXに取り組んでいます。営業デジタル改革の一環として、営業DXに取り組む中小企業は年々増加の傾向にあります。
営業DXに取り組む企業が増える一方で、営業DXの問題点も徐々に明らかになってきました。その問題点に陥って、「あなたのDXは間違っています!」と言われないよう、DXに取り組む際の注意点をまとめました。営業DXの導入には落とし穴があるのです。
営業DXの落とし穴:数字の追求と市場の見失い
営業DXでは、ITツールを活用して営業活動を可視化することが基本です。SFAなどのITツールの導入することにより、営業の受注数や受注金額、提案数、見積り提出数、顧客訪問数が数値化され、データに基づいた科学的な営業管理が可能になります。
営業活動は企業活動におけるお客さまとの唯一の接点であり、お客さまの要望に応えてその対価を得ることが事業の核心です。このため、営業活動は経営にとって非常に重要とされています。経営者は、この重要性を踏まえて可視化された営業データを分析し、その意味を理解しようと努めます。
しかし、ここに大きな落とし穴が存在します。
事業とは、限られた経営資源(人・モノ・お金・時間など)を使って、お客さまの無限の要望に応えることです。お客さまの要望は無限ですが、経営資源は有限です。戦略的に満たすべきお客さまの要望を選択し、そこに有限の経営資源を集中させる必要があります。
有限の経営資源をうまく使ってより多くのお客さまの要望を満たした成果が、自社の売上になります。市場には競合も存在します。お客さまの要望を競合以上に満たすことで、市場シェアを拡大し、売上を増やしていくのです。これが事業のあるべき姿です。
重要なのは、営業DXによってお客さまの要望と競合の動向を可視化し、その変化を捉えることです。お客さまの要望も競合の動きも、時間とともに変化します。この変化は通常、ゆるやかに起こるため、人の目では捉えにくいことが多いです。これを時系列で記録し、中長期な変化を捉えることが必要です。
しかし、営業DXの導入によって営業活動がデータとして可視化されると、経営者がそのデータに気を取られすぎることがあります。顧客訪問数や見積り提出数などの営業データを分析することは、営業管理という社内管理にすぎません。この社内管理には、事業において重要な「お客さま」という要素が欠けています。どんなに社内管理を強化しても、せいぜい社内の経費削減には貢献できるかもしれませんが、売上の改善にはつながりません。
営業DXの導入により、経営者が多くの時間を社内管理に使ってしまうのが営業DXの大きな落とし穴となっています。
営業活動が営業DXによって可視化されると、営業データの追求に偏りがちになります。しかし、事業の本質である「お客さまの要望や競合の動向に注目し、適切に対応すること」を忘れてはなりません。
そのためにも、SFAではお客さまの要望や競合の動向が明確に捉え、経営者はそれに焦点を当てる必要があります。社内管理に注力するだけでは売上は伸びないのです。
営業DXの落とし穴:デジタル至上主義が引き起こす顧客喪失
デジタル営業やデジタルマーケティング施策の一環として、お客さまにデジタル手法で営業や販売促進の活動をする「型」が流行しています。特に2020年のコロナ禍以降、メールマガジンが再び人気を集めています。
メールマガジンを送るだけでなく、マーケティングオートメーション(MAツール)を活用して、メールマガジンのリンクを通じて自社のホームページを訪れた見込みのお客さまを特定し、さらに続くメールを送る手法をとる企業も増えてきました。
しかし、営業DXやデジタルの流行に乗じて全てをデジタル手法に営業活動を切り替えることが本当に適切かどうかは問題です。
営業活動の基盤はお客さまとの信頼関係の構築です。お客さまとの信頼の築くためにはコミュニケーションが欠かせません。コミュニケーションの質を考慮すれば、デジタルよりも対面が優れていることは明白です。対面では、お客さまの表情や雰囲気、仕草など多くの情報を双方が得ることができます。
営業DXにより営業活動がデジタル一辺倒になると、重要なお客さまへの頻繁なメール送信や、その他のお客さまへの月一のメールというデジタルだけを活用した接触頻度に応じた顧客接触戦略を考えてしいがちです。この背景には、繰り返し接触することによって、好意や親しみを感じやすくなるという心理効果の単純接触効果があるかもしれません。
デジタル営業やデジタルマーケティングでは、「購買につながるWEB行動をしたお客さまへ自動追従で売り込み型のメールを送る」という手法があります。しかし、本来電話や訪問で対応すべき重要な見込みのお客さまにはこの手法をとるべきではありません。コミュニケーションの質を考慮すると、デジタルよりも電話、電話よりも対面が望ましいです。特に重要なお客さまには、直接訪問することが大切ですが、人手不足で対応が難しいお客さまにはデジタルでの接触を試みます。営業DXの文脈でデジタル至上主義を唱える主張もありますが、これには問題があります。
営業DXは、対面型営業をデジタルに移行することではありません。デジタルの良い面を取り入れつつ、従来の対面型の営業活動を補完する形が理想です。
特に経営資源に限りがある中小企業では、営業人員の制約から対応できるお客さまの数に限界があります。対応すべき営業場面を限定し、限られた営業人員でより多くのお客さまに対応する理想です。
売上が大きいお客さま、直近で購入可能性が高いお客さま、将来的に大きな売上が見込まれるお客さまは最重要顧客として扱い、できるだけ対面などの質の高いコミュニケーション手法を活用し、お客さまとの信頼の構築に努めるべきです。
最重要顧客にデジタルでの営業手法を展開している間に、競合会社が対面などの質の高いコミュニケーションでの接触を試みることで、お客さまを取られてしまう懸念が大いにあります。
営業人員だけで対応できないその他のお客さまには、接触頻度を減らすなどの対応が可能です。それでも対応が難しいお客さまにこそデジタルを活用した接触をすべきです。
営業DXの落とし穴:仕組み化なき営業DXは形骸化する
営業DXの成功要件の一つに、営業やマーケティングの仕組み化をすることが挙げられます。
多くの組織の営業成果の分布においてパレートの法則が当てはまります。パレートの法則とは、営業成果の例でいうと、「上位2割の営業部員が全体の8割の売上を占める」とう経験則に基づく仮説です。パレートの法則が当てはまる組織では、属人的な営業に依存し、一部の高成績者に頼っています。営業組織としての平均的な生産性が低く、営業部員のモチベーションも低い状態に陥りがちです。
このような組織に営業DXを導入すると、ITツールをうまく活用する営業部員とそうでない営業部員での差が生じます。ITツールや営業DXの仕組みを活用する営業部員は高成績者として売上を伸ばす一方、他の営業部員はこれをうまく活用できず、売上が伸びない傾向にあります。結果として、ITツールがあまり使われず、組織内の格差が拡大し、成績不振である営業部員の立場が悪くなるどの組織の不和を生じることになります。
パレートの法則に従えば、高成績者以外の営業部員は一般的な社員になるため、結果的に営業DXはほとんど利用されず、形骸化する可能性が高くなります。
一方で、営業活動の標準化や仕組み化には注意が必要です。
標準化や仕組み化では、トップセールスの営業活動や個々の行動を、自社の標準営業プロセスとして仕組み化することが一般的です。営業における仕組み化には落とし穴があるので気をつけてください。
トップセールスの能力を他の営業部員にそのままコピーしようとしてもうまくいかないことが多いです。形はさまざまですが、トップセールスは将来達成したい理想的な状態や目標を抱いており、そこから発生する強い動機を持って業務にあたっています。加えて、彼らは営業としてのスキルを持っています。トップセールスの動機を生み出す原動力は、個人の非常に複雑な要素から構成され、属人的です。これを自社の標準営業プロセスとして他の営業部員に再現することはほぼ不可能です。
したがって、一般的な営業部員が活用可能な能力や仕組み、業務の流れを整理し、他の営業部員にも適用できる仕組みを構築することが重要です。社内でうまく営業DXを活用できる基盤を整備し、誰がやっても一定の成果が得られるような仕組みを確立することが求められます。
さいごに
あなたの営業DXはこれにいずれかに該当しないでしょうか。心当たりがあるようであれば、いまからでも自社の営業DXを見直すべきです。
毎週メルマガにて情報をお届けしております。登録はこちらになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
