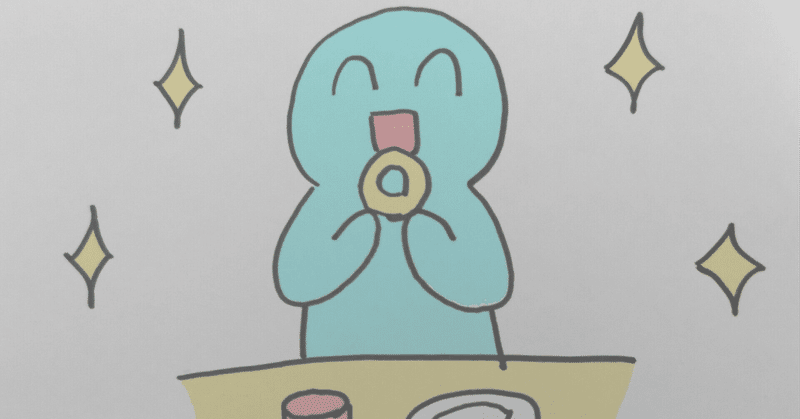
脱・砂糖依存の教科書
こんにちはパーソナルトレーナーのだいちです。
これまで100名以上のダイエット相談を受け指導させていただきました。
今回はある方へ特別なお知らせがあります。
ある方とはこんな人です。
✅甘いものがやめられない
✅お腹は空いていないんだけど異常に甘いものが欲しくなる
✅お米やパンを減らして主食の代わりにお菓子を食べている
✅常にお菓子のことを考えてしまう…
そういった方々はぜひこの記事を読み進めてみてください。
逆にこれらに当てはまらない人はこれ以上読んでもあまり意味がないです。
甘いものがやめられない原因は?
ダイエットをしているけど甘いものを見ると我慢できずについ手を伸ばしてしまう。
昔のボクもそうでした。たとえばこんな感じです。
今日の夕飯の材料を買いに行こうとスーパーへ。お菓子コーナーが見えて気づいたらカゴいっぱいに入ったお菓子をレジに持っていき購入。
結局毎日ファミリーパックのお菓子を食べ続けるという生活をしていました。
「あーダイエット中なのに。自分にダイエットなんて無理じゃないかな…。」
こういった経験があるからこそ、同じような悩みを持つ人へ向けて今、記事を書いています。
そして甘いものを止めるためには根性や我慢といった自分を抑え込むようなことはしなくても大丈夫です。
なぜかというと、あなたが甘いものを食べたくなる時ってどんな時ですか?
おそらく、ストレスを感じた時が多いのではないでしょうか。
ストレスを感じるとビタミンCやタンパク質、マグネシウム、ビタミンB群といった体に必要なエネルギーが失われていきます。
今はストレス社会といわれているので、このことからも現代の人はカロリー自体は足りているけど、栄養が足りていない質的栄養失調と言われる状態になっている可能性があります。
つまり、何が言いたいのかというと、ストレスを感じた時にこそ”健康的な食事”が重要になってくるわけです。
栄養が失われるのであればそれらが不足しないように栄養価の高い食べ物を積極的に摂っていく。これが大きな解決策になってくるのですが…
多くの人は、ストレスを感じたときに、甘いものを欲してしまったり、ジャンキーな食べ物を欲してしまったりしますよね。
もちろん味覚的に甘いものが大好き!という人も当然、中にはいます。
ですが後ほど解説しますが、多くの人はある原因を解決することで甘いもの欲を確実に減らしていくことができます。
以前、ボクが指導させていただいた20代女性のお客様の例で言うと、指導を始めた時点で甘いものがやめられないという状況でした。
ですが睡眠を改善したり、食事を改善したりあらゆる手段を使うことで1ヶ月後には甘いもの欲はスッと消えていったんです。
ボク自身の経験からも甘いものがやめられない状況が続いていましたがやはり、同じようにアプローチをすることで甘いものへの欲求を減らすことができています。
今回の記事でお伝えしたいのは以下の通りです。
✅甘いものが好きな人は〇〇
✅甘いものがやめられない原因
✅甘いものを減らすための行動フロー
✅甘いものを減らすための栄養素
✅甘いものを減らす行動フロー
・睡眠が食欲を整える
・睡眠の質を高める方法5選
①朝食の正しいとり方
②部屋の明るさはどれくらいが正解?
③カフェインの摂取タイミング
④何時までに食事をすればいいの?
⑤運動をすると睡眠の質は上がる?
・食事で甘いものへの欲求を減らす
・甘いもの欲を減らす内側の施策
・低血糖と甘いもの欲の関係性
・低血糖改善のシンプルな方法
・1ヶ月で甘いもの欲を減らすプランニング
また、ダイエット指導を含めると確実にお得になっているのでぜひ手に取って見てください。
80名ほどダイエット指導をさせていただいた中で培ったノウハウと、自身のダイエット経験も活かしているのでかなり参考になるかと思います。
では本編に入ります。
甘いものがやめられない原因
「甘いものがやめられない…」そう感じている人の中にはいると思います。
しかし、最初にも説明していますが甘いものをやめられないのには味覚的に好きな人もいますがそうでない人もかなり多いと感じています。
つまり、甘いものがやめられないのには原因があり、改善可能と言うことです。
そもそも甘いものがやめられない人は全員ではないですが、ストレスを感じやすい人が非常に多い傾向にあります。
簡単に理由を解説します。
人は甘いもの(特に砂糖)を食べると血糖値が急上昇し、ドーパミンやセロトニンというホルモンを分泌します。
そして、血糖値が下がるとストレスを感じやすくなります。
本来、下がった血糖値を上げるために甘いものをドカッと食べてしまったり、幸せホルモンと言われるセロトニンを出したいがために食べてしまうのです。
後ほど解説しますが、セロトニンは腸でおよそ95%がつくられると言われるので腸内環境が悪くなるとうまく作られずこれもまた甘いものを欲してしまう原因になってしまいます。
さらにいうと、そもそも女性は男性に比べてセロトニンの分泌量が少ないのでストレスを感じやすいといえます。
このことからも女性が甘いものを欲しくなるのが多いことがわかります。
なので今までの説明を一言で表すなら「ストレスを感じやすい状況を抜け出す」ことが甘いもの欲を取り除く方法だといえます。
「育児でストレスフル!!」
「いや職場の上司ウザすぎるけど仕事辞めるわけにもいかんねんけど」
「時間に追われすぎてストレスやばいねんけど」
こんな感じでストレスを消すことって難しいですよね。
なのでもう一度言いますね。
”ストレスを感じやすい”状況を抜け出すことが大切です。
ストレスは0にすることはできなくても感じにくくすることはできます。
今回は食事でできる内面からできるアプローチ方法を解説していきます。
甘いものを減らす行動フロー
甘いもの欲を減らすために改善していきたい部分を洗い出すとこんな感じです。
・腸内環境
・胃酸
・睡眠不足
・栄養不足
・低血糖
1つずつ優先していきたいものから解説していきます。
腸内環境を整える
腸内環境は大切!とよく言われますよね。それは本当で腸内環境が悪くなってしまうとやはり、栄養はうまく吸収されません。
なのでカロリーは足りているのに吸収できない、つまり「質的栄養失調」となってしまいます。
また、吸収されたものが体の中で使われる(代謝)のはその他臓器、ミトコンドリアと呼ばれる場所で行います。
そして先ほどチラッと言いましたが、幸せホルモンであるセロトニンは腸でおよそ95%がつくられるといわれているので腸内環境が荒れるとストレスを感じやすくなってしまいます。
こういった背景からも腸内環境の整えることは甘いものを止めるためには極めて重要だといえます。
では腸内環境を整えるためにはどうすればいいのでしょうか?
それは減らすこと、増やすことを決めることが大切になります。
主に減らしたいのは小麦(グルテン)や乳製品(カゼイン)、オメガ6などの腸の炎症を引き起こしやすいものです。
少量なら問題はないと思いますが、やはり大量に摂取すると炎症が起こり、リーキーガットという腸に穴が開くことで栄養がうまく吸収されない状態になってしまいます。
リーキーガットが進んだ状態がアレルギー反応です。
もちろん、これらは体質的に合う人合わない人、また味覚的に好きな人もいると思うので食べる頻度と量を減らすことを意識して見てください。
また人工甘味料やタンパク質の過剰摂取も腸内環境の悪化につながると言われているので日常的な大量摂取を控えるという認識を持っておいてください。
そして増やすべきこととしては水溶性食物繊維、グルタミン、プロバイオティクス、発酵食品です。
実は腸を動かすための栄養素は食物繊維ではありません。『グルタミン』です。
グルタミンはアミノ酸なのでお肉やお魚などのタンパク質からとることができます。
またグルタミンは腸のエネルギーになるだけではなく、免疫機能にも関わるのでできるだけ不足しないようにしておきたい栄養素の1つです。
そして水溶性食物繊維ですが、これは善玉菌と呼ばれるビフィズス菌や乳酸菌のエサとなることから水溶性食物繊維の摂取はおすすめです。
腸内には善玉菌の他にも日和見菌、悪玉菌が存在しています。
・善玉菌:2
・日和見菌:7
・悪玉菌:1
このような比率になることが理想だと言われています。
ちなみに、日和見菌は善玉菌の量が多いと善玉菌、悪玉菌の量が多いと悪玉菌を味方にする働きがあるので善玉菌の量を増やす必要があります。
少し話がごちゃごちゃしているので腸内環境を良くするために減らすべきものと増やすべきものをまとめると
・減らすべきもの
・小麦製品
・乳製品
・オメガ6
・人工甘味料
・タンパク質過剰摂取
・増やすべきもの
・プロバイオティクス
・水溶性食物繊維
・グルタミン
・発酵食品(キムチや納豆など)
となります。
しかし、腸内環境を良くするためにこれらの要素をおこなったとしてもうまく改善されないパターンがあります。
なぜかというとそれが『胃』の働きです。
胃にアプローチをかけることで腸内環境はより良くなる
腸内環境を整えるのは大事ですがそのためにも胃の働きを正常にする必要があります。
それは胃は消化を行う場所だからです。
胃で消化を行い、腸で吸収するという流れがあるので胃でしっかりと食べたものが消化されることで、腸の吸収もスムーズにいくことができます。
胃の話をする上で欠かせないものが胃酸です。
胃酸は過剰に出てしまうと胃もたれや胸焼けなどが起こります。しかし、逆に胃酸が少ないとどうしても消化がスムーズに行われません。
今回、お話ししたいのは胃酸が少ないパターンのことです。
例えば胃酸が少ないとタンパク質の消化不良や鉄の吸収など体にとって重要な栄養がうまく行われないので結果的に栄養不足となってしまう可能性があります。
なので胃酸が少ない低胃酸の状態はできるだけ改善したいのです。
✅胃酸の分泌量のチェック方法
①起床後(胃の中に何もない状態の時)に重曹2g+コップ1杯100mlの水を飲む。
②3分後ゲップが出るか確認
ゲップが出ない場合は、低胃酸の可能性があります。あくまでも可能性なので必ずしもゲップが出ないから低胃酸とはならないので注意です。
胃酸をしっかり分泌させる対策としては一番はまず『咀嚼』ですね。
そもそも咀嚼をすることで唾液に含まれる消化酵素が消化を助けてくれます。
それとレモン水やリンゴ酢なども胃酸を出すのを助けてくれるので消化不良起こしていると感じている人は食事に取り入れてみてください。
睡眠不足が甘いものをやめられない原因に?
「睡眠不足は痩せれない」
こういった情報を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
結論からいいます。
睡眠不足になるとかなり痩せにくくなるのは事実です。それと同時に甘いものがやめられなくなる原因にもなり得ます。
それを解説していきます。
ちなみに睡眠についてはこちらの記事でもある程度書いていますが、できるだけ内容が被らないように解説します。
睡眠不足が痩せれない、甘いものがやめられなくなる原因は、交感神経過剰になってしまうからです。
自律神経は交感神経と副交感神経に分かれます。
✅交感神経:日中に優位に働く。体を緊張、興奮させる働きがある
✅副交感神経:睡眠時など休息時に働く。リラックスさせる働きがある。
本来であれば交感神経と副交感神経のバランスが保たれていることが重要ですが、睡眠不足によって交感神経が過剰に働いてしまうと必然的に副交感神経が働かなくなってしまいます。
そして副交感神経は消化管を支配しているので、交感神経が働きすぎると消化や吸収がスムーズに行えなくなってしまいます。
ここまでの説明でなんとなくわかったと思いますが、睡眠とダイエットには大きく関係性があるということです。
これをもう少し踏み込んでみると、栄養価の高い食べ物を食べたはいいけど消化や吸収がうまくできないのでエネルギーが作れない。つまり、質的な栄養失調となってしまいます。
エネルギーがつくれないとなると、体はいち早くエネルギーをつくることができる糖質を欲しがってきます。
特に甘いものは血糖値を急激に上げることができるので脳がエネルギーが入ってきたと感じやすいのです。
そういったことがつながって、睡眠不足は甘いものがやめれなくなる原因になりかねないのです。
よく疲れた時に甘いものを食べて誤魔化そうとする人います。しかしそれは逆効果です。
疲れを感じた時に甘いものを食べて血糖値を上げると、一時的には幸せな気持ちが訪れますが、次にくるのは虚無感や喪失感です。
これを繰り返さないようなためにも睡眠を改善する方法を後ほど詳しく説明します。
栄養不足
甘いものがやめられないという人の中にはシンプルに食事内容が悪い人が多いのです。
食事内容が悪いとはどういう状態でしょうか?
それが、栄養価の低い食べ物を食べすぎているという点です。
加工食品がいい例で、カロリー自体は一丁前にあるくせにビタミンやミネラルはすっからかん、といったようなものが非常に多いです。
特に甘いものがやめられないという点に特化した栄養素だとビタミンB群、マグネシウム、鉄、といったところでしょうか。
こういった養素を不足することなく日々の食事から取れていない状況であればそれらを摂取することで改善できる可能性も十分にあります。
もちろん先述した腸内環境を整えたり、胃酸の分泌などができていない場合は栄養をうまく使うことができないのでこれらを改善するのも重要です。
改善方法も後述しています。
低血糖は改善しなさい
低血糖という言葉を聞いたことはありますか?
低血糖はその言葉通りで血糖値が正常の範囲を越えて下がることで頭痛や異常な空腹感、イライラといった症状が起こることをいいます。
そういった症状が起こる方は定期的に糖分を補給することが大切になります。
ボクはダイエット指導をする際には、基本的に3食で十分だと伝えていますが低血糖気味の方はちょこちょこブドウ糖を10g程度補給するように指導します。
ラムネなどが特におすすめになります。
しかし、ここで摂取する食べ物に関してはあまり強制しない方がいいと考えています。
一般的にダイエットをするときにはGI値の低い食べ物(玄米やオートミールなど)といわれます。ごもっともな意見だと思います。
ですが優先して改善するべきは低血糖だと考えています。
そもそも低血糖になるとかなりの疲労感が起こったり、ひどい人だと生きるのが辛いなどといった感情が起きる人もいます。
そういった方々に対して砂糖は控えましょう!添加物はやめましょう!というのはムチを打ちすぎだと考えています。
そういった観点から、低血糖改善をする際には糖質の質に関してはあまり問いません。
ですがこれもいつまでも体に悪いものばかりを食べているのも問題なので慣れてきてからはできるだけ体に負担が少ないものを食べるようにしてください。
1つだけポイントを伝えると、糖分を補給するときは「低血糖になる前に補給する」ということです。
低血糖になった時点でコルチゾールと呼ばれるホルモンが分泌されます。
実はこのコルチゾールと呼ばれるホルモン、血糖値を上げる役割を持っているのですが過剰に分泌されると逆に出なくなってしまうのです。
コルチゾールは副腎と呼ばれる場所から出てくるのですが副腎が疲労してしてしまい、分泌ができなくなってしまうという流れです。
そしてコルチゾールが分泌されなくなると代償としてアドレナリンの過剰分泌となってしまいます。
これがイライラしたり攻撃的になったり、消化器の動きが低下すると言われています。
消化器の動きが低下するので血糖値の乱れ→低血糖になったりするのです。
そのため、無理やり血糖値を上げようとして甘いものが急激に欲しくなることが起こってきます。
なので途中でも解説していますが、低血糖を改善するためには低血糖症状が起こる前に糖分を補給するというのが大事になってきます。
後ほど食事意外のアプローチ方法も解説します。
1ヶ月で甘いもの欲を減らすプランニング
ではここからは1ヶ月で甘いもの欲を減らす方法について具体的に解説していきます。
見るべき視点は以下の3つです。
・食事
・睡眠
・自律神経
これらをフローごとに分けて解説していきます。
食事改善で甘いもの欲を減らす
栄養状態をよくすることで得られるのは、
・腸内環境が整う
・栄養を過不足なくエネルギーにすることができる
・睡眠の質を高める
・低血糖を改善できる
・ストレスを感じにくくなる
こういったメリットがあります。ここまでの流れでなんとなくわかると思いますが、食事を改善することで甘いものがやめられない状態というのはある程度緩和できます。
そこでやるべきことをざっとまとめます。
・カロリーの減らしすぎを無くす
・炭水化物を3食は食べる
・朝食で炭水化物とタンパク質
・食物繊維1食6〜7g(特に水溶性食物繊維)
・野菜をできるだけ多くの種類食べる
・鉄、ビタミンB群、マグネシウム
・グルタミン摂取
・サプリメントばかりに頼らない
・よく噛んで食べる
・寝る3時間前には食べない
・カフェインは昼以降はできるだけとらない
これらを徹底して1ヶ月やってみてください。これらを改善できて甘いものがやめられない人はそうはいないです。
こういった質の良い食事はストレスを感じにくくすることや睡眠の質を高めることにつながるので初めは難しいと感じるかもしれませんが期間を決めて取り組むことでやりやすくなると思います。
といっても1ヶ月も続けるとこういった食事が当たり前になってくるので習慣化してしまいますが笑
ではなぜこのような食事がいいのか、解説をしていきます。
カロリーの減らしすぎを無くす
まず、カロリーの減らしすぎをなくすという点においてです。
そもそもカロリーがない状態だと体はエネルギーを欲します。体にとってエネルギーがない状態というのはかなり危険な状態なのですぐにエネルギーにできるものを要求してきます。
ここまできたらもうお分かりでしょう。
それが糖分です。特に砂糖などの甘いものを余計に欲してしまいます。
そうならないようにもカロリーは摂りすぎず、減らしすぎずという絶妙な部分を見つけていかないといけません。
「そうはいってもどうすればいいんだろう…?」
という方もいると思うので一般的に言われる数値を目安にするといいです。
体重×35kcal以上だと食べ過ぎ傾向、体重×30kcal未満は食べなさすぎだと言われます。
つまり、体重×30〜35kcalがダイエットに良いとされているカロリーになります。
まずはこのあたりで食べる量を調整して見ることがおすすめです。
もちろん、最終的にはカロリー計算せずにお腹の調子に合わせた食事量で体重を維持or減らすようにしていくことが重要になります!
炭水化物を3食は食べる
炭水化物もカロリーと同じで不足すると甘い食べ物を過剰に欲しくなってしまう原因になります。
糖質制限をしたことがある人はわかると思いますが、糖質を減らすと以上に糖質への欲求が起こったことはないですか?
ボクは…あります!笑
だけど糖質は取らないようにしないといけないので質の悪い油を使った低糖質スイーツに走ってしまうという流れがあります。
そもそも糖質は脳でも1日120gは使用されるといわれます。なので糖質を減らすことで頭も働かないので気づいたらお菓子をぺろりと食べていたなんてことにもなりかねません。
そういった意味でも糖質を減らすこと、糖質制限をすることはあまりおすすめしません。
朝食で炭水化物とタンパク質
ダイエットには朝食が大事と聞いたことはあると思います。
さらに何を食べるかも大事で、それが炭水化物とタンパク質をとることです。
理由は主に2つ。
・セカンドミール効果
・睡眠の質を高める
簡単に解説をしていきます。
✅セカンドミール効果
セカンドミール効果を聞いたことがない人もいるかもしれません。
これは簡単にいうと、『1食目の食事が次の2回目の食事に影響する』ということです。
例えば朝食で菓子パンやカフェラテといった血糖値が急激に上がる食べ物をとると2食目も血糖値が乱れやすくなります。
これは朝食を抜いた場合でも同じで、朝食を抜いた状態で2食目を食べても血糖値の急激な上昇が見られたそうです。
血糖値の乱れを起こさないためにも朝食をとることはもちろん、より健康的な食事をとることが重要です。
睡眠の質を高める方法については後ほど詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
(ページ内リンク)
食物繊維1食6〜7g(特に水溶性食物繊維)
食事改善をする上で重要になるのは主に糖質、タンパク質、脂質の三大栄養素ですがボクはこれに加えて食物繊維も特に大切だと思っています。
なぜ大切なのかというと、食物繊維には腸内環境を整えること、満腹感を得られやすいというメリットがあるからです。
ですが、ボクがこれまで食事指導を行ってきた中で感じているのは食物繊維量がほとんどの方が足りていないとうことです。
食物繊維の目安量は男性:21g以上/日、女性:18以上/日だと言われています。
これは、1食6~7gということになります。
どうでしょうか?
この記事を見てくださいっているあなたは摂取量は足りているでしょうか?
もし足りていないのであれば、食物繊維を意識した食事に切り替えるだけでも大きな改善点になります。
✅特に重要なのは水溶性食物繊維
食物繊維には水溶性と不溶性があります。
不溶性は玄米やサツマイモといった穀物やゴボウ、レンコン、カボチャなどに多く含まれています。
一方、水溶性にはワカメやひじきなどの海藻類、オクラ、アボカドなどに豊富です。
そして、特に意識的に摂取していきたいのは水溶性食物繊維です。
簡単にそれぞれの役割を説明します。
・不溶性:腸を刺激して便のカサを増す
・水溶性:便に水分を含ませて柔らかくする
腸内環境をよくするという面で見た時、水溶性食物繊維を取り入れていきたいですが、最初の方で腸内細菌のお話をしたのを覚えていますか?
(ページ内リンク)・・腸内環境を整える
腸内細菌には善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類があると解説しました。
腸内環境を良くしていくためにはできるだけ善玉菌を優位に働かせる必要があるのですが…
まさに、善玉菌のエサになるのが『水溶性食物繊維』なのです。
他にもプロバイオティクスやオリゴ糖なんかも善玉菌のエサになります。
言い換えれば腸内環境を整えるためには善玉菌を増やす食事が大切ということになります。
野菜をできるだけ多くの種類食べる
野菜を多くの種類を食べる理由は簡単に上げると
・食物繊維量を増やす
・ビタミンやミネラルの摂取
・満腹感を増やす
の3点になります。
例えばブロッコリーだけたくさん食べるというとブロッコリーに含まれるビタミンCはたくさん取れるかもしれませんがそれ以外の栄養素が不足してしまうことになります。
栄養は単体で動くのではなく、チームとして動くので過不足なく取るようにすることがエネルギーを効率よくつくり、甘いものを減らすコツになります。
また、野菜はカロリーが低いのでたくさん食べても太りにくく、満足感あるので食べ過ぎ防止という単純なテクニックにもなります。
鉄、ビタミンB群、マグネシウムの摂取
鉄やマグネシウム、ビタミンB群は本当に大切な栄養素になります。
鉄は特に女性に不足しやすいといわれていますが、不足すると疲れやすくなったり、貧血を起こしてしまうことはなんとなくわかってもらえるかと思います。
ですが、それだけではなく、鉄不足になると甘いものがやめられなくなる原因にもなってしまうんです。
どういうこと?と思ったかもしれませんが栄養はエネルギーになって初めて使われます。
鉄はその栄養(糖質や脂質など)をエネルギーに変える時に必要になってくるのです。
マグネシウムやビタミンB群もです。
そういった栄養素を補酵素とか捕因子と呼びますがこれは覚えなくても大丈夫です。
なのでとくに不足しやすいマグネシウムや鉄、ビタミンB群などを不足することなくとるようにしてみてください。
グルタミン摂取
腸内環境を整えると聞くと食物繊維というイメージが強いと思います。
ですが、腸を動かす栄養は食物繊維ではありません。
グルタミンという栄養素です。
グルタミンはアミノ酸の一種で体内でもつくることはできますが、ストレスを感じることでたくさん消費されていくといわれています。
つまり、ストレスを感じやすい人は腸がうまくはたらかなくなってしまうんです。
意識的にグルタミンを摂取することでうまく腸がはたらいて、うまくエネルギーをつくることができます。
なのでタンパク質はもちろんですが、個人的にはグルタミンをサプリメントで摂取するのもいいと思います。
また、グルタミンは腸のエネルギーになることは知っている人も多いのですが、グルタミンはもう一つ大切な役割を持っています。
それがインスリンのはたらきを高めるという点です。
インスリンは栄養の運搬をするはたらきがあるので、グルタミンを摂取することで栄養を吸収しやすくするだけでなく、筋肉や脳といった細胞に栄養を運びやすくもなることがわかっています。
そういった意味でもボクはグルタミンの摂取をかなりおすすめしています。
ちなみにグルタミンともう一つ、グルタミン酸という栄養がありますがあれは別なので勘違いしてはいけませんよ笑
サプリメントばかりに頼らない
先ほどグルタミンのサプリメントすすめてた癖に手のひら返しかよ!と思ったかもしれませんがすいませんw
しかし、実際にサプリメントに頼るのはあまりおすすめしません。
そもそもサプリメントはあくまでもサポートとして使うべきなので食事を取るのが面倒だからと一粒パクッととってはい完了!となっても正直、効果を感じにくんですよね。
これはボクの体験ですが、栄養バランスを考えて食事するのが面倒だったので、ビタミンやミネラルをサプリメントでほぼとっていたじきがありました。
そして1週間ほど試しに自炊をすることにしたのですが明らかに体調が良くなるんですよね。
野菜とか海藻類など栄養価の高い食べ物をよく噛んで食べることで、ちゃんと栄養取れてるなぁって実感できたんですよね笑
これには咀嚼がものすごく関係しているんじゃないかって思ってます。
よく噛んで食べることで消化酵素もはたらきますし、胃酸もしっかりでます。そういった面も考慮するとサプリメントは本当に不足してしまう時にサポートとして取るのが一番いいと思います。
よく噛んで食べる
咀嚼に関してですがこれは、本当に意識してほしい点になります。
咀嚼にはDITを高める効果があります。
DITは食事誘発生熱酸生といって食事をした時にその消化や吸収の過程で消費されるカロリーのことです。
咀嚼回数が増えると消費カロリーが上がるって考えただけでもオトクじゃないですか?
無料でできて、かつリズム運動にもなるのでセロトニンの分泌量も増えるといわれています。
甘いものを減らすためにも『咀嚼』はとても大切になるのでぜひ意識してみてください。
睡眠改善で疲れを甘いものでごまかさない
ではここからは睡眠の質を改善する方法を説明していきます。
日中の眠気がひどい、朝スムーズに起きれないという状態が続いている人は実践することで改善できると思うのでぜひ読み進めてください。
睡眠と朝食
結論方お話しすると睡眠の質を高めるためには朝食が重要です。
睡眠には『メラトニン』という睡眠誘発ホルモンをうまく出すことが大切になります。
このメラトニンは幸せホルモンのセロトニンというホルモンからつくられます。
※くどいですがセロトニンは腸で95%がつくられるので腸内環境の状態も重要になります。
また、セロトニンの材料になるのがアミノ酸のトリプトファンと呼ばれるものになります。
簡単にまとめます。
(図解)メラトニン→セロトニン→トリプトファン
この図からわかることは、タンパク質と糖質が重要ということですね。
ですがそれでは終わらないのがこのnote。
なぜ朝食が必要なのか?この疑問が出てきますよね。
それはトリプトファンからメラトニンになるまでにおよそ15時間かかるといわれています。
はい、見えてきましたね。逆算するとだいたい朝食が重要なことが改めてわかります。このことからも毎日同じタイミングで朝食を取るのがいいということもいえますね。
普段、朝食を抜いてなかなか寝付けない人はぜひ朝食を食べるようにしてみてください。変化を感じられるはずです。
部屋の明るさと睡眠
先ほどお話ししたメラトニンですが実は光による影響も大きいのです。
明るい光を受けるとメラトニンの分泌量は抑制されるので日中はメラトニンの分泌量が少なく、夜にかけてどんどんん分泌量が多くなります。
そのため、夜に明るい光が良くないといわれるのはこの理由からです。
・スマホを夜遅くまで見る
・部屋の明かりをいつまでもつけている
・仕事が終わらずPC作業をしている
このような人は睡眠の質が下がってしまうのは当然といえば当然なんです…。
ちなみに、メラトニンは100ルクス以上の光刺激で分泌量が少ないといわれています。
この図を見てください。
なかなかこういった環境をつくることは難しいかもしれませんが少しでも部屋を暗くしたり、寝る前はスマホを見ないなどの工夫が必要になります。
部屋の明るさ対策
・寝るまのスマホを控える
・暗くなってきたらへの明るさをだんだん暗くしていく
・夜の明かりは暖色系
・寝るときは遮光カーテン
このあたりをおすすめします。
また先ほど記載していますがこちらのnoteにも具体的なノウハウも記載していますのでぜひ参考にしてください。※全て無料です。
カフェインをとるタイミングを考える
カフェインは集中力を上げたり、脂肪燃焼効果を高めてくれるので緑茶やコーヒーを普段から積極的に摂取している人も多いかもしれません。
しかし、ときには毒になることを知っておきましょう。
カフェインの取りすぎやタイミングを間違って摂取すると逆に眠れなくなります。
その結果、食欲が乱れ甘いものに手を出してしまう可能性が高いのです。
ちなみに過去のボクはこのパターンでカフェイン摂取→眠れない→夜中にドカ食いという負のスパイラルを繰り返していました(笑)
そうならないようなためにもカフェインの摂取タイミングは考える必要があります。
カフェインの作用には個人差がありますが、一般的には4〜5時間、長い人だと6〜8時間といわれています。
なので逆算して寝る6~8時間前には摂取を控えるのがよいかと思います。
ボクはカフェインの怖さを知っているので昼以降は飲まないようにしています笑
寝る3時間前には食べない
睡眠の質を高めるために寝る直前の食事は避けるようにしていきたいです。
寝る前に食事をしてしまうことで消化や吸収に内臓がはたらいてしまうので睡眠の質に悪影響が出てしまうのです。
なので寝る直前、大体3時間くらい前からはできるだけ食べないようにするのがおすすめです。
どうしても夜遅くの食事になるのであれば、消化の早い食べ物を中心に食べるようにするなど工夫をしていきましょう。
運動しないと睡眠の質は低下する
運動をすると疲労が溜まるという人は多いはずです。
しかし、ボクの経験から言わせてもらうと、大抵、そういった人は運動しないから疲労が溜まりやすくなってしまっている方が非常に多いと感じています。
どういうことか簡単に説明します。
✅精神的な疲労と肉体的な疲労感
疲労には2つの疲労があるのは知っていますか?
例えば、緊張した場面を抜けるとドッと疲れがくるとか、上司に怒られてしんどいとかは精神的な疲労になります。
逆に運動した後に来るのが肉体的な疲労です。
実は、多くの人は精神的な疲労感を感じ、疲れが溜まるといっている人が多いです。
精神的な疲労と肉体的な疲労は2つのバランスが大事になってきます。
体は全く疲れていないけど、メンタルがやられて眠れない…ということを経験したこともあるのではないでしょうか?
これは、精神的な疲労と肉体的な疲労のバランスが悪い状態です。
つまり、『運動しないから眠れず、疲れが抜けない』という言い方ができます。
なのでこういった状態を解決するのが『運動習慣』ということになります。
運動習慣がない人はまずは週2回のトレーニングをやることがおすすめです。
詳しい内容は問いませんが、心地よい疲労感を感じられる程度で大丈夫です。
もっと詳しくいうなら次は絶対にやりたくないというくらいのハードな運動はやりすぎ、またやってもいいかなと感じられる程度の強度で運動するといった感じです!
自律神経を整えるとストレス減り、食欲が正常化する
自律神経は睡眠や腸内環境との関係がとても高いので、自律神経が乱れてしまうことで結果的に甘いものがやめられないという症状へつながっていきます。
そこでこの章では自律神経系の乱れをなくす方法をいくつか紹介しようと思います。
自律神経に唯一働きかけることができる運動
自律神経は自分の意志ではコントロールができないといわれています。
しかし、唯一自律神経を刺激できる運動があります。
それが『呼吸』です。
呼吸は息を吸うときに交感神経、吐くときに副交感神経がはたらきます。
ゆっくり息を吸って、吐くを10回ほど繰り返すだけでも落ち着いたりします。
このとき、吐く動作は思いっきり吐くのではなく、息を吸った時の2倍の時間をかけてゆっくり吐くことがコツです。
太陽の光を浴びる
朝から太陽の光を浴びることも自律神経を整える方法になります。
これは体に「あさが来たよ!」と知らせるはたらきや、セロトニンを分泌して体内時計のリセットにつながります。
体内時計が正常だと、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズになるので朝起きたらカーテンを開けることは簡単にできますしおすすめです。
腸内環境を整えることも自律神経の調整になる
実は自律神経と腸は関係があることがわかっています。
この記事で口酸っぱく解説している「セロトニン」も腸でほとんどがつくられるので不足すると、ドーパミンやアドレナリンの抑制が効きにくくなります。
また、研究でも精神疾患(うつなど)の方は、下痢や便秘、セロトニン分泌量が少ない、悪玉菌が多いなどメンタル(自律神経)と腸は関係があることがわかっています。
つまり、腸を整えると自律神経が整い、逆説的に見ても自律神経を整えるアプローチは腸を整えることにもつながるということです。
このnote内で腸内環境を整える食事についても解説しているのでぜひ実践されて見てください。
自律神経を乱す根本的な原因を見つける
呼吸について解説をしていきました。
しかし、紹介した呼吸はあくまでも対処方法でしかありません。
根本的な原因を見つけ出す必要があります。
例えば、自律神経を乱す行動の1つに寝る前のスマホがあります。
これはブルーライトの刺激を受けることで交感神経が過剰に働いてしまうことで交感神経優位の状態になるのです。
なのでこうした要因で自律神経が乱れているのであればその根本的な原因を見つけ出すことがとても大切になります。
そういった意味でも『自律神経を整える方法』ばかりに頼るのではなく、原因を解決できるようにしていきましょう。
ちなみにノウハ1日で120gの糖質を使うのでこのnoteを理解しながら読み進めるだけでもダイエットにつながるかもしれません笑
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
