
リストの音を受け継いだ、天才ピアニストとの対話
イントロダクション
天才音楽家、リュドヴィック・セルミ
こんにちは、『作曲の科学』『楽器の科学』(共に、講談社ブルーバックス)でもお馴染みの、作曲家・マリンバ奏者のフランソワ・デュボワです。
今回の記事は、僕の盟友、天才音楽家のリュドヴィック・セルミとの特別対談です。作曲家としても活躍する彼の作品のスコアが、この度、日本の音楽出版社D-Projectからリリースされたことを記念した企画です。
天才音楽家の思考回路やインスピレーションの源、クラシック業界の闇に関する話題に至るまで、色々と引き出していこうと思います。
少しボリュームがありますが、彼の話は辛辣ながらも、鋭く的を射ているのでどうぞ最後までお楽しみください。
リュドヴィックの略歴
まずは彼の略歴から。

リュドヴィック・アマデウス・セルミは、フランスのピアニスト・作曲家です。フランツ・リストが創設したことで知られる、ジュネーブ・コンセルバトワールのピアノ科出身です。つまり、リュドヴィックはリストの直系弟子の流れにあたります。

その後、マルセイユのピエール・バルビゼに師事します。バルビゼはエコール・フランセーズの偉大な教育者の一人としてあまりにも有名ですが、彼曰く、リュドヴィックは非常に個性の際立った作曲家だと評しています。
ちなみに、リュドヴィックは、ガブリエル・タッキーノ(ピアノ)にまえがきを頂いた拙著『楽器の科学』にも、ゲストの一人として登場しているので、日本のみなさんとも少し接点があります。
彼とは1990年代の初頭にパリで出会いすぐに意気投合し、マリンバとピアノのデュオを結成しました。フランス各地の有名ホールをはじめ、スイス、日本にまで遠征ツアーを組み、様々な土地で演奏して周りました。だから、僕は彼を盟友と呼んでいます。
リュドヴィックのソリストとしてのキャリアも着々と展開し、ボルドー・アキテーヌ国立管弦楽団を指揮するロベルト・ベンツィとの共演など、華々しいステージに次々と登場します。
やがて、地中海沿岸のトゥーロン出身の彼は、パリを離れて再び南仏に居を構えます。彼が選んだのは、生まれ故郷からさほど遠くないタラスコンと呼ばれる、静かで美しい街。ここを拠点に、音楽活動を精力的に行っています。
それにしても、なぜ便利な国際都市パリを離れて、わざわざ田舎に移ったのでしょうか?

ずば抜けた才能に決して安住しない、型破りな人物として、常に新しい道を切り開くリュドヴィック。クラシック音楽業界における華々しいキャリアなどはじめから眼中になく、煩わしい人間関係や政治から距離を置いて、独自の道を切り開く、孤高の天才ピアニスト、と僕は絶賛するアーティストです。
そんな彼とのやり取りを、日本のみなさんに楽しんで頂こうと思います。
その前に、百聞は一見にしかず。
彼の天才ぶりが一聴してわかる、プロコフィエフの「トッカータ」の見事な演奏をご堪能下さい。
対談本編
天才音楽家同士が、忖度なしに語る
フランソワ・デュボワ(FDB):リュドヴィック・セルミ、改めてこんにちは。
今回の対談については、ひとつ提案があるんだ。二人とも業界のしがらみがない分、クラシック音楽界の話を遠慮なしに、本音を交えてしたいと思っているんだけど、どうかな?その方がこの仕事におけるリアルな部分に光が当たるし、読者には新鮮な切り口になると思うんだよね。クラシック音楽業界の話を、忖度なしにすること自体がタブーになっている風潮もあるからこそ、僕らで風穴を開けてしまおうかと。
リュドヴィック・セルミ(LS):よしきた!
FDB:国立のラジオ音楽局が嫌いだとか、そういうことも遠慮なしに言って欲しい(笑)。
LS:ああ、フランス・ミュージック(※)ね!あそこはほんとに耐え難い組織で、「政府公認」「お墨付き」の音楽家じゃないと、怖くてゲストに迎えられないという、信じられない連中だよ。
(※クラシック音楽専門の国営ラジオ局)
FDB:いきなり落として来たね!
実を言うと日本でも多少の違いはあるものの、似たようなことが起きているからこういうのはフランスだけの話じゃない。
LS:組織だけじゃなくて、アーティスト個人レベルでも、迎合主義な連中があまりにも多いのが、クラシック業界だね。干されないように、絶対、組織や派閥の枠を出ようとしない。仕事を失いたくないという気持ちはよく分かるけど、アーティストとしてそういう身の処し方って悲しくないか?って思うね。
FDB:そう。話の核心をついたね。
その話に深く触れる前に、まずは、君が住んでいるタラスコンの街の魅力について聞かせてくれないかな?
LS:よろこんで!今住んでいるタラスコンに落ち着いたのは、実は何度も引っ越しを繰り返した末なんだ。騒々しくて汚い大都市に辟易していたので、とにかく、穏やかな環境を手に入れたかったのが一番の理由だね。
そういう意味でタラスコンは本当にぴったりの場所に見えたんだ。いくつもの大きな街の中間地点で、飛行機にもTGV(超高速鉄道)にも簡単に乗れて移動にも便利だし。
非常に美しい街で、見どころがたくさんあるよ。あのモネ王の城や、立派な教会に、名の知れたイタリア式劇場もある。俺はもともと南仏出身だから、太陽と静寂が必要だったんだ。


大都市から離れる傾向は、ソリスト仲間でもどんどん増えている昨今だけど、俺はそのずっと前にいち早く実行してしまっただけさ。
コミュニケーションは直(じか)のやり取りがもちろん一番だけど、今はインターネットのおかげでやり取りの質も格段に上がって、かなりたくさんのことができるようになったしね。
華やかなキャリアに、一切興味なし
FDB:君の場合は、天才的な音楽センスを持ちながらも、音楽業界の中心地からわざわざ遠ざかりたかったという強い意思を感じるんだよ。会食やカクテルパーティーに勤しんで、とにかくのし上がってキャリアに磨きをかける!っていう道に真向からNOを突きつけたよね。誰もが憧れる、街から街へ、国から国へ、一年中コンサートをして世界を飛び回るようなキャリア志向じゃない。

LS:そうだね。すべて流れに任せておきたいんだ。これまでも何の支障もなくこのやり方でこれたので、それで十分だと思っている。まあ、俺もちょっとばかしピアノが上手いから、みんなまた呼んでくれるしね(笑)。
これもひとつのネットワークと言えばそうかもしれないけど、厳密に言うと俺の場合、一般のそれとは明らかに違う大事なポイントがある。それは、ギャラの額で演奏するかどうかを決めないって点だ。逆にそういうのは、絶対に耐えられないんだ。他のソリストみたいに、所属エージェントやコンサート主催者が、ギャラの額から演奏する内容、共演者と場所まですべて勝手にどんどん決めていかれるなんて俺は絶対嫌だよ。
FDB:キャリア志向のコンサート奏者(※ソリストコンサートのみで生計を立てる音楽家)になろうと決心したら、その世界で生きていくためのルールを自分に強要せざるを得ないことがあるからね。
LS:そう。しかも、室内楽の共演者まで強制的に当てがってくることもあるからね。
アーティスト人生の理想とリアル
FDB:アーティストってさ、この世知辛い世の中でできる限りの「自由」を手に入れて、迎合しないで生きていきたい!という想いが活動のモチベーションだったり、原点だったりするよね?それを思うと、みんなが本来目指していることと実際にやっていることが乖離し過ぎて、その矛盾をどうして我慢できるのか、解せないんだ。
ベテランのソリスト友人たちは、異口同音に「演奏旅行がしんどい。もう辞めたい。」って、会う度に言うくせに、しがらみが多すぎて辞められないループにずぶずぶにハマっている。
LS:世界中に名の知れた偉大なソリストでも、時の政権に担がれている輩と共演せざるを得ない時もあるしね。政権に担がれている音楽家達は、実力以外の様々な理由でその地位にありつけたり、据えられたり。読者のみなさんも、ぜひ自分で調べてみるいい。色々な事実が出てきますよ
つまり、そういう人間とも協力をしないと、知名度が上がらないし、大きな仕事がもらえないのがクラシック音楽界の現実なんだ。

この仕事をすると予想以上に多くのことを強要させられる。まして知名度を上げたければ、思ってもみなかったプレッシャーにも晒されやすくなる。
俺たちの職業は、本来、自分の感性をどんどん表現していくものだ。俺も明確な音楽性を提示してきたし、好きな音はとことん守り抜く覚悟でいる一方で、興味がない音は忖度なしに完全にスルーしている。そうやって自分の音を守り抜いていくのが、アーティストだと信じている。
リリースされたスコアの紹介
『Quintette』
FDB:じゃあさっそくなんだけど、今回D-Projectからリリースされたスコア3曲の話を順番に聞かせて欲しい。まずは1曲目の『Quintette』だけど、これはどういう曲なの?

LS:これは弦楽四重奏とマリンバの組み合わせなんだ。
FDB:ということは、マリンバはソリスト扱いではないよね。
LS:そう、四重奏に取り込まれているから、むしろ五重奏の一員の位置付けだね。
FDB:この曲の45分という異常な長さに、はじめはびっくりしたよ!
ちょっと普通じゃない長さだけど、この作品を書くにあたって表現したかったこと、そして何よりもなぜマリンバを組み入れたの?
LS:おお、さっそく軽く扱っちゃいけない質問が来たね(笑)。
マリンバに関しては、某フランソワ・デュボワという音楽家によってマリンバの魅力を発見させてもらった事がきっかけでね。この音楽家、君も知ってるかな?(笑)
それで、マリンバとピアノのデュオ曲をいくつも書いた後に、マリンバを軸にした新しい環境を次に試してみるのが相応しいと思ったんだよ。自分としては、木を叩いて直接響かせるマリンバの特性と、弦が木(のボディ)を響かせる弦楽器の特性が混じり合うとどうなるのかに興味があったんだ。
FDB:その辺り、もっと掘り下げてもらってもいいかな?
LS:この作品は、セル(セクション)から始まって、繰り返されるメリスマ・メロディック(※歌唱の技法としてよく使われ、単一の音節に対して複数の音符が割り当てられること)を使うことで、巨大なメタモルフォーゼのようになっていくんだ。中心にきらきらと輝く箇所がレース刺繍のようで、有機的で、曲頭の音よりも荒々しい感じになってくる。
FDB:かなりロック調のハーフトーンのパッセージもあるよね。
LS:そう、その通り。はっきりとした重厚なパッセージだよね。無調のパートはより幻想的な印象で、フィナーレでは弦楽器が常に真空中で震えていて、オーケストラの音合わせのような印象を与えるんだ。
これは相当身体を酷使する体力のいる曲だから、怠け者には演奏できないシロモノだよ。
FDB:それに、コンサートの半分以上の長さを占めると来た。
LS:そう、交響曲と同じ30〜40分ってところだね。
『L'addition s'il vous plaît!』
FDB:2曲目の『L'addition s'il vous plaît!』に移ろうか。この曲はマリンバとバイオリンの二重奏で、極端に短いのも、前の曲と随分対照的だね。しかも曲名がフランス語で「会計お願いします!」だなんて、周りの日本人に話したら、みんなこの言葉のチョイスに驚いていたよ!(笑)この曲について、もう少し詳しく教えて。
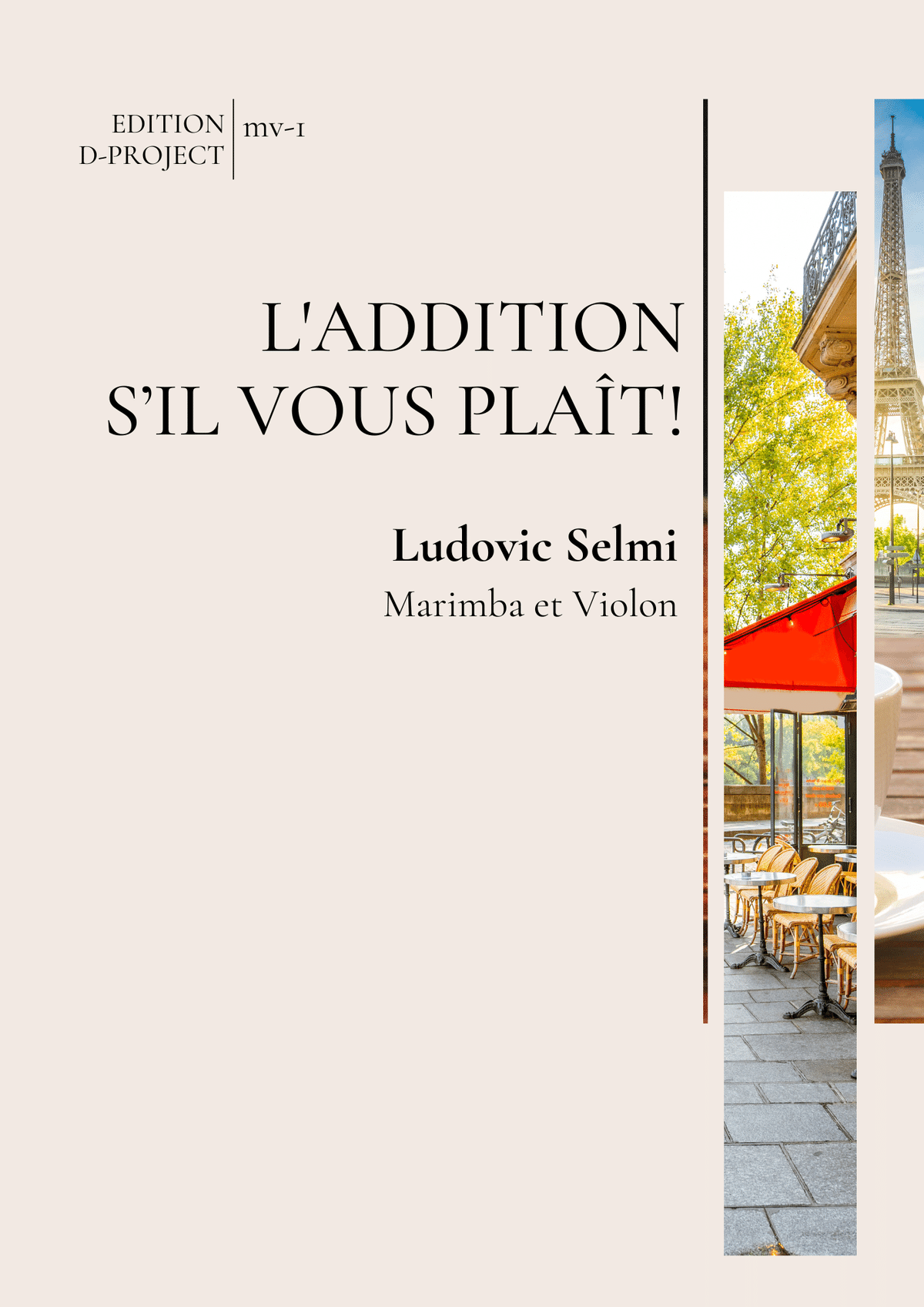
LS:まず曲名についてなんだけど、1+1、2+1、2・3+1、2,3,4とリズムの足し算(l’addition)になっているんだよ。だから、本当の意味は「足し算してください!=L’addition s’il vous plaît!」なんだ。わざと会計を願いする時の言い回しと掛けてある(笑)。
FDB:ああ、そういうことか!
LS:これは、ある種の短音階に基づくグルーピングのようなものだ。少し専門的な説明になるけど、要するに、第一音の外れ音と第五音の外れ音を利用して、バイオリンが強調的かつ執拗に演奏することで、一種の永久的な動きと催眠的な効果を生み出して、トランス状態に導くようになっているんだ。
FDB:え?でも、こんなに短かったら催眠状態に入れないよ?
LS:ははは、だから繰り返し演奏するんだよ!延々と弾き続けるんだ。
FDB:スコアのあの構造は、そういうわけだったのか!今、腑に落ちたよ。
『Amé』
FDB:よし、じゃあ3曲目の『Amé』に移ろう。これは日本語の「雨」から来てるよね。とても素敵な曲名だけど、これは間違いなく、いっしょに来日を果たした時にインスパイアされたものでしょう?

マリンバ、ピアノ、バイオリン、そしてレインスティックで構成された曲だよね。このレインスティックは珍しい楽器だけど、どんな楽器か説明してもらえるかな?
LS:レインスティックは16世紀に南米の農民によって発明されたと言われているけれど、さらに昔にさかのぼるという説もあるね。単純に、雨乞いの儀式のために使われたみたいだ。ちなみに、アフリカには雨乞いの音楽があるけど、南米のチリ辺りにはこの楽器があったというわけさ。

小さな木の幹をくり抜くか、時には竹を使うこともあって、内側にトゲを刺して中に種を詰めると、回した時に種がぽとぽと落ちる音がする。幹の両端に張られた皮が楽器の共鳴を生み出すことも、重要なディテールだね。
FDB:僕もフランスで一本持っていたよ。曲の構成としては、雨音を表現するレインスティックは同時に湿度も表現しているよね。それ以外の構成は、どういう意図なの?
LS:冒頭は非常に広がりがあって、直線的な構造にしたんだよ。こうすると移ろいやすい雨音に、ピアノがベースの役目を果たすしね。その上に、マリンバとバイオリンが繰り返し現れては去っていく。はっきりとした終わりがなくて、代わりにただ静寂に向かっていくという、非常に禅的なイメージなんだよね。
FDB:興味深いな。君が終わりについてさっきも何やら言及していたのを聞いてると、実は「終わり」が嫌いみたいだな。
LS:たしかに「終わり」が嫌いなんだよ(笑)。終盤は冒頭部分とは対照的で、非常にパワフルで激動的に仕上げてあるんだ。中間部は、少し落ち着いてから再び盛り上がる。最後はクレッシェンドで、冒頭部分とはまったく正反対の動きにしてあるんだ。
FDB:ある意味、陰と陽の組み合わせだね。二つの世界が次々と入れ替わるようだ。
LS:それだよ、まさに次々と入れ替わる。
FDB:あとレインスティックは、最後は出番がなくなっているね。
LS:実を言うと、レインスティックは、譜面上では雨を表現しているけど、同時にリレーバトンに見立ててあるんだ。演奏していない時にマリンバ奏者からバイオリニストにリレー式に渡すように書いてある。
FDB:へえ!これはすごく面白い。
『Astéroïdes et Baobab』
FDB:ついでだから、有名な音楽出版社アルフォンス・プロダクションからリリースされたマリンバとピアノのデュエット『Astéroïdes et Baobab』のシリーズ6曲についても、話をしてみたいと思う。この作品集はD-Projectから出したものではないけど、非常に独創的で人気があるので、この機会にぜひ紹介しておきたいと思ってね。この作品集が特別なのは、2つの楽器ともソリストであり伴奏者でもあるということだよね。ピアノがソロ楽器の伴奏をする、という一般的な形式とはまったく違うのが面白いんだ。
LS:そう。この曲では従来の方法を無視して、混ぜてしまうんだ!
FDB:わくわくするね。この曲のキモはズバリなんだろう?
LS:とても民主的な音楽なんだ。特に惹かれたのは、2つの音色が混ざり合うところなんだよ。ピアノとマリンバの組み合わせだと、しばらくするとどれが何を弾いているのかわからなくなるのが、これまたいいんだよ。
FDB:うん、どこに誰がいるのか本当にわからなくなっていくのに、最終的には絶妙にブレンドされているんだよね。
LS:俺の音楽言語の基本原則として、捨てるものは一切なしで曲を創るんだ。例えば、今どきのほとんどの作曲家が嫌がるハ長調の和音でも、俺だったら実に美しく響かせるよ。ハ長調だってニ長調だって大好きだし、どんな素材でも本当にいいんだよ。それよりも、曲を創るときはできるだけたくさんの音色とダイナミックレンジが手元に欲しい。だから捨てるものは一切ない。
FDB:これは、もうすべてに共感するね!僕も、それこそが作曲家に求められることだと思っている。自主検閲したり、冒険や革新を拒否するなんてあり得ない。そもそも「これが正しい考え方だ」と主張する輩と群れたがる発想そのものが知性の停滞だし、中世への回帰(=稚拙な発想に逆戻り)でしかない。「音楽の中の悪魔(Diabolus in musica)」と言われた、有名なトリトン三和音(3つの音が互いに続く和音、恐ろしく邪悪な効果をもたらすと、かつて言われていた)の時代に逆戻りだよ。この三和音は、悪魔的なものとして教会から禁止されたと言われていて、公式な文書記録はないけど、音楽家たちの間では有名な話だよね。進化しないものには退化しか道が残されていないってやつだな。

LS:トリトン三和音、大好き!(笑)たしかに、ロマン主義時代(19世紀前半から後半にかけて)にやっと今のような作曲の自由は獲得されてきたしね。ひとことで言うと、俺は自分が聴きたい音楽を創ることに徹しているだけなんだ。
FDB:これこそが重要だよ。
LS:ラジオをつけたらいつだって自分の曲を聴きたいとまでは言わないけど、少なくとも「ラジオからこれが流れてきたら、最高だよね」と思うものを創っている。今好きだと思う曲を書くし、その時に受けた影響が投影された曲づくりになるけど、それは常に進化していくしね。作品によって雰囲気が違っても、自分らしい印みたいなものに気づいてくれるととても嬉しいよね。あとは、一般的にプロの作曲家は作曲法を学んでいるもんだけど、多くの人は学んだ通りにしか曲づくりをしていない。つまり、自分の進化を止めてしまっている。
FDB:それ、コンピューターって呼ぶやつね。もっとも、今はAIを使えばその辺の人間より良いものを創ってくれたりして(笑)
天才と凡人の発想の違い
一流になりたければ、反逆的になれ
LS:多くの人は、自分自身を解放すること、今の枠から飛び出して、もっと違う何かに向かって探求しながら曲づくりをすることが難しいと感じているようだね。それと、演奏や練習方法も、先生を再現するのは本当に止めた方がいい。そうでないと自分の中にある先生信奉に押し潰されそうになりながら、「先生のように弾きたい、先生のようになりたい!」という、苦しいだけの行動や考え方、振る舞いが身についてしまう。
FDB:教え子に対して先生が「つべこべ言わずに、この低音は、こう弾くべきです。」て叱責しているのが目に浮かぶね。で、「はい先生!でも何故ですか?」って口答えしようものなら(笑)
LS:「何故もなにも、こうだからです!きー!」「それに、〇〇の弾き方がまさにこうじゃないですか!」なんて言われたりしてね。
でも、俺はフォルテでは弾きたくない、むしろピアノで弾きたいと思うところがあったら、それをちゃんと「自分の感性と言葉」で裏付けるから、絶対に先生の押し付けに屈しない。
FDB:こういう指摘は、多くの音楽家にとっては耳が痛いと思う。音楽修行のはじめの頃は、とにかく規則や先生の指示に従う事を徹底的に仕込まれて、自力で羽ばたけるようになるまでしっかりと訓練を受けなくちゃいけない世界だから。
でも、君はわりと早い時期からむしろ反逆的な精神も養っておけと言ってるよね。その心を教えて欲しい。

LS:いい質問だね。いや、根源的と言えるかもしれないな。つまりルールを超越できなくちゃいけないということなんだ。学びはじめの頃はダメだよ、前進できなくなってしまうからね。先生の言うことはちゃんと聞かなくちゃいけないけど、同時に自分の個性や、筋の通った感覚を養わなくちゃいけない。アカデミズムに蝕まれることなく、自分の伝えたいことを持つべきだ。
かなり多くのソリストは先生や師匠が植え付けた無価値な教訓に固執するあまり、それがいつかどこかで壁として立ち現れて、呆然と立ち尽くしてしまうんだ。そして、それを越えられない壁と認識してしまう。そのあとどうなるかと言うと、ソリストはただの師匠のコピーになり下がってしまうんだ。ちょっとだけ新たなニュアンスが音に加わった、先生のコピー人間さ。
そういう事を伝えたかったんだよ。

もともとの師匠が素晴らしい音楽家であれば、そうなってしまっても少しは救いようがあるね。一方、最悪なのは師匠のレベルがそもそも大したことない場合ね。ソリストは師匠から受けてしまった呪縛から自分を解放しない限り、誤った考えを元にずっと演奏を続けたり、「〇〇がこう演奏したから」という、他人軸の音を弾き続けることになる。
あとは、知ったかぶりをして実は何もわかっていない先生というケースもあるね。この場合はもうはじめから終わりまで、大惨事だ。
こういう説明で明確になったかな。
音楽業界の闇のからくり
FDB:ありがとう。君の説明には全面的に大賛成だ。でもこういう重要な分析ほど、耳にするチャンスが少ないよね。そもそもクラシック音楽業界で波風を立てるのを関係者はもの凄く嫌がる。余計なことを言うなって顔をされたり、もみ消されたりするね。なんせ迎合的な集団だから。そんなことよりも、這い上がるために人脈作りに勤しみたいから、大勢の流れに付いていく方が大事だ!という空気だよな。
LS:そう。優先順位の断トツでトップが「強い人脈づくり」、「音楽」ははるか彼方の二番手。
FDB:ここまで演奏家についての話をしてきたけど、作曲家についても話をしてみたいんだ。すでに色々とツッコんだ話をしているので、ついでに聞いてしまうよ。パブリックの助成金をもらいやすいように、“変装”して媚びた曲づくりをする作曲家が大勢いる一方で、純度の高いインスピレーションで作曲する、クリエイションの本質を守りぬくアーティストもいる。
こういう状況について、君はどう見ている?
LS:君が指摘しているのは、「公式」作曲家になりたがる連中のことだね?(笑)音楽に限らず、「そんなのはアーティストじゃなくて消防士だろ!」みたいな、放水するごとく絵の具をべちゃべちゃ塗りたくる「公式」画家とか、もっと遡ると、皇帝や王様に囲われていた「公式」肖像画家とか、そういうのは昔からいっぱい居たよね。

FDB:そう、信じられないセンスの奴もいたりする。
LS:結局、そういう類の人脈の輪に入るには、キーパーソンからお墨付きをもらう必要があるから、キーパーソンらしき人物をまずは探し出そうと、みんな躍起になるよね。だって、その人物に気に入られたら助成金を手にしやすくなる業界の仕組みがもともとあるわけだから。だから創作よりも人脈強化の方にベクトルが向いて、魂を売りさばくアーティストも出てくる。
FDB:アート業界って心底ドロドロしてウェットなところだと評価していて、僕が日本に来てビジネスや他の様々な世界にも足を踏みいれるようになって世界が一気に広がった時、音楽業界をふり返ると、余計に重さが目につくようになったんだ。こういう業界気質がある中で、我々二人に共通しているのは、魂の本音を大事にするために、ひたすら妥協せず、色んな網の目をすり抜けてきたってことだなといつも思う。君はどうやってここまでやって来れたのか、ちょっと聞かせてよ。
しがらみから一線を画す、幸せな生き方
LS:確かにな。俺は先にも少し言ったけど、オーディエンスと直にやり取りする方法にかけてきたんだ。そうやって信頼に基づいた関係性を築いていくと、有名な曲を弾くだけじゃなく、自作の曲も披露すると、みんなもの凄く喜んでくれるんだ。曲に“没頭”してくれるんだよ!素晴らしいと思わないかい?みんなだってその時々の現実をまとって生きている。社会問題や色々な影響下に晒されながら、日々を営むよね。そんな息遣いがホールを覆っているのを感じながらいつも演奏している。
去年、スイスで演奏をした時に、観客同士のなにげないお喋りが聴こえてきたんだ。「今日はこのコンサート来たけど、ぶっちゃけ現代音楽は退屈だから、時間が経つのが長く感じそうだよ。だから、このあとのレストランを楽しみにして来たんだ!」
FDB:その時は、何を弾いたの?
LS:『33体のミニチュア』だよ。短い曲がたくさん集まった俺の作品集。
FDB:ああ、あれね。もちろん知ってるよ。

LS:すべての作品を弾き続けると、ちょうど一時間の作品集なんだ。
さっきのおしゃべりも耳に入っていたもんだから、演奏前にオーディエンスに向かって直接語りかけたんだ。
「目を閉じて、僕のことを信じて、どうか最後までついてきてください。そして、一時間後どうだったか、ぜひ感想を聴かせてください!」とね。オーディエンスの心を捉えて直接語りかけると、すごく上手くいく。
俺は曲を創ったあと「まあ、あと300年もしたら、この曲は大傑作と言われるかな」なんてもったいぶらずに、今ここで、オーディエンスと一緒の時間と空間を生きたいんだ。
FDB:300年後なんて、この目で確認しようがないしね(笑)
LS:自分の死後の音楽のことなんて、あとは野となれ山となれ!だよ。
大コケしかけた大傑作
FDB:『Totem』の話もしていいかな。これは、世界の一流アーティストを支援したり、レジデンスに受け入れている財団シテ・アンテルナショナル・デザール・パリ(パリ国際芸術都市)の25周年記念式典のために共同で作曲した曲だったね。
『Totem』はラジオ・フランスの有名な104スタジオで創作して、国営ラジオ局でも全国放送されたんだよね。

(c) Maurine Tric
LS:このプロジェクトは圧巻だったよね!それにしても、もの凄い試練だった。
FDB:あらゆる紆余曲折を分かち合った忘れがたいエピソードだけど、ここは君に語って欲しい(笑)
LS:そもそもかなり破天荒な企画だったよね。しかも、初期段階からコンサートに至るまでのすべての工程におけるエピソードが多すぎる!公式発表では、本番のあの時ホールには25か国の大使が参列していたらしい。
FDB:そうなんだよ。式典のオープニング曲という位置づけで、さらにクラシック界の大御所も僕らのすぐ後に列をなして演奏を控えていただけに、こっちはその分、尖ったコンセプトでガツンとインパクトを残したいと思っていたから、もの凄いリスクを背負ったよね。で、肝心の『Totem』はどんな曲なの?どういう構成?
LS:良かったら、君が答えなよ。
FDB:今回は君がゲストだから、お願いするよ。
LS:マリンバ、ピアノ、ティンパニ、バス・ドラムの編成に、200リットルのドラム缶を叩く人気グループ『Les tambours du Bronx(レ・タンブール・デュ・ブロンクス)』とコラボをしたんだよね。
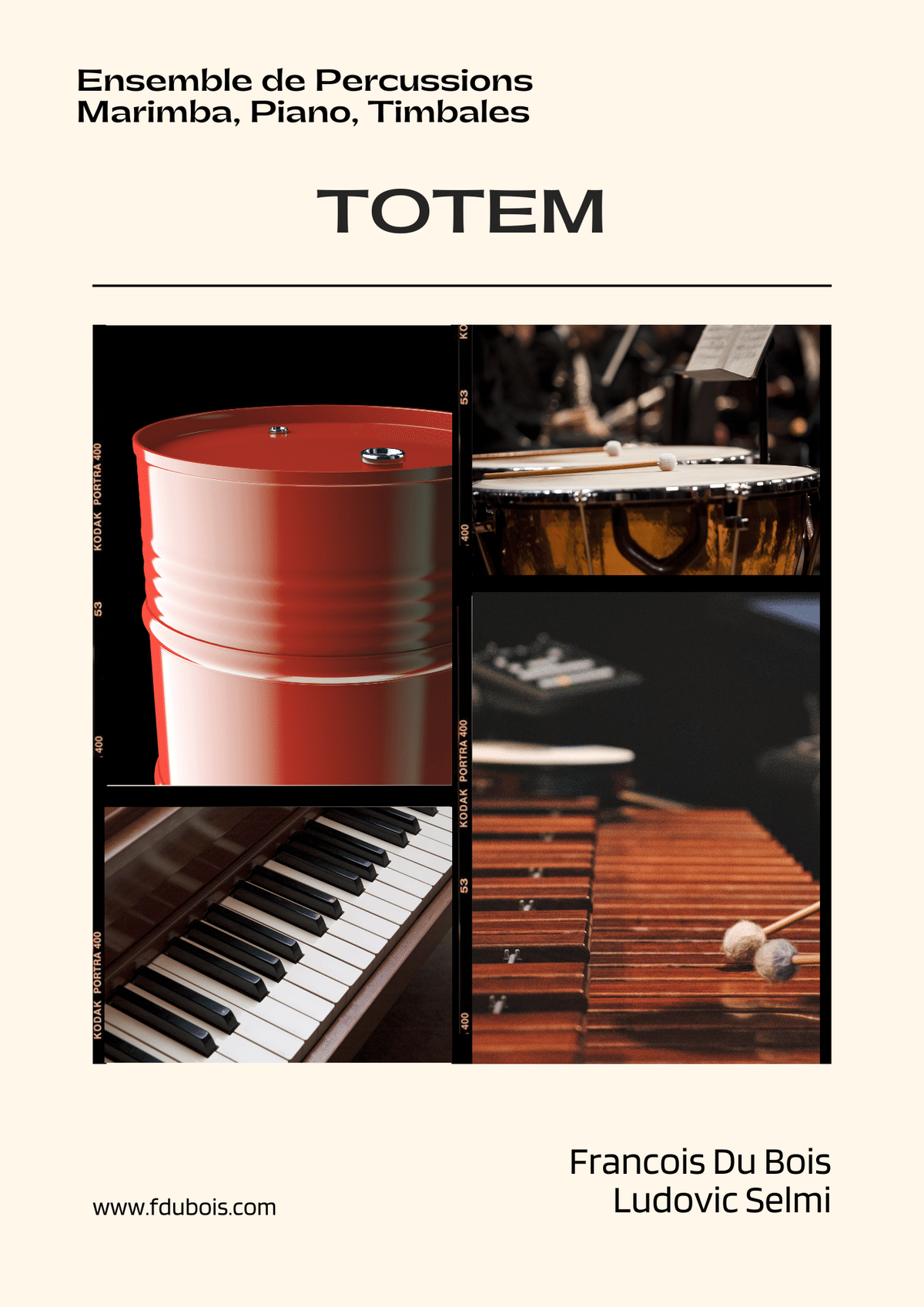
絵に書いたような不良集団で、とにかく言う事を聞いてくれない、規律がない、喧嘩をしょっちゅうふっかけてくる、時間を全然守らない、それにアルコール好きってグループだったよね。
FDB:そう(笑)何でそんなグループと共演することになったかと言うと、メンバーの中に僕の学校の幼馴染が何人かいたんだよね。何でそんな話の流れになっちゃったのか未だに不思議なんだけど、共演の可能性が非常に高かったもんだから、君と一緒にコラボの曲をとにかく書きはじめたんだよね。
LS:そうだ、君の知り合いだという話がそもそものきっかけで、そんないわくつきのグループとのコラボをラジオ・フランスでやれるというのが、俺としてはもの凄いモチベーションになったんだよ。アカデミズムの最高峰を象徴するラジオ・フランスだぜ!こんなハチャメチャなコラボの演奏場所として、これ以上の檜舞台はないだろう。
リハーサルも傑作だったよね。向こうはスコアを読めないから、耳だけを頼りに演奏するスタイルなんだけど、曲が難しすぎて弾けない!とか、リハーサルのやり方が気に入らないとか!で、みるみるモチベーションが急降下していったな(笑)はじめは25人だったのがどんどんいなくなって、とうとう最後は8人しか残ってないの!普段は歌わない彼らに、曲の途中で、「Totem!」って叫ばせたりとかね。
しかも、式典の司会進行役がフレデリック・ロデオン(※)で、俺たちが104スタジオでリハーサルをしてたら、もの凄い剣幕で説教されたあの言葉、覚えてるかい?
「君たちは、何を考えてるんだ?!この場所であんな奴らと共演するなんて、あとで無茶苦茶になっても知らないぞ!!!」ってね。
読者のために説明をすると、104スタジオというのは別名「オリビエ・メシアン・ホール」と呼ばれる場所で、メシアンにちなんで名づけられた、世界中の音楽家が特別扱いしている場所だよ。
(※フレデリック・ロデオンは、フランスのクラシック界の有名プレゼンター。ロストロポーヴィチの優秀な弟子の一人でもある。)
FDB:それにしても、君の話しぶりを聞いてると、楽しい思い出でいっぱいだな(笑)僕はこのプロジェクトで10キロ痩せたよ!しかも、いよいよ本番って時に、あいつらが行方不明になったじゃないか。ラジオ・フランスのビルはとにかく広いじゃない。高さ68メートル、外周700メートルのタワー型のビルの中に、1,000個のオフィス、63のレコーディング・スタジオがひしめく巨大迷路みたいな中を、友人やアシスタントたちと手分けして、本番までの時間がどんどん迫っている中で、必死に捜索したよね。いま思い出しても、変な汗が出てくるよ。

Par Architecture-Studio — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16373280
LS:でさ、とうとうカフェテリアの一つでのんびりビールを飲んでるのを見つけて、「もう本番だよ!」って伝えたら、あいつら完全にパニクってたよね。オープニング式典なのに、開始数分前にステージに彼らを押し出したよね!
FDB:しかも、たしか彼らがトラックで会場の建物に到着した時も、駐車場に入る時に事故ってたよね。それで守衛と喧嘩になりかけた。あの日は、ありとあらゆる災難が次々とやってきてた。
LS:でも、それらを乗り越えて最後はスタンディング・オベーションだったね。説教してたロデオンがコロッと態度を変えてさ。音声が拾われないようにマイクをしっかり手で覆い隠して「君たち、おめでとう!ほんっとに素晴らしかったよ。まさか成功するとは、思ってなかったからね!」と、思わず本音を漏らしたよね。
LS:この曲を作る時、南仏のグラースにある、有名な調香師の家を借りて篭りっきりで創作したけど、あの幾重にも重なる豊かな香りは作曲のインスピレーションになったよね。
FDB:あそこはディオールやケンゾーの香水を創る友人の家だったよ。
LS:こんな風に、創作時に起こるカオスの話をするって楽しいよね。一般のひとの耳にはほとんど届かないし、業界人は夢を壊さないために部外秘にするしね。
FDB:アーティスト連中は、政治的な人脈と繋がるほどこういうオフレコ話を怖がるよね。リークするとあとでどんなブーメランが戻ってくるかわからないのと、一番の恐怖は業界を干されたりすることだよね。実際、よくあるから。
最後に
FDB:じゃあ、今後の君のプロジェクトもぜひ教えて欲しいんだけど、今何か仕込んでいたりする?
LS:もちろん。フルートとピアノの三重奏を、今度の土曜にタラスコンで演奏予定だよ。
あと『3本のバラ』という詩人ライナー・マリア・リルケの言葉に、女性コーラス用の曲を書いているところだよ。スコアはEURO CHORALから出版もされるので、興味がある方はぜひ。
FDB:今日は、対談をしてくれてどうもありがとう。色々と忙しそうで何よりだ。これからのプロジェクトが成功するのを祈ってるよ!
今回の率直で忖度なしのやり取りにも、本当に感謝しているよ。読者のみなさんも、きっとアーティストのリアルな頭の中が、少し覗けたんじゃないかと思う。忖度しないってのは、何でも枠に収めたがる社会においても本当に大切な要素だと思うしね。
LS:こちらこそ、どういたしまして。大好きな、日いづる国日本のみなさんに、南仏から友情を送るよ。
FDB:ありがとう、また近々!
LD:ありがとう!

リュドヴィック・セルミ作曲のスコアたち:
Astéroïdes et Baobab(6曲)↓↓↓
※"Couleurs du Monde" (piano) は、子供のためのピアノ練習曲
翻訳:木村彩
