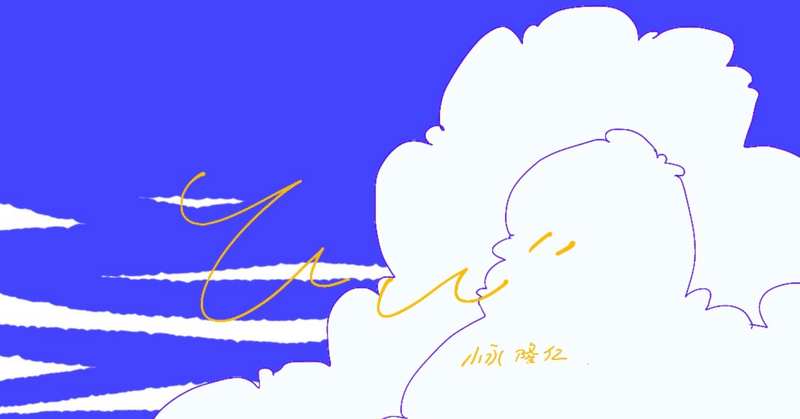
【日々】ハイウェイ・チャンス|二〇二三年八月
二〇二三年八月二十二日
最寄駅を出て、近くのスーパーで金麦を買ってすぐに歩きながら飲み干す。こんなことをしたのはたぶん生まれて初めてだと思う。別に何にもラクにはならないし、おもしろくもなかった。わたしはどこにいても、うまくやっていくことができないんだなとおもう。こんなに、人と関わること、一緒にいることが苦しい場所にいたことは、すくなくとも社会に出てからは一度もなかった。きょうなにがあったとかそういうことではなくて、実はもうずっと、無理になっていたんだと思う。気づいたのが今だった、というだけ。もう、どうすれば。たったの350ml缶ひとつで、なんだか足どりがおぼつかない。インナーにびしょりと滲む汗が気持ち悪い。つぎはどこへ行こう。行く場所は、あるんだろうか。
二〇二三年八月二十五日
うっかり寝坊した。静かにあわてながら無言で最低限の身支度だけ済ませ、家を出る。蒸し暑さできょうは一段と息苦しい。通勤ピーク終わりぎわの中央線で涼みながら数駅たどって、Oサンに会いにいく。「Oサン、ピンチです!」と開口一番。かれとこの二年ほど断続的に続けている会話は、キャリアカウンセリングという枠を使ったものでありつつ、実際にはこの世の中でどう生きようかということを本質的に考えてゆくような、井戸端作戦会議になりつつあった。けれど、きょうはいったん、場の本来の意味の方へ振り戻さざるを得なくて。だいぶ限界に近いし、それが自分の想像よりもはやく見えてきてしまって困っている。だから、半ば焦りつつ駆け込んだ。
そんなきもちをひとつひとつ、ことばにして話してゆくうちに、ちょっとずつ頭から毒が抜けて整理されてゆく。結局はすぐに、いつもの井戸端談義。国家に、資本主義に、のまれずに生きたいということ。巻かれながら巻き返すのだということ。男坂と女坂、どちらで進むかということ。確かめてゆく。確かめるたびに、数年前は何もなかったわたしにも、ちいさな思想が芽生えていることを感じる。
Oサンは自分を、「武器を渡すひと」でありたいという。Oサンらしいと思う。帰りぎわ、もうすぐにどうにかしなきゃって話なの? と聞かれて、まだそれは怖いっすと口から出たので、これが今の本心かな。確認。〝いま耐えどきよ〟ってむかしYUIがうたってた気がするけど、なんて曲だったっけ。

少し時間ができたので吉祥寺で降り、billboardでよさそうなポストカードを数枚見繕う。そのまま武蔵野文庫でモーニングして、アイスコーヒー片手にさっき買ったカードにメッセージをいれる。店員さんに水を注いでもらいながらも手を止めず、ひとつひとつ文字を書き入れているとき、あ、わたし今喫茶店で手紙を書く人になってる、と思う。そのまんまだけれど、なんだか、ただそれだけのことがちょっと嬉しかった。手紙を書くのなんていつ以来。ちゃんと届きますように。
二〇二三年八月二十六日
来客の予定があったのがなくなって、でもぽっかりあいた一日をうまく使おうって力が湧いてこない。ベッドから起きあがるだけで午前中いっぱいを費やす。ずっと身体も頭も重たいし、すべてに嫌悪感がある。前夜SNSでベラベラ喋ったこととか、おもいだしただけでいやな気分。じゃあ最初からキーボードを叩かなければいいのに。
夕方、からだの空気を入れ替えるために外に出る。すずしい、意外に、すごくすずしい。空には絵筆の洗い水に滲む絵の具みたいな雲がながれている。近所の稲荷さまに寄ってこのところの不挨拶を詫び、酒を買ってかえる。柏手がどうしても、きれいに鳴らないのがいつも気になっている。酒屋にはもう、ひやおろしが並んでいて、季節が着々とめぐろうとしていることがわかる。たくさん並ぶクラフトチューハイのなかからおもわず手にとったのが静岡のみかんをつかったものだったのは、夏の良い思い出に引っ張られたからなんだろう。

二〇二三年八月二十八日
起きてポケモンスリープをあけ、「有効な睡眠が検知されませんでした」のメッセージを確認したら、そのまま何も考えずにアプリをアンインストールする。とうとうこの一週間、一度も「有効な睡眠」は「検知」されなかった。画面の向こうとはいえ、いっしょに過ごしてきたちいさな仲間たちを丸めてゴミ箱に棄てるようでかなしい。こんなことですらみんなと同じにできないんだなと可笑しくなる。きょうもそのあと、ベッドからおりて一日を始めるのにずいぶん時間がかかった。
弁当を食べ終え、そそくさとオフィスを出る。セブンでアイスコーヒーと、価格もカロリーも無意味に高いスイーツを買って、東北本線をせわしなく往き来する列車をながめながら口に運ぶ。べつに、空腹なわけじゃない。財布とおなかがちょっと苦しくなっただけで終わる。こうやって気を紛らわしていかないと、思わずなにかを早まってしまいそうだからしようがない。しずかに自分を宥めながら、息を潜めて生きる。
二〇二三年八月三十一日
手紙は無事に届いたみたい。よかった。大袈裟になりすぎていないと良いけれど。わたしはいつも、心が動いたものに対してオーバーリアクションすぎて、相手を困らせてしまうみたいだから。
給料が入ったのを確かめ、収支が思ったより悪くなかったので、オフィスを抜けだしてひとり知らない喫茶店に落ち着く。今どき珍しいたばこのにおいをむしろ好ましく吸いこみながら、アイスコーヒーとミルクレープ。永井宏『サンライト』をすこし読み、続いて書きさしていた掌編をひとまず閉じるところまでこぎつけて店を出る。おなじように会社を抜け出して一服しているらしい東村愚太にプロットだけ送ったら、おおげさに褒めてくれる。嬉しい。
きのう、かれと下町を呑み歩いて知った素朴なしあわせの余韻がまだ残っている。さいごに燃やした花火で、わたしたちの青春はちゃんと葬れただろうか。燃やしきりたい気もするし、ちょっとくらい燃しのこしがあったらまた、来年も火をつけてみたい気もする。時代遅れの不良みたいな火遊びをして、それでもやっぱりわたしたちはワルにはなりきれていなくて、根っこが真面目なんだよなとおもう。でも、いつも身につけているものをいっときバサっと剥ぎ捨てられた気がして、それが気持ちよかったな。
燃え切らなかった八月が、終わってゆく。
*
*
*

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
