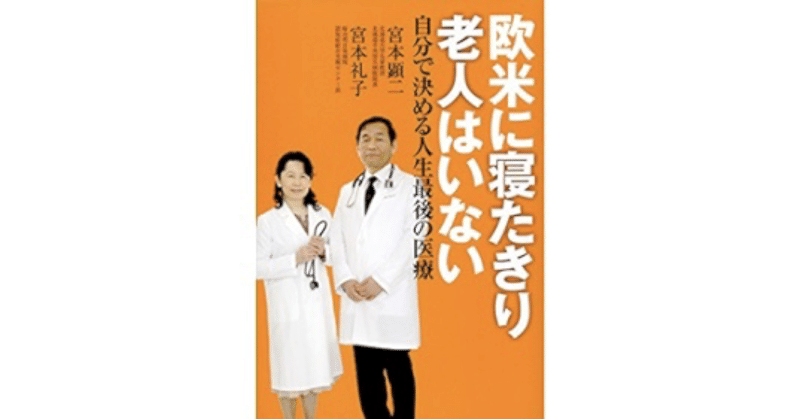
欧米に寝たきり老人はいない
スウェーデンでは高齢者が食べなくなっても、点滴や経管栄養は行わない。たべるだけ、飲めるだけだが、安らかに亡くなる。スウェーデンの医師の父は亡くなる前日まで話すことができて穏やかな最後を迎えられる。
スウェーデンの医師曰く、ベッドの上で点滴で生きている人生に何の意味があるの、と。
スウェーデンも昔は高齢者が食べなくなると点滴や経管栄養を行っていたが、20年かけてなくした。
患者さんが点滴を抜いてしまうなどしても、一部の治る病気を除き、医療は体を縛ってまで行うものではない。
今の日本では助かる見込みがなくても治療のため人工呼吸器がつけられることがあり、気管に入っている管を抜かないように両手が縛られ、声も出ない。つらいためまぶたをパチパチさせている。
ある看護師は、こんなことが許されるのか、医療が高齢者を食い物にしている、と。
ある人は、生命維持装置で生かすのが博愛主義や人道主義だとの勘違いは即改めて、個人の人間性を守るために、完治する見込みのない高齢者の死ぬ権利を認めるべき。
ほとんどの親は子供や孫に負担をかけずに静かに天寿を全うすることを望んでいるはず。
人口的に延命するのは許せないお節介。
無理な延命はメシのたね。
ある医師曰く、今日は当直。胃ろう、点滴、モニター、尿道カテーテル、抑制帯などに繋がれて、回復の見込みがなく一人ぼっちで横になっている老人の姿を見ていると切ない気持ちになる。当直室は広くて閑散としているので、余計空しくなる。
無重力状態で長期間生活をすると、手足の筋肉が細くなり、骨がもろくなる。
毎日運動する宇宙飛行士でも地上に降り立った時、両脇を支えられないと歩けない。
通常、一ヶ月寝たきりだと筋肉は細くなり、筋力も半分になる。
骨の量も半年間で3分の2になる。
ある看護師曰く、胃ろうや点滴などチューブが抜かれないように手足を拘束したり、車椅子から立ち上がって転ばないように車椅子に縛りつけたり…。高齢者は寝たきりになっているのではなく、寝たきりにさせられている。
法律では死後48時間以内に火葬することが法律で定められている。
大往生したければ救急車を呼ぶな。
自分の親の死に直面すると、本人の意思に関係なく家族は延命治療を強く希望する。
本人が延命措置はしないでと書き残しても。
この問題の1番の解決策は終末期を迎えた高齢者には濃厚医療を行わないことが社会の常識になること。
アメリカでは終末期には人工呼吸器を外すのが当たり前だが、日本では結果無罪になったとしても殺人罪で逮捕される恐れがあることから、患者とその家族の意思を尊重できない現実がある。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症した50歳男性が訴えた言葉、人生は大切に生きろ、感謝して生きろ、あなたたちは幸せだ。私は病気になるまで大切に生き、感謝して生きてきた。でも今は苦しい、地獄のような苦しみだ。今は死が幸せだ。だけど死ぬこともできない、それが地獄。今を大切に生きろ。
日本で自然な死が迎えられない理由の一つに診療報酬の問題がある。
経営を考えると中心静脈栄養や人工呼吸器装着を行うと診療報酬が高くなる。
急性期病院では在院日数が長くなると診療報酬が減るために胃ろうをつくって早期に退院させる。そのため不要な延命措置を医師は行ってしまう。
グループホームや自宅で延命措置を行わずに看取るためには、自然な看取りを理解して24時間体制で訪問診療してくれる医師が必要。
現状では延命措置を選んでも選ばなくても、家族に葛藤は生じる。家族の葛藤を少なくするためには、終末期の高齢者には経管栄養や中心静脈栄養の適応がないことを医学会がはっきりと伝えることが必要。
そしてやはり、自分の最期はどうしたいのかを判断能力があるうちに家族に伝えておく事が大事。
人間は死が近づいてきたら、だんだん食べなくなる。空腹や喉の渇きを訴えることもない。それが自然の姿。
人生の終末を迎えた高齢者に栄養管理は必要ない。数値で判断するよりも、おいしさを感じてもらうこと、無理やり食べさせないことの方が大切。
終末期とは医療によってももう助からない状態のこと。
医療は不確実なもの。治療の結果はやってみないとわからない。
日本は1人の患者を回復させるために99人の植物状態の患者をつくっている。
反対に欧米は99人の植物状態の患者をつくらないために、1人の患者を回復させていないのかも。
統計上95歳以上は8割、100歳を超えるとほぼ全員が認知症になる。
自宅で自然に看取った場合、かかりつけ医がいないと警察が検視に来る場合があるため、医者嫌いでも普段からかかりつけ医を決め、終末期はどうするか話し合っておくべき。
町医者がかかりつけでない方の死亡を確かめるために呼ばれたとき、診たことのない患者には死亡診断書は書けず、死体検案書になり、他殺の可能性があれば、一応警察に通報する義務がある。
認知症の場合、医者に診せずにいると高齢者虐待を疑われるので、かかりつけ医を持つしかない。
自然な看取りすら警察沙汰になる可能性がある。
高齢で終末期の患者に血液検査が必要か?
検査をしたら異常が見つかるのは当たり前。
異常を見つけたら、医師は何もしないというわけにはいかない。
認知症病棟で経管栄養や中心静脈栄養による延命を希望しないと、点滴を行っていたが、それにより2、3ヶ月延命できるが次第に意識がなくなり、極端に痩せ細っていく。
そのことを家族に話し、点滴にこだわらなくなると終末期の患者さんは食べるだけ、飲めるだけで看取るようになる。そのようにして亡くなった患者さんは死に向かって穏やかになっていった。点滴をして亡くなった人は苦しそうだったのに。
終末期、何もわからないまま人工栄養や人工呼吸器で生かされたくないと思っている人、納得いく死を迎えたいと思っている人は、事前に終末期の医療について自分の希望を書面に残すことを勧める。
欧米と違い法的根拠はないが、それなりの効果が期待される。
・リビングウィル(生前の意思・遺言)
・事前指示書(リビングウィルに医療代理人(代弁してくれる人)の氏名と署名が加わったもの)
上記のものは、医療の内容が曖昧だったり、自宅に保管しいざという時に見つからない場合がある。
これを解決するためにアメリカやオーストラリアでは医師、患者、関係者が生命維持治療について確認し署名する医師指示書がある病院も。これは拒否も可能。
日本でも2008年に後期高齢者に限り、事前指示書の制度が開始されたが、マスコミを中心に高齢者は早く死ねばよいのかなど世論の反発を受け、3ヶ月で凍結された。
日本でリビングウィルが生かされないと考えられる3つの理由
①リビングウィルに対する家族の見解が一致していない
②リビングウィルが法的に認められていないので、医師は訴訟を恐れ治療を中断できない
③急性期病院では診療報酬を上げるため濃厚治療が行われる
希望しない延命が行われる5つの理由
①延命至上主義。戦争で多くの命が失われた反動から命の質よりも長さを尊ぶようになった。
②最期の医療の希望を家族に伝えていない
③社会制度の問題。
病院が診療報酬を得るため、中心静脈栄養や人工呼吸器を装着する。その後、胃ろうをつくり早期に退院させる。
また、親の年金を頼りに生活していることも。
④医師が延命措置を怠ったと訴訟される危険を恐れているから。
⑤物言わぬ高齢者への倫理観の欠如。自分は受けたくないのはずなのに。
急性期病院から施設に引き取ってもらうために胃ろうが必要な理由は2つ。
一つは手間のかかる食事介助に人手がないこと
もう一つは経口摂取ができない方を施設で看取ることについて社会的合意がなされていないから。
年金をもらうために終末期の高齢者に何年間も延命措置をするようなことは、年金制度も医療制度も破綻につながる。
おっとに先立たれた妻には遺族年金として、それまでの老齢厚生年金の75%の支給が続く。
口から食べられなくなったら寿命、そう考えている人は、意思を家族に話すだけでなく、書面を残して下さい。
日本の医療は、高齢者に死期が迫っても最期まで濃厚な医療を行おうとする。
そのあいだに次から次へと合併症が起こり、その結果高齢者は苦しんで死ぬ。
終末期の高齢者に不必要な濃厚医療を行わなければ、我が国でも、自宅や施設で看取ることができるはず。
日本では自然分娩が普通で猛烈な痛みを伴うが、アメリカやイギリスでは無痛分娩が普通。
また、アメリカでは胃カメラや大腸カメラは薬で朦朧とした状態で行うのが主流。
日本では患者に痛みを我慢させる風潮がある。
一方アメリカやイギリスではまず患者の苦痛をとることを優先する。
この考えの違いが終末期医療にも表れている。
日本では終末期の高齢者を縛ってまで、点滴、経管栄養、人工呼吸器装着、けつえきとうせきが行われ、痰の吸引や気管切開ぶのチューブの交換時には、拷問かと思うほど苦しさを与える。
緩和医療どころか、医療という名の下に、虐待が行われている。
日本の保険診療ではがんとエイズのみを緩和医療の対象疾患としているが、世界保健機構は生命を脅かす全ての疾患を緩和医療の対象としている。
欧米では高齢者の終末期には緩和医療が行われている。
日本の保険診療も、生命を脅かす全ての疾患を緩和医療の対象とすべき。
胃ろうは不要な治療法でなく、適応をしっかりと見極めた上で行うべき治療法。
例)食道がんで食堂が詰まってしまう人、頭も体もしっかりした誤嚥性肺炎を繰り返してしまう高齢者など。
日本では人生が終わりに近づき、食べれなくなった高齢者にも、人工的水分・人工栄養が行われているが、これは世界的にも珍しいこと。
人工栄養には、経腸栄養、静脈栄養、皮下輸液法の3つがある。
点滴1本の栄養(通常使う5%グルコース500ml)はたったの100kcal。
気休めに過ぎず、体を縛ってまでする必要があるかどうか。
高齢になるほど肺炎による死亡が増加し、80才を越えると急増。
そのほとんどが口や胃の内容物が誤って肺に入る誤嚥によるもの。
死期が迫ってるから食べないのであり、食べないことが死の原因になるわけではない。
終末期の患者とその家族への対応
・経口、輸液、経管などで栄養を入れても、症状を軽減したり、延命することはできない。
・終末期の脱水に対して、口渇で苦しむことはなく、末期の脱水では症状が出る前に患者は意識を失うため苦痛はないと、家族等に伝えて安心させる
・経静脈栄養は肺水腫や末梢の浮腫を憎悪させ、死の経過を長引かせる。
・嚥下困難状態では、経口摂取を強いてはならない。
・無呼吸や呼吸困難に対して、意識のない患者は窒息や空気飢餓感で苦しむことはないと家族等に伝える
すべての治療は不利益と利益の両方を併せ持っており、通常の治療と特別な治療を区別して考えることは倫理的ではない。
個々の患者にとって、負担が利益を上回る時はどのような介入も行うべきではない。
自然な看取りは餓死とは違う。
空腹を感じるから苦しい。
終末期の患者は食欲がほとんどない。
胃腸も弱り食べ物も受け付けない。仮に何か食べたとしても、ほんの少し食べ物を口にするだけで満足する。
口渇を訴えても、少量の水や氷で喉の渇きは癒せる。
自然な看取りをする病院や施設では、「皆さん眠るようにして亡くなられます」と言う。
安らかに亡くなることを裏付ける研究がある、動物を脱水や飢餓状態にすると脳内麻薬であるβエンドルフィンやケトン体(鎮痛・鎮静作用)が増える。
自然な看取りではこれと同じなはず。
老衰や認知症の終末期になると食べたくないと言ったり、食べさせようとしても口を開けなくなる。
そのような時は、鼻腔から経管、胃ろうから経管、中心静脈・末梢静脈(いわゆる点滴)栄養もせず、食べるだけ、飲めるだけが一番良い。
微量の点滴でも死期を不自然に伸ばし痩せ細り、こちらの都合で死期を延ばしていることになる。
点滴や経管栄養をしなくても苦しむことはない。むしろ最後まで話すことができて、安らかに亡くなる。これが本来あるべき姿。
日本の医学教育は延命させることが命題で、患者のことは考えていない、残念ながら、医療の発達が安らかな死を妨げている。
ヨーロッパの福祉大国、デンマークやスウェーデンには、いわゆる寝たきり老人はいない。アメリカ、イギリス、オーストラリアでも。
スウェーデンで寝たきり老人がいない理由は、終末期の人は食べれなくなるのは当たり前で、経管栄養や点滴などの人工栄養で延命を図ることは非倫理的であると考えられているから。
これは国民みんなが認識しており、そんなことをすれば老人虐待という考え方さえある。肺炎を起こしても、抗生剤の注射はせず、内服投与のみ。
多くの患者は寝たきりになる前に亡くなっていた。
イギリスのある一例
94歳で亡くなるまで一人暮らし。
老いたと言う理由だけで子に従い世話になるという発想がない。
ヘルパーやドクターの訪問が充実。
老いても1人でいられるというのが、彼らの誇り。
肺炎をこじらせ入院後は、十分に生きたからと食物の摂食をやめ、10日ほどで亡くなった。
子に頼らない老後の覚悟を持てる社会づくり、という選択肢もあるか。
スウェーデンのある一例
宗教観が違い、死に対する考えが違う。
キリスト教では脳死が人間の死であり、意識がないことはたとえ息をしていても死である。胃ろう、中心静脈栄養などの行為は悪であるとの認識。
また、最終決定権が医師にあるので、延命を望んでも断ることができる。
若年性認知症は死に至る病気であるが、スウェーデンの施設では、よくパーティを開き、アルコール依存症でなければ、お酒は毎日飲んでも良いとのこと。
生きている間は人生を楽しみ、死ぬ時は潔く死ぬという生き方。
民間のナーシングホーム(介護度合いの高い人)でも、昼食はレストランのようで、ワインは飲み放題、アルコールは食事につきもの。
人生は楽しむためにある。
日本では認知症の人など、高齢者の行動は制限されることが多い。
スウェーデンでは散歩にどうしても行きたい認知症の人をGPSの携帯電話を持たせて、1日2時間だけ許可するということも。
日本では勝手に外出した91歳の女性が踏切事故を起こし、JRが家族に損害賠償を求める訴訟を起こし、賠償金を支払ったことも。
このような認知症患者の起こした事故は家族に損害賠償を求めるのではなく、社会的賠償制度で被害者を救済すべき。
それに比べスウェーデンでは自由と引き換えに、それに伴う危険を国民が受け入れているようにも思える。
過小でも、過剰でもない医療が理想だが、スウェーデンは過小かも。
日本のように縛ってまで過剰な医療は行わない。
スウェーデンは延命措置を行わないので、日本より平均寿命がさぞ短いかと思ったが、2012年日本83.1歳、スウェーデン81.7歳。我が国の濃厚な終末期医療も寿命を1.5歳伸ばすに過ぎない。
スウェーデンは高福祉と考えるが、高齢者の場合は高福祉ではない。
高齢者ケア関連予算は高齢者が増加する中で削減されている。
その理由は、高齢者の生活環境や健康は、国の優先課題ではないから。
実際に80歳以上の高齢者の施設入所率は下がってきている。
高齢者ケアの流れは介護施設から自宅介護へと変わってきている。しかし、施設介護が必要であったり、それを望む高齢者がいるのも事実。
オーストラリアの高齢者介護施設における緩和ケアガイドライン
・食欲がない入所者に無理に食事をさせてはいけない。
・栄養状態改善のための介入は倫理的な問題がある。
・脱水のままでも、経管栄養や輸液は有害である。
・口渇は少量の水や氷で改善するが、輸液では改善しない。
・最も大切なことは入所者の満足感であり、輸液の有無ではない。
多くの国では、間も無く死を迎えると予想される患者が夜中に亡くなった場合は、翌朝になってから、医師が死亡の確認にくる。
死は自然なことと考えるからか。
オランダは最初に安楽死を合法化させた国
オランダ人の病院死は20%弱、ほとんどが自宅か介護施設。
オランダでは終末期の希望はほぼ、何もしない。それが倫理であるからとのこと。
アメリカ、カリフォルニアではほぼ無料で病気は何であれ、医師から6カ月の余命宣告をされた人はホスピスサービスを受けられる。
ここでは治癒や延命の医療は行わない。
特筆すべきは患者の死亡確認は医師以外に、看護師も行えること。
これが特に問題にならないのは、生まれることと死ぬことは自然なことと考えられているからか。
アメリカのある施設では、食べられなくなった入所者にスプーンを持たせるだけで、口の中に食べ物は入れない。
介助が当たり前と思っていたが、自分で食べられなくなった時は人生の終わりと考えているからか。
手袋がボロボロになったら、手を守れないように、体がボロボロになったら魂を守ることはできない。
人間楽しいとか嬉しいがわからなくなったら、生きていても仕方ない。
アメリカで自宅で死ぬためには、子供の数が多く、家族から介護を受けられるか、お金があって介護者を雇えるかのどちらか。
アメリカでは個人主義的で、親の面倒を見ない子供たちは多いが、全般的に身障者や老人などの弱者を労る若者は多い。
高齢者コミュニティが日本でも2010年に千葉に初めてできた。著者も住みたいとのこと。
日本ではがん以外で死ぬ人の方が圧倒的に多いのに、がん以外で死ぬことに納得できない人が多すぎるので、寝たきり老人が多いか。
また、一旦開始した人工栄養なとを中止すると警察が介入し、訴えられる可能性がえるから。

★
日本は国民皆保険であり、医療費を支出するのは公的機関であるが、医療費を請求するのはほとんど民間。
支出する側が医療費抑制のため、2年ごとに診療報酬を下げてくるので、病院側は経営のため濃厚医療を行わざるを得ない。
対して、欧米豪では、人口栄養で延命されたくない国民の要望と、医療費を抑制したい政府の方針が一致しているので現在の状況が生まれたか。
2030年には年間の死亡者数が今(2013年)より約40万人増加するが、病院のベッド数不足を解消するため、人口栄養を行わないとすると、寝たきりで2年間生かされている老人が、自然死で2ヶ月で亡くなる。
そうするとベッドの回転率が上がり、療養病床は現行のままで確保が可能。
★★
高齢者に死について話しても多くの高齢者は怖がることはない。
むしろ、自然死の希望がいえて、心配がなくなったという人も。
高齢者は私たちが考えている以上に死を自然なこととして受け止めているのかも。
しかし、それは死に方についてで、死についてではないかも。
一見達観して見える高齢者も、それは真の心ではない。
終末期の人には3回の食事では多く、2回とおやつにするとお腹が空くため、起きている時間が増えて、残さず食べるようになる。
★★
あなたがして欲しくないことは私にしないで。
これは高齢者の週末医療を行う上で、今まさに必要とされている言葉。
ある人は、子供たちに、将来私たちがしてほしいように介護するから、よく見ていてねと、余命宣告された母親を、訪問看護の力を借りて自宅で過ごさせた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
