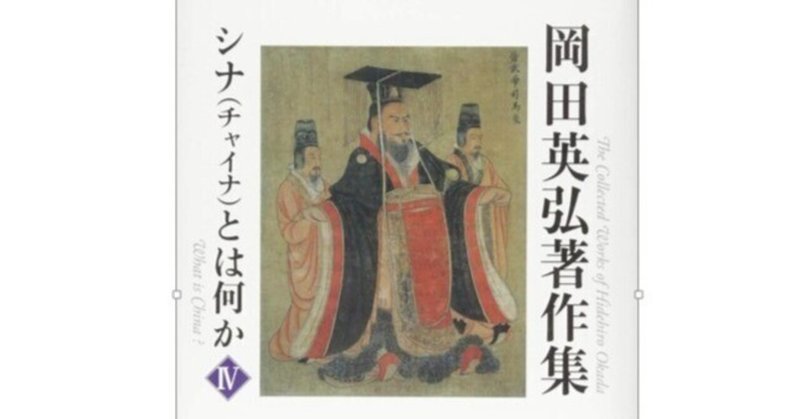
(1)中国:民族の成立とシナの歴史
中国人の企業経営
20年程前の10年間ほど年に数回は中国をはじめ東南アジアの各国に出かけて工場を訪ねていた。中国の経営者たちには毎回驚かされたものだった。国内、海外を含めて数百社を訪問し、企業を見、経営者から話を聞いていた私にとって、まだ企業経営を始めて10年に満たないそうした中国人経営者の話は新鮮だった。
建設業からアパレル縫製業、自動車、半導体・・・までこれを一人の企業家が経営しているのが中国の企業の特徴だった。財閥ではない、儲かると聞けば専門性や業種に関係なく、どんどん手を伸ばす。どれも一社一工場、これっきりの中小企業なのである。しかも、誰もが天下を取ったような勢いだった。
1978年の鄧小平による改革開放、92年の南巡講話いらい資本の開放がすすんで私企業が奨励されるようになった。それによって、それまで押さえつけられていた中国人の金儲け願望が解き放たれたのだろう、経営意欲はとんでもなく旺盛で、われ先にと金の儲かる方へと手を出し始めた。
建設業が儲かると言えば手を出し、次は服が儲かると言えば縫製業に手を出し、自動車がいいと聞けば自動車に手を出し、儲けた金を次に儲かる業種に投資する。躊躇も遠慮もない、鬼を退治するかのような勢いでわれ先に進出する。
縫製業が栄えれば、当然ミシン製造も盛況になる。高品質として売れる日本製ミシン,JUKI、ブラザーなどのブランドがもてはやされれば、すぐさまJAKI、JIKIなどのブランドの中国産品が見本市にあふれる。何の遠慮もない。儲かる商品をマネするのは当たり前、チャンスを目の前にやらない方がマヌケとでもいうような感覚である。日本メーカーの担当者と見て回りアキレタものだった。
そして、日本人経営者なら遠慮がちに話す成功譚を、天下を取ったかのように自慢げに話す。個人の能力も優れてはいるのだろうが、景気上昇の波に乗った好調さによるビギナーズラックの要素も大きそうに見えた。が、その言動は、ウルトラマンになりきった幼児の持つ万能観のように見えたものだった。
とても日本人では発想しないようなこの勢いと自信はどこから来るのだろうかと思いながらもやもや感じながら話を聞き、工場を見せてもらったのを覚えている。
そのモヤモヤをなんとなく、解明してくれたのがnoteでフォローしている虹雲猫さんのページで紹介されていた『岡田英弘著作集Ⅳ シナ(チャイナ)とはなにか』だった。
以下、「シナ文化の特異性」として紹介されている中から、一人合点して腑に落ちたところをいくつか紹介したい。
●承前啓後のエクスキューズ・・・(と言いながら、けっこう勝手に解釈していますのでご容赦。詳細は本書をご参照ください)
岡田英弘(東京外語大名誉教授)さんが中国を総称して「シナ」と呼んでいるのは、簡単に言えば、中国という国名は、1949年の毛沢東・共産党が政権を取ってからの名称であり、それ以前は国名として呼ばれているようなものは特になく、殷、周、秦、漢、隋、唐、宋、元、明、清・・・とその時代の皇帝や王朝名で称されていたということによる。
江戸時代はじめ新井白石(1657-1725)が、始皇帝の「秦」の古音のイタリア語の「チーナ」を「支那」と音訳したものを使いはじめたが、日清戦争のあとに来日した清国人が「支那」という言葉を初めて知り、便利であったので使い始めた・・・という経緯があり、岡田は、1949年の中国建国以前の国名として「シナ」を採用している。
いま、チベットや、新疆ウィグル、内モンゴルの一部まで含めて「中国」と称しているようだが、かつては万里の長城でもわかるように、北京のすぐ北の方は別の国とみられており、そうした地区を含めて中国と称してしまうことには問題がある、という判断もあるようだ。
(1)中国:民族の成立とシナの歴史
東アジアの大陸部に、シナと呼んでもいいような政治的統一体が初めて完成したのは、言うまでも なく、前221年の秦の始皇帝による統一からである。ここに始まったシナの歴史は、それぞれの時代においてシナの観念が適用されうる地域の広がりと、漢人に含まれる人々の範囲を基準として区分すると、4つの時期に分けられる。
・第1期:(前221-589)秦の始皇帝の天下統一から589年の隋の文帝による再統一まで800年
・第2期:(589-1276)元の世祖フビライ・ハーンによる南北統一まで700年
・第3期:(1276~1895年)モンゴル化したシナ(元朝)から日清戦争の敗戦まで600年
(前期)(1276-1368)モンゴル帝国の植民地化
(中期)(1368-1644)モンゴル帝国の支配
(後期)(1644-1912)清帝国
・第4期:(1912-1949-日本化の時代-中華民国以降
これによれば、前221年より前の時代は、シナ以前の時代ということになる。
これらの時代が、のちの漢人の祖となったいろいろな種族が接触して商業都市文明をつくり出した時代であった。また1895年よりのちの時代は、シナ以後の時代と言え、 漢人にとっての歴史がシナの範囲を超え、外のできごとや影響によって左右されるようになった時期である。
そして岡田氏は、この第4期を「日本化の時代」として、現在の中国を形成するうえで日本が大きな役割を果たしたが、中国人、日本人とも、そのことをほとんど忘れていると主張している。そのことは、おいおい・・・
《シナ(チャイナ)文化の特異性》(岡田英弘著作集Ⅳより)
(1)中国:民族の成立とシナの歴史
(2)第4のシナ:日本化の時代-中華民国以降—日本の影響
(3)中国民主化の始まり――孫文・辛亥革命
(4)中国人は人を信用しない。
(5)中国には外交政策・世界政策がない
(6)漢人にとって「公」とは、私腹を肥やす手段
(7)現代中国語に革命をもたらした日本語
(8)日清戦争――日・シナ関係の歴史的大逆転
(9)シナ/中国における支配者のカリスマ性と正義
●おまけ「中国にもない漢字・漢文の大系が日本で出版されているわけ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
