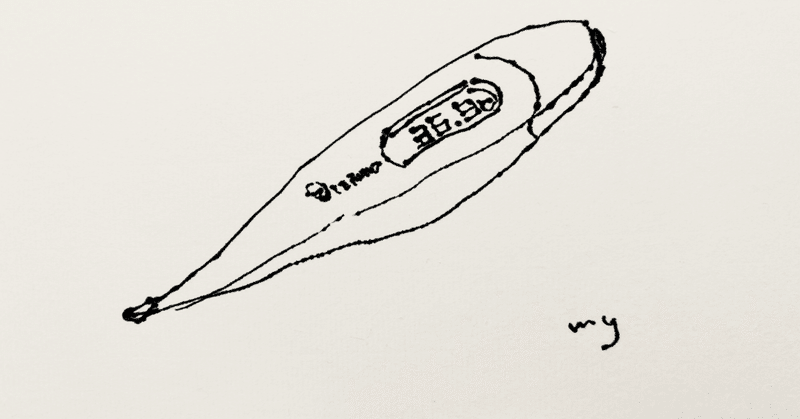
体温計が見つからない。
知恵熱だと思った。薬ならぬ、文学の過剰摂取といえば聞こえはだいぶ良いだろうか。その日、大型書店で目的の本を買った私は帰宅後シャワー浴び、有名作家の本を読んでいた。
髪を乾かしたほぼ直後に眠剤も摂取していた。あとは身体の熱が下がれば、自然な眠気がくるという算段だった。すぐ誤算となった。身体が熱い、だるい、頭が痛い。今日は酒も飲んでいないのだから、この頭痛は私の中で不可思議であった。
体温計を探した。私の身に起こっている不自然を説明してくれる何かが欲しかった。体温計はすぐ見つからなかった。なぜ必要なものは必要な時にスッと見つからないものか。イライラのイが頭に浮かんだ。頭痛を悪化させた気がした。体温計を探る腕に力は入らない。あったはず、ここに…。
驚くほどシンプルに体温計は白い本棚の上にあった。色が同化していて気づかなかった。体温計をカバーからひったくり、脇にさす。安堵。頭に上っていた血がひいていくのを感じる。ぴぴぴっと音が鳴った。37.3度。まあ、微熱。
身体の不具合に一つ、説明はついた。あとはこれをどうするか。解熱剤か、たったこんな微熱ぽっちで?保冷剤か、少し大袈裟すぎやしないか?と考えるうちに、今着ていたスウェットが裏起毛だったことに気づき、脱ぎ捨てた。幾分かはマシになった。
脱いだ服を傍目に、哀れな体温計、と思った。私は不健康を察知した時にこそ体温計を求めるが、それ以外は不必要、の言葉で片付けられるほど、体温計を軽視していた。…と気づいた。
体温計も人の意志に阿ることなく、その役目を果たす。ただ感知した温度を数字で示す。その数字は私の予想や願望を裏切ることもある。私の求めた不調の説明たり得ないことも往々にしてある。でもこれは体温計の仕事だから、人の意志や願望云々で数字が左右したら、それこそ体温計の存在価値そのものが危うい。
人肌に密着しないとその役目を果たせないのに、その役目を果たすためには人に忖度しない。なんだかそう考えると体温計って、いや体温計に対してそんなことを考えている自分が可哀想になってくる。
愛着を感じてるわけじゃないけど、何だかこの小さな白い物体に弄ばれている気さえした。多分、本格的に調子が悪い。体温を測ってくれるだけの存在だ、何を恨めしそうにする。意味がない。
体温計が、ではなく、私の体の温度が早く下がってくれさえすれば、コイツに責任をなすりつけることも、恨みを覚えることもない。風、外の風にあたりたい、少し涼しさを、心地よさを感じたい。
まだ日は昇ってないけど、外に出ようか。火照りを鎮めるために。体温計に怒る前に。投げつけたり折ったりする前に。きっと今の私は君と距離を取る、文字通り、クールダウンの時間が必要だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
