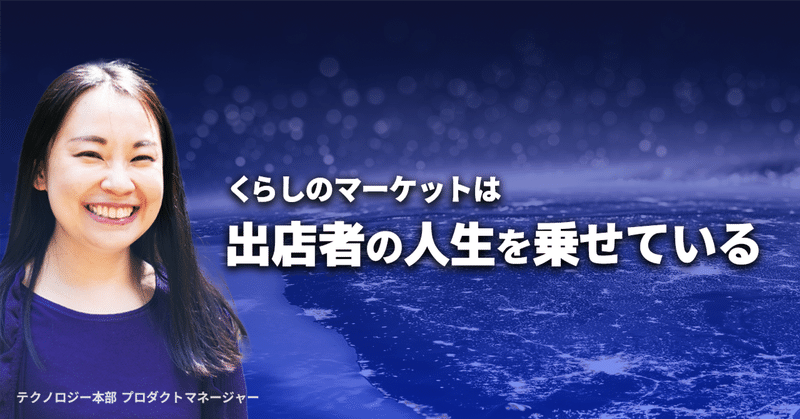
学長がPMの田崎さんにいろいろと聞いてみた。
こんにちは学長です。社長の浜野に代わってみんマで働く人に話を聞いていきます。今回はテクノロジー本部でPMとして活躍する田崎さんに話を聞きました。田崎さんは映画シン・ゴジラに出てくる官僚のようなキャラなので文字数多めになりました。なぜ田崎さんは官僚をせずにくらマでPMとして働き続けるのでしょうか。当社でPMを志望する方はぜひ読んでください。
大変か、大変じゃなかったかで言うと大変でした(笑)
―田崎さんはみんマに入社する前は何をしてたのですか?
みんマの前は、何万人といる大企業で総合職として働いていました。いろんな業務を経験させてもらったんですけど、メインでやっていたのは店舗の開発の仕事ですねー。その中で店舗の生産性を図るっていうことも…ちょっと、なんだろうなー。店舗の生産性を図る指標を考えるみたいな!例えばなんですけど、売り上げがあんまり良くなくても、来てもらうことに価値があるみたいなことってあったりするんですよ。つまり、売り上げだけでは店舗の生産性って測れないみたいなのがあって。じゃあ、どうやってその生産性を測ろうかということで、来店数ってどうやって考えるかとか。店先にセンサーがあるわけじゃなかったりするので。そういうものを計算したり考えたりしていました。
―あーなるほど!くらしのマーケットも、データで測っているものもあれば測っていないものもあったりしますよね。データが無い中で色々なことを決めていかなきゃいけないわけですが、前職からそれをやっていたということなんですね。
そうですね!本当は測りようがないけど、推測するみたいな感じですね。くらしのマーケットでも「店舗の良さって何だ?」って言った時、単に売上や口コミ評価の高さだけではなく、色々な面があるじゃないですか。その色々な面を評価するためには、今ある数字をどう使えばいいのかとか、その塩梅だとか。そういうのを微調整しながら考えるみたいなことをしていました。
―当社に入社してから今まではどんなお仕事をしてきたのですか?
最初はコンサルティング本部で、出店者に電話をして売上を上げるための提案をするコンサルタントの仕事をしていました。その当時のみんマはまだ規模がめっちゃ小さくて、コンサルの社員は片手で収まるぐらいだったので、各店舗の売上や予約数みたいなデータさえまとまってなかったんですよね。
―え!そうなんですね!
そうなんですよ。なので、私その辺は割と得意ですし、前職でもやっていたので、最初はそこでバリューを出せたらいいなぁと思ってやってました。取れるデータは取って、スプレッドシートにまとめて、関数を作るみたいな。そういうことをしてたら、3ヶ月後ぐらいにコンサルティング本部の部長を任せていただくことになりました。そこからは「コンサルの仕事ってどういうものだろう」ということを考えることから始まり、組織の方向や目標を決めたり、メンバーのマネジメントもしてましたね。
―大企業から数人しかいないようなベンチャー企業への転職は、相当大変だったんじゃないですか?
それがそんなに大変じゃなくて。意思決定のスピードが全然早いってことも覚悟した上でスタートアップに移ったので、特に違和感はなかったですね。入社する前に「何もまとまってないですよ、この会社」ってすごく念押しされて「まぁそうだろうな」と思ってたので、入社後は「思ってたより色々あるじゃん!ちゃんとまとまってるな!」ぐらいの感覚でした。出店者に提案するっていうコンサルの仕事内容も、大枠は前職と変わらないので、そこまで大変でもなかったです。前職では「これをこういう風にすると○○が良くなって、コストはこのくらいです」みたいな提案内容を稟議書にまとめて関連する部署や組織にプレゼンして合意を取っていくみたいな仕事をしていたんですけど、それとコンサルって割と似てるんですよ。ただ、マネジメントについては本当に初めての経験だったので、そこはすごく悩みながらやってましたね。
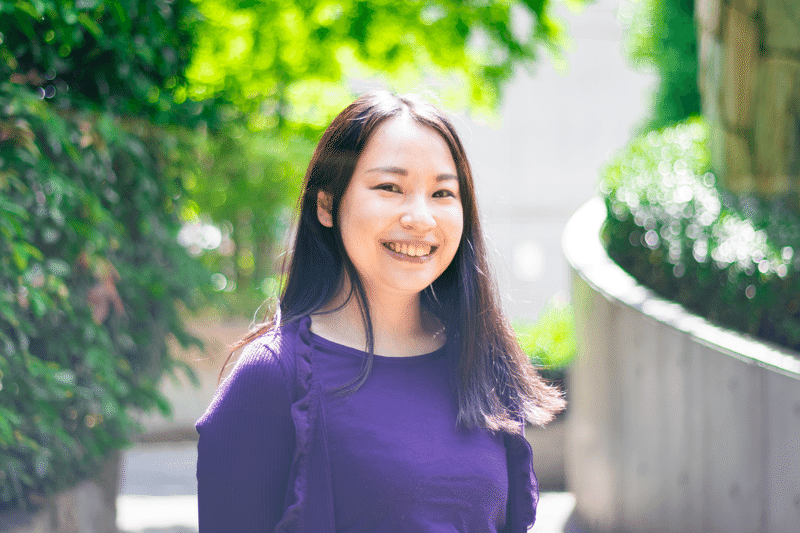
―僕は当時傍から田崎さんを見ていて「入社したばかりでいきなり出世しててすごいなー」と思ってましたけど、大変だったんですね。
そうなんですよ。コンサルティング本部のメンバーが最大で30人くらいいた時があって、もう訳が分かんなかったです。その時は。本当に手探りでやっていて、今でも「あんまりよくできなかったな」って思うこともあります。まあでも、20代でそんな仕事を任せてもらえることは基本的にないので。大変か、大変じゃなかったかで言うと大変でしたけど、いい経験でした。本当に。
―組織づくりって一番興味あるのでもっとお聞きしたいんですけど、多分日が暮れちゃうのでこれくらいにします(笑)。育休が明けた後はどんな仕事をしていたのですか?
1回目の育休から戻ってくるタイミングでテックに異動し、PMの仕事をすることになりました。その後、2回目の育休から復帰した現在も、変わらずPMを続けています。
出店者にヒアリングできるPMであることが私の強み
―PMの業務はもともと未経験だったんですよね?大変でしたか?
はい。PMも普通に大変でした(笑)。育休が明けるほんと数日前に「テクノロジー本部に異動です」って言われて「おー!テックか」と。それまでテクノロジー本部の仕事はしたことがなかったので、まぁ何したらいいのか全然分かんないですよね。そこでアサインされたのが、新しいプロジェクト。「会社としてはこういうことをやりたいから、エンジニアがそれを開発できるような状態に持っていってください」ってざっくり言われて。「おーーー」みたいな。
―うちらしくて良いですね(笑)。当時はPMがめぐみちゃん一人で大変だったので、田崎さんなら大丈夫と考えたのでしょう。PMとしての業務はどのように習得していったのですか?
とりあえず最初はCTOに「何かおすすめの本ありますか?」って聞いて何冊か本を紹介してもらって読んだり、SchooとかUdemyで要件定義やPM的な仕事の講座を見て、なんとなくPMはこういうことができればいいんだなというのを自分の中で具体化していきました。それと並行して新しいプロジェクトを進めなくちゃいけなかったので、それはそれでやっぱり大変ではありました。「くらしのマーケット」というものがあって、その上に乗っけていくという意味では完全にゼロからのスタートではないんですけど、プロダクトとしても前例がない種類の開発だったので、どう進めたらいいのかは結構迷いました。CTOとその時にいたメンバーと話し合いながら作っていった感じですね。
ー新しいプロジェクトの開発はどうやって進めていったのですか?
会社として緊急の駆けつけ系のジャンルに参入したいっていう話だけあって、どこをやるかとかは何も決まっていない状態でした。なので、市場調査から私がやりました。
―市場調査はどんなところを見ていくのですか?
カテゴリとして有望かどうか。そもそもくらしのマーケットというプロダクトに合うか合わないかみたいなところもあるんですよ。
―お〜。...というと、どういうことですか?
くらしのマーケットは料金が事前に分かるサービスのECサイトなので、作業料金の決まり方が事前にある程度予測できるかどうかとか、そういうところですね。市場の規模はもちろんあるんですけど、規模が大きいだけではなくて、うちが参入してうまくいきそうか。あと、対応できる事業者の数が極端に少ないジャンルは出店者の獲得が難しいとか。そういうのも含めて総合的に考えて、有望なカテゴリをまず決めました。最初に開発に着手したのは「水道のつまり修理」のカテゴリなんですけど、じゃあ、まず「水道のつまり修理ってどうやって料金が決まるんだろう」ってことを調べなきゃいけなくて。そういう部分って、結局現場で料金が決まったりするのでウェブで調べても分からないんですよ。なのでどうやって調べるかと言うと、実際にやってる事業者の方に電話したり、直接会ったりしながら聞いていく。工賃を左右する要素は何かとかをヒアリングして明らかにしていって、それをプロダクトに落とし込んでいくというようなことしていましたね。
―数字で色々読み取って想像していくだけじゃなくて、数字の見えない部分を出店者に聞いて、総合的に判断していくということですよね。田崎さんの強みが生かされてそうですよね。
あー、そうですね。出店者にヒアリングできるPMであるのが、この会社における私の強みだと思うので。それが割と活かせたかなっていうのはありますね。

何が本当の困りごとか見極めるのが一番大事
―改めてになりますが、PMとして具体的にどんな業務をしているのか教えてください。
PMとして、当社で開発するもの全ての企画を担当しています。当社のPMは、何を、どうして作るかというところから、どういうものを作るかという要件定義の部分まで全て担当します。ユーザー側に見えているくらしのマーケットの部分もそうですし、店舗が使う店舗管理システムもそうですし、社内で使っているシステムの開発も全部やります。今ある機能の改善もあれば新機能の開発もあるし、最近では社内向けの管理機能のリプレイスも担当しています。ベトナムで開発しているものもあり、そこの開発については基本的にブリッジSEの人とやり取りしながら進めています。
―かなりマルチというか、いろんなことをやってるなという印象なんですけど、当社のPMの場合、コーディングとかプログラミングのスキルって必要ですか?
それでいうと全然いらないです。まぁ私できないですし。ただ、出来たらその人の強みにはなると思います。要件定義する時って、裏側のデータの持ち方をある程度想像できないといけないことがあるんですよね。こういうものを出力したい、こういうものを表示したいみたいなことを想像できた方が要件定義がしやすいので、それで言うと多少プログラミングとか、データベースの考え方が分かる方がいいっちゃいいよねって感じです。ただ全然必須じゃないですね。
―なるほど。当社のPMに求められることってどんなことですか?言い方を変えると、当社のPMの難しいところってどんなところですか?
当社のPMは見る範囲が本当に広いので、一番大事なのが課題の定義です。何をやるのかというところがやっぱり大事。っていうか、そこがずれちゃうとやる意味がなくなってしまうので。こういう問題が起きてますという時に、この問題を本当に解決するべきなのかも含めて、どこが課題なのか、何が本当の困りごとなのかをちゃんと見極めることが難しいなと思います。課題の根底にあるのが業界の商習慣や前例だった場合、プロダクトに落とし込むにあたってそれに逆らう必要もあるんですけど、その辺ってちょっと抵抗があったり、先入観があってできなかったり、考え切れない時がある。そこをちゃんと考えるのが難しい。難しいけれど、やっぱりPMが一番価値を発揮するべきところだなとは思います。
―他にはありますか?
当社のPMは要件定義までするので、その時にUXをちゃんと考えられるかも大事です。うちにとって不都合な状態が起きないように、例えば注意のモーダルを出すとか、安易にそういうことをやったりすることがあるんですけど、それって本当にいいのか?という話があって。結局それはユーザーに手間を取らせたりストレスを与えるということなので「それって継続的に使ってもらうために本当に良いんですか」っていう。あえてやることもあるんですけど、なるべくユーザーにストレスなく使ってもらうことをまず考えなくちゃいけない。あと、つい色々な機能を足していきたくなっちゃうんですけど、機能が多ければ多いほど良いかと言うとそうでもない。減らすとかシンプルにするみたいな観点も必要なのが難しいかなと思います。
―当社のテックチームの人と話すと「無闇に機能を追加しない」みたいなことをよく聞くんですけど、それは会社の方針なんですか?
んー、どうでしょうね。まぁただ、うちのプロダクトってすでにすごく大きいんですよ。多分全ての機能を分かっている人が社内にいないくらい大きくって。私たちが分からないレベルのことを、ユーザーや出店者が使えるかというとそれは難しいと思います。なので、安易にどんどん機能を追加するのではなく、本当に必要なのか、今の機能の中でできないのかはちゃんと考えた方がいいのかなと思います。歯止めというか、そういう観点は絶対持っていた方がいいんじゃないかっていうのをみんな思っているのだと思います。

自分が知らないなら、その人に触れていくしかない
―これまでにもいっぱいPMがいましたけど、辞めていく人も多かった。そんな中で田崎さんは今も活躍しているわけですが、当社のPMとして活躍できない人ってどんなタイプの人だと思いますか?
人に話を聞きに行くのが嫌な人は難しいと思います。うちの開発って「こんな感じの問題を解決したい」みたいなふわっとした状態で始まるので、その中で何をしたらいいかを考える時に解像度を上げていかないと無理なんですよ。例えば、コンサルが使う社内のシステムのことだったら、絶対コンサルにどういうところで困ってるのかとか、どういう使い方をしてるのかを聞いた方がいいですし。要件定義する時に「こういうことって出来るのかな」という疑問が出た時にはエンジニアに聞いた方がいいので。場合によっては、さっき話したビジネスの裏側みたいなところは出店者に聞かないと分からないので、出店者に聞いたりもします。そうやって人に聞きに行って、自分の中で課題の解像度を上げていかなきゃいけないんですけど、聞きに行けばいいのに"なんか行けない人"っているんですよね。自分の頭だけで考えたり、ウェブに落ちている情報だけで考えようとすると先に進めなくなっちゃうので、うまくいかないと思います。実際うちのPMって、開発した後も、運用面や集客、売上まで責任もって見ることが多いです。そういう時は他の部署を巻き込んで「この機能をリリースしたらマーケのCSではこういう対応してください」「コンサルではこういう対応をしてください」とか、結構お願いすることもあるんです。
―待ってたら勝手にどっかの部署がやってくれますみたいなことは無いと?
リリースもしてない新しいプロダクトだったら、そのプロダクトについて詳しく知っているのは自分だけなわけで、周りの人が勝手に分かってくれるわけはないですよね。巻き込んでいく必要があるっていうので言うと、やっぱり人にどんどん「こういうことしたいんですけど、誰が担当になりそうですかね?」みたいな感じで聞いていくのはあるなと。そういうところで、聞きに行くのが苦手な人には難しいなと思います。
―やってる業務自体は、色々分析したり計算したりと緻密な感じがするんですけど、結構人間臭いというか、泥臭いこともできなきゃいけないんですね。
そうですね。土台は泥臭いです。数字って多分それを補強する材料でしかなくて。私は元々コンサル時代の経験もあり、出店者がどういう人かは比較的分かっているので、あまりヒアリングをしなくてもどの辺が課題か分かることも多いです。でも、新しくうちの会社に入ってこられる方だと全然分からないですよね。やっぱり出店者の方がどういう人かイメージできないと、なんかズレた課題解決になっちゃったりするので。そういう意味ではどうしても、自分が知らないんだったらその人に触れていくしかないっていうのはありますね。
―なるほど。分かりました。ところで、田崎さんの仕事の流儀というか、大事にしてることはどんなことですか?
PMとして大事にしてるのは、可能性をすごく広めに考えること。それと同時に、捨てるところをはっきりするということ。本当はいろんな人に使って欲しいのでいろんな使い方を考えるんですけど、100%の人が満足するものって作れないし、全部取ろうとするとすごく複雑になっちゃうので。なので、大多数の人が満足できるラインを引くのを意識しています。それで言うと、要件を考える時に他のPMから指摘をもらう「レビュー会」での視点の補強は、私の中ではすごく大事にしています。指摘を受けて「そういう可能性を考慮はするんですけど、そのパターンはこういう理由でなしにしたいと思います」とか「そういうパターンは結構起きそうなので、検討します」とか。その辺の振り分けは結構意識してるところですね。
―ずっと決断の連続というか。そういう仕事だということですね。
そうですね。PMは判断するのが一番の仕事だと思います。エンジニアから「ここどうしますか?」って聞かれることも結構多いです。「それは許容で」とか「それはちょっと使いにくいのでこれを直してください」とか、本当に判断の連続です。

めちゃくちゃ難しいことをしてます(笑)
―プロダクトに関して、くらマの最大の課題はどこにあると思いますか?
くらマとしてはもっとカテゴリを拡大していきたいです。ただ、今と違うカテゴリをどんどん入れていくと、ユーザーの体験もどんどん異なってくる。で、それぞれに最適な形で機能を作っていくと、色々な機能ができることになって。それをユーザーが迷わずに使えるような形にするにはどうしたらいいのかが最大の課題だなと思っています。現在でも、ハウスクリーニングみたいに料金が最初から決まっていてオンラインで予約するパターンと、外壁塗装のように指定見積もりを取るパターンと、電話で予約する緊急系カテゴリという3つの予約のパターンがあるわけで。ユーザーもなんとなく「なんか前と違う予約の方向だな」とか思いながら予約してるんじゃないかなと思うんですよね。それをユーザーが混乱せずに使える形に考えるのがすごく難しいなとは思います。で、それは出店者側も同じで。機能が増えてくると出店者がそれについてこれなかったりもする。今までの商習慣から抜け出してもらう必要もありますし、その浸透のところも難しいですね。ユーザーと出店者、双方が違和感なく使える、使いこなせるプロダクトを作るっていうのは難しいなと思ってます。
―めちゃくちゃ分かります。それは難しいなー。出店者側の商習慣、今までのやり方がある中でそれをこっち側に持ってくるってかなり難しいじゃないですか。でも、今までのやり方や商習慣に色々と問題があるからユーザーもなかなか良い事業者に出会えなくて...っていうので悩んでるわけですよね。
そうなんですよね。今の商習慣がユーザーに合ってないから、それに代わる新しい体験を私たちが考えるんですけど。それはユーザーにとっても出店者にとっても新しいので、違和感なく使ってもらえるプロダクトにするのが本当に難しい。でも、だからこそくらしのマーケットが必要なんだと思うんですよね。面白いけど、めちゃむずいですよね。
―面白いけど僕はやりたくないなぁ(笑)。色々な課題はあると思いますけど、今のくらマの完成度は10段階であらわしたら何ですか?
まだ3くらい。今は「くらし」といってもほぼ家の中で完結しちゃってて、参入できてない領域がまだまだいっぱいあるので。そうなってくると、さっきの複雑化問題がやっぱり壁になってくるんですよねー。それで言うとまだ全然半分も、道半ばにも届いてないんじゃないかなって意味で3ですね。
―そこのジレンマですよね。どんどん拡大していって、それぞれに最適なシステムも用意したい。でもそれを本当にやってくと、どんどん複雑で巨大なシステムになってしまって...。うーん、めちゃくちゃ難しいことしてるなって思っちゃいました。
はい、めちゃくちゃ難しいことをしてます(笑)。
―3から10に持っていくためには何が必要だと思いますか?
んー...。機能をどうするかっていう問題はあるんですけど、やっぱりその前に新しい領域にチャレンジしていくのが先かなと。私たちと接点がない領域のことは、今私達が付き合っている出店者からお話を聞いても分からなかったりするので。新しい領域に参入していくと、結果としてデータが集まってきて「本当はこうした方がよかったね」みたいなのが見えてきて改善できてくるっていうのはあるのかなと思うので、それでいうと、どんどん拡大していくのが一番の近道なのかなと思います。

くらしのマーケットは出店者の人生を乗せている
―田崎さんがこの会社に入社したのっていつでしたっけ?
2015年の10月ですね。今年の10月で8年ですか。
―入社した時はコンサルで、次にPMになって、そうやってこの会社で長く働いてる理由ってなんですか?面白いとか楽しいとか、何かしらあるからだとは思うんですけど。
一番大きいのは多分プロダクトが好きだから。好きと言うか、このプロダクトにすごく責任を感じてる...みたいな。くらしのマーケットって出店者の人生を乗せてるじゃないですか。コンサルの時それをすごく感じて。くらマに出会って人生が変わった人、くらマで活躍したけど、悪いことしちゃうとペナルティもあるので結果苦しんでる人とか、まあ色々いるわけじゃないですか。良くも悪くもくらしのマーケットが出店者の人生をすごく変えている。コンサルの部長をしてた時は、まだ会社もすごく小さかったですし余計に「このサービスがいっぱいの人の人生を乗せてるんだから、絶対に潰しちゃいけないな」と思って仕事に打ち込んでいましたね。今ではPMとして、よりいろんな人に使ってもらえるプロダクトになれば、くらしのマーケットに出会って人生が変わる人の範囲もより広がっていくと思っています。くらマに出会って幸せになる人を増やしたいなという意味で、このプロダクトが好きで続けているってところは大きいかなと思います。
―給料とか人とか働きやすさとか、仕事を続ける意味は人によって色々あると思いますけど、くらしのマーケットそのものに責任を感じてやってるってことですよね。
そうですね。よく皆さん「良い商品に関わりたい」「人の役に立つ仕事をしたい」みたいなことを言うじゃないですか。それで言うとくらしのマーケットって、その人の人生を変えるぐらいの、人の役に立つサービスだということを心の底から腹落ちしてるので、やりがいを感じます。割とよくある言葉で言えば多分そういうことだと思うんですよね。
―いい話ですね。くらしのマーケットに関わる出店者やユーザーが田崎さんのベースにあるんですね。お話を聞いて、田崎さんもかっこいいですし、くらマも本当にいいサービスを提供しているんだなーって思いましたね。
そうですね。くらマも本当に大きくなってきたので、これからもっともっといろんな人に使ってもらえると思います。それでいうともう一つは「飽きない」というのもありますよね。まだまだたくさんの領域があって、やったことがないことがいくらでも落ちてるので。
―たしかに。同じことをずっとやるっていうのはないですね。くらマの拡大は一生終わらないっちゃ終わらなそうですけどね。
そうですね。この会社で「これ以上やることがない、もうやりきったな」みたいなのは、PMに関しては来ないなと思うので。そういう意味では長く働けるかなと思いますね。
―ありがとうございました!

田崎さんにはユーザーが見えているんだと思いました。利用する出店者やお客様の顔が浮かぶのだと思います。「好きと言うか、このプロダクトにすごく責任を感じてる」という言葉から、田崎さんのくらマへの想いが見えたインタビューでした。自分から行動できるコミュ力のある方のご応募をお待ちしています!
