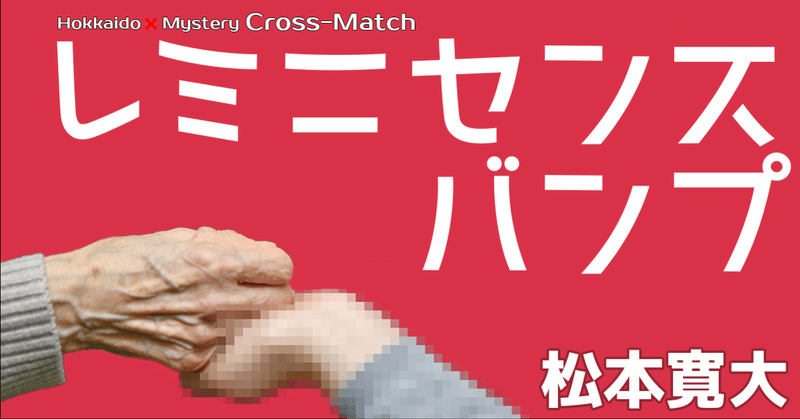
松本寛大『レミニセンス・バンプ』
Reminiscence Bump
人が自らの過去を振り返ったとき、もっとも想起する割合が多いのは十代から二十代にかけての記憶とされる。これをレミニセンス・バンプといい、高齢者ほど、この現象が顕著である。そもそも十代から二十代ころがもっとも記憶力に長けている時期であることに加え、出来事に新奇性が強く、印象が強烈なものになりやすいこと。また、アイデンティティの確立時期に合致し、社会的にも変化の大きい年代であることなどがその原因とされている。なお、本人にとってもっとも幸福な記憶ともっとも哀しい記憶とを比べた場合、前者においてレミニセンス・バンプが著しいという実験結果がある。
1
思い返せば、初夏のころには病の兆候はあった。祖母は時折、こちらの言葉を無視したり、話の途中でなにもいわずに部屋を出て行ったりした。
おばはそうしたことがあると、「なんのつもりなんだか」と、ぐちをこぼしていたものだ。家族の誰もが認知症など想像できるはずもなく、ただ年寄りのわがままだと思っていた。おそらくは、本人もそう考えていただろう。
祖母は起床が早いものの、朝は自室から出ないことが多かった。朝食も自室でとっていた。わたしが塾から帰るころにはもう就寝していたから、週末以外には顔をあわせる機会もない。わたしが祖母の変調に気づいたのは九月初旬のことだった。
その日、わたしたちは郊外型スーパーマーケットでの買い物を終えて、家に帰ろうとしていた。
駐車場は広く、車を停めた場所まで祖母を歩かせるのは酷だと思ったから、おばと祖母にはスーパーの入り口で待ってもらっていた。
おじは入り口の近くに車を移動させて、
「じゃあ、お母さんとおばあちゃんを呼んできて」
正面出入り口のそばではひびの入ったガラスを交換するために業者が作業をしていた。車が小石をはね飛ばしでもしたのか、アスファルトに置かれたガラスには蜘蛛の巣のようなひびが入っている。作業員は新しいガラスの梱包を解いていた。
地面に置かれたガラスは午後の陽を照り返してまぶしく輝いている。ガラスの上につなぎトンボが止まっていた。
その日は残暑が厳しく、北国とは名ばかりで気温は三十度に近かった。例年ならば涼しい風が吹きはじめるころだったが、秋の訪れは無数に飛び交うトンボによって知るばかりであった。
「あ、おばあちゃん」
わたしが車を降りて正面入り口近くまで進むと、祖母の姿が見えた。手になにかの商品のパッケージを持っている。そうして店を出たところでベンチに腰を下ろし、パッケージを開けた。おまんじゅうかなにかのようだった。
わたしは祖母に手を振って呼びかけようとして、上げかけた手を止めた。警備員が走り寄って、祖母になにか話しかけている。
「聞こえてる? おばあちゃん、それ、お金はらってないでしょ。お金はらわないと駄目でしょ。それじゃ万引きだよ。万引き。わかる? 家族の人、誰かいないの?」
祖母はまるで無視を決め込んでいる。わたしは駆け出した。祖母が手に持ったおまんじゅうにかぶりついた。
「おばあちゃん、家族の人いないの? ねえちょっと、それ食べちゃ駄目だよ。わかんないの?」
警備員は祖母の目の前にかがみ込み、おまんじゅうのパッケージを取り上げようとする。祖母は「なにするの!」と大声を出した。ふたりのそばまで駆け寄ったものの、わたしは目の前の事態に、いったいどうしていいかわからなくなっていた。
「あの、すみません……」
振り絞るようにして声を出す。買い物客や、ガラスを交換していた業者がこちらをちらちらと見ているのがわかり、いたたまれない気持ちだ。
「このおばあちゃんの家族の人?」
「はい、そうです。祖母がなにかしたんでしょうか……」
わかりきっていることをわたしは訊く。ほかにいうべき言葉を見つけられなかったからだ。
「困るんですよね。売り場のまんじゅうを勝手に持って出て、ここで食べはじめたんですよ」
「すみません、ほんとう。お金ははらいますから」
祖母のほうをちらりと見る。祖母は仏頂面で、むしゃむしゃとおまんじゅうをほおばっていた。
「はらえばいいってもんじゃないでしょうよ。名前は?」
「山口(やまぐち)です」
「山口さん。いま、ご家族はあなただけ? お父さんかお母さんはいっしょじゃないの?」
わたしはふりかえる。おじが怪訝そうな顔をしながらこちらに近づいてくるところだったので、手招きをする。
「父はいま来ます。母にもすぐ連絡しますから」
わたしがおばに電話をかけようとしたとき、祖母が急にベンチから立ち上がった。なにごともなかったかのようにすたすたと歩きはじめる。
「おばあちゃん、困るんだよ。もうちょっとここに座ってて」
警備員がいった。祖母は無視をしている。
「おばあちゃん! ちょっと! 聞こえてないの? おばあちゃん!」
「おばあちゃんってなにさ。わたしにはあんたみたいな孫、いないよ」
「聞こえてるんでしょ」警備員は不満げに、「とにかく、勝手に行かないで」
次の瞬間、わたしは思わずあっと声をもらした。
祖母はまるでわざとのように、道に置かれたひびの入ったガラスの上に足を踏み出した。あわててトンボが逃げていく。
一瞬、ガラスが割れるかと思った。だが、意外に丈夫なようで、割れはしない。
「ちょっと、ちょっと」
ガラスを交換していた業者が立ち上がり、祖母を止めようとする。祖母はだだっ子のようにしてガラスを踏みつけた。今度は、ガラスのひびは広がった。このときにはおじも事態の異常さを悟ったらしく、走ってこちらに向かっていた。
おばがやって来たのは、祖母を囲んで、おじとわたしと警備員が声を上げているところにである。あとで聞いたところでは、ちょっと目を離したすきに祖母がいなくなり、持たせているはずの携帯電話にもまったく出ず、あちこち駆け回って探していたそうだ。
「いい加減にしてくださいよ、ねえちょっと」
祖母の正面に立ち塞がるようにして、警備員が祖母にいう。立場上、手をつかんで引っ張るわけにもいかないのだろう。語気は強いが、祖母の行為を止めかねている。
「なにやってるの? これはなんなの?」
おばはひどく疲れた顔でそういった。祖母はことさら素知らぬ態度で、おばが持っていた紙袋に乱暴に身体をぶつけながら、そばをすりぬけようとした。「あっ」とおばが声を上げた。
紙袋にはわたしの十八歳の誕生日を祝ってくれるケーキが入っている。いまさらそんなことは照れくさいと遠慮したのだが、たまたま出店していた有名ケーキ店の前を通りがかったとき、おばが半ば強引に買うと決めたのだ。
「いい加減にしてっていっているでしょ」
おばは、周囲の目もはばからず、大きな声を上げた。立ち去ろうとする祖母の腕をつかむ。祖母はその手をはらいのけようとする。
袋が地面に落ちたせいで中身は崩れただろう。ケーキなど買わなければ、おばがこんなふうに怒ることもなかったのだと思うと、おじとおばには申し訳ない気持ちだ。
*
「母さん、やっぱりぼけたのよ。これからたいへんよ」
「まだ早いだろ」
「ちっとも早くないわ。もう七十一よ」
おばが不満げな声を上げたが、おじは気のない表情だ。
スーパーでの騒ぎのあと、警備室でお説教を受けてから、わたしたちは家に戻った。祖母はなぜあのようなことをしたのかと訊かれても終始だんまりを決め込み、警備員が話しかけている最中であるのに立ち上がって部屋を出て行こうとすらした。警備員はしっかり目を配るようにとおじとおばに注意して、その日は終わった。
去り際の、「認知症の検査は受けているんですかね」という警備員の言葉に、わたしたちは顔を見合わせた。そのときまで、認知症の疑いなど持ってはいなかったのだ。
とにかく一度、いつも行っている小さな医院で認知症について相談しようということになったのだが、事情が事情であるため、おばがついていかねばならない。
だが、こうしたところがおばは上手くない。なにか祖母の機嫌をそこねないような適当な理由を考えればいいものを、有無をいわさずついていくという方法をとった。案の定、玄関先から祖母の声がした。
「いつもわたしひとりで行っているのに、今日に限ってなんなの」
無理もない、とわたしは思ったものだ。その日はけっきょくおばがついていくことはできなかった。
医院に電話をかけ、事情を説明すると、まずはおばだけが呼ばれることとなった。いつくらいから症状が見られるようになったか、過去、家族に認知症の患者はいなかったか――そうした、様々なことを訊かれたらしい。
「で、医者はなんといっていたんだ」
「認知症の疑いがあるけどはっきりとはしないって」
「なにもわからないってことじゃないか」
「もっとしっかり検査しないとなにもいえないんだって。最近、調子が悪いからって薬を変えたでしょう。そのせいかもしれないらしいのよ」
「薬を変えたくらいでそんな簡単に認知症みたいな症状が出るのか?」
「出るらしいわよ。薬のせいなら治しようもあるけど、もしほんとうに認知症だったら……」
「それはだから、まだ決められないんだろう?」
「すごくいろんな可能性があって、とにかく調べないとわからないらしいのよ。認知症の検査っていうと意固地になる患者も多いから、やさしく諭して検査を受けさせるようにだって」
「簡単にいうなあ。それができたら苦労しないだろう。とりあえず薬のせいかもって医者がいうんなら、しばらく様子を見たらどうだ」
「でも、検査は必要だわ」
「俺のお袋は八十過ぎても、頭のほうはしっかりしていたけどなあ」
おじの実母は先年、癌で亡くなっている。たしかに、認知症の兆候などはまったくなかった。
「じゃあなんで万引きなんてするの?」
「お前、あの日、なにもなかったのか」
おじがおばから眼をそらしながらいう。
「なんのことよ」
「お前になにかいわれたとかで腹を立てて、あてつけにあんなことしたんじゃないのか。前にそんなことがあっただろう」
「じゃあ母さんが万引きしたのはわたしのせいだっていうの?」
「そんなこといってないよ」
「なんでそんな人ごとみたいなのよ」
「もういいよ」
「なにがいいのよ」
おじの会社は今年、大規模なリストラに踏み切った。それで、長くいっしょに働いてきた同僚や上司が会社を去ることになり、おじの頭が仕事のことでいっぱいであったのは、無理もないこととはいえた。おばもそのことはわかっているのだろうが、あからさまに自分には関係のないことだという態度をとられれば、それは腹も立つ。
そのあとしばらく、おばは不機嫌さを隠さなかったが、やがて矛をおさめたようだった。
祖母が医院に行った際のことだ。医師は過去何日かの食事の内容をたずねた。塩分はひかえめにするようにだとか、食べ過ぎないようにといったことや、前回の診察で薬の管理の話をしたが覚えているかなどといったことを話す。
祖母は知らないことだが、実はこのときおばも医院にいた。別室で待機していたおばに、医師はあとから、実際に食卓にのぼった食事の内容を確認した。そのようにして照らし合わせ、祖母の記憶がたしかか調べるのである。
診察結果は、「認知症の疑いはあるが、症状は軽度で、はっきりとはしない」というものであった。
そこで、認知症の症例を多く取り扱っている近所の病院を紹介してくれたのだが、はたして祖母がすなおに検査に同意してくれるかが問題だった。
「侑希(ゆうき)」
居間でひとり遅い食事をとっていたわたしを、おばが呼ぶ。
「なに、お母さん」
「食べ終わったら、おばあちゃんのぶんの食器もいっしょに洗ってよね」「はあい」
「それと、侑希」
わたしは次の言葉を察して、先回りした。
「まだ向こうから連絡とかはないんでしょう? 十八歳になったのだってついこの前なんだから、そんなに急がなくても……」
話が長くなると面倒なことになる。わたしはあいまいな表情のおばに「食器、片付けてくる」といって、祖母の部屋に向かう。
祖母が自室で食事をとるのは、本人にいわせれば、「あんたがたと食べるとあわただしいから」とのことだ。食事はお盆に載せて上げ下げすることになっていた。
「おばあちゃん」
わたしは声をかけてふすまに手を伸ばす。電灯はついているもののテレビの音がしない。もう寝ているかもしれないと思いながらそっとふすまを開けると、祖母は仏壇の前に座っていた。
おじの両親の位牌は、おじの兄の家の仏壇におさめられていると聞く。我が家にあるのは、この、祖母の部屋の小さな仏壇だけ。隣に置かれた腰までの高さのタンスの上には、二枚の写真が飾られている。一枚は祖父、もう一枚はわたしの実母、つまり、おばの妹のものだ。
「おばあちゃん、ごはん、食べ終わってる?」
わたしはいった。祖母はこちらを見ようともしない。小さな文机の上を見ると、食事はまだ半分ほど残っている。祖母の夕食の時間はいつも六時くらい。いまは八時を回っているから、もう食べる気はないのだろう。
「おばあちゃん、ごはん、どうする? もう食べられないなら、片付けていい?」
もう一度呼びかけると、祖母は振り向いた。
「なに?」
「ごはん、もう食べない? 片付けるよ?」
「悪いね。ちょうどいま、出かけるところだったから」
「え。いまから?」
「花を買いに行かないと。明日は有子(ゆうこ)の命日だから」
わたしの侑希という名前は、父と母から字を借りてつけられたのだと聞いている。
両親よりもずっと長生きして、幸せになってほしいという意味で名付けたとのことだが、わたしが一歳の誕生日を迎えた直後に急性白血病が由来の脳出血のために母がこの世を去ったというのは皮肉に過ぎる。わたしは自分の名前があまり好きではない。端的にいって、それはわたしには重い。
「耀子(ようこ)がなにもしてくれないから。病院の帰りに買ってくれば良かった」
「でも、もう八時過ぎだよ」
「疲れちゃったからね、少し休んでいたんだよ」
「花屋さんしまっちゃってるよ」
「駅前に行けば、まだ開いている店があるでしょう」
会話がかみあっているのかいないのか、よくわからない。たしかにスーパーなどはまだ開いているし、そこでもちょっと花を売っていたりはするが……。
「どうしたの? なにしてるの?」
おばが顔を出した。すでに祖母はストールを羽織り、財布を手にしていた。
「あ、おばあちゃんがいまから出かけるって……」
「なんで?」
「明日は有子さんの命日だからお花を買いに行くって」
わたしが母のことを有子さんと呼びはじめたのはいつのことだっただろうか。
それまでは〈有子母さん〉と呼んでいた。呼び方を変えたとき、おばはいぶかしげな顔をしていたが、そのうちに慣れたようだった。どうして、とは聞かれなかった。わたしも理由についてはいわなかった。
「なにいっているの。いまごろ」と、おばが眉根を寄せていう。「そんな、無理しなくても、明日行けばいいでしょ」
「情けない。なんでそんなひどいこというの。耀子、あんたはもう有子のことなんか忘れちゃったんだね」
驚いたことに、祖母はその場でしくしくと泣きはじめた。仏壇の前に座り、線香に火をともすと、おりんを鳴らした。
「ああ、悔しい、悔しい。有子、かわいそうにねえ」
「なにそれ」
おばの顔つきが変わった。
「悔しいね。ほんとう。有子、ごめんね、許してね。わたしのせいだね」
「わたしだってね」おばの声が震えている。「忘れたことなんかないわよ。なんなのよ」
「やめなよお母さん」わたしはおばの袖を引く。
「わたしのせいで有子が死んだんだよ。わたしが有子を殺しちゃったんだよ。それを耀子は責めているんだよ。ねえ有子、ほんとうにごめんね。許してね。有子は許してくれるのかね。耀子がわたしのことを責めるんだよ」
わたしはぎょっとして祖母を見る。祖母が有子さんを殺した?
おばは絶句したように祖母の背中を見ていた。
「ああ、ごめんね、ごめんね、つらい思いをさせちゃったね。わたしが殺しちゃったせいで、ほんとうにごめんね、有子」
祖母は数珠を手にしてじゃらじゃらと音を立てながら、拝むとも侘びるともとれる様子で頭を垂れていた。
2
気が重い。このところはこればかりいっているような気がするが、まあとにかく気が重い。祖母がスーパーの店先で問題を起こしたあの日に、わたしが十八歳になってしまったからだ。
お祝いのケーキは崩れてしまったが、おばがしきりに悔やんでいたほどにはわたしは気にしていなかった。あの店は毎月おこなわれているスイーツフェアでも滅多に出店しない有名店で、一ピースが五百円だ。高いケーキは崩れてもおいしい。
そもそも写真でしか知らない実の父親なのだ。十六年前におじおばとわたしが養子縁組をしたときに「十八歳になるまでは顔をあわせないほうがこの子のためだ」といい出したのは、その父である。
母が倒れ、赤ん坊のわたしを抱えて父は途方に暮れた。父の勤務形態は不規則で、残業が常態化してもいた。乳飲み子を預けられる場所はそう簡単に見つかりはしない。そういった事情で、見かねたおばがわたしを世話することになったらしい。養子縁組をおこなったのはそれから一年後。ただし、それなりに早い時点で養子を考えていたようなふしはある。
おじいわく「筋を通すため」ということらしいが、我が子として育てる以上は養育費は受け取れないと、頑として拒否したらしい。
だが、「ではわたしは娘に会うのをやめましょう」と父がいったときには、おじも驚いた。養子縁組は実の両親の存在を消し去ることでは決してない。あえて関係を断ち切ることもあるが、それは虐待などのなんらかの理由がある場合だ。
おじは「あなたから子供を奪うのが目的ではない」とあわてたそうだ。だが父も「そんなふうにとらえてもらっては困ります。ただ、こちらも筋を通したいのです」と譲らず、話し合いは平行線となった。
けっきょく、「十八歳になったら、娘に決めてもらいましょう」というのが結論だそうだ。そんなことをいわれても困るのだが。
高校に入ってしばらくして、おじとおばにそうした話を聞かされた。以来、わたしは内心びくびくしていたのだが、十八歳の誕生日を過ぎても、実父から連絡はない。
正直にいえば、父を恨む気持ちがないわけではない。母とわたしを捨てたようにも見えたから、案外、そもそも浮気のひとつもしていたのじゃないのかと疑ったこともある。
理不尽であることはわかっている。しかし、そのようにして父を憎んでみなければ、わたしはいまのこの家に自分の居場所を見いだすことの罪悪感から逃れられそうになかったのだ。
わたしは両親のことをそもそも知らない。だから、なんの感情もない。たぶん、そう。そのはずだ。どうしたってわたしの両親はおじとおばのふたりでしかありえない。
わたしはキリスト教系の幼稚園に通っていた。教養は身につかなかった。おそらくは素養に恵まれていなかったことに加え、これっぽっちもやる気がなかったせいだ。わたしは長く退屈なお話を黙って聞いているようなできの良い子供ではなかった。
だからキリスト教にはいまもってなんの理解もない。気づかぬうちに捨てていなければ聖書は持っているはずだが部屋のどこにあるのかもわからない。
ただ、聖書の中でひとつだけ覚えているフレーズがある。見事な銀髪の、すらりと背筋の伸びたシスターの柔和な表情とともに、わたしは折にふれてその言葉を思い出す。
「天が下のすべての事には季節があり、すべてのわざには時がある」
発表会で朗読させられたので、覚えている。十数年前の記憶である。人間ってすごい。
聖書のこの部分はなにやら難しい解釈がされる場合もあるようだが、それはわたしにはわからない。わたしにとっては、とにかく人間が生きるには時間というものがいつまでもどこまでもつきまとってくるということだ。
人の命は永遠ではないし、人の記憶も永遠ではない。わたしは祖母の部屋で有子母さんの顔写真を見るたび、それを思い知らされる。
*
家のすぐ近くの公園には池があった。
運動場が併設された大きな公園で、池もかなり大きい。小さな島が水面から顔をのぞかせており、橋を渡ってそこまで行くことができる。
木製の橋は雨風で黒ずんでいる。わたしは祖母のペースにあわせてゆっくりと足を進めていく。
日曜の午後、空は高い。風が吹き、水面に映った木々が揺れる。そこに少し華やかな色が混じっている。
そろそろ木々の緑はどこか褪せたものに変わり、高い枝の先では、すでに葉にいくぶん赤みがさしていた。
池をのぞき込むと、底が見える。せいぜい子供の膝くらいまでの深さしかないだろう。池の中央部分はそれなりに深いようで、だから、橋を渡っていくことができるのは途中の小島までだ。
それまでもこの公園は祖母の散歩コースではあったのだが、以前にも増していやに足を運ぶようになったのは、この二、三ヶ月くらいのことだ。それも、判で押したように毎日決まった時間に家を出る。家から公園まで行くコースも決まっており、そのあとは橋を小島まで行ったところで来た道をたどる。
問題は、風が吹こうが雨が降ろうが出かけようとすることで、気がついたおばやわたしがとめても、ちょっと眼を離したすきにまた玄関で靴を履いているということが繰り返された。何度かそれを止めているうちにわかったようなわからないような顔をして外出は取りやめとなるのだが、翌日はまた同じことが繰り返された。
やむを得ず、平日はおばが、土曜と日曜はわたしか、可能な限りおじがいっしょについて散歩に出ることになった。危なっかしくて仕方ないからだ。
「おばあちゃん、もう帰るよ」
わたしは祖母にいうと、橋を渡って岸に戻ろうとした。祖母は欄干に両手をつき、じっと水面をながめている。
わたしの呼びかけは届いていないようだった。祖母は水面から視線を上げると、今度は公園の木々が途切れたあたりをぼんやりと見つめ、動こうとしない。
「おばあちゃん、なに考えているの?」
沈黙。その表情からはなにも読み取れない。
おばによると、先日の、検査時の祖母の態度は最悪に近いものだったそうだ。とにかく、医師のいうことを聞こうとはしない。パズルのようなものをさせてみたり、記憶テストをおこなったりしたらしいが、祖母は無言か、あるいは適当な答えをいうので、かなり苦労したらしい。
なぜ医者のいうことにすなおにしたがわないのかと母がいうと、祖母は、「あんな、ろくに苦労も知らない若い医者は頼りにならん」といった。そういう問題でもないだろう。
祖母の医者嫌いには理由がある。なにしろ急性白血病からの脳出血であるから間に合ったかは疑問なのだが、祖母は転院のタイミングによっては母を救えたはずだと思い込んでいるようだった。
母が体調不良をうったえてまず行ったのは近所の医院であった。その場の診察でははっきりしたことはわからず、紹介状を書くから大きな病院で精密検査を受けるようにという医師のすすめを、多忙を理由に母は断った。
その後、やはり体調がすぐれないというので、地域ではやや大きめの武田病院で検査を受けた。検査の結果が思わしくなかったために、その後、すぐに市立病院に移ったのだが、脳出血のために命を落とした。それは突然だった。
それでどうなるものでもないとはいえ、祖母は何十回、それとも何千回、哀しみ、悔やんだのだろうか。
先日、祖母は「わたしが有子を殺した」といった。もっと早く、強引にでも市立病院に連れて行けばもしかしたらという、後悔のあらわれだろう。
思えば夏の終わりころから、祖母は「武田病院に行かずに最初から市立病院に行っておけば」と繰り返すようにもなった。
いまだに後悔しているのだというべきか、あるいは認知症のせいで判断能力がにぶり、心の底に押し込めていた後悔がよみがえったものか。
今後、もし認知症の症状がもっと進んで、過去の後悔をも忘れさせてくれるのなら、それは祖母にとって良いことなのだろうか。
母が診察に同行したとき、医者の問診はそっちのけで、お前はなんのつもりでこんな病院に自分を連れてきたんだと、祖母はぐちぐちと文句をいった。
非常によくあるケースだそうなのだが、認知症の患者は自分が認知症であると認めたがらないらしい。
それで、反抗的になったり、その場を適当にいいつくろって、自分が医師に訊かれたことに答えられないのをなんとかしてごまかそうとしたりといったことが、しばしば見られるそうだ。
とはいえ、正確な診断を下すためには大きな病院に入院して検査を受けなければならない。MRIやCRTといった機器での検査を実施するほか、日常生活の様子を観察する。あとは検査結果に応じて今後の治療方針を決定するという流れだそうだ。
また、認知症の症状を呈した原因によっては、より厳しい闘病生活となる。認知症というのは要するに脳の機能が損なわれて物忘れなどの症状が出ることで、ではなぜ脳の機能が損なわれたのかというと、これは脳の萎縮の場合もあれば、脳腫瘍の場合もある。一見、認知症の症状に思われて、実はうつ病や統合失調症というケースもある。そうしたことを母は医師に説明されたそうだ。
空きがあれば来月、そうでなければ再来月にも入院だ。そのころには、このあたりの木々は赤と黄色に染まっていることだろう。
「おばあちゃん、寒くなってきたよ。もう行こう」
もう一度わたしが呼びかけると、祖母はうなずき、ゆっくりと欄干から手を放し、歩きはじめた。
*
それからしばらくしたある日のことだ。
「調剤薬局によらなかったの?」
おばが眉をひそめていった。その手には、院外処方箋が握られていた。祖母はおばから視線を外し、無感情な顔つきで黙って座っていた。無視されたと感じたのだろう、おばの声のトーンがわずかに変わる。
「調剤薬局で薬をとってこなきゃならなかったのに、そのまま持って帰ってきちゃ駄目じゃない」
「チョーザイヤッキョク」
祖母がおばの言葉を繰り返した。
「なんで薬をもらってこなかったのって訊いてるのよ」
「薬は、くれなかった」
「くれなかったんじゃないわ。お母さんがもらってこなかったの」
祖母の物忘れは薬に限らなかった。その内科では料金の支払い後、受付窓口で次回の予約をとる必要があったのだが、これを忘れてそのまま帰宅してしまったこともある。
「いいよ。塾の前にわたしが行ってくる。早めに行って、始まるまで自習室で勉強してるから」
わたしはおばから処方箋を受け取ると、駅前へと向かった。十月も半ばを過ぎると、夕方には真っ暗だ。
空気は冷たく、自転車のハンドルを握る手がかじかむ。もうまもなく、朝晩にはストーブをつける生活となるだろう。
駅前の薬局で、わたしは窓口に処方箋を出し、認知症の祖母の代わりに薬を受け取りに来たと、事情を説明した。
このところの日々は、そうした苦労の連続であった。祖母は、夏にはなんでもなかった様々なことができなくなっていた。
わたしたちの思うよりも変化は急だった。
認知症の進行度合いの問題なのだろうが、それなりに面倒なことができるかと思えば、どうということのないことができない。
自分でやかんに水を入れてお湯をわかし、棚から茶筒を取り出してお茶をいれるということはできるが、居間のソファの上におもらしをしてしまった下着を脱ぎ散らかしてそのままにしておいたりする。自身の洗濯物を洗濯機の前のかごに入れておくという習慣を忘れてしまうようだ。
こうなると、いつやかんを火にかけてそのこと自体を忘れてしまうかわかったものではない。危なくて仕方がない。
時には祖母は、意味不明の行動をした。母の写真や手紙などの遺品の入ったブリーフケースを、そのままゴミに出して捨てようとして、おじが見とがめたことがあった。いつかは処分せねばと思いつつそのままだったものではあるが、急にそんなことをしたのでずいぶん驚いた。どうして捨てようとしたかと問うと、「今日は燃えるゴミの回収日だから」と、会話が通じない。
それでいて、医師になにか困ったことがないかと問われると、べつに困っていることはないと答える。
さらに不思議なことには、物忘れのテストをおこなう際には、これを楽々とクリアしたりするのである。医師が祖母の持ち物を借りて、隠す。少しの問診をはさんだのちにあらかじめ用意しておいた様々な物品とともに祖母の持ち物を並べ、「先ほど机の上に置いてあったものがなにかわかりますか」とたずねると、迷う様子すらなく自分の持ち物を手にとる。
医師は認知症の初期段階ではそうしたことも起こるという説明をするのだが、家族としては中途半端にできることがあるといっそう困るのだ。
祖母はなんでも自分でできると思い込んでいたからおじやおばのいうことを聞かなかった。おばはこまごまと行動のチェックリストを作ったり、忘れることのないようにと祖母の手の届く位置にものの置き場所を変更したりと工夫をしたが、祖母は知ってか知らずかそれを無視した。それが認知症のせいであればやむを得ないのだが、祖母の態度がいちいち反抗的で、まるで嫌がらせだと、おばはぐちをこぼした。
明らかにおばは祖母の変容に動揺し、その重みを受け止めかねていた。
それまではさほど深刻に受け止めていなかったわたしたち家族の眼前に、介護の問題がちらつきはじめた。
そうなれば、負担はおばにのしかかる。現在はパートの時間を調整してなんとかしているようだが、いずれそれも辞めざるを得なくなるだろう。おじの会社は今後業績が回復することがなければ二度目のリストラに踏み切ることも予想できたし、その際はおじが対象にならないとも限らない。
そうしたこともおばの不安をつのらせる原因で、ふたりが口論しているらしい声が寝室から聞こえるときもあった。
ある日、祖母が早くから眠りについて静かになった居間で、わたしがおばにふとたずねたことがある。「仕事、辞めるの?」と。
「そうね。あとで後悔するのはイヤだから、時間を短縮するかも」と、おばは答えた。
おばが社会とつながっていたいという思いで働きに出ていたことは知っている。それに、収入のことが頭から離れないわけはない。
一瞬、おばが口をつぐんだ。きっと、「学費のことは心配しないで」という言葉が、おばののどまで出かかっただろう。しかし、そうはいわなかった。
おばはいつも、わたしに対して気を遣っていないふりをした。わたしも、おばには遠慮しないふりをしている。そうして十数年、わたしたちは母子でありつづけた。
わたしには、この家のお金を使って大学に行く資格などないのだ。べつにたいして勉強が好きなわけでもない。多少の努力はするのだが、教科書の内容はちっとも頭に入らない。我ながら、根本的にあまり頭が良くないのだと思う。努力を積み重ねてそれを学業に反映させている友人を見ていると、ほんとうにそう思う。家のお金を使う以上はなんとかしたいと、焦るばかりだ。
台所のシンクには、おばが買ってきた花があった。小さな紫色の花弁がついた、可愛らしい花だった。
「この花」とわたしはつぶやいた。紫色の花は祖母の好みではないことをわたしは知っていた。地味すぎて華やかさに欠け、娘に供える花としてはふさわしくないと祖母は思っていたようだ。
「ああ、それ。たまにはいいでしょう。地味に見えるけど、有子はその花がけっこう好きだったから」とおばはいった。
「ふうん」
「嫌みをいわれるかもしれないけどね、べつにいいわ」
おばは笑ってみせた。
3
祖母は、その後も問題を起こした。家のものを家族に無断で捨てようとするのである。
それは手帳や本のときもあれば、アルバムのときもあり、しかも、執拗だった。つい一時間前にとがめられたことを忘れたかのように、こちらの目を盗んで同じことを繰り返した。
驚いたのは、家族共通の本棚の本を洗濯機に投げ込んでスイッチを入れたことだ。音を不審に思って洗濯機のふたを開けたおばは、水浸しの本を見て目を丸くした。
べつだん捨てても構わないような古い文庫本ばかりだったのだが、なぜこんなことをしたのかと問いただすと、祖母は黙り込んだ。おばがさらにとがめると、かんしゃくを起こしてものを投げつけた。
病院の先生には、認知症の薬があわないのではないかと相談をした。時に感情の高ぶりや攻撃性が見られるなどの副作用が出ると聞いたことがあったからだ。
だが、薬を変えても症状はおさまらなかった。
そもそも、認知症は薬で治るものではない。わずかなりと現状を維持することを期待しての投薬に過ぎない。それでも、十数年前に比べると薬の種類も増え、量や組み合わせを工夫することで症状の軽減効果が見られるのだと医師はいった。信じるしかなかった。
様々な理由からずいぶん先延ばしになっていた総合病院での精密検査が近づいたある日、祖母は家族が驚くようなことをしてみせた。放火未遂である。
コンロの火を消し忘れたとか、そうしたことではない。ろうそくや線香に火をつけるための専用のライターを使って、風呂場で例の母のブリーフケースを燃やそうとしたのだった。
ブリーフケースは無事だった。そもそもそう簡単に火がついたりはしなかった。いずれにせよ、祖母の行動に気がついたおばが金切り声を上げて、それは未遂に終わった。理由を問いただされたときの返答は「わたしが燃やさずに、誰が燃やすの」だった。
気が休まるときがない。それでも日々はつづいていく。誰かが助けてくれるわけではない。
祖母を総合病院に連れて行く際も、ひともんちゃくあった。正直、わたしはいっしょに行ったことを後悔した。
わたしたちの暮らす家は市の北西部にある。祖母が検査入院をする総合病院は市の中心部をはさんで南東である。電車や地下鉄は乗り換えが必要であるし、短い期間とはいえ入院の荷物も何かと多い。そうしたわけで、わたしたちはおじの運転する車で病院へ行くことになった。
家を出ると、おじは高速道路のインターチェンジへと車を走らせた。中心部を通ると渋滞に巻き込まれる。そのあいだ、祖母が車の中で騒ぎ出したら面倒なことになるからというつもりらしかった。
実際、そうしたことがあったのは一度や二度ではなかった。車の中でじっとしていることに祖母は耐えられなかった。十分としないうちに、「降りたい」「具合が悪くて吐きそうだ」「めまいがするから車をとめてくれ」といい出すのである。
以前の祖母はそんな人ではなかった。認知症が進んで子供がえりが始まっていたのかもしれないと、わたしたちは思っていた。
けっきょく、わたしたちにそれを受け止める余裕がないということなのだろう。そんなことはおじもおばもわかっているはずだ。
だが、出かける前にもあれがない、なにをしなければ、それが気になると祖母がいい、あれやこれやと支度が遅れるし、それでいざ外に出てみると、「車を降りたい」である。祖母のいいぶんを聞いていると、三十分で終わる通院や買い物に一時間や二時間はかかる。
家で留守番をしていてもらえれば問題はないのだが、祖母を家にひとりにはしておけない。きっと勝手に家を出て行ったり、風呂に湯をはろうとして部屋中を水浸しにしたりといったことをするだろう。
その日は、「トイレに行きたい」であった。高速道路に乗ってしまってからそうしたことをいう。高速に乗る直前に祖母はトイレに行っていたし、それから十分は経っていない。降りる予定のインターチェンジまでのあいだに休息所などありはしない。
「お願い、我慢して。あと十分くらいだから」おばがいう。
「トイレ。もらす」
「もうちょっとだけだから。トイレ、ないから」
「おしっこもらす。もう無理」
「じゃあ、そのまましても大丈夫だから」
祖母はこのとき、紙おむつをしていた。何度かおもらしをしてしまったことがあり、あらかじめ用意をしていたのだ。
「とめて。車降ろして」
「降りられるわけないでしょう!?」
それからのことというのは思い出すのも苦痛だ。
祖母は後部座席に座っていた。シートベルトを引っ張り、運転席の背中側に足を踏ん張り、身体をよじる。何度も、運転席を蹴り飛ばす。
「もらす! もらす! もう降りる!」
「いい加減にして! 無理だっていっているでしょう!? 大丈夫だから、そのままもらして!」
「助けて! 助けて! 有子、助けて! 耀子がひどいのよ!」祖母の甲高い声。それより大きなおばの怒鳴り声。
「有子のことをいうのはもうやめて!」
「有子! 有子! 許して! 有子!」
「やめて!」
「うるさい! お前も黙っていろ!」おじが叫んだ。
「だったらあなたが黙らせてよ!」おばが怒鳴り返す。
おじがハンドルを殴りつけた。わたしはできることなら耳をふさぎ、目を閉じたくなった。なぜこんなことになるのか。誰が悪いというのか。祖母は悪くない。おばだって、せいいっぱいやっている。なぜ、なぜと、わたしは問いを繰り返した。
少ししてインターチェンジを降り、近くのセブンイレブンに飛び込む寸前まで、この騒ぎはつづいた。わたしが手を引いて連れて行ったのだが、トイレが終わると、車内での騒ぎは嘘のようで、祖母は「お菓子が食べたい」といった。
またトイレといわれても困るのでお茶は買わず、一口サイズの小さなおまんじゅうだけを買った。レジで会計を待っているあいだ、祖母は鼻歌を歌っていた。先ほどまでのあれやこれやがわたしの頭の中でぐるぐるしていた。
「百十円です」
わたしよりも年下らしく見えるアルバイトの少女は、わたしが泣いていることに驚いているだろうに、表情にはまったく出さなかった。ずいぶんと教育されているんだなと、コンビニのアルバイト経験がないわたしは、頭のどこかで考えていた。
「有子さんのことだけど」
病院からの帰り道で、わたしはそう切り出した。いままでは話しづらかったのだが、こうした機会に聞いておきたかった。
「おばあちゃんは、なんであんなにもこだわっているのかな」
帰りの車内は、静かなものだった。おじもおばも、疲れた顔で黙り込んでいた。車窓から見る街路樹はすでに色を落とし、秋の深まりを告げていた。
「自分の娘よ、当たり前でしょ」
つぶやくようにしておばがいった。
「認知症でも、そのことだけは忘れないんだろう。責任を感じているんだよ」
おじがいうと、おばはため息をついた。
「なんの責任よ。母さんのせいじゃないわ」それからわたしに、「なんでそんなこといい出したの」
「もし心残りがあるのなら、わかってあげたいから」
「心残りは、あるわよ。どうやったって」
おばのいいかたが突き放したようで、わたしは自分でも驚くほどにショックを受けた。できる限りそれを表情に出さないようにするのには苦労した。
「武田病院に行かせて失敗した、っていっていたよね」
「医療過誤とか、ないから。お母さんがいっているだけだから。真に受けちゃ駄目よ」
以前にも聞いたことはあったのだが、おばはあらためて、母が亡くなったころについて教えてくれた。
武田病院では、二度、検査をおこなったそうだ。最初の検査のあと、一週間してから、入院しての精密検査。おそらくはその時点で、白血病を含めていくつかの疾患が疑われたのだろう。採取した血液は外部の検査センターに回され、より詳細に調べられることになった。
数日の入院のあいだに、すでに専門医のいる市立病院の血液内科へ転送の手配がとられていた。転送された直後に母は脳出血を発症。出血部位は止血の難しい場所で、意識を回復しないまま翌日に亡くなった。医師に過失はあったかといえば、第三者的には「ない」といえる。
だが、我が子を亡くした親がどう思うかというと、それはもう理屈の問題ではない。
「とにかく、おばあちゃんにしたところで、いまではもう細かいことなんか覚えていないさ。ぼけていれば、なおさらな」
おじがいう。
「それでも後悔の念だけが残っているとしたら、寂しいわ」
「それもすぐに忘れるよ、きっと」
「つらさも忘れるっていうこと?」
「そう。だとしたら、楽になれるっていう考え方もあるんじゃないかな」
わたしも、一度はそんなふうに思ったことがある。おじは納得している様子だったが、少なくともいまのわたしはそうではなかった。しかし、ここで食い下がるのも変な話だ。話の糸口を見つけることができず、そのまま黙り込んだ。
窓の外では、風が強いらしく、群青色をした夕雲の下、枝からちぎり取られたポプラの葉が舞っていた。
*
おじとおばは総合病院の診察室の丸椅子に腰を下ろしている。わたしは壁際に立って黙っていた。
「結論から申し上げますと」医師はいった。髪の毛が真っ白で、口ひげも白い。眼鏡をかけており太っているせいで、カーネル・サンダースそっくりに見える医者だった。
「認知症の一種で、前頭側頭型認知症と呼ばれるものです。以前はピック病という呼び名で知られていました」
「アルツハイマーとどう違うんですか」
聞き慣れない言葉にとまどったのだろう、おばがなんともいえない表情をする。
「トラブルを起こした脳の部位が異なります。むろん、症状も異なります。一般的によく知られているアルツハイマーの物忘れと異なるのは、記憶それ自体が失われるというよりも、意味記憶と我々は呼んでいますが、言葉の意味がわからなくなってしまう症状が見られることですね。テーブルの上にものを並べて任意のものを指さしてもらうというテストをおこなうと、正しく答えます」
「以前にも同じ検査をしました」
「しかし、時計を示してこの名前をいってくださいとたずねると、眼鏡ですかと答えました。腕――とこちらがヒントを与えると、ウデメガネですか、と、意味の通じない言葉で返します」
「ああ……」
「処方箋を薬局に持っていかなかったり、来院の予約をしなかったりということが何度かあったということでしたが、これも、言語による指示が理解できなかったのだと思われます」
「はい」
「ほかに見られる症状としては――認知症の患者さんが近所を徘徊するなどの事例は聞いたことがあるかもしれませんが、前頭側頭型の場合は、目的もなくふらふらとさまようという感じじゃありません。判で押したように、決まった時間に、決まった場所に行きます」
「心当たりがあります」
おばもわたしと同様、公園への散歩を頭に思い浮かべたのだろう。
「なにより、この疾患の場合、いちばん顕著であるのは人格の変化でしょうね。行動障害型という呼び名があるのですが、急に人が変わったように、抑制が外れ、自分勝手な行動をとるようになります。今後は、こうした人格障害に加えて、先ほども申し上げましたような、言葉が通じない場面が増えることが予想されます。行動障害や言語障害にもタイプがありますが、それらが合併症状としてあらわれるケースもままあります。いずれにせよ、結果、患者さんとのコミュニケーションはさらに困難となっていきます。このことは覚えておいてください」
おばは肩を落とし、額に手をやった。
「しばらくは自宅で療養をつづけていただくことになります。しかし、いずれそれも困難になっていくでしょう。ご家族でよく話し合ってください」
おばが声を出さず、ただ深くうなずく。そのほほに涙が伝うのが見えた。
そのあとは生活上注意すべきことなど、こまごまとしたことを聞かされた。
医師の話を聞く限りでは、物忘れに対処するためといっておばが行動のチェックリストを作ったり、しつこいくらいに繰り返して祖母にやるべきことの説明をしたりといったことは、どうやら的外れであったらしい。これからのことを思うと、その困難さにめまいすら覚えそうになる。
話が終わり、おじとおばが椅子から立ち上がろうとしたとき、わたしはいった。
「あの、最後に聞きたいことがあるんですが」
「侑希?」泣いていたために鼻のあたりを真っ赤にしたおばが、驚いた顔で振り返った。
「人が変わってしまう症状のほうが顕著で、物忘れはさほどではないということでしたけど、古い記憶とかは、じゃあ、忘れないものですか」
「古いとは?」
「二十年近く前の記憶は」
「どうでしょうね。少なくとも病状の初期には保持されていると思います」
「ありがとうございました」
この娘はいったいなにをいい出したのか、と思っているのだろう。頭を下げるわたしを、おじとおばは奇異な目で見ていた。
4
「侑希」
おじに名を呼ばれて、わたしは顔を上げた。侑希。有子の有の字をもらい受けた名前。そして、洋希(ひろき)の希をもらい受けた名前。
目の前の男性は、写真で見知った姿よりもずっと線が細く見えた。まだ五十を少しこえたばかりのはずだ。
「侑希が寂しい思いをしていないようで、ほんとうに良かった。心からお礼を申し上げます」
「お礼などは不要です」おじが頭を下げる。おばも言葉につまったのか、とりあえず頭を下げてみせた。わたしもつられた。
父は、娘に会うためにせいいっぱい身だしなみを整えたのだろう。パンツもシャツもブレザーも、クリーニングに出したばかりに見えた。申し訳ないとは思うが、彼のことを父だと考えるのは極めて難しい。三島(みしま)洋希さんである。心の中でその名をつぶやいてみるが、まったく落ち着かない。
三島侑希。中学生になったばかりのころ、わたしは紙にその名前を書いてみたことがある。名字と名前のバランスが悪く、しっくりこないと思った。どう考えても山口侑希のほうがいい。姓名判断のサイトで調べてもみた。三島姓と山口姓のどちらとも、流派によって大吉だったり大凶だったりしたので、頭を抱えた。わたしはそれからなにか悪いことをしたかのような気になって、おばに決して見つからないようにその紙を細かくちぎって捨てた。
父は――しっくりこないにせよ、さすがに三島さんと呼ぶのは気が引ける――その後、独身のままだったようだ。
再婚して、あらためてわたしを引き取るということは考えなかったのだろうか。不意にそう思ってから、父のかたくなそうな顔つきを見る。
おそらく我が家の場合はそうはならなかっただろうが、あらためて引き取るなどとなれば、世間では裁判沙汰となってもおかしくない。おじとおばがその責任感ゆえにわたしのことを養子にしたいと希望したのは、結果的にはということだが、父にとってはやはり子を奪い取られることに等しかったのかもしれない。
老舗のホテルのティールームで、ぎこちない世間話がつづく。それにしても、落ち着かない。
窓の外では、午後の空にトンボが飛び交っていた。
敷地の一角に遅咲きのコスモスの花壇があった。植え替えの最中だったのだろうか、地面に刺した竹のあいだにビニール紐が張り渡されていた。中に入るなということらしい。
そのビニール紐がやわらかな陽に照らされている様は、風に吹かれて揺れていることもあって、まるで、それ自体がきらきらと輝き、波打っているように見えた。そのビニール紐につなぎトンボが一組、また一組とやってきては止まっていた。ちょん、ちょんと、ビニール紐におしりをくっつけている。
わたしは不意に祖母がスーパーマーケットで万引き騒ぎを起こした日のことを思い出し、トンボたちから目を離せなかった。
あのとき、つながったトンボはガラスの上に止まっていた。あれは産卵のためだったのだ。トンボは水に卵を産み付ける。だから、きらきらと、鏡のように光るガラスを水面だと思い込んで、卵を産み付けようとしていたのだ。いまもトンボたちは、ビニール紐の上で産卵しようとしている。その卵はきっとかえらないのだが。
そこに自分の境遇を重ねるほどわたしは感傷的でも独善的な人間でもないつもりだ。
ただ、こういうことだ。鏡は水で、水は鏡。どんなことだって、表面に見える以外の理由があるものだ。
「わたしもそろそろ、突然病に倒れることを考えなければならない年齢になりつつあります」そういってから父はつけ加えた。「誤解なさらないでほしいのですが、侑希に迷惑をかけるようなことは、むろんしないつもりです。ただ、なんといいますか、侑希が会ってくれて、いまはもう、これで十分という気持ちです」
父は深々と頭を下げ、わたしに詫びた。わたしはというと、ただとまどうばかりだった。というか、勝手だ、とさえ思った。内緒だが。
*
わたしが身構えていたよりもずっと平穏無事に実父との面会は終わった。年に何度かは今日のように顔をあわせましょうという、なんとも微妙な提案がどちらからともなく出されて合意された。
それよりも、祖母のことだ。
病状の進行は、やがて祖母に周囲の人間との軋轢を生じさせた。決してきれいごとですまされるわけではない日々がつづいた。祖母に残された時間がさほど長くないことは家族の誰もがわかっていた。肉体的に、という意味ではない。だからこそよけいにつらい。
ぼや騒ぎを起こして以来、祖母からはライターとろうそく、線香が取り上げられた。ただし、ないと祖母が文句をいうので、代わりにろうそくの形をした電灯を購入した。
祖母が焼こうとした母のブリーフケースは、けっきょくわたしの部屋に保管することになった。中のものをひとつひとつ取り出して、おばは損傷状態を確認した。「たぶん、焼け焦げてしまったものはないと思うけれど」と、おばはさみしそうにいった。
その日わたしは、自室で、母のブリーフケースの中身を手にとってながめていた。なんとなくその気になれず、これまではなるべく触れないようにしていたものだ。
わたしは六十ページほどの小冊子を手にとった。白血病のハンドブックで、裏には武田病院の名称や住所のハンコが押されていた。どこの病院でも配布されるものなのだろう。母の荷物の中には、まったく同じものがもう一冊あって、そちらは市立病院と印字されていた。
市立病院のハンドブックは折り目ひとつないが、武田病院のほうは、赤いボールペンで線が引かれ、第一章から終章まで、ところどころ、ページの角が折られていた。抗がん剤による治療とその副作用について線を引いたのは、母だろうか。自分の病気を知らされて、なにを思ったのだろうか。やりきれない。
父との会食のあと、「この機会に」と、おじとおばはわたしに母の貯金や生命保険の記録を見せた。
「成人したら、あなたが自分で管理しなさい」
その記録は詳細だった。ふつうの家庭ならここまで詳細なものを残してはいないだろうと思うくらいに。わたしが養子だから、しっかりしておきたかったということなのだろう。生命保険の受け取り手続き(受取人は父だ)に必要な死亡診断書のコピーもあった。
そこには発症から亡くなるまでの過程が記録されていた。硬膜下出血があったのは市立病院の転送直後、九月十七日の午後四時五十分。亡くなったのは十八日の午後十一時十六分。死因は脳ヘルニア。
素っ気なく事実だけが記録されている殴り書きのような文字からは、母の人生を読み取ることは難しい。
先日、父と話した際、おじやおばが気を遣って少し席を外してくれるタイミングがあった。そのとき、父は、もう一度わたしに頭を下げた。
「すまなかった」というのは勝手な言葉だと思う。それで父は罪をあがなった気になり(罪があればの話だが)、少しでも心が穏やかになる。けれどもわたしは?
父はその場で、母に対しても謝罪の態度をあらわした。
父には悔やんでいることがあった。十七日の午前中、多忙のために母からの電話に出られなかったことだ。
精密検査の結果は午後早くに出ると聞いていた。
白血病の疑いはあったが正式には診断は下りていなかった。確定次第、すぐに転送の予定だったようだ。たぶん母は、結果を待つあいだ不安で、父に電話をかけたのだ。父はその電話に出なかった。
午後三時近く、再び着信があった。出てみると祖母で、結果はまだはっきりしておらず、母は追加の検査をしている最中だという。
聞いていた話とは違う。どこか緊急性が感じられた。はたして、それから一時間後に電話をしたときには、どうしてもつながらない。武田病院に直接電話をするとやはり白血病との診断で、転送をしたのちだった。市立病院に駆けつけると、すでに母は脳出血でICUに入っていた。
つまり、父はその日、母と会話をする最後のチャンスを逃したのだ。
むろん、それが最後のチャンスだったとは、誰にもわからないことだ。
父によると、家族の待機室にはその日仕事が休みだったおじがおり、祖母は眠っていたそうだ。母の脳出血の報を耳にして興奮し、鎮静剤を飲んだのだった。おばがわたしを連れて市立病院に到着したのは父のあとだったが、父は、わたしを見るなり泣いたという。
「あんまり写真、残っていないんだな」
両親のつきあっていたころの写真は、わずかな枚数があるだけだった。わざわざプリントしなかったということなのだろうか。SDカードの場合は、紛失してしまえば思い出はまとめて失われる。
というよりも、思い出というのは、そのとき限りのものなのだろう。
天が下のすべての事には季節があり、すべてのわざには時がある、というわけだ。
わたしは気まぐれにスマートフォンで、その、聖書の一節を検索した。
「天が下のすべての事には季節があり、すべてのわざには時がある。生るるに時があり、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、殺すに時があり、いやすに時があり……」
まだまだつづく。
「愛するに時があり、憎むに時があり、戦うに時があり、和らぐに時がある」
わたしはため息をつく。
「神のなされることは皆その時にかなって美しい」
*
その日をきっかけに、わたしはひどく落ち込んだ。疑心暗鬼になることを止められなかった。
気づかなければ良かった、とも思った。
*
雪が降った。十一月に入ってまもなくのことだ。
その日、おばとわたしは家のそばの公園を歩いていた。晴れているのに気温は低い。
葉を落とした公園樹が広がる青空に映えている。みぞれめいた湿った雪が芝生を覆い、光の粒が波打つように見える。見た目はきれいだが、ひときわ強い風が吹くと、肌に突き刺さるような寒さを感じた。
「ねえ、話しておきたいことがあるんだけれど」
「進路のこと?」
わたしには、おばの態度が卑怯に見えた。
たぶん、わたしがこのところなにをかぎまわっていたのか、こうして散歩をしようとおばを誘ったのはなぜか、うすうすは察しているはずだ。
それでいて、進路のことなどと口にするのはずるいと思った。そのせいだろうか、少しきつい口調になったかもしれない。
「有子さんって浮気していた? お母さん、そのこと知ってた?」
「急になにをいい出すの、この子は」
声音でわかった。これは、おばの機嫌が悪いときの声だ。やはり図星なのか。
「わたし、むかし、父さん――三島さんが浮気していたんじゃないかって疑ったことがあった。それで、有子母さんが死んだあと、わたしを捨てて、べつの女の人と幸せに暮らしているんだろうって」思わずわたしは母のことを「有子さん」ではなく、むかしのように母さんと呼んだ。だが構うものか、そのままつづけた。「そうじゃなかった。浮気していたのは有子母さんのほう。違う?」
「違う」
「わたししか知らないことを先にいっておく。三島さんから聞いたの。有子母さんが亡くなった日、話せなかったことを、三島さんは後悔していた。わたしに謝った」
かいつまんで、当日の時系列につきわたしはおばに説明をして、それから、
「おかしいと思ったのは二冊ある白血病のハンドブックだった。一冊は武田病院のもの。もう一冊は市立病院のもの。武田病院のほうは読まれていて、何カ所か、ドッグイヤーがあった。あ、ドッグイヤーっていうのはしおり代わりに本のページを折り曲げることで、形が犬の耳に似ているからそういう名前がついているの。あとはボールペンで線が引かれてもいた。市立病院のほうは、ほぼ新品。変でしょう?」
「変?」
「まず、ハンドブックを誰かが読んだのは、たぶん、有子母さんが脳出血を起こす前。市立病院に三島さんが到着したあとは、もうそれどころじゃなかったはず。白血病の抗がん剤治療とその副作用とかに赤線が引いてあったけど、だって脳出血でICUだもの、そのときには、そういう心配は飛び越えているとしか思えない。
たぶん、武田病院で受け取ったハンドブックは、転送の際には入院荷物の中にしまわれていたと思う。そのあとは誰が手にとるにせよ、読むなら市立病院でもらったハンドブックのほうでしょ」
「そんなの、そうとは限らない」
「三島さんが到着した時点で市立病院にいたのはお父さんとおばあちゃん。おばあちゃんは興奮して鎮静剤を飲むくらい、パニック状態だった。その時点でハンドブックを読んだとしたら、お父さんだよね。それじゃ、お父さんは、自分のものじゃないハンドブックにボールペンでラインを引いて、ページの角を折ったということ? ふつうに考えて、わりと抵抗があると思うよ?」
「ちょっと待って。そんなに早口でまくしたてないで」
「実は、いまいった、有子母さんがもらったハンドブックのページに他人が折り目をつけることへの違和感っていうのは、例外がある。わたしの感覚なら、夫婦か血のつながりのある人間なら、そうしてもおかしくない。三島さんにその時間はなかっただろうけど。
じゃあハンドブックに目を通したのはおばあちゃんかどうかだけど、そこは問題じゃない。それよりもハンドブックのアリバイの話」
「どういうこと?」
「午後三時、追加の検査の最中だとおばあちゃんは三島さんにいった。午後四時には、すでに転送。そして、午後四時五十分には、硬膜下出血。診断が確定する前に白血病のハンドブックを患者に渡す病院があるとは思えない。でも、追加検査が終わったあとで診断が確定したのなら、のんきにハンドブックを読んでいるヒマがあるようには見えない。これ六十ページ読むのって、けっこうだよ?
病院の証言や死亡診断書の記載を疑っても始まらないから、この時間的な矛盾については、おばあちゃんが三島さんにいった午後三時の追加検査が嘘だったと思うしかない。白血病の診断は、たぶん、予定通りに午後の早い時間に出たんだと思う。それで、転送の準備が整うまでの二時間か三時間のあいだに、ハンドブックは有子母さんかおばあちゃん、ふたりのどちらかによって読まれた。これならつじつまはあう。
けど、そもそもなんでおばあちゃんはこんな嘘をいったんだろう?
お医者さんがいっていた。認知症といっても、前頭側頭型だから、初期段階ではそれほど記憶力は衰えていないって。でもわたしは、スーパーでおまんじゅうを食べてしまったのも、会話の受け答えがおかしいのも、病院での検査の際に返事をしなかったのも、なにもかも、おかしな行動はぜんぶ認知症のせいだって思った」
「だってわたしたちは医者じゃないもの。細かな違いなんてわかるわけがない」
「そう。だから、わたしだけじゃない。家族みんなが、おばあちゃんは認知症になったって単純に考えた。それで、検査のために病院にも連れて行った。だったら、おばあちゃん本人だって、実際はそうじゃないのに、自分からは記憶力が急速に失われたんだって考えたっておかしくない。
わたしは、おばあちゃんがこんなふうに思ったんじゃないかと想像してみた。なにかすごくすごく、忘れがたい、つらい、後悔があった。それについてはずっと隠してきた。でも自分は認知症になってしまった。これからも隠し通さなければならないのに。それがなんだったのかはもう思い出せないけれど、いまのうちに、人に見られては困るものを、処分しよう」
「あっ」
「だから、それらしく思える物――有子母さんの荷物を捨てたり、水浸しにして台無しにしたり、さらには火をつけて燃やそうとした。ぜんぶ止められたけれど。おばあちゃんが処分しようとしたのは、手帳? 日記? 写真? もうとっくに処分済みなのか、最初からそんなものはなかったのか、とにかく、べつにいまごろあわてて処分する必要はなかった。そのことは、お母さんがブリーフケースの中身を点検してから、わたしにそれをくれたことからもわかる。その中にはわたしに見せたら困るものは、入っていなかった。そういうことでしょう?」
「侑希、話を聞いて。たぶんあなたは誤解している」
おばはどことなく脅えを含んだような、こちらをとがめるような目線を向けた。
「手帳や写真を処分しようとしたことからは、有子母さんが浮気相手と会っていたというのがなんとなく妥当な推論に思える。おばあちゃんがそうまでして隠そうとした理由がほかに思い当たらないから。
有子母さんに白血病の診断が下りたとき、その浮気相手に電話をかけるというのはありそう。三島さんには連絡がつかなかったわけだし。それで、おばあちゃんは、突然仕事の都合をつけて病院にやってきたりしないようにと、三島さんを遠ざけるための嘘をついた。有子母さんのアリバイ作りをした。
この数ヶ月、おばあちゃんは有子母さんを殺したのは自分だとか、それを母さんが責めるんだとかいい出した。いままで、十何年も黙っていたのに、病気のせいで歯止めがきかなくなって、後悔と罪の意識を口に出さずにはいられなくなってしまった。
これに気づいたとき、ああ、父さんは――三島さんは、それでわたしを捨てて出て行ったんだって思った。どのていどわかっていたか知らないけれど。なんとなく感づいていたんだろうね。こうなってくると、わたしが三島さんの娘っていうのも怪しくない?」
養子が実両親を知る権利につき、法律では明確に定められてはいない。だから、それと知らされていない場合、熱心にルーツ探しをおこなう養子もいるとは聞いている。それを補助する団体もあるようだ。おそらくはそこに答えがないにしても、人は「私は誰なのか」という不安から逃れられない生き物なのだと、いまさら知る思いだった。
「三島さんに会ったとき、わたしが成人したときの、お金の受け取りの話とか、したよね。DNA鑑定とかしたほうがいいのかな? 法律のことは調べていないけど、ほんとうの親子じゃなくても、お金を受け取る権利、あるのかな?」
おばはまくしたてるわたしを見て哀しそうな顔をしていた。「侑希!」それから、怒鳴りつけた。感情のままに。そのことに、わたしは少し驚いていた。
「お願いだから話を聞いて。少なくとも、浮気ではないのよ。有子が高梨(たかなし)さんとつきあっていたのは、三島さんとの関係が始まる何年も前のことだから」
「有子母さんが病室でその高梨さんと会おうとしたっていうのはあたっていた?」
「それはそう。――有子は、まずは三島さんとあなたのことを第一に考えたんだと思うわよ。でも、自分の残り時間が少ないかもしれないって思って、三島さんにも電話がつながらなくて。そんなとき、高梨さんに電話をしたこと。そうして、高梨さんが人目をはばからず、急いで駆けつけてしまったこと、それってそんなに悪いこと? わたしにはふたりを責められない」
「有子母さんに後ろめたいことがあったから、おばあちゃんにアリバイ作りをさせたんでしょう?」
「高梨さんは、なにもいわずタクシーで駆けつけたのよ。三島さんが知ったら、それは面白くないでしょうね。だから妙に気を回した母さんが、嘘の電話をかけた。あとで母さんに聞いたけれど、ふたりは二十分も話していないわ。もう一度聞くけれど、それってそんなに悪いこと? それとも、そもそもこんなこといっても信じてもらえない? それで気が済むなら、DNA検査でもなんでもして」
「…………」
「誰だって、あんなことになるとは思いもよらなかった。結果的に、脳出血の直前に高梨さんは有子と話せたけれど、三島さんはそうでなかった。有子も、あんなことになる前にあなたを抱きたかったに違いない。でも、後悔すらできなくなった。そうしたことを、お母さんは、ぜんぶ、自分のせいだって思い込むことから逃れられなかった。飛躍もはなはだしいんだけれど」
「高梨さんというのは、いま、どこでなにをしているの?」
「知らない。一度も連絡をとっていない。向こうもとる気はないと思う。なにもかもを飲み込んでどうにか生きているのだと思うけれど、もうわたしたちとは関わりのない人よ。十八歳になったばかりのあなたが有子のことをどう思うかわからない。わたしはもう、自分が十八のころにどんなことを感じていたか、すっかり忘れてしまった。いまのわたしには、そういうことだってあるよとしかいえない」
おばはわたしのそばから離れた。
長い時間、おばは黙っていた。
それから、いった。
「わたしにあやまってほしい? あやまる機会がずっとなかったから、いままでの十七年間のこと、まとめてあやまってもいいけれど」さみしそうに笑う。「後悔しない生き方なんてない。この年になると、自分の人生が無意味に感じられてならないものよ。でも、振り返ると、不思議なことに、良かったことのほうを思い出す」
それから、おばはなにかをいいかけて、口を閉じた。ゆっくりと首を振って、ほほえむと、わたしの名を呼んだ。いまのわたしには受け止めづらい名前を。
「侑希、話のつづきはあとで聞くわ。あなたには考える時間はまだある。わたしはもう病院に行かなきゃ。――ねえ、あなたはどう思う? もうお母さんに、話、通じないかな。わたしのしていること、無意味なのかな。でも、あさってより明日。明日よりきょうは、それでもまだ、伝わるようにも思う。そうじゃない? だからわたしはもう行く。侑希はどうする? 行く?」
わたしはおばを見返した。
参考文献
佐藤浩一・越智啓太・下島裕美『自伝的記憶の心理学』(2008)北大路書房
田邉敬貴『痴呆の症候学』医学書院(2008)
遠藤英俊『痴呆性高齢者のクリニカルパス』(2004)日総研出版
日本聖書協会『口語旧約聖書』(1955)
![]()
松本寛大(まつもと・かんだい)
一九七一年札幌市生まれ。二〇〇九年、島田荘司選・第一回ばらのまち福山ミステリー文学新人賞を受賞した『玻璃の家』(講談社)でデビュー。他の著書に『妖精の墓標』(講談社ノベルス)など。探偵小説研究会会員。本格ミステリ作家クラブ会員。ホラーを中心に映画・小説の評論も手がける。評論分野の著書(共著)に『北の想像力』(寿郎社)、『現代北海道文学論』(藤田印刷エクセレントブックス)がある。また、「クトゥルフ神話TRPG」にも長く係わり、ソースブック等に寄稿。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
