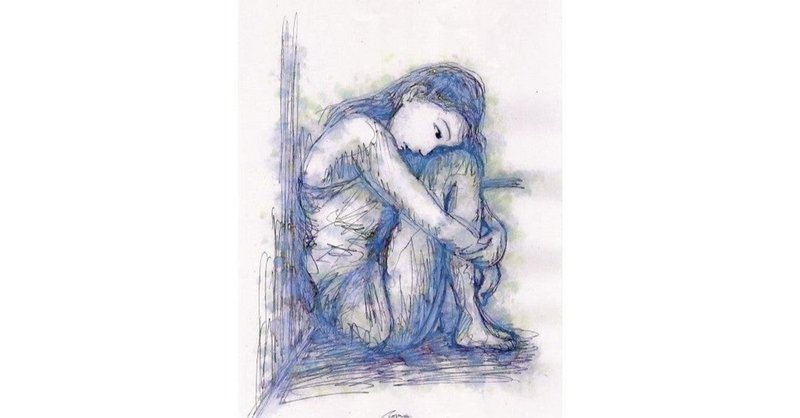
個性強要社会と変人
こんにちは。
学部長の谷村です。
「個性を大事に」という言葉はあきるほど聞かされてきていますよね。
現代はもはや個性強要社会といえるかもしれません。
今回はこの個性と変人について考えていきたいと思います。
就職活動においても、学習指導要領においても、「個性の尊重」「個性をアピール」と耳にたこができるほど言われてきたかと思う。
この個性とは何なんだろうか?
広辞苑によると、個性とは「①個人に具わり、他の人とはちがう、その個人にしかない性格・性質。②個物または個体に特有な特徴あるいは性格。」とのことだ。
ここで興味深いのは、「~その個人しかない」とか、「特有な~」といったように、個性を絶対的で限定的な存在として捉えていることだ。
ちなみに、個性というのはすべての人間に具わっているのだろうか?
個人的には具わっているのだろ思う。一人として同じ人間はいないからだ。姿形といった外見も、価値観などの内面も。
では、変人とはどう違うか。個性が絶対的な存在であるのに対して、変人は相対的な存在だ。「この人は変人or変人ではない」と判断する人がいてはじめて変人は定義できる。そして、その判断する人の主観において、普通からずれている人を変人と判断する。
普通からのズレを考える時、おそらく同心円状に広がる世界がみえているはずだ。中心に行けば行くほど普通。周縁へと外れていけば行くほど変人だ。そして、人によって普通の幅が狭かったり、広かったりする。
人はみな個性を持っているので、それぞれの判断する人の同心円状の様々な地点に位置づけられるのだが、特に大きく中心からずれている人が変人と認定される。
ちなみに、個性は全員持っているにも関わらず、個性を強要する社会になっているとはどういうことなのだろうか?
仮説は2つだ。1つ目は、「人々は持っている個性を隠しているので、それを表現するように求められている。」ということだ。
同調圧力が強いと言われるこの社会の中で、人々は自らの普通を中心とした同心円を描いている。だが、それだけではなく、周囲の人々の様子を気にしながら、周囲の人々が持つ同心円を予想し、自分をその中の普通の枠内に納めることで心理的安全性を保とうと努力している。
それ自体は人間の生存本能の一つだろうし、何も悪いことではない。だが、以前の回でも指摘したが、これが過度になることで自らのアイデンティティが消滅し、自己肯定感の低下など精神的悪影響を及ぼす。社会にとっても、人々が単純化する方向に収斂していくことで、多様性が失われイノベーションなどが起きず閉塞状況に陥る。そのため、ある程度は個性を解放することが重要視されるのだ。
2つ目は、「そもそも本来的な個性が求められているのではなく、わかりやすい個性が求められている。」ということだ。これは、特に閉塞した社会状況を背景としていたり、イノベーションの喚起を意図していたりする。だが、わかりやすい個性(つまり、その社会の普通から大きくずれた個性・変人性)は意図して身につけるものではない。人々が個性を発揮した中でたまたまその個性がその社会の普通から大きくずれており、かつ価値があると認定された時にここで求められている個性になる。これは完全に運次第なのである。
そうにも関わらずに、無理に変人性を身につけようとすることで起きるのは、以前別の回でも指摘したが、失敗した戦略的変人に陥るのみだ。
空虚で無理している感満載の変人アピール。就活での「盛ったエピソード」やいわゆる「意識高い系」と揶揄される武勇伝を語る若者のような状況だ。
私たちが大事にしている個性とは何なのか。無駄な命がないのと同様に、個性は、それがその時代に突飛なものだから評価されるとか、わかりやすい個性だから評価されるとかそういうことではない。
個性を持つ人間の存在そのものを楽しむという姿勢でありたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
