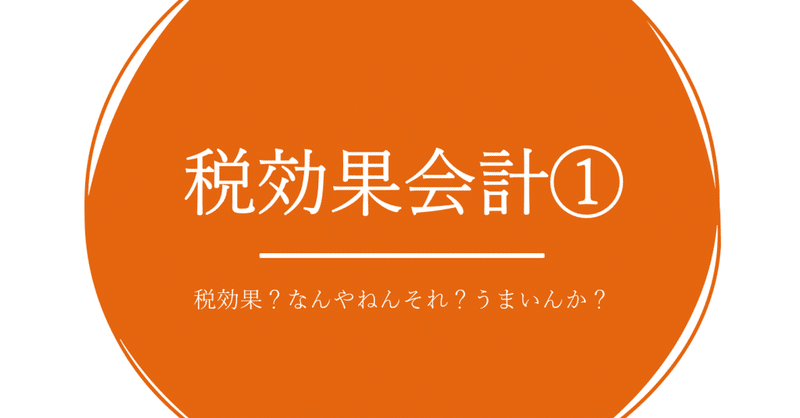
税効果会計①-税効果?なんやねんそれ?うまいんか?
こんにちは、kkです!
今回から4回に分けて、財務会計の「税効果会計」の理論を解説していきます!
自分はけっこう税効果会計はおもしろいな、と思っているんですけど、友達がヒイヒイ言ってるので、そんな方の力になれたら嬉しいです!
(あと、大原の第3回短答対策演習の範囲でもあるんでね!)
それでは、さっそく第1回スタートです!!
そもそも税効果会計ってなんすか?
簡単にこたえると
「企業が行う企業会計」と「法律に則って行う税務会計」のズレを調整する会計のこと
って感じです。 自分で言ってても難しいな、っておもいます笑
じゃー、なぜ税効果会計をするのか、その説明から始めたいとおもいます!
なんで税効果会計をやるの?
この説明をする前に、まずは「企業会計(財務会計)」と「税務会計」の目的の違いについて、軽くふれておきます。
企業会計・・・企業の財政状態や経営成績などを、利害関係者に情報提供する
税務会計・・・法律にもとづいて、公正な課税所得を計算する
両者は、上のように目的が異なります。
なので、たいていの場合、収益(益金)と費用(損金)を認識するタイミングや、資産と負債の額にズレが生じます。
ということは、税効果会計を適用しないと
税務で計算した利益に課される「法人税等の額」と企業会計で計算された「税引前当期純利益」が期間的に対応しません。
また、将来の法人税等の支払額に対する影響が表示されません。
なので「法人税等の額」と「税引前当期純利益」を合理的に対応させる目的で、税効果会計を適用することになります!

ここで出てきた、「繰延税金資産」と「繰延税金負債」について説明すると、
繰延税金資産・・・将来の法人税等の支払額を減額する効果をもつ資産
繰延税金負債・・・将来の法人税等の支払額を増額する効果をもつ負債
これは、税効果の話をするうえで、最低限知っておいてほしい知識です!
法人税等の支払額を増減する効果、ですからね!?
いつ税効果会計をやるの?
税効果会計の方法には、「資産負債法」と「繰延法」の2つの考え方があります。
〈資産負債法〉
会計上と税務上で資産・負債の額にズレあり &
そのズレが解消する年度の「課税所得を減額or増額する効果」をもつならば、
一時差異が生じた年度に、ズレの分だけ繰延税金資産(負債)を計上する方法
税率は「一時差異が解消する年度のもの」を使う
→繰延税金資産の資産性、繰延税金負債の負債性を重視する
(=将来の税金の支払額にあたえる影響を重視)
〈繰延法〉
会計上と税務上で収益・費用の額にズレがあるならば、
期間差異が生じた年度に、ズレの分だけ繰延税金資産(負債)を計上する方法
税率は「期間差異が生じた年度のもの」を使う
→期間差異が発生した年度の、「税引前当期純利益」と「法人税等の額」の対応を重視する
ここで、差異の種類についてふれておきます。
![Book1 (version 1)[自動回復済み] - Excel 2020_11_24 21_20_42](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/39479255/picture_pc_3e0853982f8e90b55deaaa00439a3a8a.png?width=800)
期間差異とは、会計上と税務上の収益・費用の額のズレのうち、将来解消されるもの
一時差異とは、「期間差異」と「評価差額」を合わせたもの
(⇒会計上と税務上の資産・負債の額のズレから認識される)
※今回は繰越欠損金にはふれません、また機会があったらその時にします
以上から
繰延法でも、資産負債法でも、期間差異については税効果を適用することになります。
![Book1 (version 1)[自動回復済み] - Excel 2020_11_24 21_49_35](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/39482209/picture_pc_688c8d086428586e81586442be8b2839.png?width=800)
この例での、繰延税金資産は「将来の税金支払額への影響をB/Sに表示」しており、資産負債法の考え方と整合します。
一方、法人税等調整額は「当期のP/Lに計上される税引前当期純利益と法人税等の額を対応」させており、繰延法の考え方と整合します。
このように「一時差異」と「期間差異」が同時に発生するときは、資産負債法と繰延法のどちらの考え方でも、税効果を適用します!
(期間差異が発生したら、必ず一時差異も発生する)
なら、期間差異は発生せず、評価差額(一時差異)が発生するときはどうなるでしょう?
「期間差異が発生しない」ということは、
「会計上と税務上で収益・費用の額はズレていない」ということです。
なので、繰延法の考え方では税効果は適用しません!
しかし、みなさんは計算での知識があるので「評価差額がでたときも税効果やってるやろ?」と思っているはずです。
そのとおり、この場合でも税効果は適用するんです!
なぜか?
それは、「税効果会計に係る会計基準」で、資産負債法が採用されているからです!
なので、評価差額が生じて、会計上と税務上の資産・負債の額にズレが生じたら、税効果会計を適用するんです!
![Book1 (version 1)[自動回復済み] - Excel 2020_11_24 23_05_58](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/39489894/picture_pc_e117646b15696109e6dcb73dd466c532.png?width=800)
よって、この繰延税金負債の「将来の税金の支払額が増える」という効果がB/Sに反映されることになります。
ちなみに、この場合の仕訳で法人税等調整額が出てこない理由は大丈夫ですか?
この場合は、期間差異がでていない = 会計上と税務上の収益・費用のズレは出ていないんです。
なら、会計上と税務上で利益の額はかわらないし、そこから計算される税金の額もかわりません。
それなのに、法人税等調整額を計上して、わざわざ金額をズラすようなことをして何してんの?っていうわけです!
一時差異のあれこれ
さいごに、いままで散々でてきた「一時差異」について、少し説明します!
さきほど、「一時差異は会計上と税務上の資産・負債の額のズレから認識される」といいました。
この一時差異はさらに次の2つに分けるとこができます。
将来減算一時差異・・・差異が解消されるとき、その期の課税所得を減額する効果をもつもの
⇒この差異にかかる税金の額を、繰延税金資産として計上
将来加算一時差異・・・差異が解消されるとき、その期の課税所得を増額する効果をもつもの
⇒この差異にかかる税金の額を、繰延税金負債として計上
いいですか、一時差異は課税所得を増減額するんですよ!!
そして、繰延税金資産(負債)は税金の支払額を増減額するんです!!
ここを論文であべこべに書いたら、おそらく点はもらえません!!
要注意です!!
まとめ
以上で今回はおわりです!
パート1は計算処理の背景となるような話が多かったですね~
資産負債法と繰延法は、税効果の考え方の大元なので、しっかり理解しておきましょうね!
連結の税効果の話でも、また登場しますよ!
ちょっと最後のほうがごちゃごちゃっとしてしまったので、わかりにくい解説になってしまったかもしれません🙇🏻♂️
次回パート2は「繰延税金資産の資産性」についてです!
これに関しては、今回よりも説明がうまくいきそうな感じがしているので、期待していてください!笑
さいごまでよんでくださった方、本当にありがとうございます!
それではまた!!
