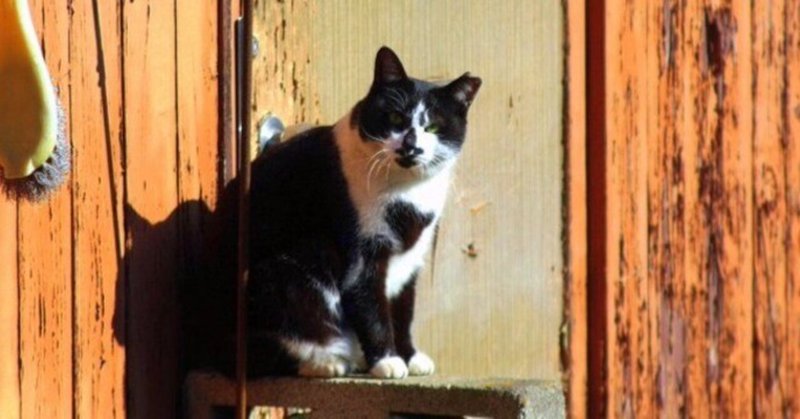
英語を喋るぞ!!
昨年01月26日から
小中学生への学習支援で得た知見を基に
色々書き始めて77回目です。
09月07日に「英語が喋れない!」という書き込みをしました。
その中で、およそ学校教育の中では取り上げられることのない
以下のような英語発音の特徴を取り上げました。
①音声変化(リエゾン):文章中の二語以上の単語がつながって発音される
➁連結(リンキング):単語と単語を連結して発音する
③脱落(リダクション):元々単語内にある音を発音しない
④同化(アシミレーション又はアソシエーション)
:音が繋がると発音を変え スペルとは異なる音に変化する
⑤弱形(イントネーション):文章の中で重要度が低い単語は弱く発音する
⑥抑揚(アクセント):特定の音節を他の音節より強く発音し強弱をつける
これらに慣れる事が
英語が喋れるようになる第一歩のような気がしています。
また、日本語の母音は5であるのに、英語では15あったり、
同じく日本語の子音は10なのに英語では22あるという、
微妙な発音の違いにも注意が必要です。
更に、英語は世界中で使われているため、
地域による特性が含まれています。
こうした英語環境に対し、全てを満足させることは
現実的には不可能のようです。
そこで、私の関わる学習支援では次のような方法を試行錯誤しています。
Wi-Fi環境と、PCと、生徒と同時に音が聞こえる機器が必要になります。
因みに、音響機器はヘッドフォンを改造して使っています。
①まず、ABCはエー・ビー・シーとは発音しないことから始めています。
具体的にはフォニックスを生徒と一緒に聞き一緒に発音練習をします。
できれば、手鏡で口の開き方と舌の使い方を、一緒に練習します。
よく使ってるYou-Tubeは以下のコンテンツです。
→https://www.youtube.com/watch?v=WUeYlbQMrFg
②発音方法に慣れてるのと並行し生徒の知っている英語の歌を聴きます。
その際、歌詞を画面表示してみると、
意外に知っている単語が多いことに気が付くでしょう。
よく使っているのは、SpotifyやYou-Tubeです。
③次第に、
アメリカ東海岸英語や西海岸英語
イギリス英語の歌を流すようにします。
こうした歌をマネをして歌うことで、実際の発音を体験してゆきます。
音声を聞きながらマネをして発音するシャドーイングという手法です。
④ある程度、聴き取れるようになり始めたら、
歌詞を聴き取り書き残す作業をします。
聴き取った英文を書きとるデクテーションという手法です。
このようにして生徒が自主的に英語に慣れる環境を作っています。
但し、コンテンツの利用は同時に再生するなど、
著作物の一次使用の範囲にしてください。
録画や録音をしたりすると、二次使用に当たるので、
著作権侵害になってしまいますのでご注意ください。
子どもたちの学習に関与している方々へ
大半の生徒にとって、数学の次に嫌いな科目が英語のようです。
それは数学の公式と同様に英語は記憶する科目だと誤解しているからです。
言葉はコミュニケーションツールです。
そのぶん、時代を反映し
地域によって 時代によって
少しづつ変化しています。
だから余計に
伝えにくい科目かもしれませんね。
でも、皆さんの働きかけ次第でなんとかなりそうです。
どうか よき手本として
また よき話し相手として ご活躍ください。
14.SEPT.2022.ARAI
