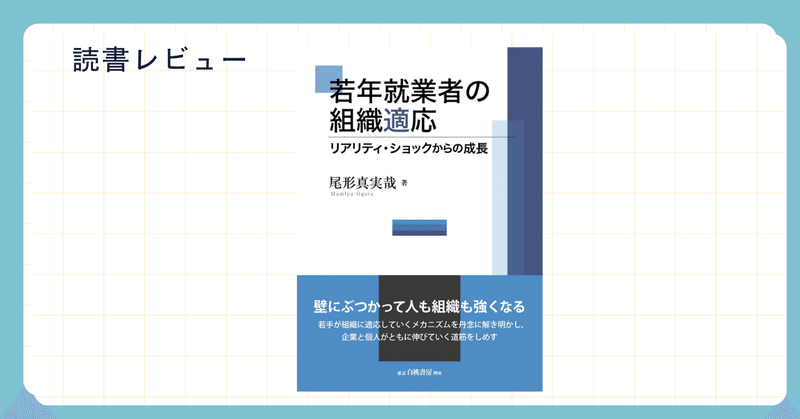
リアリティ・ショックとは何か~『若年就業者の組織適応』より#2~
こんにちは、紀藤です。さて先日より著書『若年就業者の組織適応』より、新入社員が組織になじむプロセスについて、学びを共有しております。
本日は第三章の「リアリティ・ショック」を中心にお伝えしたいと思います。それでは早速まいりましょう!
(前回のお話はこちら↓)
リアリティ・ショックとは
リアリティ・ショック。これは組織に参入した「最初の適応課題」として取り上げられるテーマとして有名です。その定義は、以下の通り。
リアリティ・ショックとは
「高い期待と実際の職務での失望させるような経験との衝突」(Hall, 1976)
「期待してたけど、実際ちゃうやん・・・」という失望が、リアリティ・ショックということですね。うーん、わかりやすいし、経験的にもよくわかります。
また、リアリティ・ショックは「未使用の潜在能力症候群(syndorome of unused potential)」を引き起こすとされています。これは、”潜在能力や才能が十分に発揮されず、その能力が無駄になっている状態”を意味する概念です。つまり、「自分の能力、全然使えている気がしない・・・」と感じてしまうわけですね。
そして、特にキャリア初期の新人の場合、自己イメージ・態度・大望・モチベーションの全てをネガティブな方向に大きく変化させてしまうそう。
そうした帰結として、(1)新人の辞職、(2)モチベーションの喪失と自己満足の学習、(3)キャリア初期に能力の不足部分を発見し損なう、(4)キャリア後期に必要となる価値観や態度とことなる価値観と態度の学習、などの否定的な結果に招くことになる(Schein, 1978)、と述べられています。
恐ろしや、リアリティ・ショック。
これは、受け入れ側もきちんと、考えなければならないと思わされますね。
リアリティ・ショックはなぜ発生するのか
さて、リアリティ・ショックはなぜ発生するのかですが、「入社前」と「入社後」のどちらもが関わっているといいます。
入社前は「予期的社会化段階」といいます。
まず、個人が持つ職業観(家族や友人、教育、メディアなどで作られたもの)で新人と言えども白紙の状態ではありません。”働くこと”についての考えができあがっているものです(職業的予期的社会化)
そうした個人に対して、組織が採用過程で「言ってたことと違う」とならないように、リアルな情報を伝えることを行います(組織的予期的社会化)。
そしてこれらの、個人の職業的予期的社会化と、組織的予期的社会化が合わさって(舌噛みそう・・・)、期待が形成されていくことになります。
「期待」の種類
ちなみに「入社前の期待」の分類として、以下のように示されていたのが興味深いものでした。
<入社前の期待の分類>
自己:自己の能力信頼の獲得
タスク:職務内容、多忙さ
職務環境:{会社}方向性、社風、
{職場}フットワークの軽さ、意思決定の迅速さ
{人間関係}関係の良好さ、受容
報酬:{内的報酬}自己成長:知的成長、精神的成長、技能的成長、自立
{外的報酬}給料、出世、出会い
リアリティ・ショック発生のメカニズム
そして、予期的社会化ステージで期待が形成され、その後、実際に組織に参入をしていく中で「期待してたけど、実際ちゃうやん・・・」というリアリティ・ショックが生まれていくことになります。
その流れが、著書にて図示されていました。以下ご紹介いたします。

リアリティ・ショックの実証研究
さて、そんなリアリティ・ショックについて、本書では実際に「リアリティ・ショックの多様性」を理解するための実証研究が行われており、その内容が非常に興味深いものでした。
まず、若年ホワイトカラー(入社1年目~3年目)を対象にインタビュー調査を行い、「実際にどのような対象に対して、リアリティ・ショックを感じているのか」を調べました。
すると、以下5つのリアリティ・ショックがあることがわかりました。
それが、「組織・仕事・他者能力・人間関係・評価」です。たとえば、「組織」でいえば会社の理念、会社の将来性、会社の雰囲気・社風、「仕事」でいえば仕事から得られる成長機会、仕事上与えられる自律性、仕事そのものなど16の項目でした。
そして、これらの項目に対して、探索的因子分析・確証的因子分析を行った結果、11の観測項目と4因子(同僚同期ショック、仕事ショック、評価ショック、組織ショック)にわかれたのでした。

リアリティ・ショックがもたらす影響
そして、本書においては、これらのリアリティ・ショックが、「組織適応」(職業社会化、文化的社会化、情緒的コミットメント、離職意思)にどのような影響を与えるのかを調査しました。
結果、「仕事ショック」「評価ショック」「組織ショック」は「情緒的コミットメントに負の影響を与える」こと、そして「離職意思を高める」ことがわかりました。

ポジティブ・サプライズの影響
ちなみに、続く第4章では「ポジティブ・サプライズ」というものが紹介されます。これは「良い意味で期待以上だった」という逆の意味でリアリティショックなのですが、これらの影響を実証研究として調べられています。
その結果、仕事から得られる達成感・成長機会・自律性という「仕事ポジティブ・サプライズ」や、職場の同僚・同期との人間関係という「対人関係サプライズ」や、上司や同僚・同期の能力という「他者能力サプライズ」、そして、昇進機会や自分自身の能力や適性という「キャリアポジティブ・サプライズ」の4つが見られました。
そして、「仕事ポジティブ・サプライズ」は、情緒的コミットメントを高め、「対人関係ポジティブ・サプライズ」は、文化的社会化と情緒的コミットメントを高めました。
一方、興味深かったのが、「他者能力ポジティブ・サプライズ」は、職業的社会化(=自分の仕事を上手くこなすうえでの技能や能力を身につけることなど)に”」負の影響があった”ということです。
周りの同僚・同期の能力が予想以上に高くなると、「こうならねば・・・」というプレッシャーを感じてしまい、知識習得が阻害されてしまう、というのが考えられるようです。(実に興味深いですが、わかる気がします。大学院入学当初もそんな感じだったなあ・・・(遠い目))
ちなみに、離職意思は下がるので、他者能力のポジティブは萎縮するかもしれないけど、残りたいという気持ちも高まる、非常に複雑な人間心理を表しているようで、興味深く感じました。

まとめ
今回は第3章のリアリティ・ショックについて、本書からの学びをまとめさせていただきました。改めて、こうした専門書ゆえに、その定義も明確で非常にわかりやすく勉強になりました。
さらっと読むのではなく、改めて自分で文字にしながらなぞると、非常に学びが深くなるな、と感じた次第です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
