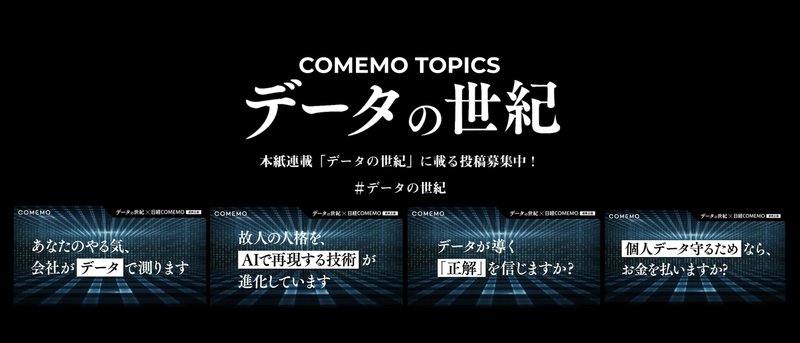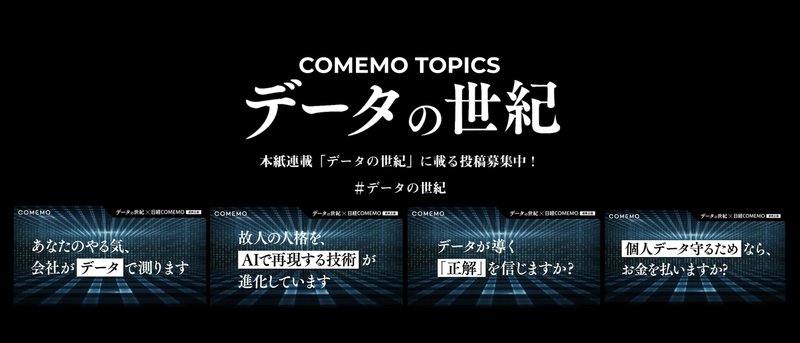HRテック?HRハック?日本型人事システムとマネジメント理論、HRテックの活用などについて考える
米国のギャラップ社が2017年に公表した従業員のエンゲージメント(仕事への熱意度)調査によれば、日本は「熱意あふれる社員」の割合が6%しかいないことが分かった。GAFA等の企業によるイノベーションが生まれる米国の32%と比べると大幅に低く、同社が調査した139カ国中132位と最下位クラスとなっている。
また、パーソル総合研究所が行ったアジア・太平洋地域14カ国を対象とした「はたらく意識」の調査結果では、日本は「勤務先以外での学習や自己研鑽」を実施していない者が46.3%とな