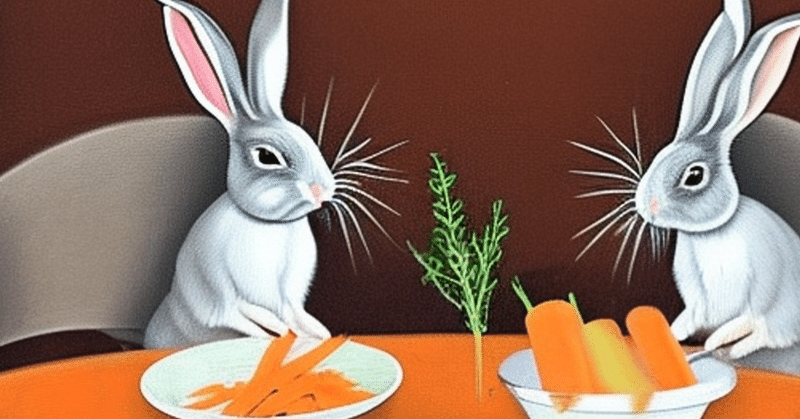
一世風靡した「関西グルメ1000店」がクリエーターのデビュー
大流行した女性誌、〈anan〉や〈non-no〉が「京都おんな一人旅」というような特集をして、独身女性が1人で京都に旅するのが流行り、雑誌片手に嵐山や嵯峨野を歩く女性が増えた。これに目を付けた大手出版社が地図に女性向の京料理やレストラン、中華料理、カフェ、喫茶店、甘党の店などの情報を集めて「関西グルメ1000店」という雑誌を発行することになり、わが社は京都を担当した。これがわたしのクリエーターデビュー作である。
チームメンバーが離脱、しかし全部をやりきった
京都が700店、奈良、大阪を入れると1,000店で、雑誌の名前の「関西グルメ1000店」となる。取材は5名がエリア決めて担当することになったが、それをわが社が統括する。取材から、記事の執筆、1店につき画像を1点添付する。得意先から提供されたリスト700店を取材する。ざっと一人が140件の取材、記事を書き、撮影し、画像としてレイアウトに入れる作業は膨大である。日程が厳しいので、2週間で取材を終える必要がある。スケジュールでは1日約10件の取材がノルマだ。そう説明すると2名が辞退し、わたしと中年の米田、アルバイトの1名が担当する。初日、アルバイトは取材に行き、根を上げた。クリエーター希望だった。わたしは咲く前にしおれる花はないと思っていたが、そうではないこともあると気づいた。
食い意地の張った性格が、足を引っ張った。
わたしの取材チームは、わたしと米田。知り合いの紹介で来た人物で、わたしよりもかなり年上で、不遜な態度が経験豊富に見せていた。驚いたことに、彼は異常に食い意地の張った人物だった。この仕事は一日10件の取材ノルマがあるが、わたしはノルマより多く取材しようと考えていた。米田はノルマのことを頭から外して、地図にどこでなにを食べる、ドリンクを飲む、というスケジュールを記入する。ある区画を20件選び、2人で分けてスタートするが、彼は飲み食いするから時間が長く、出てくるのが遅い。彼は食べるのが嫌になるほどにスローなのだ。わたしが終わってもまだ半分も終えてないので、わたしがその分をカバーしていく。この計算でいくと取材リストの700件のうち、7割程度はわたし一人が死ぬほど汗かきながらこなしたことになる。しかもわたしは、帰った後、メモの整理、記事を書き、写真をプリントしてデスクに渡す。そんなルーチンワークが一番大変なのに、米田はまるっきり関心なく、どこかにふらりと行ってしまう。原稿も書くが、恐ろしく遅くて絶対に間に合わない。それなのに、人には二人でやっていますと口癖のように言う。それをいつも見せられて唖然とした。彼はわたしより年上なのに頼りになるどころか、とんだ足手まといだった。客観性のない人間は、誰が処理したかも認識せず、何でも自分がやったと誤解すると知って愕然とした。
有名な小料理屋で「商人は裏口から入って」に唖然!
美しい白木の入り口を入ると、鰹と昆布の香りが出迎える。老舗の小料理として全国に知られた店。「あかん、あかん、商人は裏の勝手口から入ってて!」とおばさんに怒鳴られる。名刺を渡しながら自己紹介して取材の趣旨を説明するが、横柄な態度は変わらない。その人物はそこで働いているにすぎないのに、まるで会社のオーナー気取りのでかい態度である。『はい、はい、わかりましたよ。じゃあ、この店は、めちゃくちゃまずいと書いておきます!』と啖呵切って帰りたかった。しかし、それではクライアントである出版会社にクレームがいく。しかたないので作り笑いで「わかりました」と言って、勝手口にまわり、ものの3分で聞き取り、2分で内部と正面を撮影して取材を終えた。生涯でたった一度、「商人」と死語になった言い方をされた。しかしほとんどの店は、ただで宣伝してくれることを喜び、一口味見してくださいと、お菓子や佃煮などを小さな器で試食させてくれる。とても感じのいいオーナーもいて、丁寧に説明してくれたが、わたしは1件に15分~20分と決めてやっていた。スケジュールのことを考えると、早く終わるために早口になりがちだった。だんだん慣れるにしたがって心理的な余裕ができて無駄がなくなった。10日後にはわたしは1日に20件、25件の取材をこなし、記事を書くようになっていた。
印刷した雑誌をみて、クリエーターに
数か月後、「関西グルメ1000店」の制作ディレクターがオフィスに来て、段ボールに入った印刷物をドンとテーブルに並べた。「ああ、できたの‼」思わず感激の声を出していた。中をぺらぺら見ると、苦労が報われた。取材後の編集作業は莫大な業務だったが、印刷物になったものを見ると苦労を忘れ、すがすがしい気持ちになった。はじめてのクリエーター業務で、人がいかにあてにならないか、自分だけが頼りだということを痛感した。クリエーターとして仕事をする回数が増えるごとに、人が当てにならないことを実感する経験が積み重なった。悲しいクリエーターの性ともいえるが、最初に5人のチームメンバーが崩れていってからのいろいろな出来事が、即戦力をつけることをプッシュした。だれも頼らず、実践のクリエーター魂が身についた。人生に捨てるものなし、という人がいるが、捨てたからできたのか、捨てるものがなかったのか、今もわからないままである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
