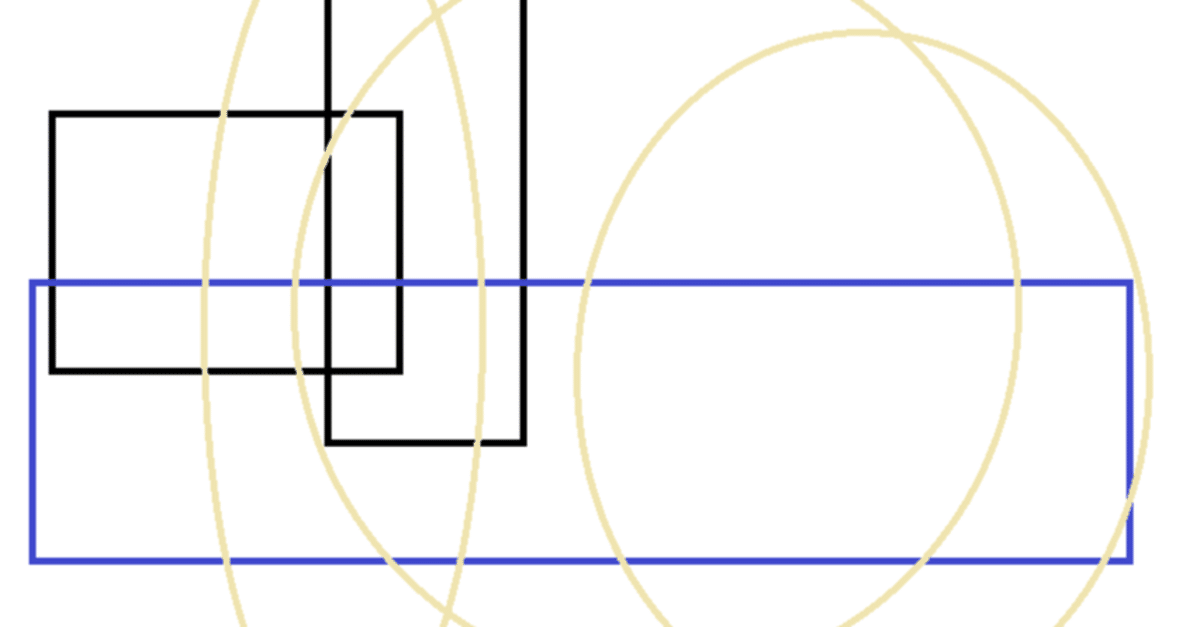
【超短編小説】眠り姫、もしくは不眠症患者が見た夢
コネチカットの大学に通っていた一時期、ぼくはひどい不眠症に悩まされたことがあった。眠り姫を見たのはそれとちょうど同じ頃だ。
秋の午後、ぼくは木立に囲まれた図書館にいた。レンガ造りの壁には木漏れ日がまだら模様を作り、閲覧室では広々とした空間を静けさが満たして、あるかなきかの咳払いや囁きだけが空気を震わせていた。立ち上がった時、ぼくの視線はふとひとりの女子学生に惹きつけられた。彼女は机の上に突っ伏して、安らかな寝息を立てていた。淡いブルーのシャツとぴったりしたジーンズがほっそりした、それでいて華奢すぎない肢体を包み、その上につやつやしたブリュネットの髪が垂れ下がっていた。
その顔にはどこまでも曇りのない穏やかさとエレガンスがあった。フランドル派の絵画にしばしば描かれるマドンナみたいに、あるいはフラ・アンジェリコの筆による大聖堂みたいに、窓から差し込む光が彼女のまわりだけをステージライト風に周囲から浮かび上がらせていた。ぼくは思わず息を呑んだ。ここには何か特別なものがあると感じたからだ。彼女にもっと近づきたい、その横顔をいつまでもただじっと眺めていたいという強い欲望にかられたけれど、次の授業が控えていたため、後ろ髪を引かれる思いで図書館を後にした。
二度目に彼女を見たのは、キャンパス内の礼拝堂へと続く、蔦が絡まる散歩道でのことだった。その日は薄曇りで肌寒く、石柱が立ち並ぶ石畳の小径をぼくはいつになく物思いに耽りながら歩いていた。突然目の前にベンチに座って石柱にもたれ、うつむき、長いまつ毛を伏せた彼女の姿が出現した。ぼくは不意打ちに驚き、足を止めた。彼女はひとりきりだった。そしてまたしても深い眠りの中にあった。ダボダボしたえんじ色のセーターを着た彼女は、前よりもいくらか少女めいて見えた。かすかな風が吹き、ぼくと彼女の間に落葉がはらはらと舞い落ちた。
ぼくはそろそろとベンチに近づいた。彼女のしどけない姿を感嘆の念をもって眺めるために、そしてそのたおやかさの中に自分をなめらかなバターのように溶かしこむために。あらゆる緊張と警戒から解き放たれ、夢の中をタンポポの種子よろしく浮遊しているその姿、その寝息の平穏さは、ぼくに永遠を感じさせた。そして空を横切る雲が彼女の上に透明な影のグラデーションを投げかけた時、ぼくは彼女の隣に腰を下ろしたいと願った。その眠りを妨げないままそっとベンチに腰を下ろし、彼女の隣で同じ空気を吸ったり吐いたりしたいと。
が、そこはキャンパスの中でも特に人通りの多い場所だったし、ぼくは変質者として警備員に目をつけられたくなかったので、すみやかにその場を離れた。
三度目は大きな教室の中だった。しとしと降り続く長雨のせいで、巨大な窓ガラスが縦に流れる川みたいに濡れそぼっていた。授業が終わって室内にざわめきが広がったちょうどその時、みんなから離れたいちばん後ろの席に彼女を見つけた。柔らかい雨音と薄暗がりが彼女を黄昏の風のように取り巻いて、ぼくの目から隠していたのだ。この時の彼女は突っ伏してもいず、また何かに寄りかかってもいなかった。頬杖をつき、まるで哲学的な難問に取り組むロダンの彫像か何かみたいに、粛然とうつむいていた。けれどもまたしても眠りの中に、しかもとりわけ甘美な深いまどろみの中にいるのは明らかだった。授業が終わっても微動だにせず、周囲のざわめきから完全に切り離されて、背中だけが呼吸にあわせてほんのわずか上下していたからだ。
雨が窓ガラスを通して描き出す光と影の波模様が、彼女の全身をゆるゆると洗い清めているように見えた。顔はよく見えなかった、けれども垂れ下がったブリュネットの髪の隙間からのぞく白い頬と鼻は、これから生まれ出ようとするアフロディテさながらのみずみずしさだった。ぼくはどうしてもそこから目を離すことができなかった。
そうやって立ち尽くしているうちに、他のみんなは教室を出て行った。たぶんぼくは彼女に近づいて、「終わりましたよ」と声をかけるべきだったのだろう。それぐらいのことはできたはずだ。が、黒板の前にいる教授が「どうしました?」とぼくに声をかけた時、つい「なんでもありません」と答えて、そそくさと教室を出てしまった。彼女がいつまで雨音とともにあの場所にとどまっていたか、ぼくは知らない。
それからというもの、ぼくはキャンパス内で飽きることなく、執拗に、彼女の姿を追い求めることになった。それがぼくの生活の基本テーマとなり、オブセッションとなった。願いは時にかなえられ、時に挫折した。ぼくは心の中で彼女を眠り姫と呼んだ。なぜならいつでもどこでも、ぼくが見かける時には必ず彼女は眠っていたからだ。どれほど切望しても、待ち伏せても、あるいは友人を通して画策しても、起きている彼女―――目をさまして動いたり喋ったりしている彼女を見ることはできなかった。まるでそれが、ぼくにだけ禁じられた恩寵か何かみたいに。
そんなある日のこと、全然良くならない不眠症をなんとかしようと、ぼくは評判がいいセラピストのオフィスを訪れた。セラピストは40歳ぐらいの女性で、シェリルという名で、きびきびしていて、ジョディ・フォスターっぽい聡明さを湛えた明るい目をしていた。
「やって欲しいことが二つあります」とシェリルは言った。「まず、料理は好きですか?」
「嫌いじゃないですけど」とぼく。
「ボルシチを作ったことは?」
「ありません」
「ではひとつ目。眠れない夜にはボルシチを作って下さい。あれは、時間をかけて煮込めば煮込むほど味が良くなるのです」
「それは治療と関係あるんですか?」
「不眠症患者の作るボルシチがいちばんおいしいのです」
「ぼくに何ができるとしても、おいしい料理だけは作れません。それだけは自信を持って言えます」
彼女はじっとぼくの目をのぞきこんで言った。「それでは、おいしくする努力をしてください。それを食べる相手が誰であっても。人生において、それが一番大事なことです」
ぼくは夜通しかけてボルシチを作り、タッパーに入れて次のセッションに持ってきた。シェリルはそれを温めて深皿に入れ、エビアンと一緒に診察室のテーブルに並べた。だからその後の会話はすべて、熱々のボルシチを食べながら進行することになった。
「味つけは悪くないけど、もうちょっと煮込んだ方がいいわね」とシェリルが言った。「で、二つ目にやって欲しいことは、日記です。あなたは日記をつけていますか?」
「いいえ。小学校以来ありません」
「では今日からつけて下さい。簡単でいいです」
「ここであなたとこうやってボルシチを食べたことも?」
「あなたが幸福だと思ったこと、感謝の気持ちを抱いたことを書いて下さい」
「なるほど」とぼく。「それが、人生で二番目に大事なことですか?」
「いいえ、違います。三番目です」
「じゃ二番目は?」
「それはまた別の機会に」
言うまでもなく、日記はぼくのオブセッションである眠り姫のことで埋め尽くされた。それは時には詩に接近した、と言っていいかも知れない。日記はこんな風だった。
『……ある時は机の上にぐったりと身を投げ出して、ある時はいたいけな少女のように街路樹に寄りかかって、ある時は頬杖をついて、ある時は深くうつむいて、ある時はソファーに寝そべって、彼女はいつも昏々と眠っている。その瞳はカーヴしたまつ毛の下に深く沈潜し、唇はかすかに開いて緩やかに息を出し入れする。彼女の全身は周囲の世界と調和し、その優美さはしばしば完璧の域にまでのぼりつめる……(中略)……ざわめきとせわしなさの間を行き来するだけのぼくたち目覚めた人間たちと違って、眠り姫は典雅で、怜悧で、どこまでも慎み深い。まるで人間の域を超えた天上的存在のようだ。ぼくは何度その美しさに気が遠くなりかけたことだろう。何度その神々しさに目をうるませたことだろう……(以下略)』
日記を読んだシェリルはいたずらっぽく目を輝かせながら言った。「今度彼女を見かけたら、声をかけて起こしてみて」
「どうして?」とぼくは大きな声を出した。「それ、ぼくの不眠症と関係ありますか?」
「あるかも知れないわ。とにかくやってみて」
「でももし彼女が腹を立てたら? 眠っている人は起こされると大体機嫌が悪くなるじゃないですか」
「大丈夫だって。勇気を出しなさい」
シェリルのアドバイスはぼくを困惑させた。途方に暮れさせた、と言ってもいい。しかしぼくは彼女に従う義務があると感じた。次に眠り姫を見かけたのは音楽室の中だった。そこはいつもはオーケストラ部の練習でにぎやかなのに、その時だけは人けがなかった。たまたまドアを空けると、窓際の椅子に座っている彼女が見えた。うつぶせでもなく、うなだれるでもなく、ほんの少し頭を後ろに傾けて、窓枠に頭をもたれかけた姿勢の彼女が。ちょうど飛行機の座席を後ろに傾け、そこに身を委ねて眠る人みたいにして。
ステンドグラスの模様が入った窓から、冬の白っぽい陽ざしが差し込んで音楽室の中を明るく照らしていた。立ち並んだ譜面台が鋭角的な格子模様のシルエットを投げかける中、ぼくはそっと歩き、横切って、彼女に近寄っていった。彼女が誰かを待っていたのか、オーケストラ部員だったのか、それともただ静かな場所にいたかったのか、ぼくには分からない。その時はじめて、ぼくは彼女の顔を隅々まではっきりと見ることができた。穏やかに閉じた瞼、長いまつ毛、安らかさを湛えた頬、すっとのびた鼻梁、そして小さなサクランボにも似た唇のふくらみ。
長いこと不眠症だったぼくは、まるで自分が夢の中にいるみたいな気がした。そして今、そっと声をかければ、彼女はゆっくりと目を開くだろう。そして初めて開いた赤ん坊のような目でぼくを見るだろう、と思った。その唇は開いて言葉を発するだろう、誰でもないこのぼくに向かって。ぼくは前かがみになって発声にそなえた。今や彼女の顔はぼくの目の前20センチのところにある。
そうやって一分間ぐらい逡巡していただろうか。結局、ぼくは声を発することができなかった。どうしてかは分からないが、彼女の目を覚ますことで、何か取り返しのつかないことが起きるような気がしたのだ。率直に言えば、ぼくはただこわかった。だからそのまま回れ右をし、音楽室を出て、ドアを閉めた。それが眠り姫を見た最後だった。
このことをシェリルに報告した時、彼女はただ肩をすくめた。まるで結果は分かりきっていたとでもいうように。ぼくは恥ずかしさで顔を上げることができなかった。
「つまり、これが人生で二番目に大事なことなんですね」とぼく。「好きな人に声をかけるということが。ぼくにはそれができなかった。きっと百万年たってもできないでしょう。要するに、ぼくは根性なしなんだ」
「いいえ、そうじゃないわ」とシェリルは厳かに言った。「それはケース・バイ・ケースです。人生で二番目に大事なのは、おいしい食事をしたあと食器をきれいに洗うこと。すっかり、しみ一つなく、ピカピカに磨き上げることよ。あなたには人生の三大ルールをきっちり守ってもらいます、これから毎日」
<シェリル先生の、人生においてもっとも重要な三大ルール>
1、誰に食べさせるにしても、できるだけおいしい料理をつくる努力をすること。
2、おいしい食事をしたあとは、食器をピカピカになるまできれいに洗うこと。
3、日記をつけて、幸福だと思ったことや感謝したことを書き残すこと。
まもなく、ぼくの不眠症は完治した。シェリルは有能なセラピストだったのだろう、やり方は風変りだったけれども(彼女はまだ患者にボルシチを作らせているだろうか?)。そのすぐ後、ぼくは大学の近くの舗道を歩いていて二人の娘たちとすれ違った。一人はブロンド、一人はブリュネットで、二人ともけたたましい声を張り上げて会話に没頭していた。さかんに両手を振り回し、頭を揺らして。夜、ベッドにもぐりこんだ時になってようやく、ブリュネットの方が眠り姫だったことに気づいた。思わずあっと声が出た。頭がしびれたようになり、口がOの文字を形作った。友達とにぎやかに会話しながら歩いていた彼女は、眠っている時とはまるで別人だった。彼女の目は大きすぎるようだったし、口は歪んでいるように見えた。ぼくはすれ違っても彼女だと気づくことすらできなかったのだ。
それが恋の終わりだった。不眠症がぼくから飛び去るのと時を同じくして、眠り姫もまた消えた。もうすぐ春だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
