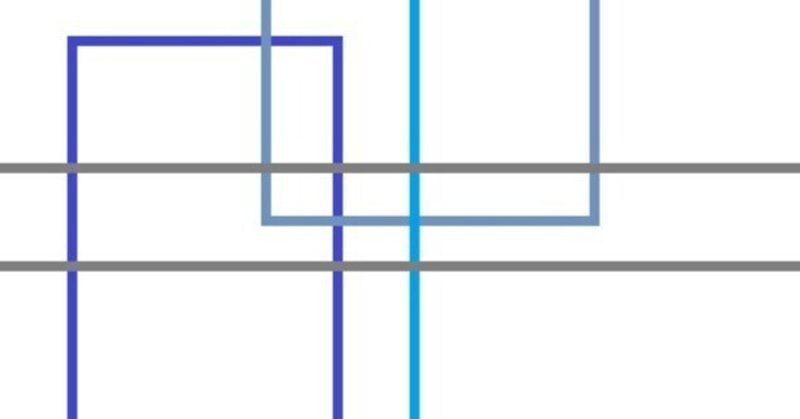
【超短編小説】アナコンダ
その日の夕刻、ブロンクス動物園の飼育人ボブは片手にバケツ、片手にモップを持ってアナコンダのケージに入って行き、そこに蛇ではなく一人の若い女を発見した。見回したが、蛇はどこにも見当たらなかった。
青ざめた蛍光灯の光の下でしばらく立ち尽くしたまま、何がなしざわつくような思いで女を眺めた。というのも女にはどことなく、アナコンダを思わせるところがあったからだ。
20代後半か30歳ぐらいで、赤毛で、汗じみたTシャツの上にごつくてキズが入った革のジャケットを羽織り、全体に薄汚れていて、だらしなく両膝を立てて地べたに座っていた。顔にいくつかあざがあり、唇の端は切れて血が滲んでいた。
「何見てんの」と女が言った。「ねえ食べるものくれないかな? あたしお腹すいて死にそう」
「どうやって入ったの?」とボブ。「それに蛇はどこ?」
「蛇なんて最初からいなかったよ」
ボブはケージの中を見回したが、女が入って来れそうな穴や隙間はどこにもなかった。女が言った。「どうだっていいでしょ。それより何か食べさせてよ。ピザかなんかでいいから」
「それはいいけど」とボブが言った。「念のために聞くけど、君は本当は蛇だってことはないよね?」
「もしかしてあんたバカなの?」
ボブはムッとしたが、女の思いがけず子供っぽい目にはぐらかされたような気がして、我慢することにした。「まあいいさ。こっち来なよ」
「ありがと。あたしローズ」
ボブがツナとレタスのサンドイッチを作ると、ローズは椅子に腰かけて食べ始めた。
「断っておくけど」とボブ。「ぼくは上司に君を不法侵入者として報告しなくちゃならない」
「それだけはやめて」
「でも仕事だから」
「あたし、DV夫から逃げ出してきたの。分かるでしょ? どこにも行くところがないの」
ボブはローズのあざと血の滲んだ唇を見た。「バンソーコいる?」
「いらない。でもしばらくここにいさせて。夫が外にいてあたしを探してるの。少ししたら出ていくから」
「出ていくって、どこへ?」
ローズは両手を広げて、何かを抱きしめるような仕草をした。「どこか、ここじゃない場所。あたしが幸せになれる場所。あたしが自分自身のままでいられて、それを認めてくれるような場所」
「そんなところがあればぼくも行きたいよ」
ボブが丁寧に皿を洗って一枚ずつ戸棚にしまう間、ローズは黙ってそれを眺めていた。「あんた、さっき私を蛇だと思ったんでしょ」
「だってあれは蛇のケージだから」
「動物が人間に化けたりするのは映画や小説の中だけよ」
「そうかも知れない。そうじゃないかも知れない」
「あんたってロマンチストなのね」
しばらく沈黙が流れた。気まずさやとげとげしさのしこりが少しずつほどけて穏やかな親密さへと形を変えていった。
「君の夫は最初からDVだった?」とボブ。
「ううん最初は優しかったわ。毎日愛してると言って、大切にしてくれた」
「それじゃ今はどうして君を殴るの?」
「分からない。でも人は誰かに甘えて依存すると、その人を傷つけるようになるんだって」
ボブは口をつぐんで、しばらくその事について考えをめぐらせた。「なんて愚かしいんだろう。でも分かる気がする」
通路からゴリラや象の鳴き声が渾然一体となったざわめきが聞こえてきた。まるで遠くのオーケストラが音合わせしているみたいな荘重な残響音を伴って、潮騒のように高まってはまた引いていった。
「あれは何? 動物ってみんな夜はぐっすり眠ってるんじゃないの?」
「眠ってるよ。あれはみんなで夢を見てるんだよ」
「で、みんないっせいに鳴くの?」
「そうだよ」
「動物に詳しいのね」
ローズが笑ってボブを見た時、そのキラキラした無垢な笑顔が彼を刺し貫いた。胸の鼓動が高まって、もしもぼくが彼女の夫だったなら、とボブは思った。きっと毎日愛してると言って、大切にするだろう。でもDV夫も最初はそうだった。彼はなぜ、愛する人を殴るようになったのだろう。
ローズが立ち上がった。「そろそろ行くわ」
「そう」
「そういえば」ローズが振り向いた。「急に思い出したんだけど、三回結婚したおばあちゃんが言ってたわ。最初の夫がいちばん長く続いたけど、彼はほんとは人間じゃなくてビーグル犬だったって」
「どういう意味?」
「最後はビーグル犬に戻って、お辞儀をして、森の中へ消えていったんだって」
「冗談じゃなくて?」
「冗談じゃなくて。真顔で言ってたわ」
「なぜビーグル犬がそんなことを?」
「知らないわ。きっとおばあちゃんに餌をもらったか何かじゃない? じゃ行くわ。サンドイッチありがとう」
ローズは出て行った。暗がりにDV夫が潜んでいないか耳を澄まし、小動物のように足を忍ばせて。
彼女は蛇だったのかも知れない、とボブは考えた。なぜなら蛇がケージから逃げられるはずがないし、ローズがケージに入れるはずがないからだ。したがってローズはアナコンダである。証明終わり。ぼくは蛇を逃した責任を取らされて、きっとクビになるだろう。
ボブはドアに鍵をかけ、上司にアナコンダがいなくなったことをメールした。それから残りのケージを掃除し、電動ブラシで歯を磨き、ベッドに潜り込んだ。彼は動物園に寝泊まりしていたのだ。毛布にくるまった途端、ひどい疲れを感じた。そしてまっ逆さまに井戸のような眠りの中へと落ちて行った。彼はここ数日まったく眠れなかったのだが、不思議なことにこの日は温かい泥の中のロブスターみたいにぐっすり眠ることができた。
メールは沈黙していた。彼の上司もまた、ぐっすり眠っていたからだ。
ボブは知らなかったが、アナコンダのケージには外から見ても分からない亀裂が生じていた。そして夢も見ずに眠るボブのベッドから直線距離にして約300メートル離れた灌木の茂みの中に、1時間前にアナコンダに絞め殺されたばかりのDV夫の死体が転がっていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
