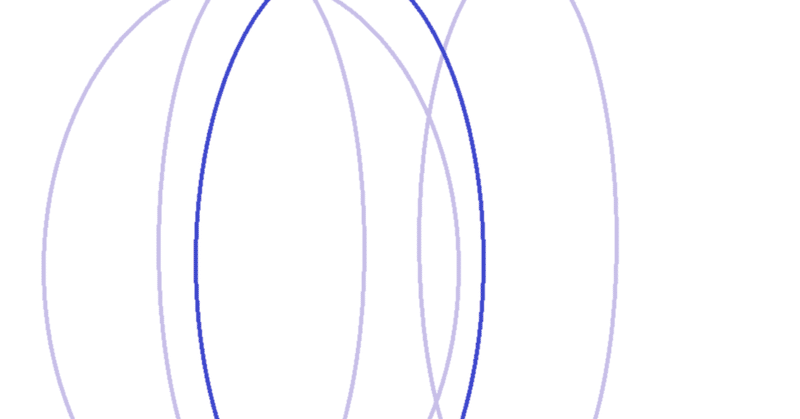
【超短編小説】妻のペンギン
何の前触れもなくペンギンが配達されてきた日のことを、ぼくは今でもよく覚えている。配達人はペンギンが入った籠と一緒に、組み立て式プールみたいなものをぼく達のアパートへ運び込んだ。それがペンギンの家だということは分かったが、その見慣れない物体が発する威圧的なオーラがぼくを落ち着かない気分にさせた。妻が「ここに置いて下さい」とか「それはあっち」とか言うのを黙って眺めている間、時々ペンギンの丸っこい目とぼくの視線がぶつかった。ペンギンは怯えたり騒いだりする様子もなく、大体において静かだった。それどころか、久しぶりに自分の家に帰ってきたとでもいうようにリラックスしていた。
配達人が出ていった後、妻にきいてみた。「これ一体何なの?」
「ペンギンよ、かわいいでしょ」
「こんなもの家で飼えるの?」
「飼えるわよ、だってペットショップで売ってるんだもの」
ソファーに寝そべってビールを飲む彼女はいつになく幸福そうで、その頬はなにがなし上気していた。一方、ペンギンは窓と窓の間にピッタリはめ込まれたプール付きのペンギンハウスの中で、ヒタヒタと足踏みしながら、妻やぼくに向かって時にいたわるような、時に問いただすような視線を投げかけていた。
この一件について最初から懐疑的だったぼくも、妻がペンギンの飼育に熱心に取り組んだことは認めないわけにはいかない。そして妻がそんな風に何かに没頭するのは往々にして何かのサインなのだということを、ぼくはよく知っていた。失意にしろ、興奮にしろ、苛立ちにしろ、困惑にしろ、あるいは何かへの異議申し立てにしろ、そのサインが意味するものを発見するのがぼくの役目なのだ。
「ねえ、君がサルサを習いたいって件だけど。悪くないと思うな」
「何の話?」
「前にサルサを習いたいって言ってたじゃないか」
「そんなこと言ってないわ」
妻はペンギンにアーサーという名前をつけた。そしてペンギンに関する本を買ってきて読みふけり、ペンギンを喜ばせたりなごませたりするグッズをあれこれ取り揃えた。彼女はこの小動物の健康状態を四六時中観察し、時々プール付きのペンギンハウスから連れ出して部屋の中を散歩させた。そんな時、赤い首輪をつけたアーサーは夢遊病者のように上体を揺らしながら、このまま空へ舞い上がりたいと願うかのように短い翼を広げた。
「君のあのバッグさ、よく見るととてもいい色だと思うよ」
「一体何の話よ?」
「前に君が買ってきたバッグさ。あの時は色が変だって言ったけど、撤回するよ。すごくいい色だと思う」
「そうだったかしら。覚えてないわ」
やがてアーサーはひとりで首輪もつけず、家の中をよちよち歩き回るようになった。紡錘形のペンギンが両手をプラプラさせ、家の中を歩き回る光景は何がなし物悲しかった。犬や猫は四つ足だからいいのだと、今更ながらぼくは思った。ペンギンは人間のように立って歩く、だから遠くから見ると愚かしい小さな人間のように見える。アーサーが嘴を振りたてながら家の中をグルグルとあてどなく、翼があるのに飛べない自分への復讐みたいに黙々と歩き回るのを見るたびに、ぼくはなんだか気が滅入った。
しかしぼくの嫌悪が決定的になったのは、その鳴き声を聞いてからだ。それまで全然鳴かなかったアーサーがある時から毎日のように、しかも決まって真夜中過ぎに鳴くようになった。その鳴き声はどういうわけか、ぼくの死んだ父親の高笑いにそっくりだった。ベッドの中でうとうとしていると、突然誰もいないはずの居間から忘れもしない父の哄笑が響いてくる。仰天して飛び起き、見に行くとアーサーなのだ。それは父がぼくの不甲斐なさやだらしなさに呆れ果て、嘲笑する時の野卑で攻撃的な笑い声そっくりだった。こんなことにはとても耐えられない、そう思って翌朝さっそく妻にクレームした。
「動物なんだから鳴くに決まってるじゃない。いまさら驚くなんておかしいって」と妻が言った。
「でも夜中にあんな妙な声で鳴かれたんじゃとても眠れないよ。アーサーは動物園に引き取ってもらおうよ」
「ばかなことを言わないで。あんなにかわいいペンギンを手放すなんて、私は絶対にイヤよ」
その夜、ぼくはある決意とともに妻の部屋のドアをノックした。
「そういえば、三年前のあのことだけどね」と切り出した。「本当にすまなかったと思ってる。これまでちゃんと謝ってなかったけど」
「一体何の話?」
「つまり、当時ぼくのアシスタントだった女の子と、ぼくの間に起きたことさ」
アイスピックを思わせる彼女の視線の中にはまじりけのない敵意が、そしておそらくは恐れのようなものがあった。「今さらそんなことを蒸し返して、どうしようっていうの?」
「いや、だからちゃんと謝ろうと思って。君を傷つけたことを。心から」
深く冷たい沈黙が広がった。ぼくの口から発せられた言葉はただ空しく床に落ち、枯葉のようにひからびていった。
そっと退室してキッチンでミルクを飲みながら、さっきのあれはまずかったと考えた。サインの意味を解読できたと考えたのはぼくの思い違いだったかも知れない。確信は持てなかった。大体これまでに、ぼくが妻のことで確信を持てたことが何かひとつでもあっただろうか。その夜、寝室から追い出されて居間のソファーで寝るぼくを見つめるアーサーの顔はまるで嘲笑しているように見えた。ぼくがアーサーに殺意を抱いたのはこの時だ。
アーサーを始末するなら、妻には絶対に分からない方法でやらなければならない。二晩頭をひねって思いついたのは、ペンギンは暑さが苦手に違いないということだった。でなければあんなに寒い場所にばかり棲んでいるはずがない(ペンギンが実は暑い場所にも棲んでいるということを、この時ぼくは知らなかった)。この思いつきからぼくは悪魔的な計画を練り上げた。ある晩、妻が眠り込んだ後にそっとベッドを抜け出し、電気毛布を抱えてペンギンハウスに忍び込んだ。そしてアーサーを毛布でくるみ、しばらく温めた。アーサーは目を覚まさず、特に苦しそうでもなかったが、これを繰り返せばペンギンの身体はきっとおかしくなるだろう。ぼくはそう思った。
変化があらわれたのは二週目だった。アーサーは歩きながらまるでパンチドランカーみたいに右に左にカーブを描くようになった。それから一週間たつとグルグル円を描いて歩くようになり、しまいには倒れてそのまま足をバタバタさせた。この異変に妻は顔色を変え、アーサーを元に戻すために色々なことを試みた。たとえば食べ物を変えたり、マッサージを施したり、青汁を飲ませたり、毛糸の靴下をはかせてみたりした。が、状況は変わらなかった。獣医に診せても原因は分からない。医者はアーサーの体にこれといって問題は見当たらないと言った。
アーサーがこの家からいなくなるなるのはもう時間の問題だ、そう考えてぼくは心安らかだったが、言うまでもなく、この考えは甘かった。朝、ベーコンエッグをつついているぼくの隣に妻がやってきて、スマホで動画を再生した。動画にはペンギンハウスに忍び込み、眠っているアーサーを電気毛布でくるんでいるぼくの姿がはっきり映っていた。
「夜間撮影できるモーションセンサー付きの小さなカメラを買って、ペンギンハウスの周辺に取り付けておいたの。何かが分かるだろうと思ったけど、まさかこんなことだったとはね」
ぼくはうなだれ、一言もなかった。翌日、彼女は書置きを残して姿を消した。『出て行きます。お願いですから探さないで下さい。夜中にこっそりペンギンを電気毛布で温めているあなたを見た時の私の気持ち、それはとても言葉で言い表すことができません。さようなら。アーサーをよろしく』
それ以来、ぼくとアーサーは一緒に暮らしている。電気毛布をやめたらアーサーはまたすぐに元気になった。ぼくたちは互いのライフスタイルとプライバシーを尊重し、なかなかうまくやっていると思う。アーサーは今も父そっくりの笑い声を響かせるし、最近では父の声で歌を歌うようになった。が、それももうぼくを苛立たせることはない。それどころか時には、その声音の中にかすかな優しさや慈しみの情を感じ取ることさえある。ぼくが生前決して父の声から聞きとることのできなかった肉親への愛情、お前はやっぱりおれの息子なんだよというようなニュアンスが、そこにはうっすらとほの見える。
妻に関して一言付け加えるならば、いちばん不思議だったのは彼女がアーサーを一緒に連れていかず、ぼくに委ねたことだ。ぼくがアーサーを捨ててしまうだろうとは思わなかったのだろうか。結局、彼女からのサインが何だったのかは最後まで分からずじまいだった。しかし何だったにせよ、確かなのはぼくがそれを読みそこなったということだ。結婚において、あるいは人生において、それはもっとも致命的と見なされている過ちの一つだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
