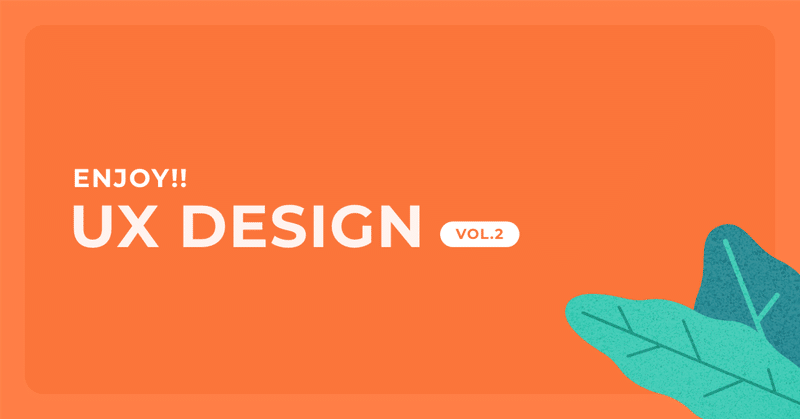
【 ENJOY!UX Design 】 オンラインワークショップ!体験づくりの心得とは?
かけだしUXデザイナーの横山です。
今日は私が普段のお仕事で行っている、
オンラインワークショップのワーク環境デザインについて、
お話ができればと思います。
オンラインワークショップとは?
一般的にワークショップとは、複数人の参加者がテーマに対して主体的に考える、いわば体験学習型の場と言われています。
私の所属するデザイン会社ではブランディング・サービスデザインの過程の中で、方針づくり・解決に向かうための手法として、クライアントと一緒にワークショップを行うことがあります。
これらを対面ではなくオンラインで完結・進行をするのが、オンラインワークショップです。
よければ過去の事例を見ていただけると嬉しいです!
オンラインツールを駆使し、参加者に促し・考え・発散してもらえるか。
やってもらいたいことを、いかにわかりやすくできるか。
それらを考えた場づくりのデザインこそが、
UXデザイナーの使命であると考えます。

オンライン化の壁は、ツールの学習コストにあり!
弊社ではワーク環境の場として、
オンラインホワイトボードMiroを活用しています。
コラボレーションツールとしてとても優秀で、
普段のプロジェクトでも重宝しています。
Miroをワークショップに活用するにあたり、
お客様によってはツールに馴染みのない方・リテラシーも人それぞれ。
導入ツールの学習コストが弊害になってしまい、
本来のワークの目的に集中できない!なんて言語道断です。。

場づくりのデザインをするなかで、
常に学習コストに目を向け、意識・工夫をするだけで、
参加者とツールが手と手を取り合える関係になれると私は思います。
そんな私が普段のワークの場づくりで心がけていることを、
2つほどご紹介できたらと思います。
【 心得01 】 良い!ではなく、あたりまえを目指そう!
そもそも、”優れた”ワーク環境をとはなんでしょうか。
カッコいいデザインがされている?
最先端の機能があちこちに使われて画期的である?
どれも間違いではないと思うのですが、
私が思う”優れた”ワーク環境とは、
参加者に委ねない・考えさせないこと
だと思います。
今の時間は何を考えアクションすべきか・次の行動が予測できるか、
用意したワーク環境の要素から参加者自身が読み取り、
いかに行動に移してもらえるかがキーとなります。
あたりまえの状態を1発で作るのは難しいので、
チームの誰かに触っていただき改善を繰り返す….
をすることをオススメします◎
【 心得02 】 させる・させないアクションルールを作ろう!
Miroのツールの中には、付箋機能・移動ツール、ペンやスタンプ機能など….
さまざまな便利機能があります。
ツール学習コストを下げるための、
具体的で近道な方法としておすすめなのが、
参加者のアクションパターンを絞ることです

上記のようなツール・付箋を事前に用意しておくことで、
決められたエリア・枠内に参加者は コメントを書くだけ となります。
このように何をして欲しいかから逆算をし、
参加者に委ねないツール設計を心がけることで、
ワークの内容に集中できることができます。
今回はオンラインツール導入にあたる、
学習コストを下げるための考え方について触れてみました。
実際の場づくりのノウハウなど、次回お伝えできればと思います。
ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
