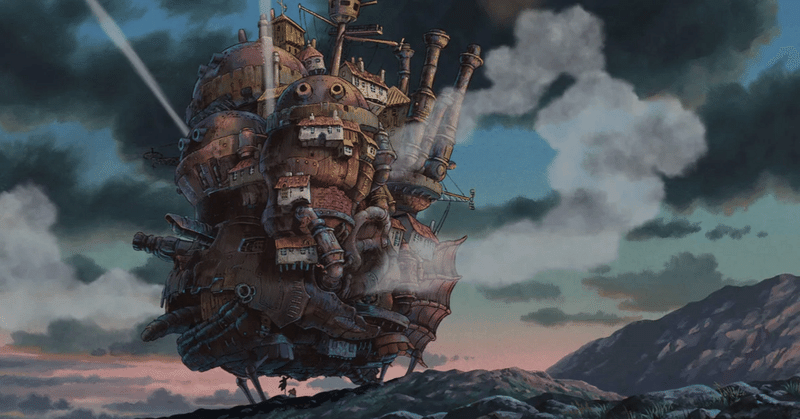
映画「ハウルの動く城」を読む【完全解説】 ⑥
●本能VS理性
ここまで、「ハウルと荒れ地の魔女」と「魔女・サリマン」の対決を「妄想(ファンタジー)VS現実」という側面から見てきたが、彼らの対決は、「本能VS理性」という側面からも見ることができるようになっている。彼ら三人は魔法使いだが、本作品では、どうやら「ハウルと荒れ地の魔女」の使う魔法と「魔女・サリマン」の使う魔法には違いがあるようだ。
まず、「ハウルと荒れ地の魔女チーム」の魔法についてだが、彼らが使う魔法を「本能的魔法」と名付けたい。本編で何度も繰り返し描かれるのは、ハウルの正体が「本能」、もしくは「煩悩」の塊であることだ。例えば、それは、「(ハウルは)魔法を自分のためだけに使うようになった」と言う魔女・サリマンのセリフや、「ハウルの正体を見せてあげよう」とサリマンがハウルを鳥人(野生化)に変えてしまうことから分かる。ハウルは、鳥人にされることで、本能に支配された時、ソフィーに「名前」を呼んでもらうことによって、正気を取り戻す。「名前」を使用するのは、「理性」を持つ人間ならではであるから、「理性」を取り戻す効用があるということなのだろう(名前を思い出して正気を取り戻すのは「千と千尋の神隠し」の千尋とハクと同じ)。また、カルシファーが「あんまり飛ぶと戻れなくなるぜ」とハウルに言うように、魔法を使いすぎると、ハウルは「理性」を失ってしまう。彼は「本能」が強過ぎるため、攻撃本能を剥き出しにして、日々、戦闘に明け暮れている。だから、ソフィーは、戦地に向かうハウルに対して「あの人は弱虫がいいの」と言うのである。いずれにしても、ハウルにかけられた呪いは、「理性の喪失」と言える。
そんなカルシファーも、当然、ハウルたちの魔法チームであり、カルシファーの赤い炎は「煩悩の炎」と見てもいいだろう。カルシファーは、「火薬の火は嫌いだ。奴らには礼儀ってものがないから」と言う。彼は、おそらく、戦火は礼儀(理性)がなくなった炎(煩悩)が巨大化したものだと言いたいのであろう。
本作品で、こうした「火」のイメージと対比的に用いられているのが、「水」のイメージである。ソフィーの心象風景である「アルプスの山間」や「アルプスの花畑」のシーンを見ても分かるように、彼女の心の中は「水」のイメージを内包している。宮崎作品では、このイメージの対比が、赤色(火)と青色(水)といった色分けとともに、よく顔を出す。

最も分かりやすいのは、「風の谷のナウシカ」でのオームの目の色、ナウシカの服の色である。オームの目は、怒りで本能を剥き出しにすると赤色になり、冷静になると青色になる。ナウシカも本能的で怒りに満ちた精神状態では、赤色の服を身にまとっており、こうした煩悩が消え去ると服は青色へと変化する。
本作品のハウルにも、全く同じ変化が表れる。それは、服の色によってではなく、彼の心の暗喩であるカルシファーの炎の色によって表現される。ハウルが本能を全開にして戦争に明け暮れている時は、カルシファーの炎は赤色であるが、「愛」に目覚めたソフィーに水をかけられると、青色へ変わる。「理性の喪失」という呪いをかけられ、心を「本能・煩悩」に囚われていたハウルだが、ソフィーの聖水によって、彼の心は浄化される。この時点で、ハウルにかけられた呪いは解けたと言ってもいいだろう。普通、炎は温度が上がれば赤色から青色へと変化するものだが、水をかけたのに逆に青色に変わるのは、どうにも不自然に思えてしまう。しかし、宮崎作品の特徴である。「火」と「水」のイメージの対比が見えてくれば、この非合理な描写も納得がいくはずである。
●戦争を終わらせたもの
「ハウルと荒れ地の魔女チーム」に対して、「魔女・サリマンチーム」の魔法は、「理性的魔法」と呼びたい。なぜなら彼女は、魔法使いでありながらも、やたらと「科学」に依存する環境下にいる。「車椅子」を使い、緑を「温室」で育てる。荒れ地の魔女から魔力を取り除く折にも、巨大な「白熱球」を使用するからだ(原始的な火のカルシファーとの対比であろう)。「科学」の力に頼った「理性的魔法」を使用することによって、「本能的魔法」を打ち破ろうとする。「本能VS理性」が繰り広げる戦争は、泥沼化する一方で、最後まで決着を見ない。

では、「本能VS理性」の戦争を終結させたものは何だったのか。もちろん、それは、ソフィーの「愛」であるが、「心をなくす呪い」にかかっていた彼女が、いかにして「愛」を取り戻したのだろうか。
ソフィーにかけられた呪いは、「本能の喪失」であろう。それは、「理性」の働かない睡眠中に呪いが解けることからも分かるが、「理性の喪失」のハウルとは逆の呪いである。「本能の喪失」に陥ったソフィーが、ハウル(=本能)と出会い、彼を求めるようになるのは自然なことなのだ。
魔女・サリマンとの闘いの後、ソフィーは、自らの部屋で横たわっているハウルの元へと向かう。このとき、ハウルの部屋は、以前のように、オモチャ箱をひっくり返したような部屋ではなく、彼が人間の姿でもないのがポイントである。暗闇でうごめく「もののけ」と化したハウルは、まさに「本能」の塊である。そんなハウルに、ソフィーは「あなたの呪いを解きたい」と告げる。それに対して、ハウルは「自分の呪いも解けないのにか」と言い返す。

しかし、この時、すでにソフィーには、ソフィーとハウルの呪いを同時に解ける兆しが感じられる。ハウルの部屋へ向かう途中、彼女は、二股の分かれ道で、ハウルの居場所が「本能(野生の感)」で分かるからだ。これは、「千と千尋の神隠し」の千尋が豚たちの中に豚にされた両親がいないことが「本能」で分かるのと同じなのだが、どちらのヒロインにも共通しているのは「愛する気持ち」を取り戻すことによって、「本能」の力が甦ってくる点である。「愛」さえ取り戻せば、「本能喪失」の呪いを解くことができ、「本能」を取り戻した者は、「理性喪失」の相手に「理性」を取り戻させることができるようになる。つまり、ソフィーは、ハウルと出会ったことで、自らの呪いを解くことができるようになり、その結果、ハウルの呪いも解けるようになったのである。
●愛は地球を救う
「愛」を取り戻すことによって、ソフィーは「理性」と「本能」のバランスを取り戻す。ソフィーのかけられた呪いは、「科学(理性)」に頼りすぎる傾向にある現代人に共通する呪いと言っていいだろう。宮崎監督は、現代人が「理性」を過信しすぎることに対する警鐘を鳴らしている。ソフィーが「理性」と「本能」のバランスを取り戻させたお陰で、戦争が終結したように、このバランスによって、世界は秩序を取り戻すのだ。「理性」と「本能」のどちらかに偏っても、人類に平和は訪れない。そのバランスを保つため、「愛」の復活が重要であると本作品は語っている。
ソフィーたちを最後の最後で救うのが、案山子(十字架=キリスト教)であるが、そのカブ頭も魔女・サリマンの「理性的魔法」によって、本来の姿をなくしてしまったように、「宗教」も「理性」に偏りすぎると、あるべき姿を見失ってしまうと語られる。そして、それを取り戻すにも、「愛」が必要なのだというオチ。「愛こそすべて」であり、本作品の最も重要なテーマは「愛」なのだ(これも「千と千尋の神隠し」とシンクロしている点の一つで、あちらは、釜爺が「愛だよ、愛!」と叫ぶのが印象的だった)。
誰かれ構わずキスをしまくることから分かるように、ラストでソフィーは完全に「愛」に目覚める。そもそも「ソフィー」という名前には、ギリシャ語で「叡智(知性)」という意味がある。ラストでは、フィロ(愛)とソフィー(知性)が結合してフィロソフィー(哲学)となり、それによって、世界があるべき姿を取り戻すのだ。世界は、「理性」と「本能」のバランスを取り戻し、哲学と宗教によって救われる。
話は少し逸れるが、実は、このヒロインの名前に「千と千尋の神隠し」との共通点がある。「千と千尋の神隠し」のヒロインの名前は、「千尋」。「無知の知」の言葉で有名なソクラテスは、自分は無知だからと、いろいろと人に尋ねることを繰り返す産婆術と呼ばれる方法で、相手の「知性」を育てる手助けをしてきた人物。「千」回も「尋」ねると書く「千尋」は、このソクラテスの産婆術を思い出せば、「知性」のことを意味していることが見えてきそうだ。
「愛」に目覚めたソフィーが、ハウルに対してだけでなく、自分に呪いをかけた荒れ地の魔女にさえキスをする。これは、ソフィーが「自己嫌悪」する心さえ、受け入れることができるようになったのであり、自分のいいところ、嫌なところ、そのどちらも愛することができる「本物の愛」を手に入れることができるようになったことを語っているように思える。

自分を好きになったソフィーがやたらとキス狂になってしまうのは、すべてのものに対して、愛することができるようになったと言いたいのはよく分かるが、彼女がロリコン好みの顔立ちだけに、ちょっとやり過ぎ感があるのは否めない。「紅の豚」のフィオナように、魔法が解けるキスは1回ぐらいで十分に思えてしまうが、ここにロリータ宮崎駿の趣味がよく表れているとも言えるだろう。
映画「ハウルの動く城」を読む【完全解説】 ⑦に続く(近日公開)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
