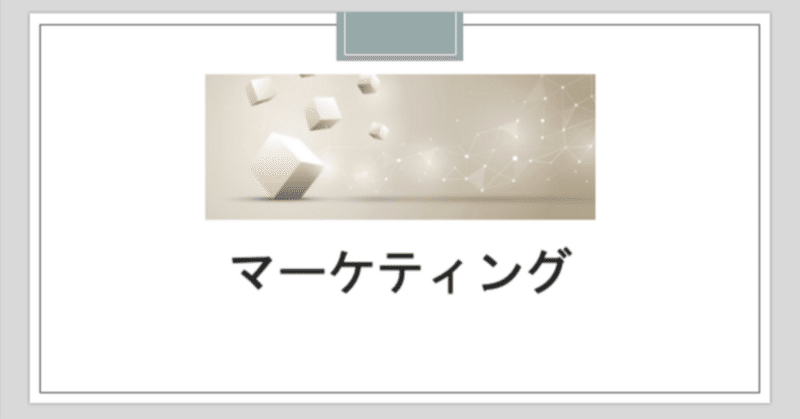
フライホイールモデルとファネルモデル:顧客獲得と成長戦略の新たな進化
こんにちは。中産連コンサルタントの岡部です。
橋本主任コンサルタントが投稿した「ユーザー体験重視のビジネス潮流においてサプライヤー企業が考えておくべきこと」について、私も大変興味深く読みました。
特にエンターテイメント精神のところは、共感するところも多く、顧客と一緒に商品・製品を創り上げるということができたら、とてもやりがいもあるのだろうな、と考えさせらました。
企業のマーケティング担当者(営業担当者が兼ねているケースが多いかもしれませんが)がユーザー体験重視を実現しようとすると、どのように考えたら良いのだろう?と思うことはないですか?
その1つの考え方に、フライホイールモデル、という考え方があります。
皆さん、フライホイールモデルという言葉を聞いたことはありますか?
フライホイールというと自動車部品製造に関わる方は、部品の「弾み車」を思い浮かべる方も多いと思いますが、このモデルはマーケティングの考え方になります。
フライホイールモデルは、2018年にアメリカのマーケティングソフトウェア会社HubSpot(ハブスポット)社が提唱した新しいマーケティングの概念です。
日本語に訳すと「弾み車」なのですが、顧客の購買行動や企業のアプローチが弾み車のように螺旋状に広がることを示したフレームワークの一種です。
2018年に提唱された概念ですので、まだまだ新しい考え方ですが、取り入れている企業も多く、興味深い概念です。
私も勉強途中ではあるのですが、今回は、フライホイールモデルとは何か?従来型のマーケティングモデルとの違いは?について、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
1.従来型マーケティングモデルの限界
従来型マーケティングモデルの代表例は、ファネルモデルが上げられます。ファネルモデルが悪いというわけではなく、顧客を獲得していく段階では大切な考え方なのですが、ファネルモデルの考え方は、顧客の購買プロセスを狭い視点で捉えているという側面があります。
具体的には、ホームページやパンフレットを充実させて認知してもらい、認知した方から問合せを頂き、営業担当が接触して商品説明などの営業活動を実施します。その後、顧客が買うか・買わないかの購買意思決定する、という流れを表現したモデルです。

ファネルモデルは、購買プロセスを表現しているのですが、顧客の購買後の行動や心情を捉えていないという限界があります。実際、新規顧客がファネルモデルのマーケティングを手伝ってくれるということは、現在では往々にして起こっています。
具体的には、購買した商品やサービスを使ってみて感じた満足度、使用した感想を口コミとしてWebサイトに掲載する行動が最たる例です。また、商品やサービスに対して大変好意的な想いを抱きファンになって足繁く店舗に通ってくれるなどのファン化も重要視されています。
つまり、ファネルモデルだけでは、現代で事業拡大するための重要な要素を見逃してしまう可能性があるということです。
2.フライホイールモデル
(1)フライホイールモデルとは
フライホイールモデルは、ファネルモデルの限界を克服するために提唱されたアプローチです。ファネルモデルでは、顧客の購買プロセスを狭い視点で捉えていましたが、フライホイールモデルではその後のファン化や顧客満足度も重視し、新規顧客が何度も顧客として循環し、さらに顧客が新しい顧客を呼び込み、顧客と企業が持続的な成長を実現することを念頭に考えられています。

(出典:HubSpot社ホームページを引用して筆者作成)
フライホイールモデルは、フライホイール自体を回す活動も重要であると考えています。例えば、営業と製造部門のコミュニケーションを良くして、営業は顧客ニーズを製造部門に伝え、製造部門は顧客ニーズに対応した製品カスタマイズを行うことが高速で行われた場合、顧客は希望をすぐに叶えてくれたと感じ、信頼を寄せるでしょう。
また、営業部門内では顧客情報を共有化しておき、営業担当者が変わっても同じような対応ができることを実現できた場合、顧客から見れば担当者が変わっても同じような安心感を得られ、信頼感も増すことでしょう。
つまり、フライホイールモデルでは、新規顧客から推薦者(プロモーター)になってもらうために、いかに高速でフライホイールを回し、顧客を成長させることに重点を置き、そのために事業や業務をどう設計するかを考えるきっかけを与えてくれます。
(2)フライホイールモデルとファネルモデルの違い
今までの内容を振り返ると、フライホイールモデルの大きな特徴は、顧客が循環し、いずれは推薦者(プロモーター)になってもらうことを考えていることです。新規顧客が一度の購買だけに留まらず、何度もリピートすること、さらには、新規顧客がさらに新しい顧客を呼び込む行動をすることで加速度的に企業が成長することを模索する考え方です。
一方で、ファネルモデルは事業拡大を図るためには、常に新規顧客にアプローチして獲得する必要があります。そうすると、継続的に広告費や営業人員などのコストを投入し続けなければ新規顧客が獲得できないことになってしまいます。

3.ファネルモデルをフライホイールモデルへ置き換えるべきか?
ここまでフライホイールモデルのメリットを説明してきました。そこで、1つの疑問が湧くかと思います。それが「ファネルモデルをフライホイールモデルへ置き換えるべきか?」ということです。
皆さんは、どのように思われますか?考えが分かれるところだと思いますし、正解がないのが経営学の良いところだと思います。
ビジネススクールでよく使われるフレーズですが、「Let's Discus!(議論してみましょう)」ですね。
私はフライホイールモデルで事業拡大を考えたからと言って、ファネルモデルの考え方を捨てるべきではないと考えます。
なぜなら、ファネルモデルは新規顧客を獲得していく上で重要な考え方で、マーケティングから入って新規顧客獲得までの直線的なプロセスであるからこそ、ファネルモデルを活用して管理をすることで、営業プロセスの問題点の発見やカイゼンを実施しやすいと考えるからです。
一方で、確かにファネルモデルの限界である、顧客獲得した後のことも現代では考えておくべきです。その際に、フライホイールモデルの考え方は、とても有効であると考えます。
なぜなら、新規顧客が新たな顧客を紹介してくれることは現代では当たり前に起こるからです。むしろ、多いのではないかと思います。だから、ファネルモデルだけで考えるのではなく、フライホイールモデルでも考えて事業や業務を設計することは重要だと考えます。
つまり、ファネルモデルで営業プロセスの管理をして、新規顧客を獲得し、一度獲得した顧客をフライホイールモデルの考え方で推薦者(プロモーター)まで顧客の成長を促す、一体化した仕組みが必要と考えます。
4.まとめ
今日はフライホイールモデルの考え方をお伝えしました。
フライホイールモデルと言われると難しく感じるかもしれませんが、私はいろいろな企業で取り組まれていることだと思っています。現実に、自社もフライホイールモデルとして整理していないだけで、取り組んでいるということは多いですよ。
例えば、自動車販売1つを取っても、新車を売って終わりではなく、自動車整備機能を有して継続的に自動車ディーラーに通う仕組みを作り、新しい車種の紹介をして次回の購買時期に離反しないようにしていたり、産業機械ロボットを販売する企業は、アフターフォローを充実させ、消耗品販売や修理サービスを提供していたりします。
いずれも顧客の満足度を高めて、継続購買してもらうための仕組みとして動かしながら、口コミや紹介によって、新たな顧客を獲得するために推薦者(プロモーター)にもなってもらえるような仕組みですね。
商品・製品を売って終わりではなく、継続的な取引につながるような事業を設計するための考え方として、フライホイールモデルを取り入れてみて下さい。
既存業務をフライホイールモデルで整理することによって、新しい取り組みや社内活動の必要性に気づくきっかけになれば幸いです。
(執筆者:中産連コンサルタント 岡部)
中小企業診断士・経営学修士(MBA) 伴走型支援が得意で、クライアント企業様と一緒に課題を見つけ・悩み・解決することをお仕事にしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
