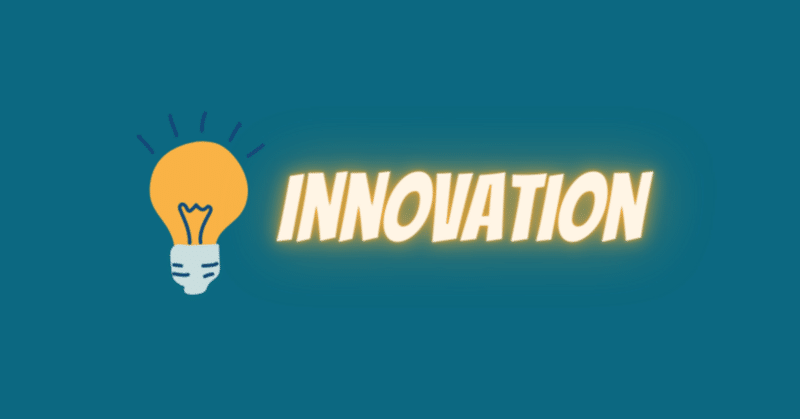
心理的安全性と多様性でイノベーションを導く
イノベーション
戦争、気候変動、災害疫病、デモグラフィック(人種・年齢・性別など集団属性)の変化、デジタル革新など不透明さが増す昨今、企業は既存の事業運営に安住できず、一層のイノベーションを求めています。
イノベーションは、提唱した経済学者シュンペーターによれば、新結合(これまでにない組み合わせのこと)により社会的な価値を生むことです。
1990年代から世界の産業構造を変える震源地となったのはアメリカ西海岸のシリコンバレーですが、ここでは開放的な気風の新興企業が自社の枠を超えて協調し、数々の機能を組み合わせた新結合であるコンピュータ、ソフトウェア、スマートフォン、ネットワーク等を創り出して巨大産業となりました。
カリフォルニア大学のチェスブロウ教授は、この地域で起こった変革を、オープン・イノベーションとの概念で表現します。自前主義の閉鎖的な事業運営よりも、他社と共同開発やM&A等で柔軟に組む方が変化の早い時代に社会的な価値を生み出し易い。今や産官学の枠も超えた連携が世界中で広まっているのは、こうした背景によります。
では、イノベーションを導くにはどうしたら良いでしょうか。組織における多様性と心理的安全性が寄与します(図1)。その論拠を順に追い、後に先端事例も紹介します。

多様性
オープン・イノベーションは同じ組織・価値観の枠を超える点に意義があります。つまり、多様性(ダイバーシティ)が動力源です。28年間に渡る大量の特許データを調べたハーバード大学は、多様な知識を持つ研究者の集団ほど前例がないテクノロジーの組み合わせ即ちイノベーションを導く傾向を見出しています。
企業がマネジメントすべきダイバーシティを掘り下げてみます。多様性と聞いてすぐに想起するのは、人種、年齢、性別などデモグラフィックです。こうした集団属性が偏らない様に統制すべく人材データを維持・管理し、例えば経営層や管理職の男女比などで目標・実績の数値を開示する企業も増えてきました。
しかし、多様性はデモグラフィックに留まらない。同じ人種、年齢、性別でも知識、技能、行動特性が異なるからです。例えば大手IT企業は、社員をアンケートから図2の様な行動パターンで分類した上、話し合う場を作って相互理解に努めています。

更に進んだ企業は、ピープル・アナリティックスやHRテックと称してデモグラフィックの他に人事(能力・行動・成果評価)や労務(出退勤・作業時間)等を組み込んだ統合データベースを構築した上、個人特性に基づく多様性の高いグループ編成や作業分担の仮説を立て、組織のパフォーマンスや生産性から効果を検証します。
心理的安全性
イノベーションを起こすために多様性だけで十分でしょうか。否。
心理的安全性がないとダイバーシティは機能しません。心理的安全性とは、集団の中で本音を語れる度合いです。
つまり、多様な知識や価値観が組織に備わっていても、メンバーが本音を語ることに不安を感じると創造性は失われます。脳科学の研究で不安は扁桃体を刺激して鼓動や発汗を促す一方、記憶や情報処理を劣化させると言います。
戦前のロシアで大統領にウクライナ侵攻の是非を問われた閣僚が上手く回答し得なかった映像は、不安による扁桃体の作用を物語っていました。
心理的安全性は、ハーバード・ビジネススクールのエドモンドソン教授の発案で、社員が7つの質問(メンバーと仕事をする時、自分のスキルは尊重され、活かされているか?等)へ回答すれば簡単に数値化できます。
日本と比べ移民が多くダイバーシティの高いアメリカで、組織パフォーマンスを上げる要因について研究されてきた中、2016年にGoogleが社内180チームでの調査結果を公表し、注目を集めました(図3)。明確な役割・プロセス等の重要な項目と比べても、心理的安全性が圧倒的に組織パフォーマンスと関係が深いと言います。

驚くのは、そうして労をかけて得た組織の研究結果を、Googleは自社の発展のためだけに秘匿せず、開示して社会的な価値をシェアする点です。当社を始めとするシリコンバレーの企業風土にはダイバーシティのみならずオープンに語り合う心理的安全性があり、多くのイノベーションを成し遂げたのでした。
先端事例
岡山県で第三の都市、津山市にある革新的な企業を紹介します。
㈱津山朝日新聞社は、明治42年に創業し、112年の歴史を誇る新聞メディアです。「正邪を明らかにし、不偏不党、もって中庸の報道により地域文化の進展に寄与せんとす」との理念で岡山県北に根ざし、住民や企業から愛される存在です。
まず多様性を見てみましょう。
43人の従業員の内、1/3が女性です。社会学者カンターによれば集団で3割以下だと少数派として意見を控える傾向があるため、当社の女性比率は3割を超えて適切にマネジメントされています。また、障がい者雇用も積極的で2023年現在3名が活躍しています。
こうしたデモグラフィックの他に行動パターンの多様性もあります。役員と部門リーダーに対し、図1で述べた手法で測ったところ、見事に4つの類型へ分散されていました。
更に、当社が優れているのは「働き方」の多様性です。従業員が望む就業時間と場所を聞き入れ、それに応じて仕事の割り振りを流動的に決めています。
日刊紙「津山朝日新聞」を輪転機で刷って配送し、同じタイミングでホームページ(図4)に記事を上げる他、印刷業やイベント業も営むので常に〆切に追われる中、時間と場所に縛られない従業員が高い生産性で協働します。その上、当社は産官学に渡る社外パートナーが非常に多く、開かれた新聞メディアとして歴史ある社屋への訪問者が絶えません。

次に心理的安全性を見ましょう。
これも役員と部門リーダーに対して測ると、相場である中立水準3点(5点満点)より0.4点の上振れでした。
特徴的なのは、福田社長よりも他のリーダーの点が高いことです。一般に心理的安全性は上位者が高く、下位者は低い傾向があります。つまり役職が上がらなければ自由にものが言えない。ところが、当社はその逆です。
これはトップの謙虚さを示します。心理的安全性を提唱したエドモンドソン教授は、本音が言える組織を作るために上位者の謙虚さを求めています。我が国にも「実るほど頭を垂れる稲穂かな」との格言がありますが、忘れ去られていないでしょうか。
多様性と心理的安全性が高い津山朝日新聞社はイノベーションを起こす土台が出来ています。実際、絶えず様々なパートナーに囲まれながら新しい企画を構想しています。その中には、AR/VRアプリ開発、脱炭素/セルロースファイバー事業など、ベンチャーの好むテーマがこの創業112年の老舗企業で語られます。筆者もパートナーもしくはサポーターの一人です。
こうした新たな取組みを起こす時、当社は「地域文化の進展に寄与」の理念で真っ先に動き出し、自社の利益は後で考えます。その姿勢もGoogleを始めとする先端企業に類似します。
イノベーションに失敗する企業の多くは、顧客や社会への貢献よりも自社の利益に基づく技術や製品の押し売りで市場から無視されます。古代中国の孟子は、人に役立つ「義」を優先し、「利」は後回しにする「先義後利」を説きました。
津山朝日新聞の福田社長は「助けたつもりが、助けられた」との印象的な言葉を残しています。
ワクワクする様な古くて新しい当社を参考に、多くの企業がオープン・イノベーションを果たす事を願って止みません。
(執筆者:中産連コンサルタント・清水)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
