
いたことだけはおぼえてて
🌼第十一回六枚道場の参加作品です🚗
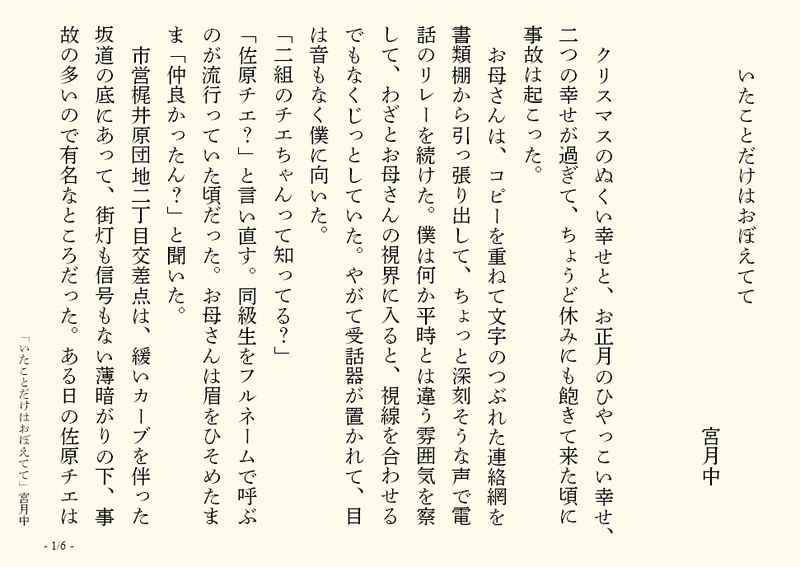





クリスマスのぬくい幸せと、お正月のひやっこい幸せ、二つの幸せが過ぎて、ちょうど休みにも飽きて来た頃に事故は起こった。
お母さんは、コピーを重ねて文字のつぶれた連絡網を書類棚から引っ張り出して、ちょっと深刻そうな声で電話のリレーを続けた。僕は何か平時とは違う雰囲気を察して、わざとお母さんの視界に入ると、視線を合わせるでもなくじっとしていた。やがて受話器が置かれて、目は音もなく僕に向いた。
「二組のチエちゃんって知ってる?」
「佐原チエ?」と言い直す。同級生をフルネームで呼ぶのが流行っていた頃だった。お母さんは眉をひそめたまま「仲良かったん?」と聞いた。
市営梶井原団地二丁目交差点は、緩いカーブを伴った坂道の底にあって、街灯も信号もない薄暗がりの下、事故の多いので有名なところだった。ある日の佐原チエはもらったお年玉の使いどころを考えあぐねた挙句、友達を連れて団地の上の駄菓子屋に少し高いお菓子を買いに行くところだった。横断歩道に差し掛かり、右見て左見て、もう一度右を見て三歩を踏み出したところに引っ越しのトラックはやってきた。その身体は何度か宙を回転したあと、道脇の田んぼの中にぺしゃりと落ちた。そういう詳細を語ったのは始業式の日の校長で、僕は高学年だったから、その話を体育館の随分後ろの方で聞いていた。
「もくとう」と聞こえて、何百人が静まり返って、やがてその中にすすり泣くような声がいくつか混じった。こっそり目を開けると、胸を押さえたやつが一人、先生に連れられて体育館を出ていくところだった。楽しくない気分のまま教室に戻ると、心の相談室が対応するみたいなプリントが配られた。
「二組の坂田ひろし、吐いたらしいぜ」と噂が聞こえて来た。僕らは存外他人事だった。それはきっと、僕らの一組と二組の間に、分厚い壁と、カバン入れと学級文庫と回転する紙の当番表が存在したからで、もし二つの教室が地続きだったなら、泣いたり吐いたりしたのは僕達だったかもしれない。でもそうではなかった。そうでなかったから、噂は妙な広がり方をした。「はねられた時、首がもげたん」「万引きしたって聞いたけど」「前の日にこっくりさんしちょったんじゃって」飛び交う噂は日毎大きくなって、ある瞬間を境に、佐原チエの実際を大きく損ねてしまった。僕らは彼女が何者であったのかを思い出せなくなって、噂が下火になった春の午後、そこには女の子の空席だけが残された。
チエの名が再び囁かれたのは二十年の後だった。その日の僕は年休の消化と同窓会と、どちらが理由か分からないまま帰省して、少しきつくなったスーツに袖を通しているところだった。
「これ、持っていってあげ」
最近老いたと感じることの多くなった母の声に振り返ると、その手にはいくつか、菊の花が握られている。
「何の花、それ」
「チエちゃんのよ。急に思い出してねえ」
どうして、という疑問を飲み込んで母の言葉を待った。母は生花をありあわせの紙袋に込めながら言った。「仲良かったって言っちょったじゃろ、よう遊んだって。一度うち来た事もあったっけかね」
同窓会は地元で一番大きなホテルで行われた。立食の会場にいくつものグループが出来上がる。幼少の面影を残す顔ぶれが、ワイングラスを片手に知らない言葉を交わし合う。僕はありったけの記憶を持ち出して黙祷をささげた日に帰ろうとする。紙袋を提げた左手が重くなる。
「お、よっしーじゃん! めっちゃ背ぇ高くなっちょる」
旧友がちらほら集まってきて、そのうち思い出話に花が咲く。
「運動会のときの写真まだ持っちょるんよ」「稲井と川澄結婚したん、知っちょった?」「お前山本ん事好きじゃったろ」
誰もが楽しかった事ばかりを口にする。ちぎれた紙の切れ端みたいな記憶が重なって、僕らの小学校が作り替えられていく。僕の焦りは腹立たしさに変わっていく。花はいっそう重くなる。まるで僕が扉を開くのを待っているみたいに。
「チエのこと憶えてる?」
たまりかねて口に出すと、旧友たちは不思議そうに首を傾げた。やがて誰かが口を開く。
「ああ、都市伝説! 懐かしい」「流行ったよねー、中尾の交差点やっけ」「梶井原じゃなかった?」「テレビでやってたやつ」「三年の頃」「五年じゃろ」
「違うだろ。僕が言ってるのは、本当に、本当に死んだ佐原チエの話で」
僕があまりに真剣なものだから、気を利かせた旧友が卒業アルバムを持ち出して広げた。二組の集合写真の、左上の小窓に女の子がいた。小窓の下には小さく名前が書いてある。でもそれが誰だか誰も分からない。合成された、知らない顔が笑っているみたいに、それが誰かを認識できない。僕らは顔を見合わせた。何かいたことだけが確からしかった。
同窓会が終わっても二次会へ進む気にはなれなかった。僕らの酔った足は自然と梶井原へ向かった。いつの間にか街灯も信号機も整備された交差点の端に、まだ置かれて間もない花と、ジュースと、ぬいぐるみが居座っていた。僕の菊はその隣に音もなく座った。
通りがかりの老婆が僕らを見て「チエちゃんたちのことを知っとるんかえ」と聞いた。僕が頷くと老婆は、少し驚いた顔をして、やがて小さく吐き捨てるように言った。
「もう、四十年も経つのにねえ」
遠くでチエの声がした。確かにした。一度も話したことのない、女の子の声だ。
🌼 🚗 🌼 🚗 🌼 🚗 🌼 🚗 🌼 🚗
朗読はこちら
お読みいただきありがとうございます✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
