
石になる
●第三回阿波しらさぎ文学賞の一次通過作品です。テキストと画像で用意しました。読んでいただけますと幸いです。(テキストはページ下方にあります。そっちの方が読みやすいかも)

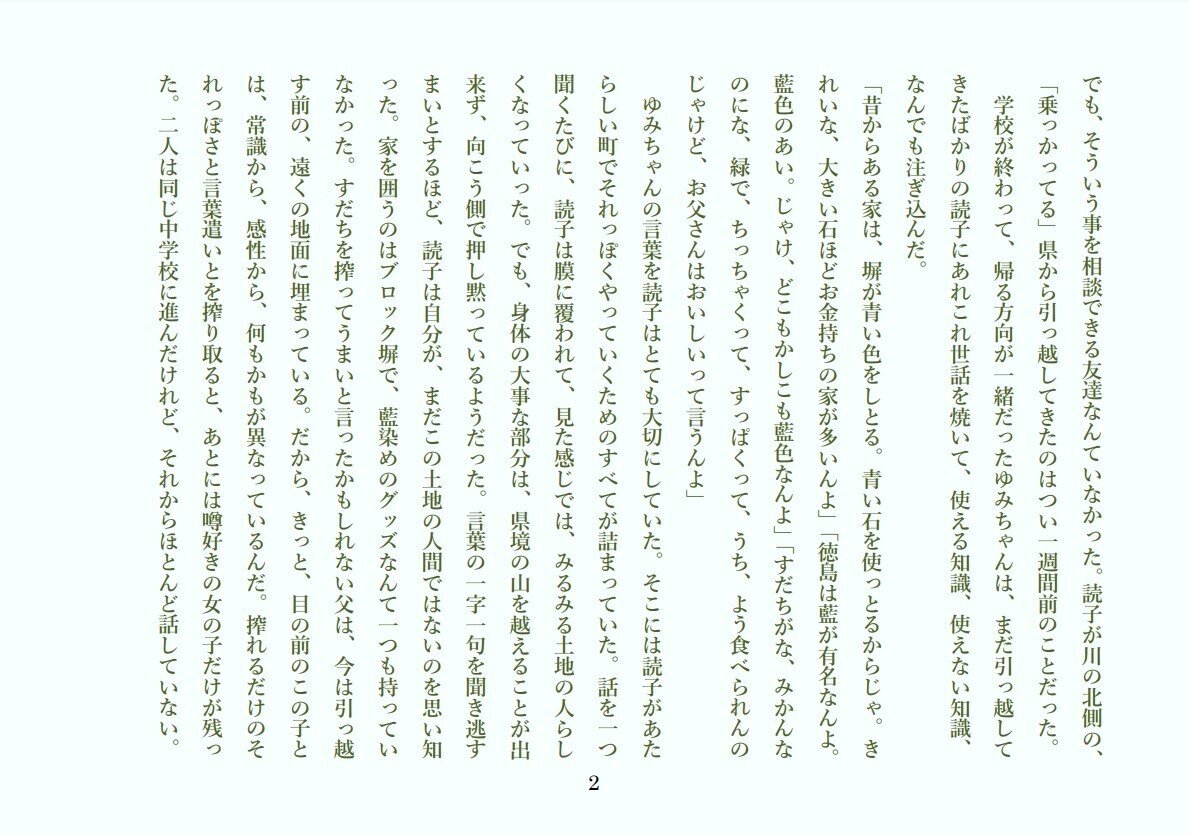



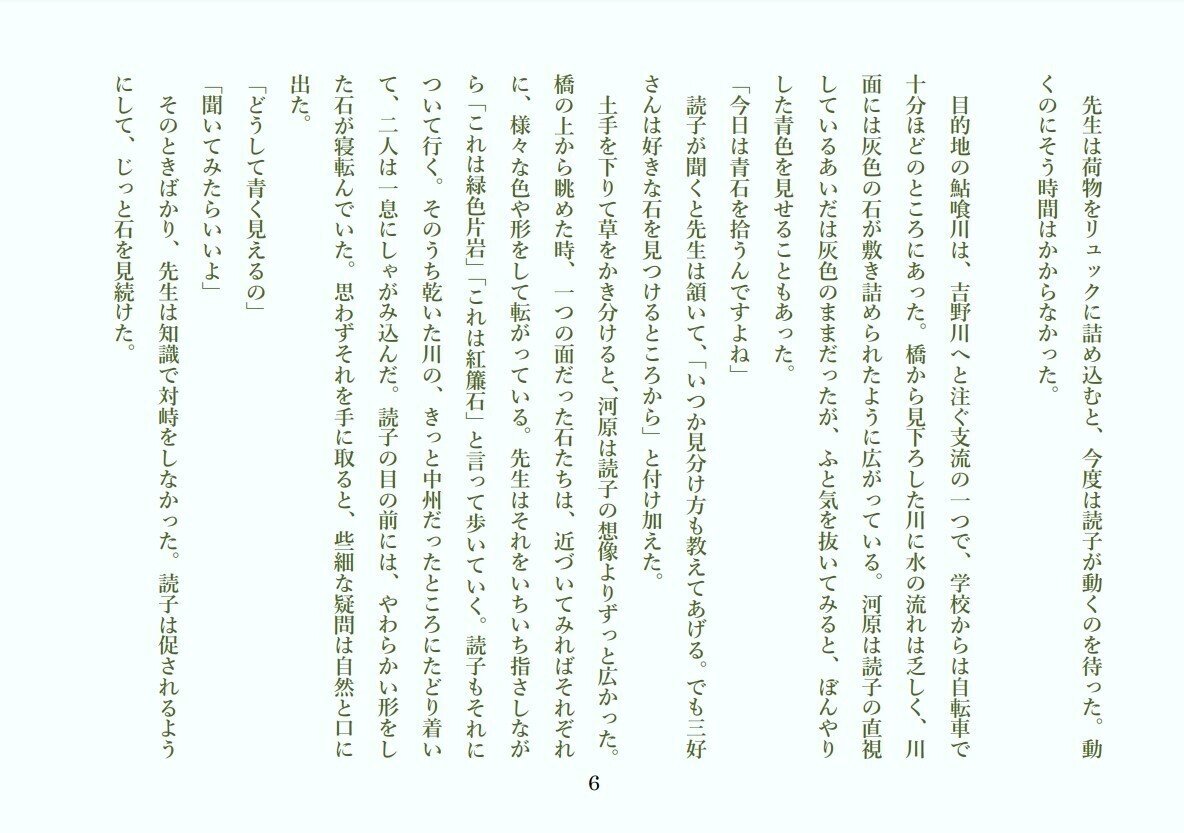


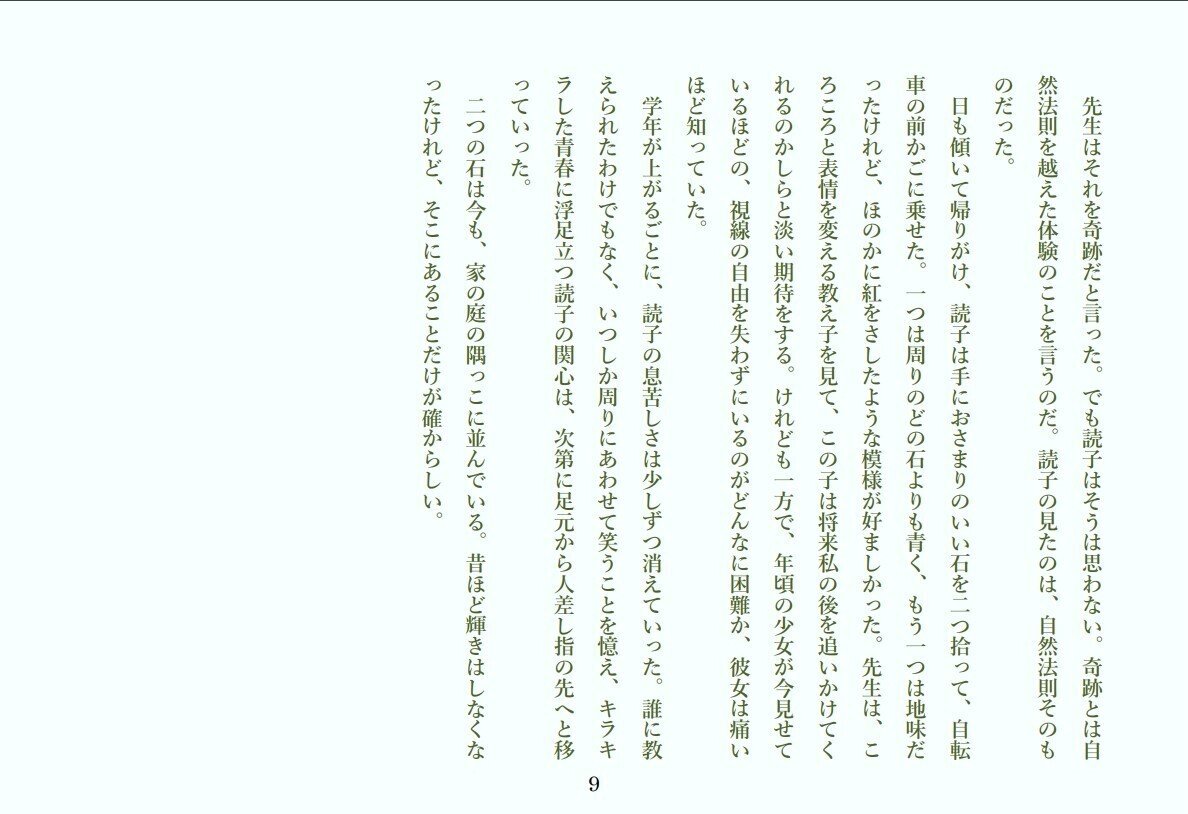
●『石になる』 宮月中
読子(よみこ)は四国を四枚おろしにした過去を持つ。
わたしたちの国は、四つの大きな島と、七千近くの小さな、たくさんの島で出来ていて、いま、わたしたちがいるのは、その四つの大きな島のうちのひとつで、名前を四国と言って、四国はまた、四国と言うくらいだから、四つに分けられるのです、と先生が言った時、読子の頭の中には、父の書斎で見た四国の地図が広がっていて、だから先生が黒板に描いた下手っぴな四国を、誰か四つに分けてみてくださいと言った時、まっさきに、それも一番高く手をあげたのは読子だった。
読子は得意げに教室の前へと躍り出ると、白亜のチョークを黒板にカッツリと立て、それから勢い付けて横一文字に線を引いた。横線は三本引かれ、教室は静まり返った。四国は四枚おろしになった。
「あいつ、アホじゃわ」と誰かが言って、クラスが少しざわめいた。先生も、叱るでもなく、曖昧にはにかんで「まあ、こういうのも面白いけれど」と言葉を濁した。先生のスベスベの手に赤のチョークが握られて、読子の解答に正解が上書きされた。
「下に弧を描くのが高知。その左上にかぶさっているのが愛媛。右側の三角のやつが徳島。その上に乗っかってるのが香川で……」
先生が説明しているあいだ、読子はじっと下を向いていた。わたし、何か、間違えたかしら。でも、確かに見たはずなんだ。パパの書斎で確かに。でも、そういう事を相談できる友達なんていなかった。読子が川の北側の、「乗っかってる」県から引っ越してきたのはつい一週間前のことだった。
学校が終わって、帰る方向が一緒だったゆみちゃんは、まだ引っ越してきたばかりの読子にあれこれ世話を焼いて、使える知識、使えない知識、なんでも注ぎ込んだ。
「昔からある家は、塀が青い色をしとる。青い石を使っとるからじゃ。きれいな、大きい石ほどお金持ちの家が多いんよ」「徳島は藍が有名なんよ。藍色のあい。じゃけ、どこもかしこも藍色なんよ」「すだちがな、みかんなのにな、緑で、ちっちゃくって、すっぱくって、うち、よう食べられんのじゃけど、お父さんはおいしいって言うんよ」
ゆみちゃんの言葉を読子はとても大切にしていた。そこには読子があたらしい町でそれっぽくやっていくためのすべてが詰まっていた。話を一つ聞くたびに、読子は膜に覆われて、見た感じでは、みるみる土地の人らしくなっていった。でも、身体の大事な部分は、県境の山を越えることが出来ず、向こう側で押し黙っているようだった。言葉の一字一句を聞き逃すまいとするほど、読子は自分が、まだこの土地の人間ではないのを思い知った。家を囲うのはブロック塀で、藍染めのグッズなんて一つも持っていなかった。すだちを搾ってうまいと言ったかもしれない父は、今は引っ越す前の、遠くの地面に埋まっている。だから、きっと、目の前のこの子とは、常識から、感性から、何もかもが異なっているんだ。搾れるだけのそれっぽさと言葉遣いとを搾り取ると、あとには噂好きの女の子だけが残った。二人は同じ中学校に進んだけれど、それからほとんど話していない。
昔のこと、思い出していたからかしら。放課後、校舎の、中庭の花壇に目がとまり、読子は藍色をしたスカートの、歩くたびに翻していたのをふわりと止めた。花はまだ咲いていない。肥料の混ざった淡い色の土が、旧家の石塀やお城の石垣と同じ、青い石に囲われている。近寄って見てみると石は、青というよりは、緑がかった灰色をしていて、その明るさは個によってまちまちだった。読子はそこに都市の色を見た。朝方つけたテレビの、天気予報の始まる時なんかに流される、薄く靄(もや)がかった都市の色だ。
「青石(あおいし)に興味があるの?」
肩のあたりに声がかかって振り向くと、理科の赤崎先生が立っている。赤崎先生は理科の全部を教えていたが、本当は地学が専門だった。先生は読子の隣にしゃがみ込むと、この土地の名産でもある石たちを愛おしそうに眺めながら言葉を繋ぐ。
「一年二組の三好さんよね。これから教材にする石を拾いに行くんだけど、興味があるなら付き合ってくれないかしら」
先生はそれまで石に送っていた微笑を、そのまま読子へと向けた。読子は、分からないけれど、少しむっとしていたかもしれない。この人、友人の少ない自分に同情したんじゃないかしら。それとも、先生も友達いなくって、同類だと思って声をかけたのかも。読子のそういった勘ぐりはちゃんと顔に出ているようだった。先生は「まあそう警戒しないで」と言うと立ち上がり、ひとり勝手に歩き出した。彼女には読子がついて来る無根拠の確信があって、じっさい読子はそうしたのだった。
「あなたのお父さん、先生の先生だったのよ」
道具を取りに理科準備室へと向かう廊下で、先生は先生を繰り返した。「大学のね、三好先生のゼミ。変わった人だったな……三好さんも、お父さんに影響受けたんじゃない?」
「父の?」読子は思わず聞き返す。「受けてないと思いますけど……」
「石見てる時のね、目が、お父さんそっくりだった。三好さんもね、石の表面より、もっと奥に潜れる人だなって思ったのよ」
「……小学校の頃、四国の地図に線を引きなさいって言われて、横線三本引いて笑われたことならありますよ。書斎で見た地図です」
「ああ、なるほど」先生は事もなげに言って笑った。「準備室にあるから、少しお勉強してから行きましょうか」
目当ての部屋はすぐ目の前だった。引き戸が開いて、部屋の薄暗がりと古い紙のにおいが外の廊下にまでちらついた。先生はそこに躊躇いなく飛び込むと、西日を避けるようにして置かれた木造りの書棚から、四つ折りの大きな紙を一枚、引っ張り出して机に広げる。地図は懐かしさをもって読子の前に現れた。右から左、東西に向かって四国を横切る直線たち。うっすらと色分けされた美しい縞模様。意味の取れなかった言葉たちも、今ならなんとなく理解できる。地図の左上には『四国地方・表層地質図』と記されていた。あの日、読子が黒板に描き出して見せたのは、四国の、地面そのものだったのである。
「四国は大きく分けて、三つの断層帯で区切られているの。上から順番に、中央構造線、稲荷鉾(みかぶ)構造線、仏像(ぶつぞう)構造線。断層は、地震を起こしながらちょっとずつ地面をずらして、異なる種類の岩盤を隣り合わせにする。今私たちがいる徳島市は、三波川(さんばがわ)変成帯という地面の上、吉野川が運んできた石の積もったところです。そこから中央構造線を越えて、領家(りょうけ)変成帯の上に乗っかってるのが、三好先生の、あなたのいた香川県……」
先生の説明を聞きながら、読子は一つの発見をする。それは刹那に、絶望と諦観とを伴う発見だったかもしれない。読子はこれまで、いかにこの土地の人間になるかを考え続けてきた。土地の雰囲気を知り、文化を受け入れ、言葉を操り、あたかも、生まれた時から藍色の空気を吸っていたような顔をして過ごす。それが出来なくちゃ、うまくやっていけないんだと信じていた。だけどそうではなかった。隔たりはすべて、はじめから、決まっていたことなんだ。生まれた、育った、踏んでいた地面が違うんだ。それは論理の破たんした、突拍子のない発見だったかもしれない。でも、読子の身体には十分の真実だった。
「先生、わたし、ずっと違う地面の上にいる」
先生は読子の曇った顔をのぞき見て、憶えのある表情にどきりとする。人とのつながりや、社会の常識や、すべてが嘘っぽく見えて、何より強固な地面を求めていた日のことを思い出す。思い返せばそれは、時期や慣れが解決する問題だった。でもそのためにはまず、地面の広さと深さを知ってほしかった。
「日の沈まないうちに河原へ行きましょう。あなた、たぶん石になれるわ」
「石になる?」
「三好先生がよく仰ってた。石をじっと見ていると、時々、自分も石になったような風景を見ることがあるんだって。私はよくわからなかったけれど、三好さんならきっと……」
先生は荷物をリュックに詰め込むと、今度は読子が動くのを待った。動くのにそう時間はかからなかった。
目的地の鮎喰川(あくいがわ)は、吉野川へと注ぐ支流の一つで、学校からは自転車で十分ほどのところにあった。橋から見下ろした川に水の流れは乏しく、川面には灰色の石が敷き詰められたように広がっている。河原は読子の直視しているあいだは灰色のままだったが、ふと気を抜いてみると、ぼんやりした青色を見せることもあった。
「今日は青石を拾うんですよね」
読子が聞くと先生は頷いて、「いつか見分け方も教えてあげる。でも三好さんは好きな石を見つけるところから」と付け加えた。
土手を下りて草をかき分けると、河原は読子の想像よりずっと広かった。橋の上から眺めた時、一つの面だった石たちは、近づいてみればそれぞれに、様々な色や形をして転がっている。先生はそれをいちいち指さしながら「これは緑色片岩」「これは紅簾石(こうれんせき)」と言って歩いていく。読子もそれについて行く。そのうち乾いた川の、きっと中州だったところにたどり着いて、二人は一息にしゃがみ込んだ。読子の目の前には、やわらかい形をした石が寝転んでいた。思わずそれを手に取ると、些細な疑問は自然と口に出た。
「どうして青く見えるの」
「聞いてみたらいいよ」
そのときばかり、先生は知識で対峙をしなかった。読子は促されるようにして、じっと石を見続けた。
ふと音が消えて、視界から、先生や、河原や、渡ってきた橋が遠のいた。ただ一色だと思っていた石は、目を凝らしてみると小さな、白や黒や緑の集合であるのが分かった。読子はそこにもう一度、都市の風景を見つける。今はその正体がよく分かる。町も、アスファルトの黒や、屋上の白や、街路樹のちょっとした緑や、いろんなものが混ざり合って、それで青く見えている。石も河原も都市も、たぶんわたしも、みんな何かの集合で出来ているんだ。
じゃあ、あなたはどこから来たの。
声なき声がこだまする。手に持つものを、握る力が強くなる。
今なら石になれる。そう読子は思った。願ったのかもしれない。
背中を支えていた何かが途切れて、読子は仰向けに倒れこむ。束の間、世界は逆さになった。石の川は頭の上を流れ、右手に四国山地、左手に阿讃山脈、形は似ているのに、違う岩石で出来た山たちが、向き合うようにして垂れ下がった。強い日差しに熱せられた石たちは申し訳なさそうに読子の身体をよけ、身体はゆっくりと地面に沈んでいく。自分の身体の広いのを感じて、気付いた時には読子は中州そのものであった。中州ははじめ、形のない胎児のようで、その色と大きさをちぐはぐさせながら、産道の、川の間をするすると下っていく。そのうち読子は小さく丸く崩れていき、細かい礫や砂粒となって、広く海の底へと沈殿した。
時間も場所も忘れた頃、読子は偏在する自分がことごとく、地殻の割れ目の、底の方へと引っ張られるのを見た。はるか地球のマントルへ、沈む身体の深いところは圧力に、浅いところは高温の熱にさらされる。そうして読子は石になる。時折光を反射して輝く青い石に。どこかで父の声がする。父だけではない。先生も、ゆみちゃんも、徳島も香川も、全部が混ざって重なって、それが読子の身体を形作る。
ふとお尻のあたりに断層を感じて、それはみるみる読子の身体を押し上げた。億千の微動に衝き上げられるようにして、ようやく地表へたどり着いたら、そこは木陰で、先生は心配そうにうちわをあおいでいて、読子はどうやら、熱に浮かされたようだった。
「父に会えた気がします」
先生の買ってきたお茶を飲んでしまうと、読子はそんなふうに話を切り出した。
「お父さんに? 元気だった?」
「声だけでした。何も、教えてくれたりはしなかった。でも、なんかそれで、一緒なんだなって思ったんです。この土地も、父の眠る土地も、もとは一つの場所にあって……」
読子の言葉を聞いて先生は目をぱちくりとさせた。
「三好さん、知ってたの?」
読子は首を横に振る。少し間をおいて、先生の口から、今いる地面の歴史が語られる。
「……三波川帯と領家帯はね、恐竜のいたジュラ紀までは、同じ一つの塊(かたまり)だったんだよ。三波川は高圧低温で、領家は低圧高温で、白亜紀に異なる熱を受けた塊は、水平にして六十キロ、深さをして二十キロ離れた、二つの石に分かれたの。でもその後、断層が少しずつ地面をずらして、六千万年かけて、今、この場所で隣り合ってる」
先生はそれを奇跡だと言った。でも読子はそうは思わない。奇跡とは自然法則を越えた体験のことを言うのだ。読子の見たのは、自然法則そのものだった。
日も傾いて帰りがけ、読子は手におさまりのいい石を二つ拾って、自転車の前かごに乗せた。一つは周りのどの石よりも青く、もう一つは地味だったけれど、ほのかに紅をさしたような模様が好ましかった。先生は、ころころと表情を変える教え子を見て、この子は将来私の後を追いかけてくれるのかしらと淡い期待をする。けれども一方で、年頃の少女が今見せているほどの、視線の自由を失わずにいるのがどんなに困難か、彼女は痛いほど知っていた。
学年が上がるごとに、読子の息苦しさは少しずつ消えていった。誰に教えられたわけでもなく、いつしか周りにあわせて笑うことを憶え、キラキラした青春に浮足立つ読子の関心は、次第に足元から人差し指の先へと移っていった。
二つの石は今も、家の庭の隅っこに並んでいる。昔ほど輝きはしなくなったけれど、そこにあることだけが確からしい。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
