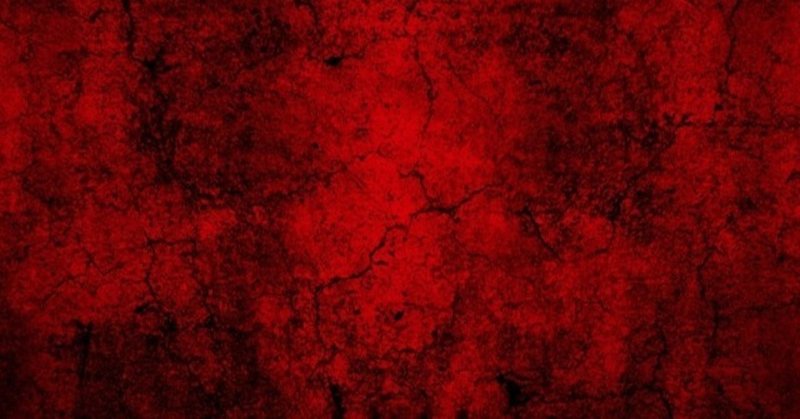
ぼくのなかの日本(第38回、少年A)
少年A
第1の事件が、1997年の2月にすでに起きていたことを知ったのは、遥かあとのことだった。中国にもブロードバンドが普及しはじめ、その一方でアクセス規制がまだ緩く、諸外国のサイトを自由に利用できていた頃、ぼくは自分が日本にいた頃に起きたこの事件を調べていた。それは自分を悩ませた謎を独力で解明することを諦め、答えを見ようとする心理であったが、猟奇的好奇心があったことも、否定のしようがなかった。
事件の発覚は、1997年5月下旬だった。新しいクラスに順調に馴染み、ゴールデンウィークに見た名探偵コナンの劇場版第1作『時計じかけの摩天楼』がまだ余韻として残るなか、神戸の小学校の前に、男児の切断された首が置かれていたことを、ぼくはテレビで知った。
20年後の今なら、あまりの猟奇さに世間への影響を懸念し、報道規制をする可能性がある事件。しかし、当時は『電波少年』のような放送倫理スレスレの番組がウケていた時代、いいか悪いかはさておき、マスコミが飛びついたのは言うまでもない。ぼくがテレビの日本語を理解できるようになってから、これほど各局が一つの話題に集中することを見るのは、間違いなく阪神淡路大震災以来である。奇しくも舞台はまたもや神戸、災害と事件の関連性を内心疑いながら、ぼくも連日テレビにかじりついた。
普通なら、これだけの事件は、学校でも話題になるはずである。しかし、ぼくの記憶の限りでは、誰とも事件のことについて話し合ったことがない。親からも先生からも、議論するなとは一言も言われていないが、平凡な公立校に通うぼくたちは、あまりの恐ろしさに自主規制したのかもしれない。
犯人は最初の報道から約1ヶ月後に捕まった。やや落ちついてきた報道のトーンは、まるで今回こそが本震とでも言わんばかりに最高潮に達し、この1ヶ月間自分たちが「犯人は高学歴」「30代以上」「複数犯か」などとチンプンカンプンなことを言っていたのをすべて忘却という名の救世主に託し、「14才の少年」という一点にのみ飛びついた。逮捕当日の夜、まだ『ニュースステーション』という名称だった報道番組で、現地から中継が入ると、記者の後ろで地元の少年たちがカメラに向かってピースしたり、飛び跳ねたりしていたが、それを見たスタジオの久米宏氏は、ゲストに向かって「しかし、先程の中継のバックに映った子どもたちの反応は、なんとも腑に落ちないものです。これが今の子供達の現状でしょうか」のようなことを言った。ぼくは久米宏氏を尊敬しているが、この言葉には全く納得できない。「あんたが子供の頃も、きっと同じだったろうに」と、可能であれば本人に言ってやりたかった。
ぼくは間違いなく、テレビカメラを前に興奮する地元の少年たちに共感していた。事件どうのこうの関係なく、カメラが来ているという事実のみに、彼らが興奮していることがぼくにはよく理解でき、おそらくその場にいたら自分もそうしただろうと思った。その視野の狭さ、思慮の浅はかさ、共感力のなさこそが、少年というものであり、子供というものである。それと同時に、急速に成長する体力と知力は、ぼくたちにあれだけの犯罪を可能にする能力を与えた。この2つの特徴が不幸にも結合したとき、類まれな残酷さとなって表れたのである。
その結論に至ったぼくは、テレビの報道がいよいよつまらなくなり、久米宏以降はなにも覚えていない。ぼくからすれば、犯人も地元の少年もひどく身近に感じられるのに、テレビの伝え方はまるでこれがフィクションの出来事かと思わせるものだった。ぼくの猟奇的好奇心は、ある意味自身の心の奥底を覗こうとする試みだが、それを口に出して議論することは、遂に叶わなかった。
思えば、あの頃、ぼくは数ヶ月に渡り、知らない人を見たときに警戒心が強くなったのを感じた。いつもの通学路でもビクビクするほどで、普段会わないような人を目にすると、ついつい距離を取り、通り過ぎたあとに振り返って相手の様子を伺う。「さっきの人目が死んでたような…」などと失礼極まりない想像もどんどん浮かんできたものだ。もちろん、実際は何の被害もぼくに身に降り掛かっていない。もしかしたら、少年Aと同年代のぼくのほうが、実は周りからもっとも恐れられていたのかも知れない。いずれにしても、事件によってすべての人の心になにかしらの変化が起きたはずだが、少なくとも表面上はそれを悟られないようにした。学校でも相変わらず誰も事件のことを口にしない、表面上の平静を保ちながら、なんとか深いところでも元へと戻そうと、先生と生徒全員が暗黙の了解で懸命に努力していたかもしれない。
しかし、中2の少年少女たちは不安定なものである。思いとは裏腹に、トラブルは起きるものだ。たとえばある日、うちのクラスの男子1名が、数学のテスト中に先生に注意されたことに逆上し、先生の足を何度も踏みつけた。ちょうど見える位置に座っていたぼくは、「おいおいやべーぞ」と驚くと同時に、「足を踏むだけなんだな、殴ったりしないところから見ると意外と自分を抑えてるじゃん」と、冷静に分析していた。案の定生徒指導室に呼ばれる彼、友だちがいなく、エロいことばかり口走るから女子からも敬遠されたその男子が可哀想ではあったが、ぼくも保身を決め込み、自分の分析を誰かに話すことはなかった。しかし、予想外のことに、その日の放課後、緊急の学年集会を行われ、熱血教師の宮崎先生が学年主任として、こんなことを言ったのである。
「先生たちもいろいろ話し合いをしましたが、やはり『今年の2年生は荒れてるな』という点で、みんな一致しました」
例外なく全員「荒れてる」というレッテルを貼られてしまった2年生たち。ここまで言うからには、うちのクラスの一件と同じような事件がほかにも起きていたのだろう。しかし、先生、「今年の2年生」ってどういう意味だ、今年の2年生は去年の1年生だ、そのときはあんたなにも言わなかった。この1年の間に荒れるようになったのだとすれば、それはあなた方の指導に問題あるんじゃないんですかーー相変わらず口に出さずに、心の中で減らず口をたたくぼくであった。
まさかあの指導が功を奏したわけはないと思うが、その後記憶に残るような暴力事件やトラブルが起きなかったのは、事実である。マスコミが報道をしなくなると事件が風化するのと同じように、日々多くのことが起きる中学校でも、この事件は自然と風化していったのだろう。しかし、少なくともぼくのなかでは、宮崎先生の指摘をきっかけに、いくつもの疑問が新たに生まれた。あの頃のぼくがテレビに映った地元の少年に覚えた共感は、今なお消えておらず、事件への猟奇的好奇心も持ち続けている。そのぼくも、本当に2年になってから荒れはじめたのだろうか。それ以前もその後も、ぼくは「荒れる」と言われるようなことを一度もしていないが、それはなぜだろうか。おそらくあのクラスの大半の人が無事に平凡な一生を送るようになるが、それはなぜか。もし今後あのクラスから、少年A同様な凶悪犯が出たら、それは中2の年の事件と関係があるのだろうか。いくつもの疑問が残るのだ。
だが、疑問が残ることはむしろ幸運だろう。その御蔭で、ぼくは他人から与えられた一見説得力のある答えに満足せずに、今なお「なぜ」と自問自答を続けることができ、正気を保つことができているのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
